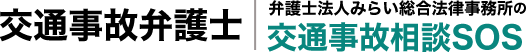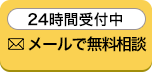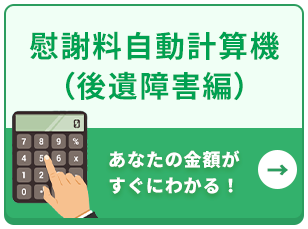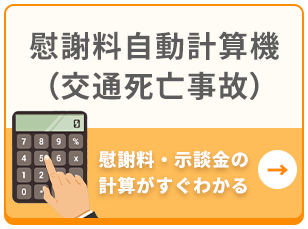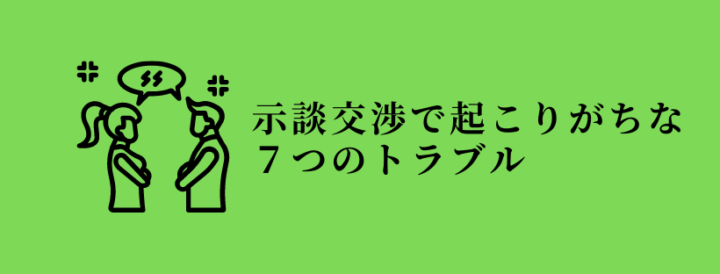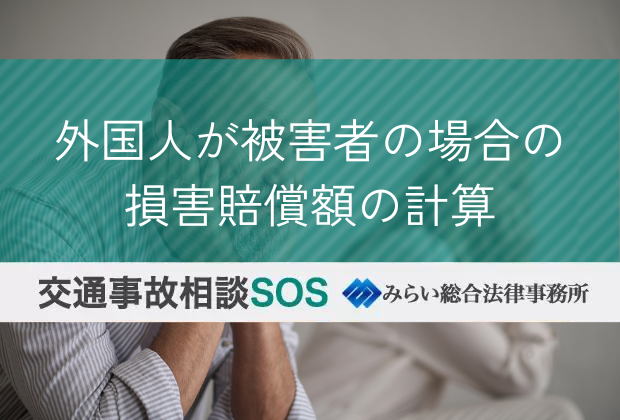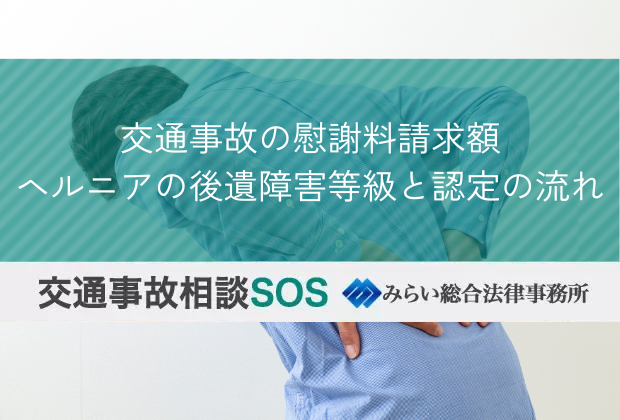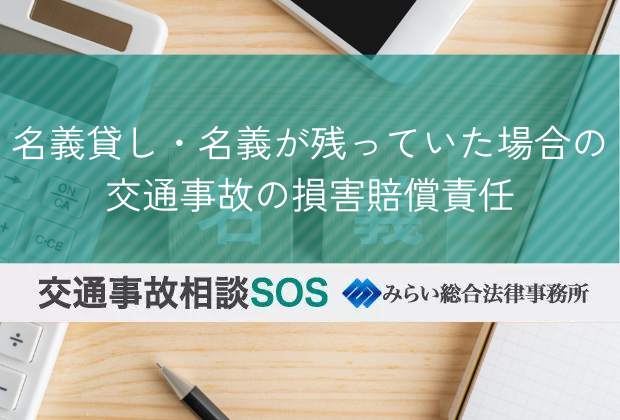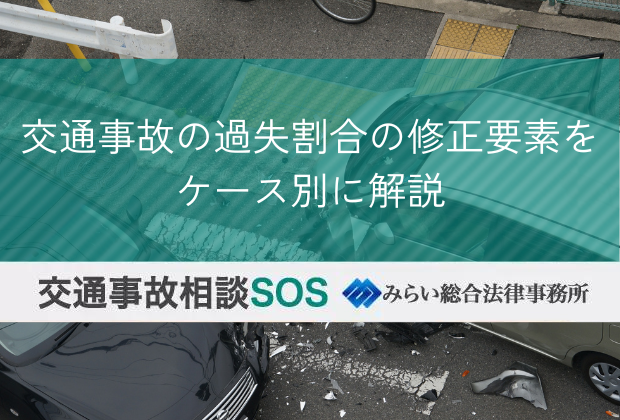交通事故の示談交渉で起きる7つのトラブルと対処法
この記事を読むとわかること
交通事故での示談交渉とは?
示談交渉の開始から成立までの流れ
示談交渉で起こりがちなトラブル
トラブルの解決方法
被害者の方が注意するべきこと
交通事故の被害でケガをした、または後遺症が残ってしまったという場合は、示談交渉を行なう必要があります。
しかし、示談交渉というのは、なかなかすんなりと解決せず、争いになってしまう場合が多いのも現実です。
では、そもそも示談交渉とは、どういったもので、何のために必要なのでしょうか?
被害者の方の交渉相手は誰なのでしょうか?
トラブルが起きた場合、どう解決すればいいのでしょうか?
交通事故の被害など初めて、という方がほとんどでしょうから、知らないのは無理もありません。
しかし、どんなトラブルが起きがちなのか知っておくことで、“転ばぬ先の杖”としていくことができますし、いざトラブルが起きた時には、すみやかに解決に向けた対応ができます。
(1)交通事故の示談とは?
示談とは、交通事故が起きた際に、被害者側と加害者側の間で次のような問題となることについて話し合い、解決をして、和解することです。
その解決までのやりとりが、示談交渉になります。
①交通事故によって、どのような損害が生じたのか?
②その損害額は、金額にしていくらになるのか?
③支払い方法は、どのようにするのか?
和解をする、といったように、示談交渉は裁判のように勝ち負けを決めるものではありません。
まず、そこが示談の重要なポイントになります。
(2)示談交渉は誰と行なうのか?
では、示談交渉は誰と行なっていくのかというと、通常は加害者側の任意保険会社の担当者ということになります。
任意保険の契約内容には「示談代行サービス」というものが組み込まれている場合が多いため、被害者の方が直接、加害者と対面するわけではないからです。
(3)示談金額(損害賠償金額)の何を話し合うのか?
具体的に、示談金(損害賠償金)の金額については何を、どう話し合っていくのでしょうか?
①示談金の内容について
示談金というのは、被害者側と加害者側で示談により金額が合意されるので「示談金」といます。
被害者の方から見れば、被った損害を賠償してもらうものなので「損害賠償金」ともいえますし、それを保険会社が支払う場合は、保険契約に基づく「保険金」となります。
つまり、示談金、損害賠償金、保険金というのは状況によって呼び方が違うだけで、同じものということになります。
また、慰謝料と損害賠償金は同じものだと思っている方もいらっしゃると思いますが、慰謝料というのは、たくさんある損害賠償金の項目のひとつとなります。
さらに、慰謝料というのはひとつではなく、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」「近親者慰謝料」4つの種類があることを覚えておいてください。
②入通院した場合に請求できる損害賠償項目と金額
入院・通院で治療をした場合の損害賠償項目は次のとおりです。
治療費:必要かつ相当な範囲での実費金額
※特別個室、過剰診療等の費用は補償されない可能性がある
付添看護費:看護師・介護福祉士等/実費全額
近親者/入院の場合は1日6500円
通院の場合は1日3300円
※幼児・高齢者・身体障害者等で必要のある場合
入院雑費:1500円(1日あたり)
装具・器具購入費:車いす・義足・義歯・入れ歯・補聴器・義眼・かつら等の購入費・処置費などの相当額。
交通費:本人分の実費(原則として)
子供の保育費・学習費等:実費相当額
弁護士費用:裁判所により認容された金額の1割程度
※訴訟になった場合
休業損害:事故前の収入を基礎として、ケガによって休業したことによる現実の収入減分
入通院慰謝料:入通院した日数によって慰謝料を算出する
③後遺障害が残った場合に請求できる損害賠償項目と金額
ケガの治療を続けても、これ以上の改善は見込めない、完治は難しいという場合、医師から「症状固定」の診断を受けることになります。
すると、後遺症が残ってしまうので、被害者の方はご自身の後遺障害等級認定の申請をする必要があります。
【参考情報】国土交通省「自賠責後遺障害等級表」
そして、後遺障害等級が確定すると、次のような項目を請求することができます。
将来介護費:看護師・介護福祉士等/実費全額
近親者/常時介護が必要な場合は1日8000円
※平均寿命までの期間について、中間利息を控除した金額
家屋・自動車等の改造費:自動車・自宅の出口・風呂場・トイレなどの改造費、介護用ベッド等の購入費の実費相当額
逸失利益:事故前の収入額に、労働能力喪失率、就労可能年数、中間利息の控除分をかけた金額
後遺障害慰謝料:認定された後遺障害等級によって金額を算出する
④死亡事故の場合に請求できる損害賠償項目と金額
被害者の方が死亡した場合、次のような損害賠償項目を請求することができます。
葬儀関係費:自賠責保険では定額で60万円、任意保険は120万円以内が大半
逸失利益:生きていれば得られたはずのお金
死亡慰謝料:被害者の方の家庭内での立場によって変わる
| 被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |
|---|---|
| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |
| 被害者がその他の場合 | 2000万~2500万円 |
- 被害者が一家の支柱の場合
- 2800万円
- 被害者が母親・配偶者の場合
- 2500万円
- 被害者がその他の場合
- 2000万~2500万円
弁護士費用:裁判をした場合
その他:実際にかかった治療費、付添看護費、通院交通費
※被害者の方が治療後に亡くなった場合
(5)示談条件で注意するべきポイント
示談を成立させるには、その条件をあらかじめ決めておくことも大切です。
①「示談金の支払い方法」
・示談金の支払いは一括か、それとも分割か。
・振込先の銀行等の口座の確認。
②「示談金の支払い期限」
・いつまでに支払いを完了するか。
③「支払いが遅れた場合の罰金等」
加害者が任意保険に加入しているなら、示談成立から約2週間~1か月程度で保険会社から示談金が振り込まれるので問題はないはずです。
しかし、加害者と直接のやり取りでは、期日までに支払わない、という問題が起きてくる可能性があるので、まずは示談書にしっかり明示しておくことが大切です。
④「清算条項と留保条項」
示談書に記載されているもの以外の金額については請求しない、というのが清算条項です。
つまり、あとから新たな損害賠償項目や金額があることがわかっても、加害者側には請求できないので注意してください。
留保条項とは、示談成立後に新たな損害が発覚した場合、損害賠償金額についてはあらためて双方で協議する、というような条項です。
たとえば、被害者が子供の場合、成長にともなって後遺障害の状態が変化していき新たな障害が発生したり、数年後に再手術が必要な場合があるため、現時点では症状固定とはできない場合などに、こうした留保条項を設定しておく場合があります。
示談交渉で起こりがちな7つのトラブルを解説
交通事故の示談交渉が、何の問題もなく進んでいけばいいのですが、現実的にはさまざまな問題が絡んで、すんなりとは進まないこと多くあります。
ここでは、どのようなトラブルが起きがちなのか、そしてその解決法などについて、お話ししていきます。
(1)治療費の支払いを打ち切られるトラブル
ケガの治療を続けていると、保険会社の担当者から、「そろそろ症状固定としてください。このあたりで治療費の支払いを打ち切ります」と言われる場合があります。
加害者側の任意保険会社は、自賠責保険の範囲内(後遺症のないケガの場合は120万円)であれば、病院に治療費を支払ってくれる「内払い制度」があるため、多くの場合で被害者の方は治療費を支払わなくても済みます。
しかし、たとえば、むち打ち症のケガの場合、治療期間が5か月から6か月頃になると、「自賠責保険の範囲内を超えてくる」「ケガが完治せず症状固定の診断が出る」という時期になってくるので、治療費の支払い停止を言われることがあるのです。
被害者の方としては、驚き、困惑すると思います。
また、「リハビリも必要なのに、やるなということか!」と怒りを感じる方もいらっしゃるかもしれません。
こうした場合に備え、次のことを知っておいてください。
・保険会社のいうことを、そのまま鵜呑みにしない
・症状固定の診断は、あくまでも医師が行なうもの
・医師からの診断がなければ、治療を継続するべき
・それでも治療費の支払いを打ち切られた場合は、自分で支払う
・あとから行なう示談交渉で、その治療費分も請求する
(2)過剰診療を疑われるトラブル
「治療期間が長いのは、必要以上に通院して治療を受けているからなのではないですか?」
「治療費の支払いを打ち切らせてもらいます」
このように、加害者側の保険会社から、「過剰診療」と判断されてしまう場合があります。
そうなると、治療費を打ち切られてしまい、被害者ご自身で支払っていくことになるので注意が必要です。
重要なポイントは、次の2点です。
・通院の必要性:通院して治療を受けることで、ケガの状態がよくなる(改善効果がある)こと
・通院の相当性:通院して受ける治療の内容、通院の頻度が適正であること
これらを証明していく必要があります。
詳しい解説は、こちらを参考にしてください。
【入通院慰謝料】交通事故のケガの治療で注意したい「過剰診療」のポイント
(3)後遺症と交通事故の因果関係でのトラブル
ケガの治療を続けても、完治しない場合は医師から症状固定の診断があり、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。
後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受け、それをもとに慰謝料などの損害賠償金(示談金)の額が算定されていきます。
その際、被害者の方の後遺症と交通事故との因果関係が争いになる場合があります。
たとえば、被害者の方が交通事故によって脳に損傷を受け、うつの状態を発症したが、じつはもともと、うつの気質があったため、交通事故とは因果関係がない、と否定されるケースがあります。
腕や足、首、腰などに運動障害の後遺症が残ったが、じつは今回が2度目の交通事故で、1回目の交通事故ですでに負っていた後遺症なのではないか、として因果関係を疑われるようなケースもあります。
また、特に脳の損傷による高次脳機能障害では、さまざまな後遺症が発症し、時間が経過してから後遺症が現れることもあるので判断が難しく、争いになるケースが多いといえます。
こうしたケースでは、後遺症と交通事故の因果関係をていねいに立証していくことが大切になります。
(4)示談成立後に新たな後遺障害が判明するトラブル
前述したように、一度、示談が成立してしまうと、あとからその内容を変更したり、示談交渉を再開することは基本的にできません。
これは前述したように、示談書に「清算条項」があるからです。
しかし、示談成立後に新たな後遺障害がわかったり、発生したりすることもあります。
そうした場合、どうすればいいのかというと、そのために「留保条項」を設定しておきます。
また、錯誤といって、示談内容を誤って理解したまま合意してしまったというような場合は、示談を取り消して、再び示談交渉を始めることができる可能性もあります。
ただし相手側は、それをすんなり認めることは少ないでしょうから、このような時は一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
(5)被害者の苦痛がより大きいと場合のトラブル
精神的苦痛がより大きい状況なのに、慰謝料などの増額がないというような場合、被害者の方としては納得がいかないということになるでしょう。
たとえば、次のような状況が考えられます。
・無免許、飲酒運転、著しいスピード違反、赤信号無視など加害者の悪質な運転・行為が原因の交通事故
・加害者が、ひき逃げをして被害者を救助しなかった場合
・交通事故後、加害者が被害者のご遺族に対して暴言を吐いたり、反省の態度がまったく示さないような場合
被害者の方やご遺族としては慰謝料などの増額を望む場合もありますが、加害者側の任意保険会社がそれを受け入れないケースは、残念ながら多くあります。
また、次のように被害者側に特別な事情があるケースもあります。
・交通事故による傷害(ケガ)のため、人工妊娠中絶を余儀なくされた場合
・外貌醜状などの傷害によって婚約破棄となった、将来の夢をあきらめざるをえなくなった、仕事を続けることが困難になった、といったような場合
・被害者の方の死亡や傷害によって、その親族等が精神疾患などを発症したような場合
これらのようなケースでは、被害者の方がお一人で対応していくのは難しいので、無料相談などを利用して弁護士とコンタクトをとることも検討するといいでしょう。
(6)過失割合とトラブルで示談金額で合意できない
被害者側と加害者側の争点で、もっとも大きな原因となるのは、示談金額が合意に至らないことです。
被害者の方は、ケガや後遺症によって精神的、肉体的に苦しみ、損害を受けています。
その賠償を求めるのは当然のことであり、できるだけ高額な示談金(損害賠償金)を受け取りたいと思われるでしょう。
一方、加害者側の保険会社は営利法人であるため、利益を出すことが目的となります。
被害者の方への示談金は支出となるので、これをできるだけ低く抑えようとします。
つまり、両者にとって求めることは、まったく真逆であるというわけです。
そうした両者が話し合いをして解決しようとするのですから、当然のように上手くは進まないということになります。
その争点のひとつが「過失割合」です。
過失割合というのは、その事故について、どちらにどのくらいの過失があるのかを決めることです。
たとえば、慰謝料などの損害賠償金額を算定したところ1000万円であり、加害者の過失が7、被害者の過失が3であった場合、被害者の方は700万円しか受け取ることができなくなります。
また、慰謝料や休業損害、逸失利益などの各項目についても加害者側の保険会社は有利になるように、低い金額を被害者の方に提示してきます。
そこで被害者の方が、「その金額はおかしい。納得がいかない。正しい金額を提示してほしい」と主張しても、保険会社はそれを認めることは少ないでしょう。
なぜなら、裁判にならなければ慰謝料などの損害賠償金を増額しなくても問題ないと考えているからです。
(7)消滅時効で慰謝料が消えるトラブル
被害者の方が行なう損害賠償請求には「時効」があります。
この期限を過ぎてしまうことを「消滅時効」といい、その後は法的に、一切の請求ができなくなってしまいます。
受けとるはずだった慰謝料などの損害賠償金が受け取ることができなくなる、0円になってしまうというのは、とても恐ろしいことではないでしょうか?
示談交渉がまとまらずに長引いてしまっている場合などは注意をして、期限内に示談を成立させていくことが大切になってきます。
示談トラブル時の弁護士への賢い依頼の仕方
ここまで見てきたように、示談交渉を被害者の方が単独で行なって、正しい示談金を受け取るには、さまざまなトラブルや難問、課題があることがわかりました。
そうした時、頼りになるのが、交通事故に強い弁護士の存在です。
弁護士に相談・依頼というと、「どうしても気が引けてしまう」、「そこまで大げさにしたくない」、「高い弁護士費用がかかってしまうのではないか」などと考える方が今でも多いようですが、じつはそんなことはないのです。
弁護士費用について正しい事実を知っていただきたいと思います。
みらい総合法律事務所でもそうですが、今では、着手金を原則無料としている法律事務所も増えています。
そのような事務所を探しましょう。
また、ご自身やご家族が契約している保険の「弁護士費用特約」を上手に使う方法も合わせて知っておくと、いざというとき役に立ちます。
本来、被害者が負担するべき弁護士費用を保険金で支払ってくれるものです。
詳しい解説は、ぜひこちらをご覧ください。
交通事故の被害者が知らないと損する弁護士費用の3つの知識