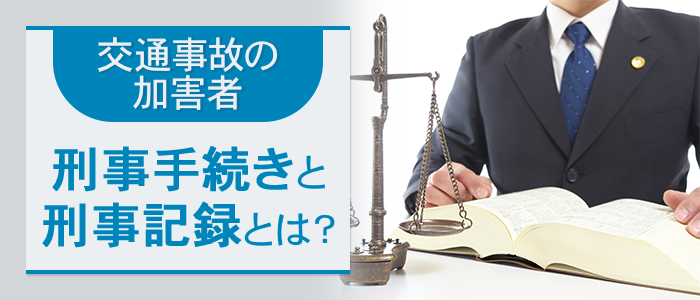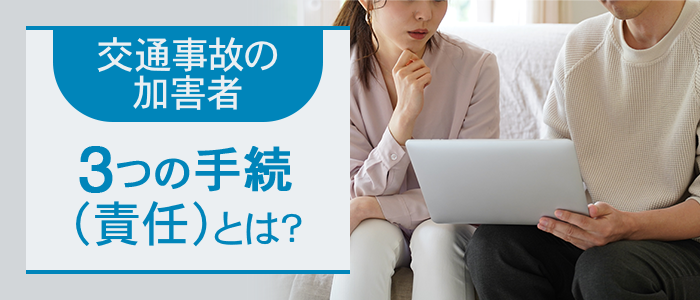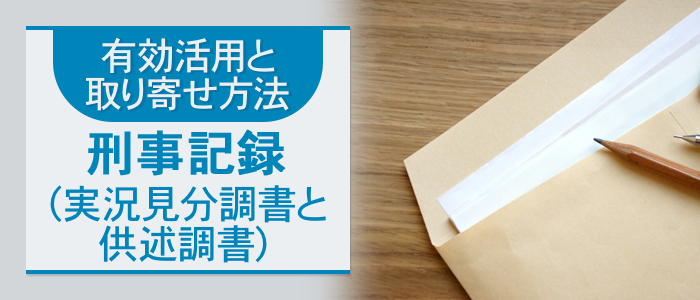交通事故の加害者の刑事手続きと刑事記録とは?
*タップすると解説を見ることができます。
人身事故の場合、被害者と加害者が存在します。
被害者の方が傷害(ケガ)を負ったり、亡くなった場合は犯罪が成立する可能性があり、加害者には刑事手続が進行していきます。
損害賠償問題の解決があるので、被害者の方は民事手続に関わりますが、刑事事件は国が加害者を裁くことになるため原則として、被害者の方は関わりません。
しかし、実は一定の場合に被害者が加害者の刑事裁判に参加できる「被害者参加制度」があります。
また、刑事裁判で重要になる「刑事記録」は民事においても大切な証拠となります。
そこで本記事では、加害者の刑事手続と刑事裁判の内容や流れ、さらには被害者参加制度とそこで必要な刑事記録などについて解説していきます。
目次
交通事故の加害者に発生する3つの手続(責任)とは?
交通事故を起こした場合、加害者には次の3つの手続(責任)が発生します。
(1)刑事手続(刑事上の責任)
刑事上の責任とは、加害者が法令上、定められた犯罪行為を行なったとして刑罰を受けることで、次のようなものがあります。
| 道路交通法違反 | 信号無視、スピード違反、無免許運転などの違反をした場合 |
|---|---|
| 過失運転致死傷罪 | 交通事故で他人にケガを負わせた場合、あるいは死亡させた場合 |
| 危険運転致死傷罪 | 自動車運転過失致死傷罪の中でも特に悪質な交通事故の場合 |
なお刑事罰には、罰金刑、拘禁刑があります。
(2)民事手続(民事上の責任)
民事上の責任とは、「自動車損害賠償保障法」に基づく運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)、「民法」に基づく不法行為責任(民法709条)、使用者責任(民法715条)などの責任をいいます。
交通事故を起こすと、加害者(運転者)は被害者に対して不法行為が成立し、被害者が被った損害を賠償しなければならない義務が発生します。
賠償の対象となる損害には、人身損害と物損害があり、人身損害にはケガの治療費や慰謝料、逸失利益、将来介護費用などさまざまな項目があります。
民事では、示談により解決する場合と調停や訴訟により解決する場合があります。
加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社から損害賠償金(示談金)の提示があり、示談成立となると損害賠償金が被害者の方に支払われます。
(3)行政手続(行政上の責任)
行政上の責任とは、免許の停止や取消しの処分です。
これら3つの手続(責任)は、それぞれは別々の制度のため、たとえば刑事処分を受けたから民事上の責任を免れる、ということはありません。
また、行政処分を受けて反則金を支払ったからといって、刑事処分を免れるわけではないですし、民事裁判で損害賠償責任が認められても、刑事裁判では不起訴や無罪になることもあるのです。
刑事事件の手続きと流れについて
通常、加害者の刑事事件は次のようなプロセスで進行していきます。
- 交通事故の発生
- 警察による実況見分
- 警察による取り調べ
- 実況見分調書などの作成
- 検察庁での取り調べ
- 検察官による起訴・不起訴の判断
- 起訴の場合は略式裁判か正式裁判かの判断
(1)交通事故の発生
交通事故が発生した場合、道路交通法では、次の2つのことが義務づけられています。
①負傷者の救護
ケガをした人がいれば、運転者は直ちに運転を止めて、負傷者を救護しなければなりません。
救護しないで逃げた場合は、いわゆる「ひき逃げ」ということになります。
同時に事故車両を安全な場所に移動させて、道路上の危険防止の措置を取らなければなりません。
②警察に通報
事故を警察に通報します。
警察への通報を怠れば、道路交通法違反となります。
(2)警察による実況見分
通報があると警察が現場に急行し、事故の捜査(実況見分)が行なわれます。
実況見分は強制ではなく任意捜査ですが、加害者、被害者ともに立ち合い、それぞれの主張を述べます。
事故の状況にもよりますが、実況見分は数十分から2時間程度と考えておくといいでしょう。
(3)警察による取り調べ
実況見分の後は警察署に移動し、聞き取り捜査が行なわれます。
交通事故で被害者にケガをさせた場合には刑事事件になり、加害者逮捕となる可能性があるからです。
ちなみに、加害者が逮捕されて捜査が行なわれる場合を身柄事件といい、逮捕されない場合を在宅事件や在宅捜査といいます。
在宅事件であっても、加害者は警察や検察の捜査に協力する必要があります。
しっかり対応しないと、証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性もあります。
なお、被害者の方が病院に搬送された場合は後日、聞き取りが行なわれます。
(4)実況見分調書などの作成
・ここまでの捜査内容を総合して、事故の状況を明らかにするために警察官が「実況見分調書」や「供述調書」を作成します。
①実況見分調書とは?
実況見分調書には次の内容などが記載されます。
- 実況見分の日時・場所・立会人名
- 現場道路の状況
- 運転車両の状況
- 立会人の指示説明(最初に相手を発見した地点、ブレーキを踏んだ地点、衝突した地点など)
※実況見分調書には、さらに事故現場の見取図や写真等が添付されます。
刑事事件では、もっとも重要な証拠の一つとなるのが実況見分調書で、検察が起訴するかどうか、また刑事裁判になった場合の量刑の決定にも関わってきます。
さらに、のちの示談交渉や民事裁判でも過失割合における大きな証拠や判断材料にもなるので、非常に重要なものです。
②供述調書とは?
警察が加害者と被害者双方に聞き取り調査を行ない作成するのが供述調書です。
供述調書は、実況見分調書と同様に刑事事件や民事訴訟において事故の状況を明らかにするために、その証拠として利用されます。
また、供述調書の作成には加害者が虚偽の申告をすることを防ぐという目的もあります。
たとえば加害者は事故直後の供述から一転して、刑事裁判では自分の過失などを否認する場合があり、そこでの重要な証拠となるのです。
死亡事故の場合は被害者の方が亡くなっているため、ご遺族が聞き取り調査を受け、遺族調書が作成されます。
遺族調書では、亡くなった方の生前の様子や加害者に対する処罰感情などについて聞き取りが行なわれるので、素直に思いを話されるといいでしょう。
③供述の際に注意するべきポイント
実況見分調書や供述調書は事故の状況を明らかにする公的な書類であるため、刑事手続だけでなく、この後の民事手続での示談交渉の際でも、加害者と被害者の過失割合を判断する資料になる重要な書類です。
ですから、供述する際は必ず記憶に基づいて正確に証言をする必要があります。
注意するべきは、警察官が推測に基づいて事故の状況について誘導的に質問する場合があることです。
その誘導に乗って、被害者の方が不利な証言をしてしまい、その内容が実況見分調書に記載されてしまうと、あとから覆すのは非常に難しくなるので十分注意してください。
(5)検察庁での取り調べ
警察の取り調べが終わると事件が検察庁に送致され、検察庁による取り調べが行なわれます。
(6)検察官による起訴・不起訴の判断
検察庁による取り調べが終了すると、検察官は起訴するか、不起訴にするかを判断します。
起訴とは、刑事事件を起こした被疑者について刑事裁判を開いて刑罰を決定するため、検察官が裁判所に訴えを起こすことです。
一方、不起訴とは検察官が被疑者を起訴しないという決定をすることです。
不起訴処分になると被疑者は刑事裁判にかけられることがなくなり、それまで勾留されていた場合は身柄を解放されます。
また、被疑者は有罪になる可能性がなくなります。
- 起訴か不起訴かの判断の際、加害者は検察から呼び出しを受け、取り調べを受けることがあります。
再度、検察官から詳しい事故の状況などについて聞かれることになりますが、この呼出は無視したり拒否しないほうがいいでしょう。
検察官の心証が悪くなりますし、証拠隠滅や逃亡を疑われ、逮捕されるケースもあるからです。
(7)起訴の場合は略式裁判か正式裁判かの判断
検察官が加害者を起訴する場合には刑事裁判が行なわれ、被疑者は「被告人」になります。
その際、略式裁判か正式裁判かを決めます。
正式裁判は通常の刑事裁判手続というべきもので、法廷で行なわれます。
略式裁判は文字通り手続が簡略化された裁判で、被告人には書面で処分が言い渡されます。
略式裁判は、一定額の罰金、または科料を科す裁判で、被告人の同意が必要になります。
検察庁:刑事事件の手続について
刑事裁判(正式裁判)の内容と流れを確認
(1)正式裁判について
正式裁判では、加害者が有罪か無罪か、有罪の場合にはどの程度の刑罰を科すかについて審理がなされます。
正式裁判は、起訴されてから1か月半程度で開かれるケースが多いといえます。
加害者が罪を認めている場合は、1回で審理は終了し、2回目の期日に判決が下されることになります。
刑事裁判の流れは、大きく4つに分けられます。
(2)冒頭手続とは?
刑事裁判は、まず冒頭手続が行われます。
冒頭手続は次のような内容と流れで進んでいきます。
・加害者を特定するための手続
↓
・検察官が起訴状を朗読
↓
・裁判官から加害者に対して黙秘権の告知
↓
・加害者が罪を認めるかどうかをという罪状認否の手続
↓
・裁判官が弁護人に意見を聞き、弁護士が意見を述べる
※ここで、加害者の主張が明らかになる。
(3)その後の手続(証拠調べ⇒弁論⇒判決言渡し)
※まず検察官が立証活動を行ない、その後に弁護側が立証活動を行なう。
↓
③弁論
※検察官が論告求刑を行ない、弁護人が最終弁論を行なう。
※被告人が最終意見陳述を行なって結審。
↓
④判決言渡し
※後日、裁判所による判決が下される
裁判所:刑事事件
加害者に科される刑罰について
略式裁判の場合は、一定額の罰金を支払うことになります。
一方、正式裁判になる場合は、拘禁刑になるのが一般的です。
なお、拘禁刑の判決が出されたうえで、執行猶予を言い渡されることがあります。
執行猶予では、刑罰の執行を猶予し、一定期間を経過すれば言い渡された拘禁刑が消滅するということになります。
この場合、加害者は刑務所に入らなくていいということになります。
検察庁:裁判の執行等について
危険運転致死傷罪ではもっとも重い刑罰が科せられ、致傷の場合は拘禁刑15年以下、死亡の場合は20年以下の拘禁刑です。
過失運転致死傷罪では、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となっています。
被害者参加制度の利用を検討している方へ
(1)被害者参加制度とは?
前述したように、刑事事件は国家と加害者が当事者になるため、原則として被害者の方やご遺族は直接関与することはありません。
しかし、交通事故の実際の状況や加害者がどのような供述をしているのか知りたい、刑事裁判に直接参加して被害者としての感情や意見を述べたい、加害者(被告人)に質問したい、という方のために「被害者参加制度」というものがあります。
被害者参加制度は、2008年12月1日から導入されました。
次のような一定の刑事事件(重大犯罪)が対象になります。
- 殺人、傷害、危険運転致死傷などの故意の
犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件 - 強制性交等・強制わいせつ、逮捕・監禁、
過失運転致死傷などの事件
(刑事訴訟法290条の2)
(2)被害者参加の手続きについて
刑事事件に被害者参加を希望する場合は、あらかじめ事件を担当する検察官に申し出ます。
検察官は、その申し出に対して意見を付して裁判所に通知します。
裁判所は被告人や弁護人の意見を聴き、犯罪の性質や被告人との関係、その他の事情などを考慮し、相当と判断した場合に希望者は被害者参加人として刑事裁判に参加することができます。
(3)誰が刑事裁判に参加できるのか?
被害者参加制度を利用できるのは次のような人たちです。
- 被害者の方
- 配偶者
- 直系の親族
- 兄弟姉妹
- 被害者の法定代理人(親権者、後見人) など
(4)被害者参加人ができることとは?
被害者参加をすると次のようなことができます。
- 原則、公判期日には法廷で裁判に出席することができる(検察官席の隣などに着席する)。
- 検察官の訴訟活動(証拠調べの請求や論告・求刑など)に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めることができる。
- 証人尋問をすることができる(情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項など)。
- 被告人に質問することができる(意見を述べるために必要と認められる場合)。
- 証拠調べが終わった後は、事実または法律の適用について法廷で意見を述べることができる。
法務省:公判段階での被害者支援
(5)被害者参加のメリット
①刑事裁判前の刑事記録の閲覧謄写
刑事事件では、捜査段階で被害者側に事故の詳しい状況や加害者の供述内容などが明かされることは少ないのが現実です。
そのため通常は、被害者の方は事故の内容を詳しく知ることができず、刑事裁判の法廷で加害者側がどのような供述しているかなどを初めて知ることができます。
そこで被害者参加をすれば、第1回公判期日の前に、刑事記録(実況見分調書や供述調書)の閲覧謄写が可能になります。
被害者の方としては、公判期日の前に刑事記録を閲覧することで、裁判で加害者の供述の嘘や矛盾を追求することができる可能性があるのです。
②裁判官に直接訴えることができる
刑事事件で加害者が罪を認めているような場合では、通常、検察官の立証は書類のみを裁判所に提出することが多いので、裁判官は書面だけを見て被害者の感情などを知ることになります。
しかし、実際の裁判の現場で被害者の方が意見を陳述することができれば、供述に迫真性があり、リアルな感情を裁判官に伝えることが可能になるのです。
刑事記録(実況見分調書と供述調書)の有効活用と取り寄せ方法
(1)刑事記録は民事でも有効に活用できる
前述したように、実況見分調書や供述調書などの刑事記録を閲覧することは刑事裁判において被害者の方にメリットがあります。
しかし、刑事記録の閲覧のメリットはそれだけではありません。
民事における交通事故の損害賠償では、過失割合が大きな争点になる場合があります。
過失割合とは、事故についての加害者と被害者の過失(責任)の割合のことで、その割合に応じて損害賠償金を減額することを過失相殺といいます。
たとえば、損害賠償金額が1,000万円で、加害者と被害者の過失割合が8対2の場合、被害者の方は2割減額された800万円を受け取ることになります。
一方、たとえば加害者が高級車だった場合などで損害額が500万円だった場合、被害者の方は2割の100万円を支払わなければならなくなってしまいます。
交通事故の損害賠償実務では、過失割合を決めるために加害者の刑事事件記録の取り寄せが行われます。
民事裁判になった場合、基本的に裁判所は実況見分調書に則って過失割合を認定します。
加害者側から不当に過失相殺を求められた場合などでは、刑事記録が大きな証拠になるのです。
また、被害者、加害者、目撃者の供述調書が取り寄せできる場合があります。これも交通事故状況や飲酒の有無、スピードオーバ-などを立証する証拠になります。
(2)刑事記録の取り寄せ方法
①加害者起訴の場合
交通事故の加害者が起訴され、公判係属中であれば、刑事事件が係属する裁判所に対して「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき申請をします。
加害者が起訴(略式含む)され、判決が確定した後は、検察庁に対する閲覧・謄写の申請をします(刑訴法53条)。
②加害者不起訴の場合
検察庁に対する実況見分調書等の閲覧、謄写の申請や、「弁護士法23条の2」による照会で取り寄せることができます。
③その他の場合
少年が交通事故を起こして少年事件になった時は、「少年法5条の2」に基づき家庭裁判所に申請します。
物損事故の場合は、警察署に対する「弁護士法23条の2」の照会により、「物件事故報告書」の取り寄せを行ないます。
いずれにしても、被害者参加制度への申請や刑事記録の取り寄せは被害者の方やご家族にとっては難しく、精神的な負担にもなってしまうので、交通事故に精通した弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
交通事故相談SOSでは
交通事故の知識を解説しています