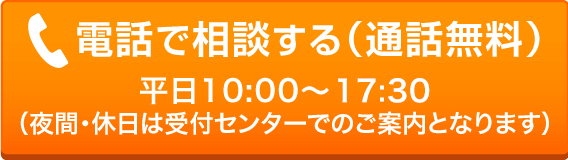従業員が加害者の交通事故で、会社にも損害賠償を請求できるか?
*タップすると解説を見ることができます。
使用者責任
任意保険に加入している場合
交通事故の被害を受けた場合、治療費や休業損害、慰謝料など、様々な損害が発生します。
その損害が発生した原因が加害者の過失にある場合には、その損害は加害者側が負担するべきということになります。
これが、民事の損害賠償の問題です。
損害額は、治療が終了した時点で確定します。そこで、治療が終了した後には、示談交渉をして、損害賠償金を受け取ることになります。
多くの場合には、加害者が任意保険に加入しているため、任意保険会社と示談交渉をすることになります。
任意保険会社は、賠償金を支払う十分な資力がありますので、対人賠償の保険金額が無制限であれば、最終的に回収できない可能性は少ないでしょう。
任意保険に加入していない場合
ところが、中には、任意保険に加入していないケースがあります。
この場合には、自賠責保険に請求した後、不足する損害額について、運転手本人に請求することになります。
しかし、特に怪我が重傷で後遺症が残ったような場合には、賠償額が高額になります。個人の場合には、資力に不安があるケースが多く、他のより資力を有する者に請求できないか、問題となります。
そこで、今回は、会社従業員の交通事故に関する使用者会社の責任について、弁護士が解説します。
民法715条は、
と規定され、雇い主の使用者責任を定めています。
従業員が会社の自動車で業務中に交通事故を起こした場合、会社に使用者責任が認められれば、会社にも損害賠償を請求することができます。
使用者責任が認められるためには、従業員の行為に関して不法行為責任が成立していること、およびその行為が事業の執行についてなされた行為であることが必要となります。
ただし、右に該当する場合でも、使用者が被用者の選任及び監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生じたという場合には、使用者は責任を免れます(民法715条ただし書)。
被用者の選任及び監督について、故意・過失がなかったことの立証は、使用者が行わなければなりません。
自賠法に基づく損害賠償責任
交通事故を起こした自動車が会社の所有する自動車である場合、会社には、使用者責任とは別に、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任も発生します。
運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことで、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者のことを言います。
従業員が業務のために自動車を運行している場合は、通常、会社に自動車の使用についての支配権及び利益の帰属が認められるので、運行供用者に該当することになります。
したがって、会社は、その交通事故に関して、
- ①自己及び運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと
- ②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- ③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと(自動車損害賠償保障法3条ただし書)
をすべて証明できない限り、運行供用者としても責任を負いますので、被害者は会社に対し損害賠償を請求することができます。
自賠責保険の請求手続や提出書類については、以下を参考にしてください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/kind.html
従業員の無断運転に関する
最高裁判例
ここでは、従業員の無断運転に関する最高裁判例を3例解説します。
使用者責任を認めた最高裁判例
従業員が無断で会社の自動車を運転して交通事故を起こした場合に、会社に使用者責任が発生するか、が争われた裁判例があります。
最高裁昭和39年2月4日判決です。
この事案は、自動車等の販売等を業とする会社の従業員が、日常的に業務に執行に使用していた会社所有の自動車を、私用に使うことが禁止されていたにもかかわらず、自宅への帰途に使用中、交通事故を起こしたものです。
最高裁は、「民法715条に規定する『事業ノ執行ニ付キ』というのは、必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合だけを指すのではなく、広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合でも足りる」として、使用者責任を認めました。
運行供用者責任を認めた
最高裁判例
従業員が会社に無断で会社の自動車を運転している途中で交通事故を起こした場合に会社が自賠法第3条の運行供用者を負うか、が争われた最高裁判例があります。
最高裁昭和39年2月11日判決です。
事案は、終業時にいったん自動車を会社の車庫に納め、鍵を返還したが、相撲大会に参加しようとしたところ、汽車に乗り遅れそうになったため、上司に無断で鍵を持ち出し、その帰途に交通事故を起こした、というものです。
最高裁判所は、
- ①自動車の所有者と第三者(運転者)との間に雇用関係等密接な関係があること
- ②日常の自動車の運転状況
- ③日常の自動車の管理状況
などから、客観的外形的に所有者のためにする運転と認められる場合には、所有者は運行供用者責任を負う、としました。
また、最高裁昭和49年11月12日判決は、元従業員が、会社を退職した翌日に、エンジンキーを差し込んだままにして、ドアに施錠しないまま駐車してあった会社所有の自動車を無断で運転して交通事故を起こした事案について、会社の運行供用者責任を認めました。
【参考情報】こちらで裁判例が検索できます:「裁判例検索」裁判所HP
運行供用者責任を否定した
最高裁判例
反対に、使用者責任を否定した最高裁判例もあります。
事案としては、会社の従業員が会社所有の自動車を私用のため無断運転中惹起した事故により同乗者を死亡させたことから、被害者の相続人が加害者に対し、損害賠償請求をした、というものです。
最高裁は、同乗者が、会社によってその自動車を私用に使うことが禁止されていることを知りながら、無断持出しを一旦思いとどまった従業員をそそのかして、同人ともども夜桜見物に出かけるため自動車に同乗したものである等判示の事実関係のもとにおいては、事故により同乗者及びその相続人に生じた損害につき、相続人は、会社に対し自動車損害賠償保障法3条に基づく運行供用者責任を問うことができない、としました。
マイカーによる交通事故
多くの会社では、マイカーの業務使用を認めていません。交通事故があった時に、使用者責任として会社の損害賠償責任が発生するため、業務に使用する自動車の任意保険を管理しなければなりませんが、個人所有の自動車では、任意保険の管理が難しいためです。
会社がマイカーの使用を禁じたにもかかわらず、従業員がマイカーを使用中に交通事故を起こした場合には、原則として、会社に損害賠償請求をすることはできません。
しかし、会社が積極的にマイカーの使用を命じたり、あるいは許可しているような場合、黙認しているような場合には、会社もマイカーに対して運行支配・運行利益を有していると言えますので、会社の損害賠償責任が発生する場合が多いでしょう。
過去の裁判例では、次のようなものがあります。
しかし、一部の従業員は、自家用車で通勤し、自分の乗る営業車の駐車位置に駐車するなどして営業所構内に自車を置いており、会社の担当者もこのことを知っていましたが、自家用車による通勤を控えるように指導したり、あるいは届けをさせることもなく、事実上黙認していた、という事案です。
裁判所は、「被告会社は、従業員の自家用車による通勤を事実上黙認していたに過ぎず、同社の業務に使用したり、自家用車による通勤を指示、奨励したこともなく被告川畑は自己の個人的な便宜のため通勤に加害車を使用したものであると認められる。これに、前記本件事故に至る経緯等を併せ考慮すると、被告会社が、本件事故当時の加害車について、運行の支配やその利益を有していたとは到底認めることはできない。」として、会社の運行供用者責任を否定しました。
また、「本件事故当時の加害車の運転行為が被用者の職務執行行為そのものに属するものでないのはもちろん、その行為の外形から観察してあたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものと認めることもできず、被告会社か使用者責任を負うべきものと認めることはできない。」として、使用者責任も否定しました。
【大阪地裁平成2年2月2日判決(判例タイムズ717号177頁)】
使用者の従業員に対する求償
従業員が会社所有の自動車を運転中に交通事故を起こした場合、使用者責任や自賠法により会社に損害賠償請求をされることがあります。
そして、会社が被害者に対して損害を賠償することがありますが、この場合、事故を起こしたのは従業員なので、損害を賠償した会社が従業員に対して求償できるか、という論点があります。
この点について判断した裁判例に、最高裁昭和51年7月8日判決があります。
最高は、使用者の従業員に対する求償を認めたものの、以下のように述べて、損害の全額ではなく、一部のみを認めました。
最高裁は、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」として、損害の4分の1の求償を認めました。
代表社員 弁護士 谷原誠

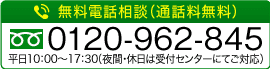

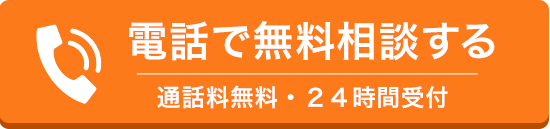







の後遺障害等級.png)