交通事故の通院をやめるタイミングとは?慰謝料で損をしない方法を解説
交通事故で負傷した場合は、適切な時期まで通院を続けることが重要です。
自己判断で通院をやめてしまうと、症状が悪化するだけでなく、慰謝料の受取額が減ってしまう可能性もあるので注意が必要です。
本記事では、交通事故による怪我をした際に通院をやめる判断基準と、損をしないためのポイントについて詳しく解説します。
また、保険会社から治療費打ち切りの連絡が来た時の対処法についても解説します。
目次
交通事故の通院をやめるタイミングの目安をケース別に解説
交通事故による怪我の治療を自己判断で中止すると、後遺症が残るだけでなく、十分な補償を受けられないリスクが生じるので気を付けてください。
怪我の治療終了時期は医師が
判断する
交通事故の通院終了の時期は、医師が判断します。
怪我の程度や回復状況に応じて通院期間は異なるため、医師に症状の改善状況や今後の治療の必要性を総合的に評価してもらい、通院の継続が適切かどうかを判断してください。
患者が自己判断で通院を中止すると、後々健康状態が悪化しても補償を受けにくくなる可能性があるので注意が必要です。
また、治療終了時点で痛みや後遺症が残っている場合は、症状固定の判断を視野に入れ、今後の補償や治療方針を慎重に検討することが求められます。
軽傷の通院期間の目安
軽傷の場合、治療期間は数週間から数か月程度が一般的です。
打撲や軽度のむち打ち症は、適切な治療を受ければ比較的短期間で改善することが多く、医師の診断をもとに通院終了の判断を行います。
治療の途中で症状が軽減したと感じても、急に通院をやめることで後々痛みが再発するケースもあるため、経過観察を続けながら適切な診療を受けることが大切です。
重傷の通院期間の目安
重傷の場合、治療は長期間にわたることが多く、通院の継続が不可欠です。
骨折や神経損傷を伴う外傷では、回復までに数か月から年単位の治療が必要となる場合があります。
また、事故前の状態に戻すには適切なリハビリが欠かせないため、骨折などが治った後も、医師の指示のもとでリハビリを継続することが推奨されます。
通院期間は慰謝料の算定にも影響を及ぼすため、適切な診療を受けながら治療終了の時期を慎重に判断してください。
症状固定の診断には通院が
不可欠
症状固定の診断を受けることは、治療をやめるタイミングの一つとなります。
症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態をいいます。
つまり、後遺障害が残ってしまった、ということを意味します。
交通事故で後遺障害が残った場合、加害者に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することになりますが、後遺障害と認められるには症状固定の診断が不可欠です。
しかし、一定期間通院を続けていないと、医師に症状固定の診断書を発行してもらうことはできません。
自己判断で通院を中止した場合、医師から症状固定の診断書を受け取れず、後遺障害として認められない恐れがあります。
交通事故の被害者が自己判断で
通院をやめるデメリット
交通事故による怪我の治療は、被害者の健康回復だけでなく、慰謝料や後遺障害の認定にも影響を及ぼします。
自己判断で通院を中止すると、適正な補償を受けられなくなる可能性があるため、通院中止によるデメリットを十分に理解しておくことが大切です。
症状の悪化と後遺症のリスク
交通事故後の治療で一時的に症状が改善したと感じても、完全に回復しているとは限りません。
通院を早期に中止すると、十分な治療を受けられず、症状が悪化する可能性が高まります。
特に、痛みや違和感が残る状態で治療をやめてしまうと、後遺症が長期化したり、新たな健康問題を引き起こすことがあります。
事故の影響は時間の経過とともに顕在化することもあるため、医師の診断を受けながら慎重に通院期間を決定することが重要です。
慰謝料・損害賠償金が減額する可能性
治療を途中でやめると医学的な根拠が不足し、症状の継続性を正しく評価できなくなります。
交通事故の慰謝料は、治療期間や通院頻度に基づいて算定されるため、通院日数が短いと補償額が十分に反映されないことがあります。
また、通院を中止すると、加害者側の保険会社が「治療が終了した」と判断し、損害賠償の支払いを打ち切る可能性があります。
さらに、後遺症が後から顕在化しても、通院を中止していれば交通事故との因果関係が否定され、適正な治療費や慰謝料を受けられなくなる恐れがあります。
そのため、こうしたリスクを避けるためにも、医師の診断を受けながら適切な治療を継続することが重要です。
後遺障害の認定と通院期間
後遺障害の認定には、一定の治療期間と診断結果が必要となるため、通院を途中でやめると認定が困難になることがあります。
後遺障害には等級があり、認定された等級によって慰謝料の額が変動します。
通院期間が適正でない場合、後遺障害の等級が低く判定されるだけでなく、後遺障害として認定されない可能性もあります。
自己判断で通院を中止すると、大きな不利益を被るおそれがあるため、治療方針は医師に相談しながら決めなければなりません。
交通事故の通院をやめてしまう
よくある理由と対処法
交通事故による治療は長期間に及ぶことがあり、仕事や生活の負担から通院を途中でやめるケースも少なくありません。
しかし、通院を中止すると、慰謝料の減額や健康状態の悪化につながる可能性があるため、慎重な判断が求められます。
痛みが軽減したと感じた時の
判断ミスを防ぐ方法
交通事故による怪我の治療を続ける中で、ある時点で「痛みが軽減した」と感じることがあります。
しかし、これは一時的な症状の改善である可能性があり、自己判断で通院を中止すると再び症状が悪化する恐れがあります。
事故による怪我は、時間の経過とともに後遺症として現れることも多いため、治療継続の可否は医師の診断や専門的な評価に基づいて決定してください。
仕事や生活への影響で
通院継続が難しい場合の対策
交通事故の治療は、仕事や日常生活に負担をもたらし、通院の継続が難しくなることがあります。
通院頻度が高く業務に支障が出る場合は、職場と相談し、勤務時間の調整やテレワークの活用を検討しましょう。
また、医師に相談して通院頻度を調整することで、仕事や家庭との両立がしやすくなります。
交通事故に伴う治療費や慰謝料の請求は、適正な補償を確保しながら経済的負担を軽減するために重要です。
そのため、必要に応じて弁護士や専門家の助言を受けながら、示談交渉を進めることが求められます。
通院費を払うのが困難に
なった際の対処法
交通事故に遭った場合、治療費は基本的に加害者側が負担します。
しかし、加害者や加害者の保険会社が治療費を十分に払ってくれないケースもあり、治療継続中に通院費の負担が大きくなり、治療を断念せざるを得ないことがあります。
そのような場合は、自賠責保険の仮渡金制度を活用することで、正式に保険金を受け取るまでの出費を補うことができます。
また、加害者側の対応が遅れる場合には、自分の任意保険の人身傷害保障特約や弁護士費用特約を利用するのも一つの選択肢です。
弁護士費用特約は、交通事故の被害者が弁護士費用を負担せずに示談交渉などを進められる制度です。
自動車保険等に特約が付帯されている場合は、弁護士を介して適正な補償を確保しましょう。
保険会社や医療機関との対応に関する注意点
通院期間や治療内容は、保険会社との交渉において重要な要素となります。
自己判断で治療を中止すると、保険会社が「症状が回復した」と判断し、治療費の支払いが終了したり、慰謝料が減額されるおそれがあります。
そのため、治療終了については医師の診断を十分に確認し、保険会社の対応も慎重に検討することが必要です。
一方、医療機関の方針で治療が打ち切られる場合もあるため、必要な治療を継続するには、他の病院や専門医の意見を求めることが有効です。
保険会社との交渉に関しては、専門家の助言を活用し、適正な補償を受けるために慎重な対応を心掛けましょう。
保険会社から治療費打ち切りの
連絡が来た時の対処法
交通事故の治療を続けていると、保険会社から治療費の打ち切りを通知されることがあります。
通知後に適切な対応を取らなければ、必要な治療を継続できなくなる可能性があるため、連絡が来た際の対処法をご紹介します。
保険会社が治療費を打ち切る
理由
保険会社が治療費の支払いを打ち切る理由には、いくつかのパターンがあります。
主なものとしては、「症状が改善し、治療の必要がない」と判断されるケースが挙げられます。
また、事故の影響が軽微とみなされた場合、一定期間が経過すると支払いが終了することも考えられます。
しかし、治療終了の判断が医師の診断ではなく、保険会社独自の基準によって行われるケースもあるため、被害者の実際の治療状況と一致しない場合があります。
保険会社が治療費の支払いを打ち切ると、適切な医療を受けられなくなる恐れがあるため、通知を受けた際は、その理由を明確に確認することが重要です。
必要に応じて医師の診断書を保険会社へ提出し、治療の必要性を証明しながら、適正な治療継続のための対策を講じましょう。
適正な治療期間を主張する
ための準備と交渉方法
保険会社から治療費の打ち切りを通知された場合でも、その場で了承することは避けてください。
適正な通院期間は医師が判断するものであり、保険会社が決めるものではありません。
打ち切りの通知を受けた際は、医師の診断書や治療経過を記録し、現在の症状や今後の治療計画を明示することで、治療継続の正当性を保険会社に説明できるよう準備しましょう。
また、打ち切りの連絡が繰り返される場合は、弁護士や専門家の助言を受けるのも一つの選択肢です。
交通事故の被害者が何度も交渉を重ねることは精神的負担となるため、弁護士を介して対応することで、相手の主張を鵜呑みにせず、適正な治療を継続できます。
保険会社との示談交渉で
押さえるべきポイント
保険会社との交渉では、冷静かつ理論的な対応が求められます。
感情的にならず、保険会社の判断基準を理解した上で、医師の診断や治療経過を根拠に交渉を進めることが重要です。
保険会社が示した治療費打ち切りの理由が曖昧な場合は、弁護士を通じて詳細な説明を求めましょう。
また、保険会社とは示談交渉でも話し合いを行うことになるため、適正な治療を受けるためにも慎重な姿勢で臨み、十分な証拠を揃えて交渉を進めてください。
まとめ
交通事故後の通院をやめる判断は、慰謝料や後遺障害認定に影響を及ぼす重要な決断です。
自己判断で通院を勝手にやめると、適正な補償を受けられなくなる可能性があるため、医師の診断に基づいて慎重に決定することが求められます。
保険会社から治療費の支払い打ち切りの通知を受けても、適切に交渉すれば治療を継続しながら補償を受けることが可能です。
交通事故の示談交渉や手続きには専門的な知識が不可欠なため、弁護士へ相談することで適正な慰謝料や補償を確保しやすくなります。
交通事故のトラブルを円滑に解決するためにも、専門家の助言を活用しながら対応を進めましょう。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠





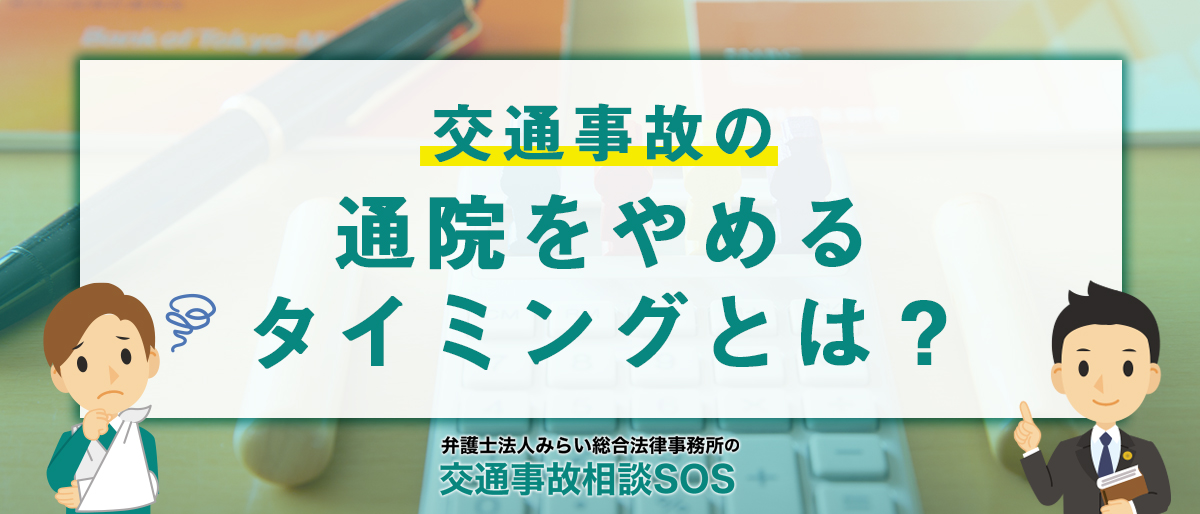











の後遺障害等級.png)


