交通事故による腓骨骨折|治療期間・後遺障害・慰謝料を解説
交通事故によって腓骨(ひこつ)を骨折すると、強い腫れや痛みに加え、歩行困難や関節の可動域制限が生じ、日常生活に大きな支障をきたします。
治療には数か月を要することもあり、後遺症が残った場合には、後遺障害の認定や慰謝料の算定が重要な課題となります。
本記事では、腓骨骨折の原因と症状、治療期間の目安、後遺障害の等級認定、慰謝料請求のポイントまでを体系的に解説します。
目次
交通事故による腓骨骨折とは
腓骨骨折は、歩行や日常生活に深刻な支障をきたす重大な骨折の一つです。
交通事故では、下腿に強い外力が加わることで腓骨が損傷し、長期の治療やリハビリが必要になることがあります。
腓骨の位置と役割
腓骨は、下腿(膝から足首まで)の外側に位置する細長い骨で、脛骨と並んで足首や膝の安定性を支えています。
体重の大部分は脛骨が担っており、腓骨は主にバランス保持や支持の補助的な役割を果たします。
骨折の種類と特徴
腓骨は細くて脆弱な構造のため、交通事故で強い衝撃が加わると骨折しやすくなります。
骨折には、完全骨折、不全骨折、関節内骨折などがあり、完治までの期間は損傷の程度や部位によって異なります。
早期の画像診断によって骨折部位を特定し、適切な治療方針を立てることが重要です。
交通事故で起こる
典型的な骨折ケース
腓骨骨折は、バイクや自転車の転倒、歩行者が車両に衝突された場合などに多く見られます。
側面からの衝撃や足をひねるような動きによって、過度な力が集中することで骨折に至ることがあります。
腓骨骨折の症状と経過
交通事故によって腓骨を骨折した場合、事故前の状態に戻るためには、適切な治療とリハビリが欠かせません。
初期症状としては、患部の腫れ、内出血、強い痛みが現れます。軟部組織の損傷によって炎症が起こり、腫れが数日間続くこともあります。
骨折の程度や部位によっては、足首や膝の可動域が制限され、歩行や立位に支障をきたすことがあるため、早期の画像診断と固定処置が回復の要となります。
保存療法では、ギプス固定中は荷重を避ける必要があり、歩行可能になるまでには通常1〜3か月ほどを要します。
手術療法を選択した場合は、骨癒合の進行に応じてリハビリが開始され、歩行再開までの期間には個人差が出ます。
再開のタイミングは、骨癒合の状態や痛みの程度を踏まえ、医師の指示に従って慎重に判断することが重要です。
腓骨骨折は全治何か月?
治療から復帰までの期間
腓骨骨折の治療期間は、骨折の種類や重症度によって大きく異なります。
保存療法と手術療法の違いを理解し、歩けるまでの期間の目安を把握しておくことが大切です。
治療方法の選択基準
(保存療法と手術療法)
保存療法は、骨折部位が安定している場合にギプスや装具で固定し、自然治癒を促す方法です。
一方、外力によって腓骨に大きな転位(ズレ)が生じた骨折や、関節に影響を及ぼす骨折では、金属プレートやボルトを用いた手術療法が選択されます。
治療法の選択は、骨折の形状、患者の年齢、生活環境、合併症の有無などを総合的に判断して決定されます。
全治までの期間と
歩行開始の目安
腓骨骨折の全治期間は、保存療法で約1〜3か月、手術療法では3〜4か月が一般的です。
初期はギプス固定により荷重を避け、骨癒合の進行に応じて部分荷重から全荷重へと段階的に移行します。
歩行開始の目安は、保存療法の場合は固定後2〜3週間、手術療法の場合は受傷後4〜6週間以降とされており、医師の指示に従って慎重に進める必要があります。
リハビリの流れと復帰の目安
腓骨骨折後のリハビリは、固定解除後に筋力回復や関節可動域の改善を目的として開始されます。
初期は足首や膝のストレッチから始まり、徐々に歩行訓練やバランス強化へと移行します。
日常生活への復帰は、痛みの軽減と歩行の安定が確認された段階で可能となり、一般的には受傷後2〜4か月程度が目安です。
リハビリの継続は、後遺症の予防と機能回復に直結するため、医師や理学療法士の指導のもとで計画的に進めることが重要です。
腓骨骨折で認定される後遺障害等級
腓骨骨折が治癒しても、痛みや可動域制限などの後遺症が残る場合があります。
後遺障害の認定は、慰謝料や損害賠償の金額に直結するため、正確な理解が不可欠です。
後遺障害の対象となる症状
腓骨骨折後に残る症状のうち、医学的に回復が困難と判断されるものは、後遺障害の対象となります。
これらの症状が日常生活や労働能力に影響を及ぼす場合、後遺障害として認定される可能性があります。
腓骨骨折による後遺障害としては、以下の5種類があります。
変形障害
変形障害とは、骨折によって受傷部位に形状の異常が残る状態を指します。
骨が不正な形で癒合した場合、外見上の変形や偽関節(関節ではない部位が可動する状態)が生じることがあります。
腓骨骨折においても、骨幹部の癒合不全などにより変形が残るケースでは、後遺障害として認定される可能性があり、代表的な認定例は12級8号(長管骨に変形を残すもの)です。
また、変形の程度が著しい場合には、さらに上位の等級が認定されることもあります。
<腓骨骨折による変形障害の後遺障害等級>
| 症状の内容 | 認定等級 |
|---|---|
| 1下肢に偽関節を残し、 著しい運動障害を残すもの |
7級10号 |
| 1下肢に偽関節を残すもの | 8級9号 |
| 長管骨に変形を残すもの | 12級8号 |
短縮障害
短縮障害とは、骨折によって脚の長さが短くなってしまう状態を指します。
骨癒合の過程で骨の長さが正常より短くなると、左右の脚に長さの差(脚長差)が生じることがあります。
短縮障害に対する認定等級は、短くなった長さによって変わります。
<腓骨骨折による短縮障害の後遺障害等級>
| 症状の内容 | 認定等級 |
|---|---|
| 1下肢を5cm以上短縮 | 8級5号 |
| 1下肢を3cm以上短縮 | 10級8号 |
| 1下肢を1cm以上短縮 | 13級8号 |
機能障害
機能障害とは、骨折などの影響により関節の可動域が制限され、正常な動作が困難になる状態を指します。
腓骨骨折では、足関節の可動域が制限されることで、歩行や立位に支障をきたす場合があります。
後遺障害として認定されるかどうかは、健側(健康な側)との可動域の比較に基づき、医学的な角度測定によって判断されます。
<腓骨骨折による機能障害の後遺障害等級>
| 症状の内容 | 認定等級 |
|---|---|
| 1下肢の1関節の用を 廃したもの |
8級7号 |
| 1下肢の1関節の機能に 著しい障害を残すもの |
10級11号 |
| 1下肢の1関節の機能に障害を残すもの | 12級7号 |
神経障害
神経障害とは、骨折部位の神経損傷や癒合後の変形などにより、しびれや慢性的な痛みが残存する状態を指します。
腓骨骨折では、骨折部周辺の神経組織が損傷されることで、感覚異常や疼痛が長期化することがあります。
後遺障害として認定されるかどうかは、画像診断(レントゲン・CT・MRI)や神経学的検査、通院履歴などの医学的根拠に基づいて判断されます。
<腓骨骨折による神経障害の後遺障害等級>
| 症状の内容 | 認定等級 |
|---|---|
| 局部に頑固な神経症状を 残すもの |
12級13号 |
| 局部に神経症状を残すもの | 14級9号 |
醜状障害
醜状障害とは、手術や外傷によって皮膚に目立つ傷痕が残り、外見上の変化が生じる状態を指します。
腓骨骨折では、手術による皮膚切開や外傷の影響で、下肢の露出部に傷痕が残ることがあります。
後遺障害として認定されるかどうかは、傷痕の大きさ・位置・露出面の範囲などに基づいて判断されます。
<腓骨骨折による醜状障害の後遺障害等級>
| 症状の内容 | 認定等級 |
|---|---|
| 下肢の露出面に手のひらの 大きさの3倍以上の醜いあとを残すもの |
12級相当 |
| 下肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの | 14級5号 |
後遺障害の認定には申請が必要
交通事故で後遺症が残った場合でも、申請手続きを行わなければ後遺障害として認定されることはありません。
審査では、通院履歴や症状の一貫性、診断書の記載内容などが評価の対象となるため、申請にあたっては、医師による「症状固定」の診断書が必要です。
症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を指し、この判断が下されるまでは定期的な通院を続けることが求められます。
書類の不備や医学的根拠の不足があると、認定が却下される可能性もあるため、専門家の助言を受けながら慎重に準備を進めることが重要です。
交通事故による腓骨骨折の
慰謝料相場
交通事故の慰謝料には、治療に対する「入通院慰謝料」と、後遺障害を負った場合の「後遺障害慰謝料」があり、それぞれ算定基準が異なります。
入通院慰謝料の算定基準と目安
入通院慰謝料は、治療期間や通院日数に応じて算定されます。
自賠責保険では、1日4,300円が入通院慰謝料の最低限の補償額に設定されています。
一方、任意保険基準や弁護士基準(裁判基準)に基づいて算定した場合、これよりも高額な慰謝料が認められることが多いです。
たとえば、入院期間1か月、通院期間3か月の場合、慰謝料は115万円が目安とされています。
なお、慰謝料の金額は通院頻度や治療内容によっても変動するため、通院記録や診療明細などの正確な記録を残しておくことが重要です。
後遺障害慰謝料の等級別相場
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負った場合に認定される等級に応じて金額が定められています。
自賠責基準では、14級で32万円、12級で94万円が目安とされており、これは法定の最低限補償額です。
一方、弁護士基準では、14級で110万円前後、12級で290万円前後と、自賠責基準の2〜3倍の金額が認められるケースもあります。
等級が高くなるほど慰謝料額も増加するため、後遺障害の正確な認定が損害賠償の成否を左右します。
慰謝料請求の流れと交渉のポイント
慰謝料を請求する際には、診断書、後遺障害の認定書、通院記録、事故証明書などの資料を事前に整えておく必要があります。
保険会社との交渉では、提示された金額が妥当かどうかを判断するために、弁護士基準との比較が有効です。
多くの場合、保険会社は自賠責基準や任意保険基準に基づいた金額を提示してくるため、被害者がそのまま受け入れると、本来得られるべき金額よりも低くなる可能性があります。
こうした事態を避けるためには、交通事故の示談交渉を弁護士へ依頼し、交渉を有利に進めることが重要です。
弁護士は、資料の精査や交渉戦略の立案、示談書の作成などを通じて、被害者の権利保護に尽力します。
慰謝料の獲得には、資料の整備と交渉戦略が不可欠であるため、交通事故に詳しい専門家へ早めに相談することが望まれます。
腓骨骨折による損害賠償は
専門家への相談が不可欠
交通事故によって腓骨を骨折した場合、治療から慰謝料請求に至るまで、医学的および法的な専門知識が求められます。
特に後遺障害の等級認定や保険会社との交渉は、被害者個人で対応するには限界があり、適正な損害賠償を得るためには専門的な支援が欠かせません。
交通事故に詳しい弁護士へ早期に相談することで、後遺障害等級の適正な認定や、弁護士基準に基づく慰謝料請求が可能となります。
腓骨骨折による損害を正当に補償してもらうためには、専門家の力を借りることが最も確実かつ効果的な方法です。
交通事故による腓骨骨折でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠





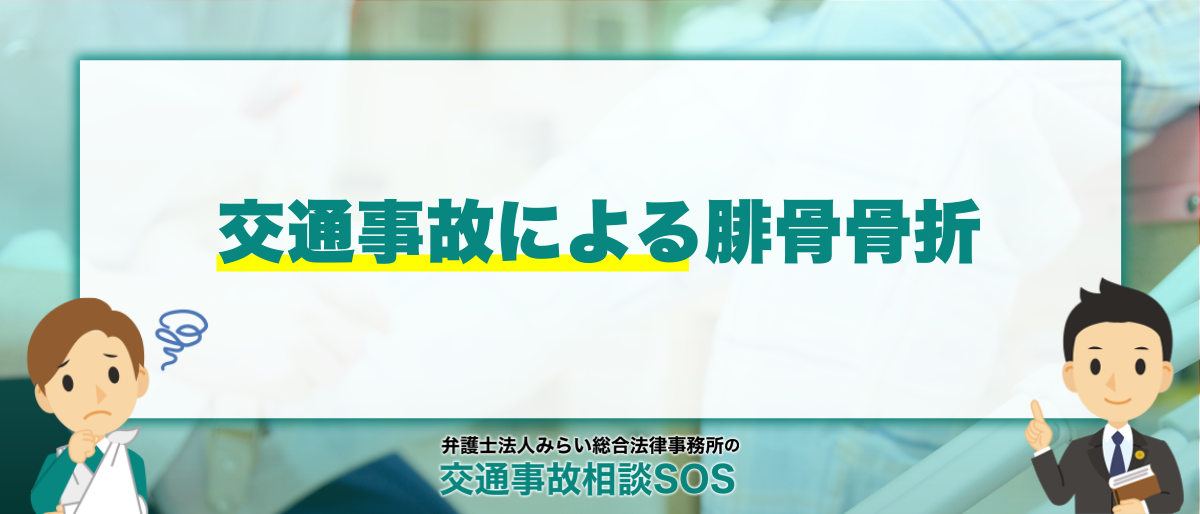












の後遺障害等級.png)


