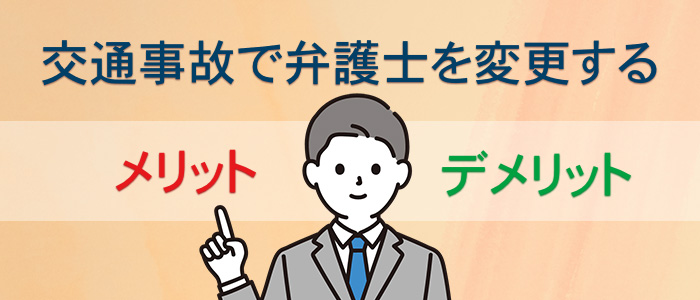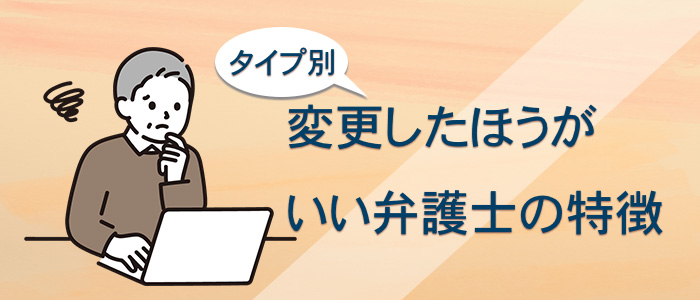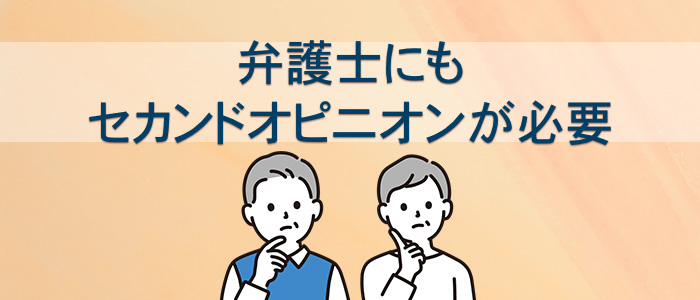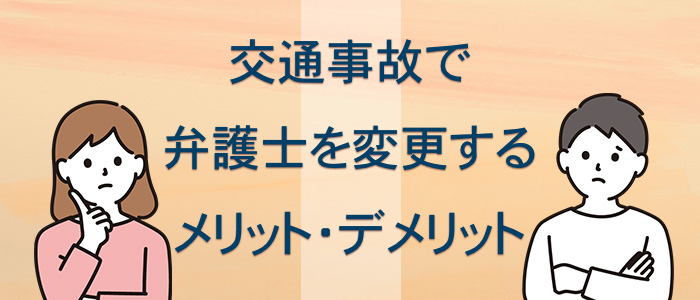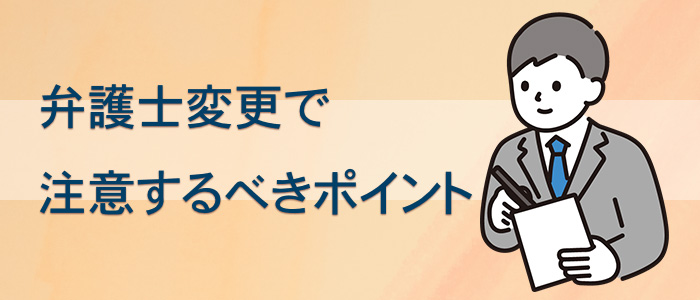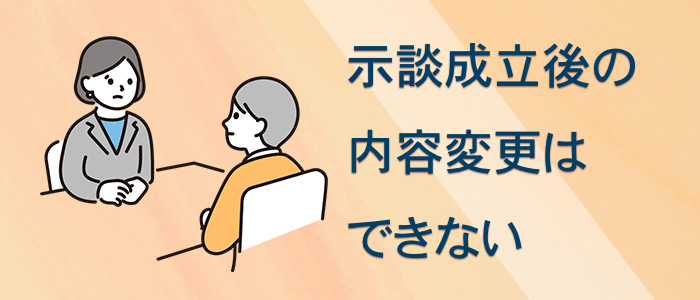交通事故で弁護士を変更するメリット・デメリット
交通事故の問題解決のために弁護士に依頼したものの、弁護士を変更したいと考える場合があると思います。
- 「しっかり対応してくれなくて不満だ」
- 「力不足な感じがして不信感を持っている」
- 「どうも人間的な相性が合わない」
といった理由がある場合もあるでしょう。
その場合、どのような手順、段取りで変更すればいいのでしょうか?
弁護士変更をした場合、どのようなメリットがあるでしょうか?
逆に、弁護士を変更したことで不利益になるなどデメリットはあるのでしょうか?
本記事では、弁護士を変更するメリットとデメリットを中心に、その際の手順や注意点も合わせてお話ししていきます。
タイプ別:変更したほうがいい弁護士の特徴
変更したほうがいい弁護士の主な特徴をまとめてみました。
心当たりがある場合は、すぐに行動することをおすすめします。
弁護士が質問、疑問にしっかり答えない
依頼者の方は交通事故の被害にあって、精神的・肉体的な苦痛と損害を受けています。
その交通事故の問題を解決したいために弁護士に相談・依頼をしているのに、被害者の方にしっかり向き合わない、答えをはぐらかしたりして、きちんと対応しないような弁護士もいるようです。
また、「私はプロなんだから、任せておけばいいんだ」などというような高圧的な弁護士も、被害者としては不安になるでしょう。
弁護士の言っていることが変わっていく
相談をした時には、「必ず増額を勝ち取ります」「大船に乗った気持ちで任せてください」などと言っていたのに、いざ保険会社との交渉が始まると、
「この金額が保険会社の出せる限界です」
「これ以上の増額は無理でしょう」
「示談交渉を長引かせるのは損なので、このあたりで和解してしまいましょう」
などと言いだし、話が変わってくる弁護士もいるようです。
弁護士の対応が横柄だったり、いい加減
中には、被害者の方が質問しても不機嫌そう、怒り出す、上から目線で威圧してくる、という弁護士もいるようです。
また、何度も連絡しても、「今、忙しいので、もう少し待ってください」という返答を繰り返したり、メールをしても返信してこない、電話にも出ない、といった弁護士もいるようです。
弁護士がお金の話ばかりする
質問をしても、あまり答えず、着手金や報酬などのお金の話ばかりする弁護士もいるようです。
その他、依頼してはいけない弁護士の特徴を詳しく動画でまとめてみたので、ぜひご覧ください。
弁護士にもセカンドオピニオンが必要
上記のような弁護士の場合、セカンドオピニオンで他の弁護士の話を聞いてみる、という選択も大切になってきます。
今や医療の世界では、セカンドオピニオンは当たり前になっています。
法律の世界でも同様に、他の弁護士にも相談して意見を聞いてみることは重要です。
その結果、弁護士を変更したことでストレスがなくなり、さらに示談金が大きく増額することは珍しくありません。
みらい総合法律事務所の増額解決事例
セカンドオピニオンで、みらい総合法律事務所に相談され、弁護士変更をした結果、示談金が約3,000万円も増額した事案です。
17歳の女性が自転車に乗っていたところ、飲酒脇見運転の自動車に追突され、死亡しました。
まず、ご遺族は地元の弁護士に依頼。
示談交渉の結果、約5,893万円の示談金が提示されましたが、この弁護士から「裁判を起すと金額が下がる可能性がある。ここで示談をしたほうがいい」と言われました。
この発言に納得がいかず、不信に感じたご遺族が、みらい総合法律事務所にセカンドオピニオンで相談。
弁護士が事件を精査した結果、「まだ増額は可能」との見解だったことから、ご遺族が弁護士変更をされました。
裁判では弁護士の主張が認められ、慰謝料の相場金額が2,000~2,500万円のところ、2,800万円に増額。
その他の項目でも増額が認められ、最終的に約3,000万円増額し、約8,835万円で解決したものです。
交通事故で弁護士を変更するメリットとデメリット
ストレスがなくなり安心できる
不信感を抱いた相手とつき合うことは心のストレスになりますが、納得のできる説明を受けて、信頼できる弁護士に依頼することができれば、ストレスはなくなり、安心して任せることができるでしょう。
被害者の方は、交通事故によって精神的・肉体的な苦痛を抱えているのですから、示談交渉でも苦痛を味わう必要はありません。
慰謝料などの示談金が増額して納得が得られる
前述したように、交通事故に強い弁護に変更することで正しい金額の示談金に増額することができます。
それには、もちろん理由があります。
交通事故の損害賠償実務の経験が豊富な弁護士であれば、次のことなどが可能だからです。
| ・後遺障害等級認定のシステムを熟知しているので、等級が正しいかどうかの判断ができ、異議申立の申請ができる。 |
| ・損害保険の知識や医学的知見もあわせもっているので、総合的な判断ができる。 |
| ・過去の判例の情報・データを持っているので、法的に正しい判断、主張ができる。 |
| ・最終的には提訴して、裁判での解決に進むことができる。 |
なお、デメリットをあげるなら、前任弁護士の契約解除手続きなどが必要になるので、多少の手間がかかってしまうことは頭に置いておいたほうがいいでしょう。
弁護士変更で注意するべきポイント
弁護士変更する場合には注意するべきポイントがいくつかあります。
1.支払い済みの着手金は返金されない
弁護士に依頼する際には、次の費用が必要になります。
| ①相談料 |
| ②着手金 |
| ③報酬料 |
| ④日当 |
| ⑤実費 |
着手金というのは、事件に着手する前に支払う手付金のようなものなのですが、これが必要な法律事務所の場合、支払い済みの着手金は返金されないので注意してください。
ちなみに、みらい総合法律事務所では原則として、相談料と着手金はいただいていませんので、0円となります。
2.金銭の清算が必要な場合もある
最初に依頼した弁護士が、すでに実務に着手している場合は、そこまでにかかっている実費や経費、さらには中途解約の違約金などの精算が必要な場合があるので、契約書をよく確認することが大切です。
3.委任契約の解除が必要
弁護士に依頼する際は「委任契約」を交わします。
新たに弁護士に依頼する場合にも必要になりますが、その前にまず、前任の弁護士との委任契約を解除する必要があります。
手続きの段取りとしては、まずセカンドオピニオンで他の弁護士の説明を聞いて、納得したら受任の約束をします。
そのうえで、前任弁護士との契約を解除し、新たな弁護士との委任契約を結びます。
弁護士との委任契約は、いつでも解約することができ、口頭でも書面でも解約を申し出ることができます。
そのうえで、次の手続きが必要になります。
| ・前任の弁護士に預けている書類は返還してもらう。 |
| ・前任の弁護士から、相手方(加害者側の任意保険会社)に辞任届を 提出してもらう。 |
| ・その後に新たな弁護士との委任契約を締結する。 |
| ・新たに契約した弁護士から相手方に受任通知を送ってもらう。 |
4.「費用倒れ」のケースでは注意が必要
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、被害者の方は後遺障害等級認定を申請する必要があります。
慰謝料や逸失利益などを合計した損害賠償金(示談金)は、たとえば自賠責保険では等級によって次のように金額が決められています。
| ・傷害(ケガ)による損害の場合:120万円 |
| ・被害者が死亡した場合:3000万円 |
| ・傷害により後遺障害が残り、介護が必要な場合:4000万~3000万円 |
| ・その他の後遺障害の場合:1級から14級の後遺障害等級に応じて 3000万円~75万円 |
自賠責法別表第1
(介護を要する後遺障害)
| 第1級 | 4000万円 | 第2級 | 3000万円 |
|---|
自賠責法別表第2
(その他の後遺障害)
| 第1級 | 3000万円 |
|---|---|
| 第2級 | 2590万円 |
| 第3級 | 2219万円 |
| 第4級 | 1889万円 |
| 第5級 | 1574万円 |
| 第6級 | 1296万円 |
| 第7級 | 1051万円 |
| 第8級 | 819万円 |
| 第9級 | 616万円 |
| 第10級 | 461万円 |
| 第11級 | 331万円 |
| 第12級 | 224万円 |
| 第13級 | 139万円 |
| 第14級 | 75万円 |
参考情報:「後遺障害等級表」(国土交通省)
比較的、後遺障害等級が低い場合では損害賠償金も低くなります。
その場合、弁護士に依頼すると、報酬金などのほうが高くなってしまう、いわゆる「費用倒れ」のケースが発生する場合があります。
弁護士変更した場合では、違約金の他にさらに弁護士費用を新たに支払うことになるので、被害者の方の手元にお金が残らない、持ち出しでマイナスになってしまうという可能性が大きくなるので注意が必要です。
示談成立後の内容変更はできない
加害者側の任意保険会社との示談は、一度成立してしまうと変更はできません。
たとえば、最初に依頼した弁護士に示談をすすめられ、よくわからないまま示談書に署名・押印したものの、後からセカンドオピニオンで他の弁護士からの説明で、示談金が低すぎるとわかってしまった場合などでは、示談交渉のやり直しはできないので慎重に判断する必要があります。
なお、交通事故に強い弁護士の探し方、選び方について動画でまとめていますので、ぜひご覧ください。
代表社員 弁護士 谷原誠