【実例付き】60歳の交通事故の慰謝料の計算

*タップすると解説を見ることができます。
近年、高齢者が加害者にも、被害者にもなってしまう交通事故の割合が増えています。
高齢者の年齢の定義はさまざまあり、一概にいえませんが、国連の定義では60歳以上、世界保健機構(WHO)では65歳以上を高齢者としているようです。
現在の日本では、一般的に65歳以上を高齢者とすることが多いようです。
そこで今回は、人生のひとつの節目ともいえる60歳を迎えた女性(主婦・夫と2人暮らし)の方が交通事故被害にあった場合の慰謝料について、いくらくらいになるのか考えてみたいと思います。
交通死亡事故の慰謝料と
損害賠償金額を計算してみる
ここでは、交通事故で被害者が亡くなった場合の慰謝料や損害賠償金について解説します。
ご遺族が請求できる
損害賠償項目
ご遺族が加害者側の任意保険会社に対して請求できる主な損害賠償項目には次のものがあります。
①葬儀関係費
②死亡逸失利益
③死亡慰謝料
④弁護士費用
⑤損害賠償関係費
⑥その他
葬儀関係費
自賠責保険では定額60万円、任意保険では120万円以内が相場になりますが、弁護士に依頼して訴訟を起こした時に認められる金額は原則、150万円となります。
かかった費用が150万円より低い時は実際に支出した金額になります。
その他、墓石建立費や仏壇購入費、永代供養料などについては、それぞれ個別の事案ごとで判断され、決定します。
死亡逸失利益
計算方法
死亡逸失利益とは、被害者が生きていれば労働によって将来的に得られたであろう収入のことです。
被害者が死亡した場合は後遺障害を負った場合とは異なり、その時点で100%所得がなくなるため労働能力喪失率は100%として計算します。
主婦の場合は、実際の収入はないので逸失利益は認められないのでは、と考える人もいますが日々の家事労働を行なっているため、当然に逸失利益は認められます。
少し難しいのですが、次のような計算式で金額を算出します。
基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
= 死亡逸失利益
<基礎収入>
基礎収入とは前年の年収のことで、国民年金などの年金収入も含まれます。
これまでの裁判例では、女性の家事従事者の基礎収入についての分類は次のようになっています。
①女性労働者の全年齢平均賃金としたもの
②女性労働者の全年齢平均賃金から何割か減額した額としたもの
③年齢別の女性労働者の平均賃金としたもの
④年齢別の女性労働者の平均賃金から何割か減額した額としたもの
実際には、被害者が行なっていた家事の程度など個別の事案ごとに、それぞれ具体的な事情を考え合わせて基礎収入額が出されます。
ここでは、①を採用して「令和元年の賃金センサス女性学歴計全年齢平均賃金」である「3,880,100円」を基礎収入とします。
<生活費控除>
生活費控除とは、基礎収入から生きていればかかったはずの生活費分を差し引くことです。
生活費控除率は概ね、次のパーセンテージが目安になります。
・被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合⇒40%
・一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合⇒30%
・男性(独身、幼児等含む)の場合⇒50%
・女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合⇒30%
<就労可能年数>
原則として、18歳から67歳までが就労可能年数とされます。
しかし、67歳を過ぎても就労することが可能だったと思われる場合(被害者の職種、地位、能力などにより判断)は67歳を超えて認められる場合もあります。
今回は、国土交通省が公表している「就労可能年数とライプニッツ係数表」による60歳の就労可能年数である「12年」を使います。
<ライプニッツ係数>
将来の収入時までの年3%の利息を複利で差し引く際の計数を、ライプニッツ係数(中間利息控除)といいます。
ご遺族に支払われる損害賠償金は、本来であれば亡くなったご家族が将来的に仕事をして得ることができるはずだった収入分を前倒しにして、現在受け取ることになります。
とすると、お金の価値としては現時点と将来では違ってくるので、その差額を調整する必要があるわけです。
国土交通省が公表している「就労可能年数とライプニッツ係数表」によると、60歳のライプニッツ係数は「9.954」ですので、これを使います。
【参考情報】
「就労可能年数とライプニッツ係数表」国土交通省
実際の計算
では、計算式に当てはめてみます。
3,880,100円(令和元年の賃金センサス女性学歴計全年齢平均賃金)×(1-0.3)×9.954(ライプニッツ係数)
=27,035,760円
これが、60歳の女性(主婦)の死亡逸失利益の大まかな金額となります。
<死亡慰謝料>
裁判基準で定められている死亡慰謝料の相場は次のようになっています。
・被害者が一家の支柱の場合 2800万円
・被害者が母親、配偶者の場合 2500万円
・被害者がその他の場合 2000万~2500万円
死亡慰謝料額は被害者の立場などによって変わってきます。
たとえば、一家の支柱の方が亡くなったと時は、ご遺族の扶養を支える人がいなくなるため他の場合よりも高い金額が設定されています。
今回の例では、被害者の方は配偶者となりますので、一応2500万円と仮定して考えていきます。
<弁護士費用>
被害者のご遺族が弁護士に依頼して裁判を提起した場合、そこで認められた請求額の10%が弁護士費用として認められます。
計算式は次のようになります。
1,500,000円(葬儀費)+27,035,760円(死亡逸失利益、年金除く)
+25,000,000円(慰謝料)×0.1
=5,353,576円
では、ここまでで算出された金額を用いて60歳の女性(主婦・夫と2人暮らし)の方が交通事故で死亡した場合の損害賠償金額を計算してみましょう。
1,500,000円(葬儀費)
+27,035,760円(死亡逸失利益)
+25,000,000円(慰謝料)
+5,353,576円(弁護士費用)
=58,889,336円
交通事故の被害者に後遺障害が
残った場合の慰謝料額
次に、被害者が交通事故で負ったケガが完治せず後遺症が残った場合の損害賠償金や慰謝料について考えてみます。
大きなポイントは、「後遺症慰謝料」と「逸失利益」です。
後遺症慰謝料とは?
後遺症が残った場合、被害者はご自身の後遺障害等級を申請する必要があります。
後遺障害等級が認定されると、被害者は加害者側の任意保険会社に損害賠償請求することができます。
通常、任意保険会社から連絡があり、示談金額が提示されて、示談交渉がスタートします。
詳しい解説はこちら⇒
「交通事故の示談の流れを徹底解説」
後遺症が残ってしまった場合の被害者の精神的損害を償うものが後遺症慰謝料です。
後遺障害等級別の後遺症慰謝料額は次のようになっています。
| 後遺障害等級 | 慰謝料 |
|---|---|
| 第1級 | 2800万円 |
| 第2級 | 2370万円 |
| 第3級 | 1990万円 |
| 第4級 | 1670万円 |
| 第5級 | 1400万円 |
| 第6級 | 1180万円 |
| 第7級 | 1000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
ただし、上記の金額は目安です。
実際の事案では、事故態様、加害者の態度、後遺症の程度など、個別の事情に応じて後遺症慰謝料額が決定されます。
逸失利益とは?
後遺障害を負ったことにより、被害者が本来は得るべきだったのに得られなくなってしまった将来的な収入(利益)を逸失利益といいます。
基本的な考え方は死亡逸失利益の場合と同じです。
後遺障害の場合の逸失利益の算出は次の計算式によって行ないます。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
= 逸失利益
労働能力喪失率とは?
逸失利益を算出するうえで大切なのが「労働能力喪失率」です。
労働能力喪失率は、原則として後遺障害別等級表記載の労働能力喪失率に従って決定されます。
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 第1級 | 100/100 |
| 第2級 | 100/100 |
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 第1級 | 100/100 |
| 第2級 | 100/100 |
| 第3級 | 100/100 |
| 第4級 | 92/100 |
| 第5級 | 79/100 |
| 第6級 | 67/100 |
| 第7級 | 56/100 |
| 第8級 | 45/100 |
| 第9級 | 35/100 |
| 第10級 | 27/100 |
| 第11級 | 20/100 |
| 第12級 | 14/100 |
| 第13級 | 9/100 |
| 第14級 | 5/100 |
14級では5%の喪失率、1級では喪失率は100%というように等級が上がるごとに労働能力喪失率は高くなります。
ご自身の後遺障害等級は、後遺症慰謝料だけでなく逸失利益にも影響を与えるものです。
とても重要なものですから、もし認定された等級に不満があり、納得ができない場合は、異議申し立てをする必要があります。
60代被害者の実際の解決事例
それでは、ここで、みらい総合法律事務所が実際に解決した60代被害者の事例をご紹介します。
【後遺障害】63歳女性
約3倍に増額!
63歳男性が、脊柱骨折により、後遺障害等級11級7号が認定されました。
保険会社からの提示額は、449万9462円です。
被害者はみらい総合法律事務所に依頼し、弁護士が交渉したところ、最終的に、1363万7770円で解決しました。
保険会社提示額の約3倍に増額したことになります。
【後遺障害】60歳女性
約4.8倍に増額!
60歳女性が、脳挫傷等の傷害により、高次脳機能障害で後遺障害等級併合6級が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、6,883,372円を提示しました。
被害者がみらい総合法律事務所に依頼し、弁護士が交渉したところ、大幅に増額し、3326万円で解決しました。
保険会社提示額から、約4.8倍に増額したことになります。
【死亡事故】68歳女性
約2700万円の増額!
68歳女性の死亡事故です。保険会社は、遺族に対し、示談金として、約2500円を提示しました。
遺族がみらい総合法律事務所に依頼し、弁護士が交渉したところ、最終的に、5200万円で解決しました。
保険会社提示額の約2700万円増額したことになります。
【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら





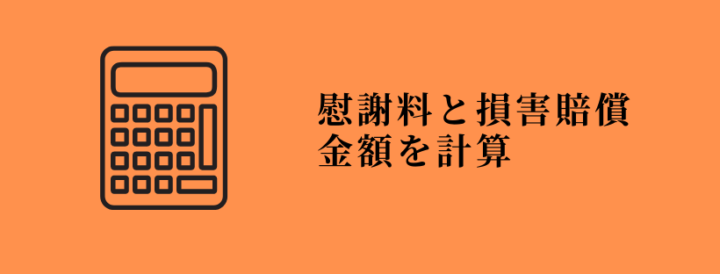
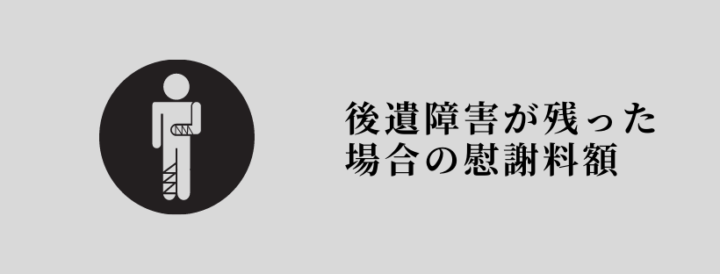
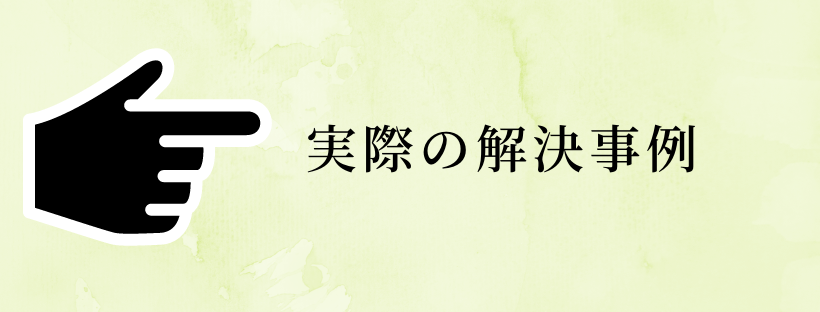






の後遺障害等級.png)

