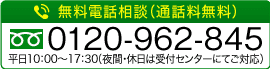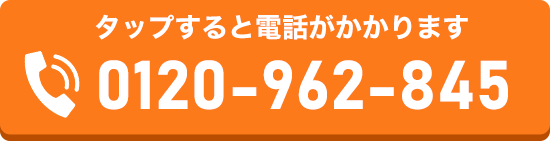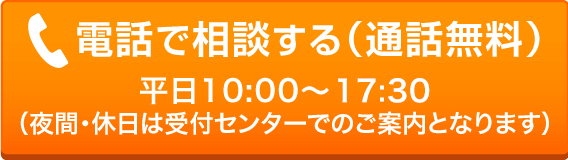逸失利益の金額の計算方法

*タップすると解説を見ることができます。
後遺症または死亡に繋がる重大事故では、被害者が今後得られるはずだった収入を「逸失利益」として請求できます。
金額こそ被害者によって異なりますが、多くは高額化し、加害者からの減額主張は十分予期できます。
ほんの少しでも取りこぼさないよう、1人ひとりの就労状況や能力を見極め、立証資料を揃えつつ正確に計算しなければなりません。
本記事で紹介するのは、逸失利益を請求できる
範囲(収入と年数)に関する基本的な判断基準です。
計算例と合わせて確認すれば、それぞれの状況に当てはめ、どのくらいの金額を受け取れるのかイメージできます。
目次
逸失利益とは
交通事故の損害額に含まれる「逸失利益」とは、労働能力もしくは生命と共に失われた将来の収入です。
その趣旨の通り、交通事故で後遺障害を負った場合、もしくは被害者が死亡した場合に請求できます。
なお、ここでは「収入」と表現していますが、労働の対価として実際に得ていた金額とは限りません。
この後説明するように、家事や事業経営にかかる判断・指示といった部分に関しても、広く逸失利益性が認められるのです。
逸失利益の発生条件
ここで押さえておきたいのは、逸失利益の基本的な発生条件です。
死亡事故の場合は、失われた収入全体を損害に計上できます。
一方の後遺症を負った事例では、その失われた労働能力に限り、収入のうち相当する分を逸失利益とします。
言い換えれば、後遺症を負っても「今まで通り働ける」と見なされれば、逸失利益の請求は認められません。
この点、労働能力の喪失の有無とその程度を客観的に評価できるよう、あらかじめ「後遺障害等級認定」を得ておく必要があります。
交通事故の被害者が後遺症を負った場合、申請により自賠法施行令に基づいて14段階で症状が評価されます。
評価を行うのは、保険会社や加害者等の当事者ではなく、あくまでも第三者の立場にある損害保険料率算出機構です。
上記の仕組みを「等級認定」と言い、申請の結果得られた等級を元に、被害者の損害額も計算されます。
逸失利益を計算する時の労働能力喪失率(※)も、重度障害で最大100%として等級毎に目安があります。
※労働能力喪失率:交通事故などで後遺障害が残った場合に、被害者が将来にわたって働く力をどの程度失ったかを、割合(%)で示したもの
逸失利益の計算方法
逸失利益の範囲は、「事故前の収入」(=基礎収入)に「労働できるはずだった残りの年数」(=就労可能年数)を乗じた部分です。
注意したいのは、上記全額を損害として計上できるわけではない点です。
将来の収入を先取りしつつ、被害者の状況が変化したことを踏まえ、公平化を図る観点で「中間利息」や「生活費」を控除すべきとされているのです(下記参照)。
もし将来分をそのまま合計してしまうと、被害者は「本来であれば少しずつ受け取るはずのお金」を一度に受け取り、それを運用することで利息などの利益を得られる可能性があるため、その利息分(中間利息)を差し引いて現在価値に換算するということです。
※中間利息の説明を先に読みたい方は、中間利息控除とはをご覧ください
ここからは、後遺障害の場合と死亡事故の場合にわけて、逸失利益の計算式を解説します。
【後遺障害の場合】逸失利益の計算式
後遺障害の逸失利益では、全体の金額に「中間利息控除」を考慮し、以下の式で計算します。
ポイントは、生活費の控除は行わない点です。
=基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 ※
※中間利息控除を計算するための係数です。
※中間利息控除・生活費控除の詳細はこの後詳しく解説します。
上記算定式に当てはめる「労働能力喪失度」の現状の基準は、自賠責保険の支払基準において以下のように指定されています。
もっとも、必ずしも表の通りになるとは限りません。
個別事例では症状やその程度を十分に鑑み、実際に基準より高い労働能力喪失度が認められるケースもあります(名古屋地裁平成20年2月27日判決等)。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失度 |
|---|---|
| 第1級 | 100% |
| 第2級 | 100% |
| 第3級 | 100% |
| 第4級 | 92% |
| 第5級 | 79% |
| 第6級 | 67% |
| 第7級 | 56% |
| 第8級 | 45% |
| 第9級 | 35% |
| 第10級 | 27% |
| 第11級 | 20% |
| 第12級 | 14% |
| 第13級 | 9% |
| 第14級 | 5% |
参考:自賠責保険ポータルサイト
【死亡事故の場合】逸失利益の計算式
死亡事故の逸失利益は、基本的に先々の収入の全部が失われたものとして考えます。
ただし、中間利息控除に加えて「生活費控除」を考慮しなくてはなりません(下記参照)。
=基礎収入 × (100% - 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
逸失利益の計算例
ここで金額の参考となるよう、後遺傷害あるいは被害者死亡に至った重大事故を想定し、計算例を2つ紹介してみましょう。
逸失利益の計算例①
32歳女性が骨折した場合
【例1】32歳女性(給与所得者/年収240万円)が骨折で後遺障害等級12級7号の認定を得た場合
=240万円 × 14% × 21.487
≒ 722万円
逸失利益の計算例②
56歳男性が死亡した場合
【例2】56歳男性(給与所得者/年収600万円/被扶養者2名)が死亡した場合
=600万円 × (100% - 30%) ×
11.296 ≒ 4,744万円
ここまでの解説を改めて整理すると、逸失利益の金額は「基礎収入」と「就労可能年数」で概ね決定します。
まずはそれぞれの判断基準について解説した上で、各種控除についても考え方を紹介します。
基礎収入額の考え方
【有職者の場合】
有職者の逸失利益は、給与明細や源泉徴収票、その他確定申告書に記載された金額をベースとします。
厳密な基礎収入の考え方は、職業によって異なります。
(1)給与所得者
(2)個人事業主・フリーランス
(3)会社役員・代表者・経営者
1つずつ詳しく解説します。
給与所得者
雇用形態に関わらず、給与所得者なら「現実の収入」を基礎収入とします。
ただし、被害者の年齢が概ね30歳未満なら、この後説明する学生の基礎収入の考え方との均衡を考慮しなければなりません。
そこで、原則上は、厚労省が毎年公表する「賃金構造基本統計調査」の結果(賃金センサス)から得られた全年齢平均賃金を採用します。
低い場合の考え方
現実の収入が低い被害者の基礎収入は、平均的な賃金が得られる見込みがある限り、若年労働者と同様に賃金センサスの金額を採用します。
個人事業主・フリーランス
自営業者・自由業者・農林水産業等については、申告所得額を基礎収入額とするのが原則です。
ただし、業態上経費と生活費の区別が難しい点は裁判例で十分に意識されており、実際には立証できる範囲で実収入を採用するのが通例です。
なお、その所得に配当金や家族の労働によるものも含まれているのなら、被害者本人の働きが寄与した部分だけを逸失利益の基礎と考えます。
どうなる?
確定申告をしていないせいで申告所得額が分からなかったとしても、逸失利益 = ゼロになるわけではありません。
この場合、帳簿や入出金明細といった財務関係書類から、実際にどのくらいの所得があったのか分析して基礎収入と考えます。
どうしても事業所得が割り出せないとしても、平均賃金を得られていたことが確からしいと認められる場合に、賃金センサスの金額を逸失利益の基礎とすることが可能です。
会社役員・代表者・経営者
被害者が会社役員である場合は、役員報酬あるいは企業収益のうち「労務提供の対価部分」を基礎収入とします。
言い換えると、「利益配当としての性質を持つ部分」は逸失利益として認められません。
肝心の労務対価部分の判断は、以下の要素から行います。
- ・会社の規模や業種
- ・被害者の地位
- ・職務内容
- ・役員報酬の金額※
- ・他の役員の職務内容と報酬額※
- ・従業員の職務内容と賃金の額※
※賃金または報酬額の直近の推移も、逸失利益の判断基準に含まれます。
基礎収入額の考え方【主婦・
高齢者・未成年者等】
逸失利益の最大のポイントは、たとえ被害者が無職や時短労働者であったとしても、それを理由に否定されることはない点です。
学歴・性別等を考慮した上で、これから説明するように、概ね賃金センサスの金額を採用する形で計上できるのです。
被害者がそれぞれ以下に該当する場合の基礎収入額の考え方を解説します。
(1)主婦(主夫)
(2)未成年者・学生・幼児
(3)失業者・無職者
(4)高齢者・年金生活者
主婦(主夫)
家事専従者(専業主婦など)は、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均額を基礎とします。
また、個別事例では「家事専従者になる前の仕事」や「家事の合間に行っていた別の労働」も考慮されます。
つまり、十分な所得が得られる仕事をやめて家事専従者になった…といった事情は、より高い値を基礎収入として採用する根拠になり得るのです。
主婦(主夫)の基礎収入の判例①
非器質性精神障害等で併合9級に認定された主婦(症状固定時64歳)につき、賃金センサスの女性・学歴計・全年齢平均賃金である約350万円が基礎収入として認められました。(東京地裁平成23年10月24日判決)
主婦(主夫)の基礎収入の判例②
妻が家業を継いだため家事全般に従事していた男性(症状固定時50歳)につき、賃金センサスの女性・学歴計・全年齢平均賃金である約352万円が基礎収入として認められました。(東京地裁平成16年9月1日判決)
逸失利益はどうなる?
家事専従というわけではなく、被害者がパートやアルバイトでも収入を得ていたなら、その金額も考慮すべきです。
そこで、平均賃金と稼働収入を比較し、より高い方を基礎収入とするのが原則とされています。
未成年者・学生・幼児
未成年者(幼児含む)や学生についても、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均額を基礎とします。
個別のケースでは、学業・進学予定・アルバイト等の就労状況から、将来得られたであろう収入を慎重に判断します。
未成年者・学生・幼児の基礎収入の
判例①
高校生の被害者(症状固定時19歳)につき、事故後に大学医学部に進学していた状況が考慮され、賃金センサスの女性医師全年齢平均である
約948万円が基礎収入として認められました。(東京地裁平成30年3月23日判決)
未成年者・学生・幼児の基礎収入の
判例②
死亡した16歳と15歳の2人の高校生につき、男性学歴全年齢平均にあたる賃金を得られないと認めるに足る特段の事情がない限り、同平均賃金を基礎収入として算定するのが相当であるとされました。(東京地裁平成28年7月19日判決)
その結果、「男性高卒全年齢平均を基礎とすべき」との被告の主張が覆され、学歴平均の
約524万円が逸失利益として採用されています。
最近の裁判例を見ると、女性年少者について「男女別」の平均賃金を採用する例は減少傾向です。
大学進学率の上昇等といった昨今の状況を踏まえ、むしろ「男女計」の全年齢平均賃金を採用するのが適切と考えられつつあります。
失業者・無職者
失業者その他事故時点では就職していなかった人でも、「労働能力」「労働意欲」「就労の蓋然性」の3基準を個別に判断し、再就職すれば得られたであろう収入を逸失利益の基礎とします。
少なくとも、得られる蓋然性(=確からしさ)がある限り、賃金センサスから得られた男女別の平均賃金は請求できるとするのが原則です。
・前職の内容…専門性や労働時間に着目
・退職の理由…転職活動の予定等に着目
・求職活動の状況…休職活動している
=同上と判断
・扶養家族の有無…扶養家族がいる
=就労の蓋然性が高いと判断
高齢者・年金生活者の場合
たとえ高齢者であっても、就労の蓋然性が認められれば、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計・男女別・年齢別平均の賃金額を基礎とします。
また、死亡事故で受給資格のなくなった年金に関しても、以下のようなものが逸失利益として認められます。
- ・老齢国民年金
- ・老齢厚生年金
- ・障害者年金
- ・公務員の年金給付
- ・農業者年金
- ・港湾労働者年金
- ・恩給
年金を逸失利益として扱えるのは、
①給付目的が本人の生活維持であり、かつ
②給付と掛金支払いとの間に対価性があり、そして
③給付継続が確実であったと見込める場合
のみです。
以上の考え方に基づけば、どんな種類の年金でも逸失利益として扱えるとは限りません。
今まで逸失利益性が認められなかったものとして、実際に「亡配偶者の遺族年金」や「障害者年金の子や妻にかかる加給分」があります。
就労可能年数の考え方
収入を損害として計上できる期間を表す「就労可能年数」は、原則として症状固定日または死亡日から67歳までの年数と考えます。
ただし、一律に同じ考え方を採用するのではなく、年齢その他被害者ごとの状況は十分に考慮されます(下記参照)。
未成年者の場合
被害に遭ったのが未成年者なら、18歳を就労可能年数の始期とするのが原則です。
ただし、進学により就労が遅れる可能性は考慮されます。
例えば、大学に進学し順当に卒業できる見込みがあるのなら、22歳から就労を開始するものと考えるのです。
考慮する際の留意事項
学業により就労開始が遅れると、その年数分だけ働ける期間も短くなり、ひいては損害に計上できる逸失利益の額も小さくなる……と考えるのが普通です。
ただし、一般に進学すると生涯年収が上昇することを踏まえれば、この限りとも言えません。
個別のケースでは、大学や専門学校の卒業予定を踏まえることで逸失利益がどう変化するのか、慎重に試算してみる必要があります。
67歳に近いorより高齢の場合
被害者が67歳に近いかより高齢となる場合は、少なくとも簡易生命表における平均余命の2分の1を就労可能年数と判断するのが原則です。
【例1】65歳男性の場合
→約10年を逸失利益の範囲とする
(平均余命=20.05年※)
【例2】72歳女性の場合
→約9年~10年を逸失利益の範囲とする
(平均余命=18.77年※)
※令和2年分のデータより
就労可能年数の修正要素
ここまでは就労可能年数の判断の原則を紹介しましたが、一律で全てのケースに適用されるわけではありません。
事故被害者ごとに職種・地位・健康状態・能力といった要素が考慮され、その結果として異なる判断になる場合があるのです。
【判例1】大阪地裁平成22年3月11日判決
税理士(60歳男性)につき、事務員による作業割合も大きく、通常の職種より長期にわたって稼働し得るとして、就労可能年数の終期は75歳とされました。
【判例2】京都地裁平成12年3月23日判決
医学部3回生の女性(22歳)につき、就労可能年数の終期は70歳とされました。
中間利息控除とは
死亡事故・後遺障害を負った事故のどちらでも考慮される「中間利息」とは、将来の収入の先取りによる「被害者側の利益」を意味するものです。
中間利息の割合は年3%(※2020年4月以降の事故の場合)とし、損害として計上する年数に応じて計算されます。
その計算を容易かつ正確に行うための値として、示談・訴訟問わず「ライプニッツ係数」が採用されています。
25歳 : 23.701(就労可能年数=42年)
35歳 : 20.389(就労可能年数=32年)
45歳 : 15.937(就労可能年数=22年)
参考:自賠責保険ポータルサイト
→上記ページの「就労可能年数とライプニッツ係数表」(別表2-1)で、被害者の年齢に対応する係数が確認できます。
生活費控除とは
交通事故の被害者が死亡した場合、損害賠償では「その後の生活費の支出は免れたもの」と考えます。
逸失利益を計上する時には、左記を考慮し、加害者の負担を適正にするために控除を行うのです。
なお、生活費を控除する時は、逸失利益全体に対する個別の割合(%)で考えます。
以降では、さらに生活費控除率の考え方を確認してみましょう。
生活費控除率の基準
生活費控除率に一律適用の基準はないものの、最近の判例からは以下のような目安があるとされています。
もっとも、後に説明するように、あくまでも原則上の割合だと考えるべきです。
| 被害者の属性 | 生活費控除率の目安 |
|---|---|
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |
| 被害者が男性(年少者含む)の場合 | 50% |
| 被害者が女性(年少者を除く※)の場合 | 30% |
| 被害者の属性 | 生活費控除率の目安 |
|---|---|
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が 1人の場合 |
40% |
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が 2人以上の場合 |
30% |
| 被害者が男性(年少者含む)の場合 | 50% |
| 被害者が女性(年少者を除く※)の場合 | 30% |
※女子年少者で男女計の平均賃金が採用される場合、生活費控除率を40%~45%とするのが原則です。
所得税等の金額は、生活費控除率を決める事由として多少鑑みられることはあります。
(詳細は後述)
しかし、課税額が逸失利益からそのまま控除されることは原則ありません。
(東京地裁平成7年3月14日判決等)
【注意】後遺障害での
生活費控除は原則しない
後遺障害を負った交通事故では、加害者から「生活費控除すべき」との主張が飛び出すことがあります。
確かに、かつては20%~30%程度の控除を認めるケースが多数存在していました。
しかし最近では、自宅療養中の雑費を支出することを見込む等して、控除を認めないのが原則です(東京地裁平成10年3月19日判決等)。
以上の点を踏まえ、加害者側の減額主張があれば、それは正しいのかしっかり検討しなくてはなりません。
逸失利益の生活費控除が認められない以上、
介護費用のうち生活費にあたる部分は請求できません。
該当するのは、施設介護する場合に支払う「居住費」「食費」、そして家賃としての性格がある「入所一時金」です。
もっとも、上記費用に「治療費としての性質」が認められている場合は、一転して請求できると考えらます。
例として、自力で食事できず嚥下機能の機能すら失われている状態の人の食費(京都地裁平成30年1月11日判決)が挙げられます。
参考:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称“赤い本”)2021年版下巻
※齊藤恒久裁判官の講演録より
生活費控除率の修正要素
生活費控除率は必ずしも原則通りに判断されるとは限らず、個別の修正要素が加味されることもあります。
下方修正され、その結果として受取分の増額に繋がるのは、不労所得や仕送りの影響がある以下のような要素です。
生活費控除率が下方修正される要素
・家族の生活費を援助していた
・離婚した相手に養育費を支払っていた
・賃料収入や配当所得等があった
反対に生活費控除率が上方修正され、減額に繋がる要素としては、以下のようなものが挙げられます。
内容を見ると分かる通り、納税額や扶養すべき家族の数が判断に関わっています。
生活費控除率が上方修正される要素
・高収入(1千万円以上が目安)
・夫婦共働きで生活していた
・子どもがおらず、両親も亡くなっている
・胎児が生まれる等して、事故後に扶養家族が増えている
年金生活者の生活費控除率
原則として、年金生活者の生活費控除率は50%~70%と高めです。
年金給付の趣旨が日々の暮らしの支援である以上、普通はその支給額の大半を生活費として費消するものと考えられるためです。
ただ、個別の事例では、年金を含む収入全体からどの程度の額を支出していたか「実態」が考慮されています(下記参照)。
【年金生活者の場合】生活費控除率が下方修正される要素
・年金とは別に収入がある(不労収入含む)
・持ち家があり、固定資産税以外に家賃負担がなかった
・親子二世帯で同居しており、生活費の支出が少なかった
・亡配偶者の遺族年金で生活費のほとんどを賄えていた
最後に
逸失利益の金額は、「基礎収入の取り方」と「就労可能年数の考え方」で概ね決まります。
被害者として意識したいのは、たとえ金銭による見返りのない労働だったとしても、少なくとも賃金センサスの平均額が認められ得る点です。
その他、生活費控除率の判断も見誤らないよう注意しなくてはなりません。
本記事で紹介したのは、ごく一般的な逸失利益の考え方に過ぎません。
実際に交通事故の被害について損害賠償請求しようとする時は、事故前の生活ぶりや将来の予定を示す資料を集め、妥当な金額を慎重に見極める必要があります。
少なくとも加害者に金額を提示された時には、弁護士に相談し、請求できる金額を独自に試算してみましょう。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠