交通事故で頭を打ったらどうする?考えられる症状と後遺障害等級
交通事故で頭を打った場合、外見に異常がなくても重大な障害が生じている可能性があります。
初期対応を誤ると、命に関わる事態を招いたり、重い後遺障害を負ったりすることもあるため、冷静かつ迅速な判断が求められます。
本記事では、交通事故で頭部を負傷した際に取るべき対応、注意すべき危険な症状のサイン、起こりうる後遺障害の種類について解説します。
目次
交通事故で頭を打った際に
すべきこと
交通事故で頭を打ったときは、外傷の有無にかかわらず、慎重に対応しなければなりません。
交通事故の頭部負傷で発生する
症状の種類
交通事故で頭部に衝撃を受けた場合、多様な症状を引き起こす可能性があります。
軽度の怪我では、一時的なめまい、頭痛、吐き気などが生じることが想定されます。
頭部への衝撃が強かったケースでは、意識障害、けいれん、記憶障害、言語障害などの神経症状を伴うことがあるため、注意が必要です。
さらに、外見から判断できない脳内損傷を負っていることも考えられるため、自覚症状がないとしても油断せず、医療機関で精密検査を受けることが大切です。
意識がある場合とない場合で
対応はどう変わる?
意識の有無は緊急度を判断する重要な指標となるため、迅速かつ的確な対応が求められます。
意識がない、または朦朧としている場合には、深刻な脳損傷が疑われます。
このような状態のときは、速やかに救急車を呼び、医療機関へ搬送することが必要です。
交通事故で頭部に衝撃を受けた後、意識があり会話が可能であっても、油断は禁物です。
外見に異常がなくても、脳内で出血や損傷が起こっている可能性は否定できません。
そのため、頭を打った際には自己判断で「大丈夫」と済ませず、必ず医療機関を受診しましょう。
救急車を呼ぶタイミングと
応急処置の基本
交通事故で頭を打った後、被害者に以下の症状が見られたら、ためらわずに救急車を呼んでください。
- 意識がはっきりしない、朦朧としている
- 嘔吐(おうと)や強い吐き気がある
- 痙攣(けいれん)している
- 頭から出血している、あるいは鼻や耳から血や透明な液体が出ている
- 強い頭痛を訴える
救急車を待つ間は、安静を第一としてください。
体を横向きにし、気道を確保する回復体位をとらせるのが望ましいです。
頭部を無理に動かしたり、体を揺さぶったりすると、症状が悪化する危険があります。
事故発生後に頭部を
不用意に動かすリスク
交通事故で頭部を負傷した場合は、頭を動かすことは避けてください。
不用意に動かすと、脳への圧迫や損傷が広がる恐れがあります。
首の骨(頸椎)が同時に損傷している可能性もあり、動かすことで神経が傷つき、麻痺などを引き起こす危険性が生じます。
被害者に意識がある場合でも、事故直後は自ら動こうとせず、周囲の人もむやみに触れず、医療スタッフの到着を待つことが最も安全です。
交通事故の頭部外傷が命に関わる
理由と死亡に至る原因
頭部の怪我は、一見軽傷に見えても、頭蓋骨の内部では命を脅かす変化が進行している場合があります。
急性硬膜下血腫など、
致命的になりうる脳損傷
交通事故で頭部を強打した場合は、急性硬膜下血腫などの脳損傷を負う可能性があります。
急性硬膜下血腫とは、強い衝撃によって脳を覆う硬膜の下にある血管が破れ、短時間で血液が溜まり、脳を圧迫する状態です。
これにより深刻な機能障害が生じ、意識低下や呼吸停止、最悪の場合は死亡に至ることがあります。
事故後すぐに意識が混濁する、片側の瞳孔が拡大するといった異常が見られた場合には、直ちに救急搬送し、外科的処置を受けることが求められます。
特に高齢者は脳の萎縮により空間が広く、血腫ができやすい傾向があるため注意が必要です。
症状が遅れて現れる
「時間差死」のリスク
初期に異常が見られなくても、後から症状が現れ、突然の意識喪失や呼吸停止に至る「時間差死」が起きる可能性があります。
慢性硬膜下血腫は急性硬膜下血腫とは異なり、症状の進行が緩やかなのが特徴です。
事故直後には意識がはっきりしていても、数時間〜数日後に脳内の出血やむくみ(脳浮腫)が進行し、容態が急変することがあります。
事故後は少なくとも24〜48時間、神経症状の有無に注意を払い、少しでも違和感があれば医療機関で再診を受けましょう。
なお、高齢者が事故後に「ぼんやりしている」「元気がない」といった様子を示した場合は、脳に異常が生じている可能性もあるため、慎重な対応が必要です。
搬送・処置の遅れによる
予後の悪化
重篤な頭部外傷では、早急に脳圧を下げるなどの専門的治療を開始できるかどうかが、生死や後遺障害の程度を大きく左右します。
たとえば、救急搬送の遅れによって脳圧が急激に上昇し、脳幹の圧迫や壊死につながる可能性もあるため、迅速な救急対応が不可欠です。
初期診断の誤りや観察不足によって処置が遅れた場合は、本来救命可能であった事例でも命を落とすおそれがあります。
そのため、事故現場で異変を感じたら、迷わず医療機関へ連絡することが求められます。
交通事故で頭を打った後に
注意すべき危険な症状のサイン
頭部外傷は、事故直後には異常が見られなくても、時間の経過とともに重篤な症状が現れることがあります。
「後から症状が出てくる」可能性を念頭に置き、危険な兆候を見逃さないことが重要です。
意識障害・嘔吐・痙攣は
危険信号
事故後に意識障害、繰り返す嘔吐、痙攣などが見られた場合は、脳内出血や急性硬膜下血腫などの重大な損傷を示している可能性があります。
話しかけても反応が鈍い、視線が合わないといった症状も、極めて危険な状態といえます。
「少し様子を見よう」という自己判断は避け、速やかに医療機関を受診することが重要です。
事故後すぐに症状が出ない
遅発性の損傷にも注意
頭部への衝撃による損傷は、事故から数時間後、数日後、場合によっては数週間後に症状が現れることがあります。
交通事故で頭だけに怪我を負い、他の部位に外傷が見られない場合でも、頭部の衝撃には重大な危険が潜んでいます。
たとえば、軽い頭痛やめまいが後に脳出血へ進行することもあるため、早期の受診と経過観察が欠かせません。
遅発性の代表的な症状である慢性硬膜下血腫は、高齢者では初期に自覚症状がほとんど現れないのが特徴です。
交通事故の後に、徐々に頭痛、物忘れ、歩行障害などの症状が見られる場合は、脳損傷が進行している可能性もあります。
そのため、事故後は一定期間、体調の変化に注意し、少しでも違和感を覚えた際には、迷わず脳神経外科などを受診してください。
子ども・高齢者が頭を打った
際に気を付けるべきポイント
子どもや高齢者は、頭部外傷後の症状をうまく言葉で伝えられないことがあるため、周囲の人が変化に気づき、適切に対応することが重要です。
小児の場合は、顔色が悪い、ぐったりしている、ミルクを吐く、機嫌が悪く泣き止まないなどの様子が見られた際は注意が必要です。
高齢者についても、急にぼんやりしている、会話がかみ合わない、普段より元気がないなど、「いつもと違う様子」がある場合には、本人からの訴えがなくても、危険な兆候と捉えて医療機関へ連れて行くことが望まれます。
交通事故による頭部外傷で
生じる症状と後遺障害
頭部への衝撃は、軽度な不調から生活を一変させるほどの重い後遺障害まで、さまざまな影響を及ぼす可能性があります。
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故による頭部外傷の治療を終えた後も、身体や精神に残る機能障害や症状を指します。
症状の種類や程度に応じて「後遺障害等級」に区分され、認定された等級は保険や損害賠償の判断基準となります。
脳への損傷が強い場合には、記憶障害、注意力の低下、言語障害、麻痺などが残り、日常生活や社会活動に支障をきたすおそれがあります。
なお、頭部の負傷による後遺障害は見た目で判断しづらいものも多いため、専門医による客観的な評価が不可欠です。
後遺障害等級認定の
基本的な仕組み
後遺障害等級とは、交通事故によって残った後遺症の程度に応じて、自動車損害賠償保障法に基づき1級から14級までに分類される制度です。
たとえば、頭部外傷で脳損傷による麻痺を負った場合、症状に応じて12級、9級、7級、5級、3級、2級、1級などに認定される可能性があります。
なお、後遺障害として認定されないと、後遺障害慰謝料を受け取ることはできないため、医師に診断書の作成を依頼するなど、申請手続きが必要になります。
頭痛・めまい・
集中力低下などの症状
比較的軽度な頭部外傷でも、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、集中力や記憶力の低下といった症状が続くことがあります。
これらは「脳振盪後症候群」や「外傷性頸部症候群(むちうち)」などに伴う症状であり、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
症状の程度や持続性によっては、9級、12級、14級などに認定される可能性があります。
後遺障害の認定を受けるためには通院が不可欠ですので、事故からしばらくしても症状が改善しないときは、必ず医師に相談してください。
麻痺・記憶障害など
重度の後遺障害
脳が直接損傷を受けると、身体の麻痺、言語障害、記憶障害、感情のコントロールができない、注意力が散漫になるといった重い後遺症が残ることがあります。
これらは高次脳機能障害と呼ばれ、外見からは分かりにくいことから「見えない障害」と言われています。
高次脳機能障害は、症状の重さや生活への影響度に応じて、9級、7級、5級、3級、2級、1級などに認定される可能性があります。
日常生活や社会復帰に困難を伴うことも多く、専門的なリハビリや周囲の支援が不可欠です。
また、高次脳機能障害でも、症状によって認定される後遺障害等級は異なり、受け取れる慰謝料の額にも差が生じます。
そのため、びまん性軸索損傷など、交通事故で重大な障害を負った場合には、治療や通院を中断せずに続けることが大切です。
交通事故の示談交渉や
後遺障害対応は弁護士へ相談
交通事故で頭部を負傷し、高次脳機能障害のように判断が難しい後遺障害を負ったときは、弁護士によるサポートを受けることを検討してください。
交通事故の被害者となった場合、後遺障害の等級認定や保険会社との損害賠償交渉など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
そのような対応も、弁護士に相談することで、適切な慰謝料を受け取るための証拠収集や手続きを代行してもらうことができます。
さらに、保険会社との交渉にも専門的に対応してもらえるため、正当な補償を受けるうえで大きな支えとなります。
被害者が治療やその後の生活に専念するためにも、できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士へ相談することが望まれます。
交通事故で頭を打った後の後遺障害でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠





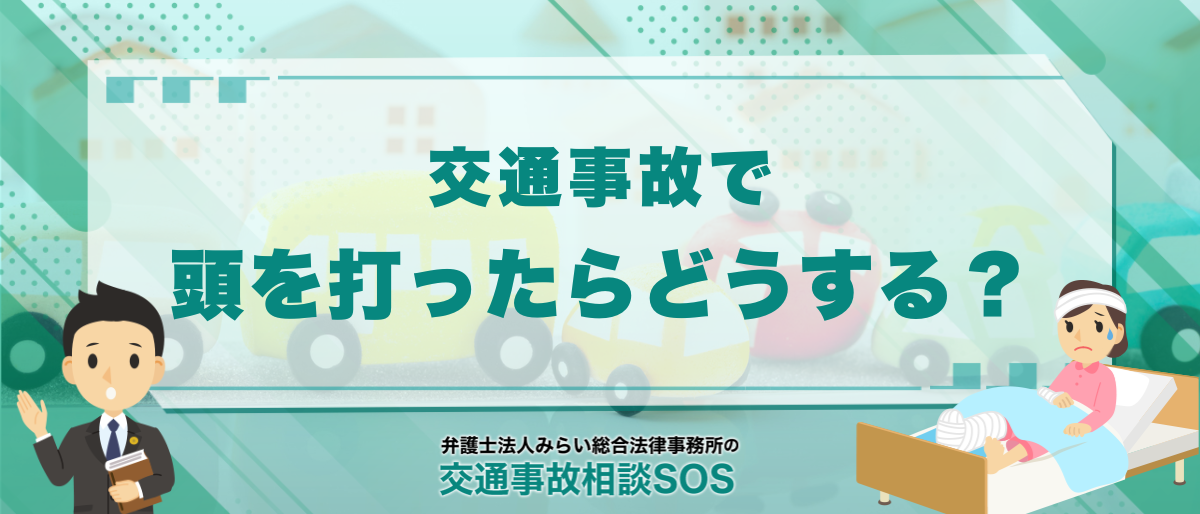





の慰謝料額と増額事例.png)









の後遺障害等級.png)

