交通事故で加害者が死亡したら泣き寝入り?損害賠償請求の方法と注意点
交通事故の被害者は、加害者に対して受けた損害の賠償を求めることができます。
ただし、加害者が事故によって死亡した場合には、任意保険の加入状況などによって、損害賠償の請求先が変わる可能性がある点には注意が必要です。
本記事では、交通事故によるトラブルで泣き寝入りしないために、損害賠償請求の基本的な仕組みと注意すべきポイントについて解説します。
目次
交通事故の加害者が死亡した場合、
損害賠償請求はできるのか?
交通事故により加害者が死亡した場合には、状況により損害賠償を請求することは可能です。
損害賠償請求権は
加害者の死亡後も有効
交通事故によって治療費・通院費・慰謝料などの実損が発生している場合、被害者は加害者の相続人に対して損害賠償請求を行うことができます。
相続が発生すると、相続人はプラスの財産のみならず、債務を含むマイナスの財産も引き継ぐことになります。
損害賠償請求権は民法において債権として位置づけられており、加害者が死亡した場合には、その法的責任が相続人に承継されます。
債務の承継と損害賠償請求の
実務上の注意点
加害者が死亡した場合、その損害賠償に関する法的責任(債務)は遺産とともに相続人へ引き継がれます。
しかし、相続人が相続放棄をしているときは、損害賠償の請求先が存在しなくなる可能性もあるため、その確認が求められます。
また、被相続人が任意保険に加入しているか否かによって、回収可能な損害賠償額に大きな差が生じる点にも注意が必要です。
交通事故の加害者が死亡した際の
損害賠償請求先
加害者が死亡した交通事故における損害賠償請求先は、相続人の有無や保険の加入状況によって異なります。
加害者が任意保険に加入している場合
加害者が任意保険契約を締結していた場合、保険契約の条件を満たせば損害賠償請求は保険会社に対して行うことができます。
任意保険には「対人賠償責任保険」などが含まれており、死亡事故による損害賠償責任を補償する内容が一般的です。
加害者が亡くなっていたとしても、契約が有効である限り、保険会社が被保険者に代わり賠償責任を負います。
加害者が自賠責保険にのみ
加入している場合
自賠責保険は、すべての車両に加入が義務づけられている基本的な保険であり、任意保険未加入時には、自賠責保険会社から賠償金の支払いが行われます。
死亡による損害は最大3,000万円、後遺障害による損害は程度に応じて最大4,000万円、傷害による損害は最大120万円が上限です。
任意保険に比べると補償額は少ないため、損害額が大きいケースでは、十分な賠償を受けられない可能性があります。
加害者の相続人に対して
請求するケース
自賠責保険の限度額を超える損害が発生した場合、被害者は加害者の相続人に対して損害賠償請求を行うことになります。
被相続人の配偶者は必ず相続人となり、子がいるときは、配偶者と子が相続人です。
子がいない場合は両親が、両親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
一方で、相続人が相続放棄をしているケースでは、損害賠償請求先が事実上消滅する可能性があるため、事前に相続状況を確認することが不可欠です。
こうした場合には、弁護士に依頼して加害者の戸籍謄本などを取得し、法定相続人を確定する「相続人調査」の実施も検討すべきです。
請求先の確定は損害賠償交渉の出発点となるため、早期に専門家へ相談することを推奨します。
加害者が死亡した場合、
損害賠償請求額に影響はあるのか
加害者が死亡していたとしても、損害賠償として請求できる金額が減額されることはありません。
ただし、加害者の経済状況や保険加入の有無、事故内容などに応じて、実質的な回収可能額には差が生じる可能性があります。
加害者の資力・保険契約の有無が与える影響
損害賠償請求額の理論的な算定において、加害者が生存しているかどうかは関係ありません。
保険が適用される場合には、加害者の死亡後であっても契約内容に基づいて補償がなされるため、請求金額への実質的な影響はないです。
一方で、加害者が十分な資産を保有していない場合や、任意保険に未加入であった場合には、実際に得られる賠償金が制限される可能性があります。
特に治療費や慰謝料などの請求が高額となるケースでは、回収の成否が相続人の支払い能力に依存するため、保険加入状況が受け取れる賠償金額に大きな影響を及ぼします。
過失割合・事故状況による
金額変動
損害賠償額は、事故発生時の過失割合および損害内容に応じて変動します。
加害者が死亡している場合でも、事故状況の客観的記録に基づき過失割合が判断され、適正な賠償額が算定されます。
交通事故の被害者に事故の発生原因(過失)が認められた場合は、その割合に応じて請求金額が減額されるため、留意が必要です。
さらに、治療費、通院回数、後遺障害の有無なども金額に影響する要素となるため、事故直後から記録や証拠書類は正確に残しておくことが大切です。
損害賠償を請求する際に
留意すべきポイント
加害者が死亡している場合は、相続状況によって請求先や回収ルートが変化する可能性があるため、事前の確認が重要です。
加害者側の保険契約内容や適用範囲、自賠責保険との関係を把握し、被った損害に対して適正な補償が受けられるようにする必要があります。
加害者の相続人に支払能力がある場合でも、補償額は示談交渉によって決定されます。
提示する請求額が妥当かつ合理的であることを証明するためには、医療費の明細書、損害項目の算定資料、事故証明書などの資料を整えておくことが不可欠です。
加害者死亡時における
損害賠償請求の方法
加害者が交通事故により死亡した場合であっても、被害者による損害賠償請求手続は法的に確立されていますが、いくつか注意すべきポイントもあります。
示談交渉で請求する際の流れ
加害者の死亡後に行う損害賠償請求は、原則として示談により解決を図ります。
被害者は、加害者の相続人または保険会社と交渉を行い、慰謝料や治療費を含めた賠償額の合意形成を目指します。
加害者が任意保険に加入していた場合は、交渉の相手方は保険会社となり、保険契約の内容に基づいて補償が行われます。
一方、任意保険に加入していなかった場合は、加害者の相続人との直接交渉が必要となります。
示談が成立しない場合には、民事訴訟により損害賠償を求めることも可能です。
訴訟においては、加害者の相続人を被告として提起し、証拠書類・相続関係・資産状況を踏まえて裁判所が賠償額を判断します。
遺産分割や相続放棄が影響するケース
加害者の死亡後に、相続人間で遺産分割や相続放棄が行われた場合には、損害賠償請求先に変化が生じる可能性があります。
原則として、加害者の法定相続人に対して、法定相続分に応じて請求することができますが、遺産分割により債務を承継した相続人がいる場合には、その者に対して損害賠償を請求することが可能です。
一方で、相続人全員が家庭裁判所に相続放棄を申し立てたときは、加害者の財産を引き継ぐ者が存在しなくなり、請求先が消滅するおそれがあります。
このようなケースでは、加害者側の任意保険会社へ直接請求することを検討します。
また、加害者が任意保険に未加入であった場合は、自賠責保険を用いた被害者請求により、限度額の範囲内で賠償金の支払いを受ける手続きを進めることになります。
損害賠償請求権の時効には
要注意
損害賠償請求権には時効が定められています。
人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の時効は、以下のいずれか早い方とされます。
- 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間行使しないとき
- 加害者不明の事故の場合は事故発生時から20年間行使しないとき
加害者が死亡しており、相続人の調査などに時間を要したとしても、時効の進行は止まりません。
また、被害者が加害者側の自賠責保険に直接請求(被害者請求)する場合には、原則として事故発生日(症状固定日)の翌日から3年で時効となりますので、可能な限り早期に行動を開始することが重要です。
交通事故で賠償請求が困難になる
ケースと泣き寝入りを防ぐ対策
交通事故において加害者が死亡した場合、損害賠償請求は理論上可能である一方、実際には回収が困難となる場面も少なくありません。
被害者が泣き寝入りを回避するためには、事前の確認と対策が不可欠です。
加害者側に支払能力がない
場合の対応
加害者が死亡しており、相続人が相続したものの相続人に資産や保険契約が存在しない場合には、賠償金の回収が極めて困難となります。
任意保険に加入していない場合には、保険会社への請求も行えず、相続人に資力がない場合は賠償金の支払い能力も期待できません。
自賠責保険による最低限の補償が適用されることがありますが、死亡事故や重傷事故においては、実際の損害額に対して補償が不足することが多く見受けられます。
このようなケースに備え、交通事故被害者救済制度の活用や、法律専門家への早期相談が推奨されます。
相続人全員が相続放棄した
場合の影響
加害者の相続人が全員相続放棄をした場合、損害賠償請求の対象が消滅してしまう可能性があります。
相続放棄によって法的には加害者の遺産も債務も承継されないため、請求権が行使できない状態となるのが一般的です。
ただし、相続人が放棄しても次順位の法定相続人が現れる可能性があり、完全に請求先が途絶えるかどうかは事例によって異なります。
そのため、加害者が死亡したケースでは、早期に相続状況を調査し、保険請求や他の法的手段を検討することが重要です。
被害者自身の保険活用の検討
交通事故において、加害者が無保険である場合や、相続人が十分な賠償能力を有していない場合には、被害者自身が加入している自動車保険の活用も選択肢となります。
たとえば、「人身傷害補償保険」は、加害者が任意保険に未加入であったり、賠償能力がない場合でも、一定の補償を受けることができる制度です。
加害者側との示談交渉は長期化することがありますが、人身傷害補償保険を利用すれば、示談成立を待つことなく、契約している保険会社から治療費や当面の生活費などを迅速に受け取れます。
また、「無保険車傷害保険」は、任意保険未加入車との事故や、当て逃げ等により相手が不明な場合、被害者または同乗者が死亡したり後遺障害を負った場合に活用できる保険です。
こうした制度の理解と整備を平時から行っておくことが、万一の事故への備えとして有効です。
泣き寝入りを避けたいときは
弁護士に依頼すること
交通事故において加害者が死亡している場合でも、被害者は自身が被った損害に対する賠償を請求することが可能です。
しかし、相続人による相続放棄や、加害者が任意保険に未加入であるなど、法律や制度上の複雑な事情が絡むことも少なくありません。
十分な損害賠償請求が行えず、泣き寝入りを強いられる事態を避けるためには、交通事故や相続問題に精通した弁護士への早期相談が極めて重要です。
弁護士は、法的な請求可能性の有無や請求先の調査、自賠責保険・任意保険の適用可否の判断など、複雑な手続きを専門的に支援します。
加害者が死亡しているケースでは、請求権の消滅リスクや手続き上の制約が生じやすいため、専門家の助言を受けながら対応することが、被害回復への確実な第一歩となります。
交通事故の加害者が死亡しているケースでお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠





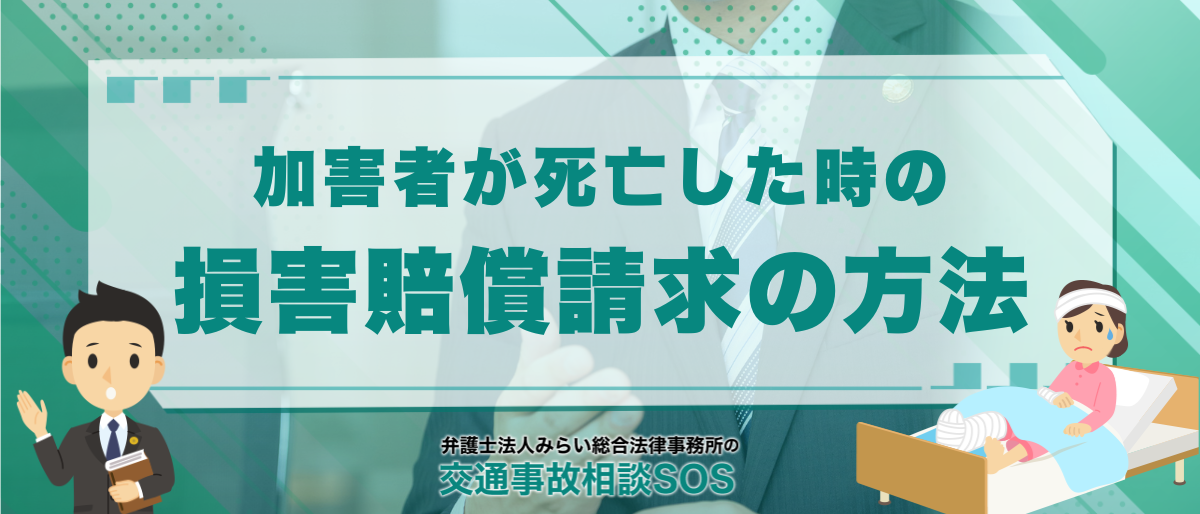














の後遺障害等級.png)

