後遺障害は再認定される?同一部位に二度目の認定が認められる条件とは
交通事故によって既存の後遺障害が悪化した場合には、再び後遺障害として認定される可能性があります。
ただし、後遺障害の再認定には一定の条件を満たす必要があるため、申請すれば必ず認定されるとは限りません。
本記事では、後遺障害の再認定の可否と認定される条件について、制度的観点から詳しく解説します。
目次
後遺障害とは
交通事故などにより生じた傷病が、治療によって症状固定に至った後も、身体に一定の障害が残存する場合には、「後遺障害」に該当する可能性があります。
※症状固定:治療を継続しても症状の大きな改善が見込めない状態
後遺障害の定義と損害賠償制度における位置づけ
後遺障害とは、事故などによる負傷が治療を経ても完治せず、身体機能・容貌・神経系に一定の障害が残存する状態を指します。
治療終了後に症状が残る状態は「後遺症」と呼ばれますが、後遺障害は所定の申請手続きを経て認定された場合にのみ成立するため、「後遺症」とは制度上の意味が異なります。
また、後遺障害と認定された場合、「後遺障害慰謝料」の請求が可能となり、被害者が受け取れる賠償額は増加します。
さらに、後遺障害によって将来的な収入の減少が認められた際には、逸失利益の請求も可能となるため、適正な損害賠償を得るには後遺障害認定が不可欠です。
後遺障害がもたらす
生活・仕事への影響
交通事故で後遺障害を負った場合、日常生活の質や就労能力に深刻な影響を及ぼします。
症状が重度の場合には、歩行・視覚・聴覚などの機能低下や、慢性的な疼痛・疲労によって、仕事や家庭内での役割に制限が生じることがあります。
職種によっては復職や継続勤務が困難となるケースもあり、収入の減少や精神的負担を招く可能性があります。
そのため、交通事故の損害賠償請求においては、こうした生活の変化や将来不安を的確に反映させることが求められます。
後遺障害等級の分類と認定基準
後遺障害は、重症度および社会生活への影響の程度に応じて、1級から14級に分類されます。
認定される等級は損害賠償額に直結するため、正確な診断と資料の整備が不可欠です。
14級は比較的軽微な障害とされ、1級は最も重篤な障害が認められる場合に適用されます。
たとえば、交通事故による両眼の失明は1級、外貌に醜状が残った場合には12級に該当します。
後遺障害の認定は、症状の客観性・継続性・医学的所見の有無などを勘案して判断されます。
同一の傷病であっても、認定される等級が一律とは限らないため、適切な申請手続きと医学的根拠の提示が重要です。
後遺障害は二度目は認定されない?
後遺障害として既に認定されている場合でも、一定の条件を満たせば再認定が認められる可能性があります。
同じ部位の後遺障害認定は
原則一度のみ
自賠責保険制度においては、後遺障害の認定は原則として一度限りとされています。
後遺障害は、治療を継続しても症状の改善が見込めない「症状固定」と判断された時点で認定されるため、一度目の認定により、後遺障害は評価されており、既に認定された等級が後から変更されることは通常ありません。
したがって、同一部位に対して再度の認定を受けるには、例外的な事情や新たな医学的根拠の提示が不可欠です。
例外的に後遺障害の再認定が
行われる条件
後遺障害の認定は、原則として一度限りです。
しかし、過去の交通事故で後遺障害を負った人が新たな交通事故に遭遇し、既存の症状が悪化した場合など、例外的に再認定が認められるケースもあります。
たとえば、初回の後遺障害で神経症状が残存していた人が、二度目の交通事故により機能障害等の新たな障害を負ったときは、異なる等級が判断される可能性があります。
また、異なる交通事故で同一部位を負傷したとしても、症状の性質が異なる場合には、別の後遺障害として再認定されることがあるため、症状に応じた適切な認定申請が必要です。
後遺障害の再認定が
認められるケース
一度認定された後遺障害であっても、症状の悪化や新たな医学的証拠の提示により、再認定が認められた判例が存在します。
二度目の交通事故で
症状が重篤化した場合
後遺障害の認定を受けている人が、新たな交通事故が原因で症状を悪化させた場合には、加重障害として扱われる可能性があります。
加重障害とは、新たな交通事故によって、既に後遺障害が認定されていた同一部位に再び障害を負い、障害の程度が以前よりも重くなった場合に適用される評価方法です。
加重障害に認定された場合、再認定された後遺障害の等級に基づく保険金額から、初回認定時の等級に基づく保険金額を控除した差額分が請求対象となります。
当初14級として認定されていた人でも、別の交通事故で12級の後遺障害を負ったときは、等級差に応じた金額を受け取ることができます。
後遺障害の再評価
(異議申し立て)
交通事故による損傷部位が同一であっても、初回認定時には認識されていなかった新たな症状や、症状の悪化が医学的に証明された場合には、後遺障害の再評価(異議申し立て)が認められる可能性があります。
たとえば、初回認定後に撮影したMRIで新たな神経圧迫が確認された場合や、疼痛の評価方法に新たな客観的所見が加わった場合には、等級が見直され、より上位の等級に認定されることがあります。
裁判などによる
後遺障害の再認定
後遺障害の初回認定後に症状が顕著に悪化し、新たな画像検査により異常所見が確認された場合、裁判や紛争処理手続きを通じて、再認定(等級の見直し)が認められた事例も存在します。
たとえば、むち打ち症で14級の等級認定を受けた人でも、神経症状の悪化および新たな画像所見に基づき、等級が12級または9級に引き上げられることもあります。
そのため、後遺障害について新たな医学的根拠と事故との因果関係が合理的に説明できる場合には、再認定の申請も選択肢となります。
同一部位における
新たな後遺障害の認定ポイント
同一部位に対して新たな後遺障害の認定を受けるためには、前回の認定時とは異なる医学的に客観的な証拠を提示することが求められます。
新たな症状が以前の障害と
異なる性質を持つ場合
前回の交通事故で認定された症状とは性質の異なる障害が同一部位に発生した場合には、新たな後遺障害として認定される可能性があります。
たとえば、以前は軽度の痺れのみであったものが、二度目の交通事故により麻痺や排尿障害など、より重度の神経機能障害が出現した場合には、症状の性質が異なるため、別の後遺障害として判断されます。
症状の変化が明確であるほど再認定の根拠として有効となるため、治療の継続に加え、症状の進行を詳細に記録することも重要です。
損傷部位の医学的な区別を
明確に示す
後遺障害の再評価を受ける場合、「以前の交通事故による障害」と「今回の交通事故による損傷」が医学的に異なることを明確に示す必要があります。
たとえば、以前は筋肉の損傷であったものが、今回は神経損傷による新たな機能障害が確認された場合など、病態が異なると診断されている場合には、新たな後遺障害として認定される余地があります。
医師の見解を裏付ける画像検査(MRI、CTなど)や、診療録による損傷部位の明確な区別は、説得力のある証拠となります。
後遺障害の認定を
受けるまでの期間
後遺障害の申請は、症状固定の診断を受けた後に手続きを行うものですが、症状固定の診断が事故後6ヶ月未満である場合には、後遺障害等級認定の審査が通りにくい傾向があります。
ただし、6ヶ月という期間はあくまで目安であり、申請時期だけで可否が決まるものではありません。
症状固定までの期間が6ヶ月未満であっても、手足の欠損など医学的に回復困難と判断された場合には、後遺障害として認定されることがあります。
後遺障害の認定手続きを
弁護士に相談すべき理由
後遺障害の再認定は例外的なものであるため、再認定を受けるためには、交通事故対応に精通している弁護士の関与が不可欠です。
再認定申請に必要な
法的・医学的戦略
後遺障害の再認定を申請する場合、医学的根拠を申請書に的確に落とし込む戦略が求められます。
単なる診断書の提出だけでは不十分であり、症状の変化、画像所見、新たな制限等を明確化し、後遺障害認定基準に沿って論理的に構成する必要があります。
一般人である被害者が、専門的な手続きおよび対策を講じることは困難です。
そのため、弁護士に認定事例との照合や申請文書の設計を依頼するなどして、認定の可能性を高めてください。
弁護士費用について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
判例・認定基準の理解と
交渉力の差
後遺障害認定は、表向きの基準だけでなく、過去の判例や認定傾向も大きく影響します。
弁護士はこれらの実例を分析し、申請書類に効果的に反映させることで、有利な交渉を可能にします。
保険会社との対応では、医学的主張を法的根拠で裏付けることにより、慰謝料や逸失利益の増額を実現できます。
専門知識の差は、認定の成否および賠償額に直結するため、適切な損害賠償金を受け取るには弁護士の関与は欠かせません。
適切な認定を受けて
賠償額を高める専門家の役割
後遺障害が適切に認定されれば、損害賠償額は大幅に増加する可能性があります。
弁護士は医学的見解の整理・補足から、認定機関や裁判所への戦略的主張までを担い、認定精度および賠償額の最大化に貢献します。
また、専門医との連携を図りながら、通院記録や診断書の信頼性を高める役割も果たすなど、弁護士は事故被害者の法的権利を守るうえで重要な存在です。
後遺障害の再認定手続きは
弁護士に依頼すること
後遺障害等級の認定の可否や賠償額の妥当性を正しく判断し、手続きを円滑に進めたい場合には、専門の弁護士に相談することが推奨されます。
交通事故による後遺障害は、医学的な複雑性と法的な判断が交錯する領域であり、被害者個人での対応には限界があります。
弁護士に相談・依頼すれば、医学的根拠と法的戦略を融合させた的確な対応が行えるだけでなく、被害者の権利保護および適正な補償の実現につながります。
交通事故の被害に直面した際には、早期に弁護士へ相談し、適正な認定および補償の確保に努めてください。
交通事故での後遺障害等級の認定でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠





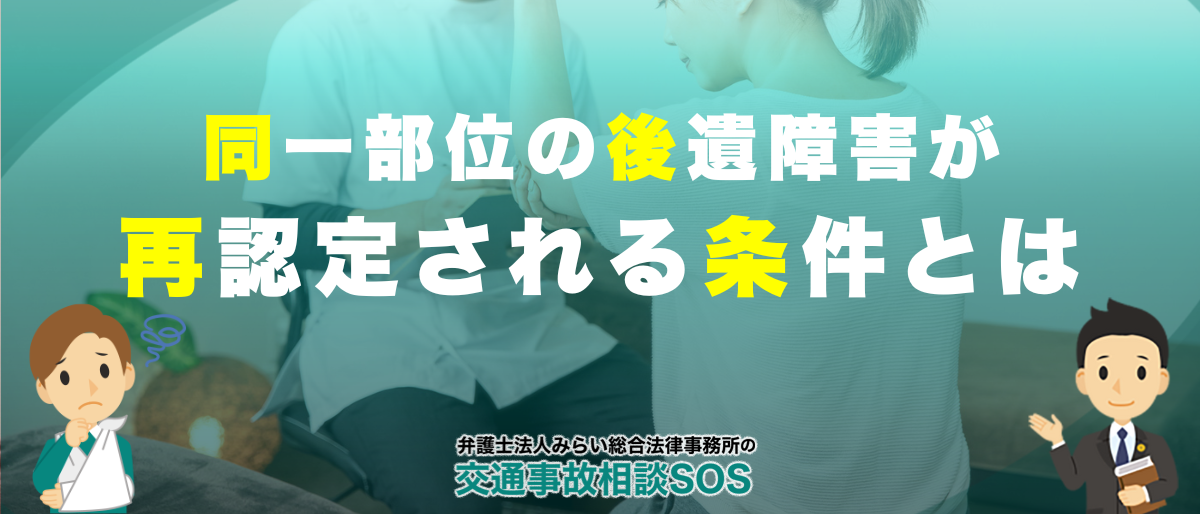














の後遺障害等級.png)


