交通事故で裁判のやり方・費用・流れを解説
交通事故の慰謝料など損害賠償金の示談交渉が決裂した場合、どうすればいいのでしょうか?
その場合、被害者の方やご家族は、提訴して裁判で決着をつける、という方法があります。
しかし、
- 事を大きくして、裁判まではやりたくない。
- 裁判では何を、どうすればいいのか、
わからない。 - 費用はどのくらいかかるのか不安だ。

といった方も多いかもしれません。
そこで本記事では、交通事故の被害者やご家族が加害者側と裁判をする際の、やり方や全体の流れと手続き、費用などについて解説していきます。
民事裁判の流れと各手続について
一般的に、民事裁判は次のような流れで進んでいきます。
訴状の提出・訴状審査
訴訟を提起するには、訴状を裁判所に提出します。
裁判所は訴状を審査し、第1回口頭弁論期日を決定します。
被告に対する呼び出し
裁判所が、被告に訴状と呼出状を送ります。
被告は、訴状の内容を確認して、答弁書を提出します。
注意ポイント
訴訟では、誰を被告にするかが問題になります。
交通事故の場合、
- 加害者
- 加害者が運転していた車両の保有者
(運行供用者) - 加害者が所属する会社など
が被告になり得ます。
※②については、「自賠責保険法」により自動車の運行供用者も人身損害の賠償責任を負担しているため、また、ほとんどの場合で自動車の保有者が任意保険にも加入しているため。
※③については、業務時間中の交通事故の場合、加害者の使用者である会社などに使用者責任が発生するため。
ただし、被告が多ければいいというわけではありません。
裁判の期日の調整が難しくなったり、争点が増えるため期間が長引いてしまう場合があるからです。
弁護士は、被害者の方が有利になる裁判を進めていくので、提訴する場合は一度、交通事故に強い弁護士に相談してみるといいでしょう。
口頭弁論
裁判では、被害者側と加害者側の双方が、事実の主張や法律上の主張を闘わせていきます。
なお、第一回口頭弁論期日には、原告と被告の双方が出席することになっていますが、原告の弁護士だけが出廷することも多いのが実際のところです。
そのため、やり取りは主に書面で行われることになります。
なお、あとで裁判所が被害者の方の話が聞きたいということで証人尋問が行われる場合もありますが、多くはありません。
ですから、この後も被害者の方が出廷しなければいけないということは、ほとんどないということを知っておいていただきたいと思います。
証拠書類の提出
交通事故による損害額の立証は被害者側が行なわなければいけません。
そのため、裁判の進行と並行して、たとえば次のような証拠書類の提出も行ないます。
・病院の診断書
・診療報酬明細書
・被害者の収入の証明書
・後遺症が残った時は、自賠責後遺障害等級に関する認定書類
・自賠責後遺障害診断書
和解の勧告
多くの場合、「証人尋問」に入る前に裁判所から和解勧告が入ります。
和解勧告とは、簡単にいうと、裁判所からのアドバイスです。
「このあたりで和解をしたらどうですか?」ということですね。
ここまでの過程で、裁判所はすでに最終的な判断に対する大体の心証を得ているため、判決は和解案と同程度の内容が出されることが多いのです。
そうであるなら、裁判に進む前に和解をしたほうがいいのではないですか? という意味が和解勧告にはあるわけです。
実際、被害者の方としては感情面では和解できなくても、「裁判上の和解」が成立することも多いといえます。
判決
証人尋問、当事者尋問などが行なわれ、判決が出されます。
控訴するかどうかは、弁護士と相談して進めていきます。
裁判の期間と費用について
判決が出るまでの期間は?
もちろん事案によって違いますが、判決が出るまでには、概ね半年間から1年間かかるのが通常です。
争点が医学的な観点になると、2~3年かかるケースもあります。
そのため、判決までいく前に双方が和解をする場合も多くあります。
裁判の費用
裁判では次の費用がかかります。
1.訴訟費用
相手に請求する金額(訴額)によって訴訟費用は次のように変わります。
<訴訟費用の概算>
- 訴額が100万円の場合 ⇒ 訴訟費用は1万円
- 訴額が500万円の場合 ⇒ 3万円
- 訴額が1000万円の場合 ⇒ 5万円
- 訴額が3000万円の場合 ⇒ 11万円
- 訴額が5000万円の場合 ⇒ 17万円
- 訴額が1億円の場合 ⇒ 32万円
訴訟費用は収入印紙を訴状に貼付して収めることになります。
裁判所:「手数料額早見表」
詳しい解説は「交通事故で裁判して得する人、損する人の違い」でも説明しています。
よくわかる動画解説はこちら
2.弁護士費用
ここでは、みらい総合法律事務所の場合で考えてみます。
「相談料」
みらい総合法律事務所では、交通事故に関する相談料は無料です。
「着手金」
0円です。
「弁護士報酬」
被害者の方の獲得金額(自賠責含む)の10%(消費税別途)です。
弁護士費用は高額なのか?
裁判というと、「弁護士費用が高額だから、自分には払えない…」と考えている方もいらっしゃるでしょう。
確かに、映画やドラマ、小説などでは高額の弁護士費用の場面などが描かれることがあります。
でも、それって本当でしょうか?
たとえば、加害者側の任意保険会社からの提示額が800万円の場合で考えてみます。
- 被害者の方が示談交渉を重ねたが決裂
- 弁護士に依頼して、交渉を再開
- 交渉が決裂し、裁判に
- 判決では、2500万円で解決
実際、弁護士が交渉に入ることで、損害賠償金額が2倍、3倍に増額するのはよくあることで、
場合によっては10倍以上になることもあるのです。
最新の解決実績はこちらから
2500万円×0.1=250万円
(消費税が+25万円)
となり、
と被害者の方が受け取る金額は、
になります。
保険会社の提示額は800万円だったので、弁護士費用を支払っても、被害者の方が受け取る金額は、
単純に計算して、1425万円もアップすることになるのです。
さらに深い内容を知りたい方は「交通事故の弁護士費用」の記事でもわかりやすく説明しています。
よくわかる動画解説はこちら
裁判で判決までいった場合の大きなメリット
もう1つ、被害者の方に知っておいていただきたいことがあります。
それは、裁判を起こして判決までいった場合、被害者の方には「弁護士費用相当額」と「遅延損害金」が追加で支払われる、ということです。
・認定された損害賠償金額の10%程度が弁護士費用相当額として加算されます。
判決で2500万円の損害賠償金が認められたなら、約250万円が加算されるのです。
・遅延損害金は、民法改正により、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%の割合で計算されます。
交通事故発生から1年後に判決が出て解決した場合、2500万円ならその3%にあたる75万円がさらに加算される仕組みです。
<この記事の裁判についてのまとめ>
- 裁判を起こす場合は弁護士に相談・依頼する
- 被害者の方が法廷に出廷するのは、多くても1回のみ
- 護士に依頼すると損害賠償金が増額する可能性が高い
- 弁護士費用を支払っても、被害者の方の手元に残るお金は大幅に増額する
- 裁判で判決までいくと弁護士費用を加害者側に負担させることができる
よくわかる動画解説はこちら
加害者に負担させる方法
代表社員 弁護士 谷原誠





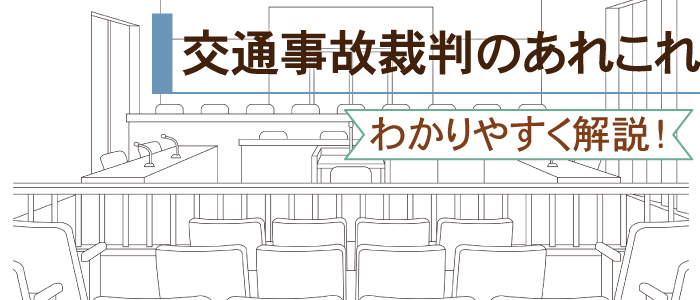

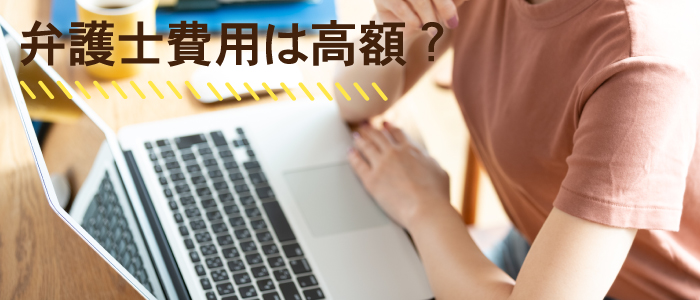







の後遺障害等級.png)

