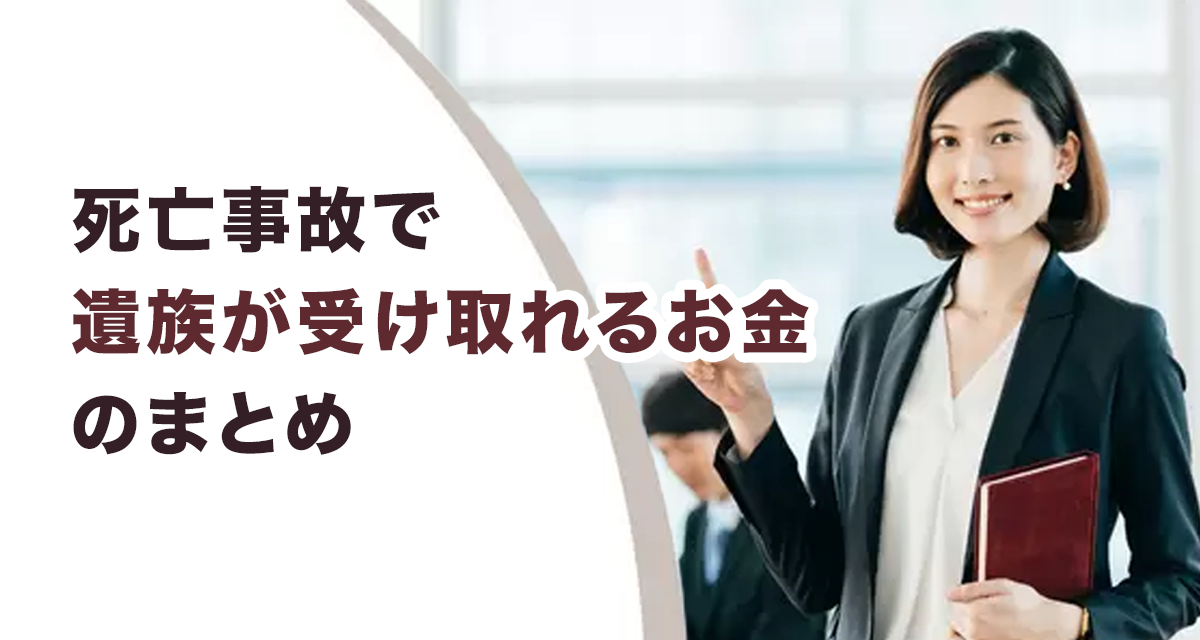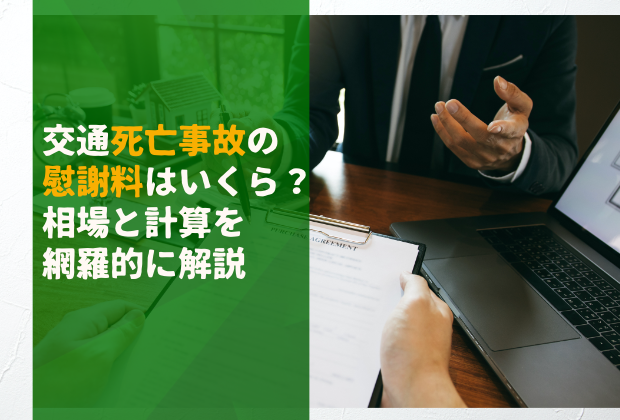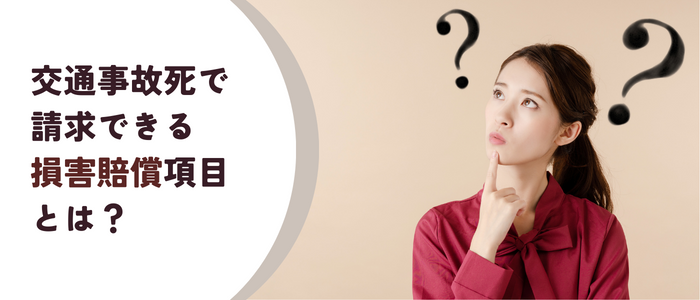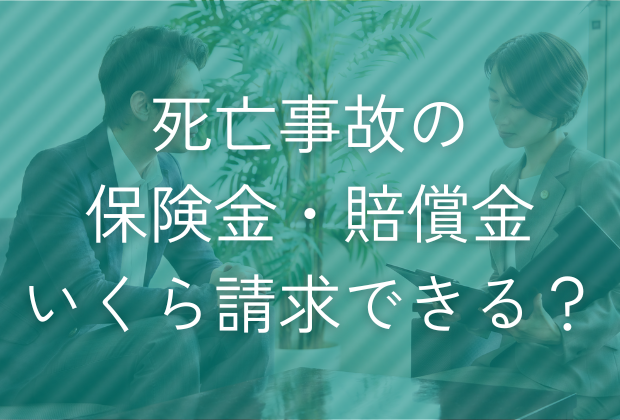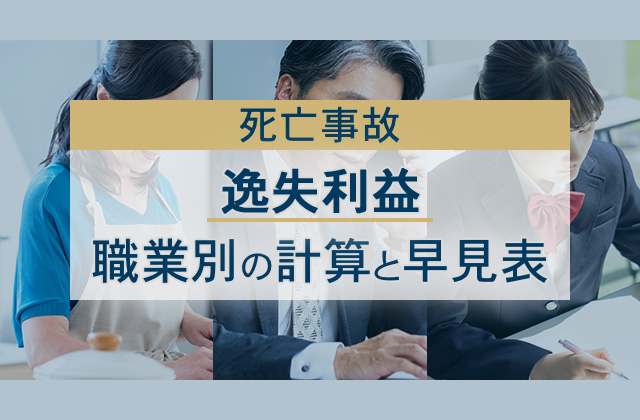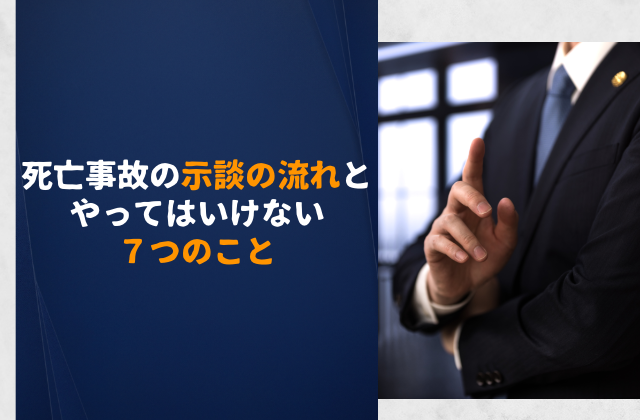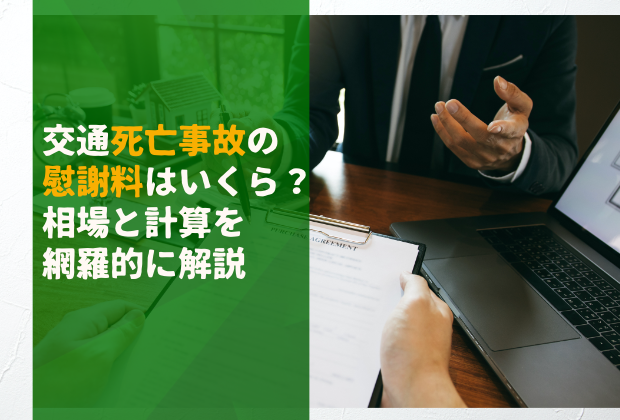死亡事故で被害者の遺族が受け取れるお金のまとめ
突然の交通事故で大切なご家族を亡くしてしまった場合、深い悲しみの中であっても、現実的に直面せざるを得ないのが「経済的補償」の問題です。
被害者が本来得られたはずの収入や生活費の補填、葬儀費用、精神的苦痛に対する慰謝料など、遺族が請求できるお金にはさまざまな項目があります。
ここでは、交通事故による死亡事故において、遺族が貰える可能性のある補償内容をわかりやすく解説します。
損害賠償請求権の相続
交通事故死の場合、被害者の家族なら誰でも加害者らに損害賠償請求することができるというわけではありません。
損害賠償請求をする前に、相続人を確認する必要があります。
相続人の確定
損害賠償請求することができるのは、被害者の相続人です。
そのため、交通事故死の場合、まずは損害賠償請求権を持っている人を確定する必要があります。
相続人の確定をする際は、被害者の戸籍を取り寄せ、相続人の確定作業を進めていきます。
子供がいないと思っていた被害者に、実は子がいた、ということもあるので、被害者の出生まで遡って相続人を調査することになります。
相続人の種類と順位
相続人の種類としては、配偶者(夫・妻)と親、兄弟姉妹、子などがあげられます。
配偶者がいる場合、配偶者はつねに相続人になるので他の相続人とともに損害賠償請求権を相続することになります。
一方、配偶者以外の相続人の場合には順番があります。
相続人順位の第1位は「子」です。
子がすでに死亡しており、子の子供、つまり被害者の孫がいれば、孫が第1位の相続人になります。
なお、子や孫がいれば被害者の配偶者は一緒に相続人になりますが、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
相続人順位の第2位は「親」です。
被害者に子がいない場合には親が相続人になり、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
ただし、被害者の配偶者は一緒に相続人になります。
相続人順位の第3位は「兄弟姉妹」になります。
子も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がその時点で死亡している場合は、兄弟姉妹の子が同順位で相続人になります。
配偶者がいれば、もちろん一緒に相続人になります。
次に、ケースごとに誰が相続人になるのかについて考えてみます。
<ケース1>
交通事故死の被害者に妻、子、親、兄がいる場合は、妻と子が相続人となり、親と兄は相続人になりません。
<ケース2>
交通事故死の被害者に子がおらず、妻、親、兄がいる場合は、妻と親が相続人となり、兄は相続人になりません。
<ケース3>
交通事故死の被害者に妻がいて、子、親、兄がいない場合には、妻が1人で相続人になります。
<ケース4>
交通事故死の被害者に妻、子、親がおらず兄だけがいる場合は、兄が相続人になります。
相続分について
相続人が確定したなら、次に問題となるのは、それぞれの相続人がいくらずつ請求できるのかということです。
仮に、被害者が生前に遺書を残していたとします。
「私の遺産の全部は〇〇に相続させる」というようなことが書かれていれば別ですが、そうでない場合は遺産分割をする必要があります。
なぜなら、誰がいくらの損害賠償請求権を持っているのか確定しなければいけないからです。
遺産分割する際には、法律で定められている「法定相続分」を知る必要があります。
同順位の相続人の法定相続分は均等
同順位の相続人が複数いる場合の法定相続分は
均等です。
日本では複数の配偶者は認められていないため、配偶者が複数いることは考えられません。
しかし、子が複数、親が2人、兄弟姉妹が複数いるというのはよくあるでしょう。
その場合、長男と長女がいるなら2人の法定相続分は均等になります。
ただし、注意が必要なのは、兄弟姉妹については、父親と母親が同じである兄弟姉妹と、父親か母親の一方だけが同じ兄弟姉妹がいる場合があることです。
この場合の相続分は、片親だけが同じ兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1が法定相続分になります。
たとえば、交通事故死の被害者に両親が同じ兄と、母親だけが同じ弟がいて、損害賠償金額が900万円だった場合は、兄の法定相続分が600万円、弟の法定相続分が300万円になります。
配偶者と他の相続人がいる場合の
法定相続分は序列が決まっている
たとえば、交通事故死の被害者に配偶者と子が
いる場合、法定相続分は配偶者と子はともに
2分の1です。
子が2人いる場合は、それぞれ4分の1ずつでこの合計が2分の1になります。
配偶者と親が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
相続の確定と損害賠償請求
相続人の確定や相続分でもめていると、被害者の遺族はいつまでも損害賠償請求ができません。
そのため、他に相続財産があって全体の相続が確定しない場合は、まずは損害賠償請求権については法定相続分にしたがって「遺産分割協議」を行なって各自の相続分に基づいて請求をするか、「遺産分割未了」のまま請求することになります。
なお、交通事故死の場合、相続の対象となる損害賠償請求権の他にも近親者特有の損害賠償請求権が発生します。
これは、近親者が被害者の死亡により深い精神的苦痛を被っているため、被害者の損害賠償請求権とは別に発生するものです。
ですから、この点は忘れずに請求することが大切です。
また、裁判になった場合、事案に応じて近親者分もすべて本人分として認められたり、本人分を減額する代わりに近親者分を認めるなどして損害分を調整することがありますので、こちらも注意が必要です。
交通事故死で請求できる
損害賠償項目とは?
交通事故死で被害者の遺族が加害者側に対して請求できる項目には主に次のものがあります。
なお、被害者が即死ではなく治療後に死亡した場合は、上記以外にも治療費なども別途請求できます。
では、それぞれの項目について具体的に見ていきます。
葬儀関係費
葬儀関係費は、自賠責保険に請求する場合は定額で60万円です。
60万円をあきらかに超える場合は、「社会通念上、必要かつ妥当な実費」が認められますが、それでも100万円以内となります。
弁護士に依頼して訴訟を起こした場合、150万円が上限になります。
墓石建立費や仏壇購入費、永代供養料などは個別の事案によって判断されます。
加害者側の任意保険会社は、大抵の場合で120万円以内の金額を提示してくるので、150万円に近づけるようにしっかり交渉するべきです。
逸失利益
逸失利益とは、被害者が生きていれば将来に得られたはずのお金です。
将来に得られたはずのお金を算定し、現時点で一時金として受け取ることを前提として「中間利息」を控除することになります。
死亡の場合その時点で所得は100%なくなるので、「労働能力喪失率」(その人が本来持っていた「働く力」がどれだけ失われたかを数値(%)で示したもの)は100%です。
また、生きていれば、生活費でいくらかのお金を費消することになります。そこで、賠償金から、生活費でかかるであろう割合を差し引くことになります。
これを「生活費控除」といいます。
そこで、死亡逸失利益の計算式は次の通りです。
(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×
(1-生活費控除率)=(死亡逸失利益)
年収は、働いていた人の場合、事故前年の年収を基本に算出します。
ただし、30歳以下の有職者の場合は、学歴別全年齢平均賃金で算出する場合もあります。
無職者(18歳未満を含む)は、男女別全年齢平均賃金で算出するのが原則です。
ただし、女子の場合は全労働者で算出することもあります。
就労可能年数は、原則として18歳から67歳とされます。
したがって、18歳以上であれば事故時までの年齢を差し引いた年数に対応するライプニッツ係数で計算します。
高齢者で67歳を過ぎても働いていた場合は、その後に何年間くらい働く蓋然性があったかによって判断されます。
年金をもらっていた場合は、その種類にもよりますが、年金額も考慮します。
通常、生活費控除については被害者が男性の場合、生活費控除率は50%とされます。
ただし、一家の大黒柱で被扶養者がいる場合は、その人数によって30~40%になる場合があります。
被害者が女性の場合は、幼児の場合も有職者の場合も30%程度で算定されるのが通常です。
慰謝料
死亡事故の場合、慰謝料は被害者本人と遺族の精神的損害に対するものになります。
相場の目安は次の通りです。
・母親・配偶者/2,500万円
・その他/2,000~2,500万円
なお、近親者が固有の慰謝料を請求する場合は、上記金額から減額され、それぞれの近親者の固有の慰謝料に割り振られたり、調整が図られたりすることがあります。
弁護士費用
死亡事案に限りませんが、訴訟となって弁護士が必要と認められる事案では、認容額の10%程度を相当因果関係のある損害として損害賠償額に加算されるのが通常です。
被害者請求をする場合の
注意ポイント
交通事故で怪我をしたり、家族が亡くなってしまった場合、加害者側の保険会社が自賠責保険金を立て替えて支払う「加害者請求」が一般的です。
しかし、加害者側とのやり取りがスムーズに進まない、あるいは過失割合などで争いがある場合、被害者自身が自賠責保険会社に直接請求できる制度を「被害者請求」と言います。
ここでは、被害者請求について解説します。
被害者請求のメリットと
デメリット
交通事故死の場合、被害者の遺族は自賠責保険に対して「被害者請求」をすることができます。
交通事故死の場合に被害者請求をするかどうかについては、まず第一に近い将来の経済生活の状況を考えることが大切です。
たとえば、一家の大黒柱が交通事故で死亡し、生命保険にも加入していなかった場合、残された家族は経済的に困窮し、路頭に迷うことになってしまいます。
そうした場合では、とにかくまずは自賠責保険に被害者請求をして、ある程度まとまったお金を得て、生活を安定させたうえで加害者側の任意保険会社と示談交渉をする必要があります。
ある程度、経済的に余裕がある場合には、被害者請求を選択するか、任意保険会社とじっくり示談交渉をしていくかを選択することができます。
被害者請求をするメリットとしては、前述のように早期にある程度まとまったお金を得ることができることがあげれられます。
また、先にまとまったお金を得ていれば、後で訴訟をする際の訴訟額が低くなるため、裁判所に納付する印紙額を低く抑えることができるというメリットもあります。
一方、デメリットとしては、申請のための資料を集めるのが大変であったり、手続きが複雑なことがあげられます。
遅延損害金とは?
一方、被害者請求をせずに裁判をするメリットもあります。
たとえば、遅延損害金が高くなることです。
その割合は、2020年4月1日より前の交通事故の場合は、事故時から年5%の遅延損害金が付加されることになります。
この遅延損害金は、民法改正により、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%の割合で計算し、その後3年毎に率が見直されることとなっています。
したがって、損害賠償請額が高ければ高いほど遅延損害金は増額します。
ただ、この遅延損害金は、示談ではつかないのが通常なので、裁判をする必要があります。
しかし、被害者請求で、たとえば3,000万円を先に受け取っていると、その分の遅延損害金が加算されなくなってしまいます。金額が大きい場合には、かなりの金額になってきます。
したがって、経済的に余裕がある場合には、被害者請求をせず、訴訟にて決着をつけることも多いでしょう。
死亡事故の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠