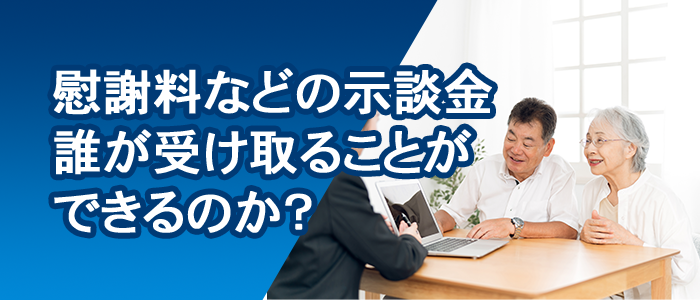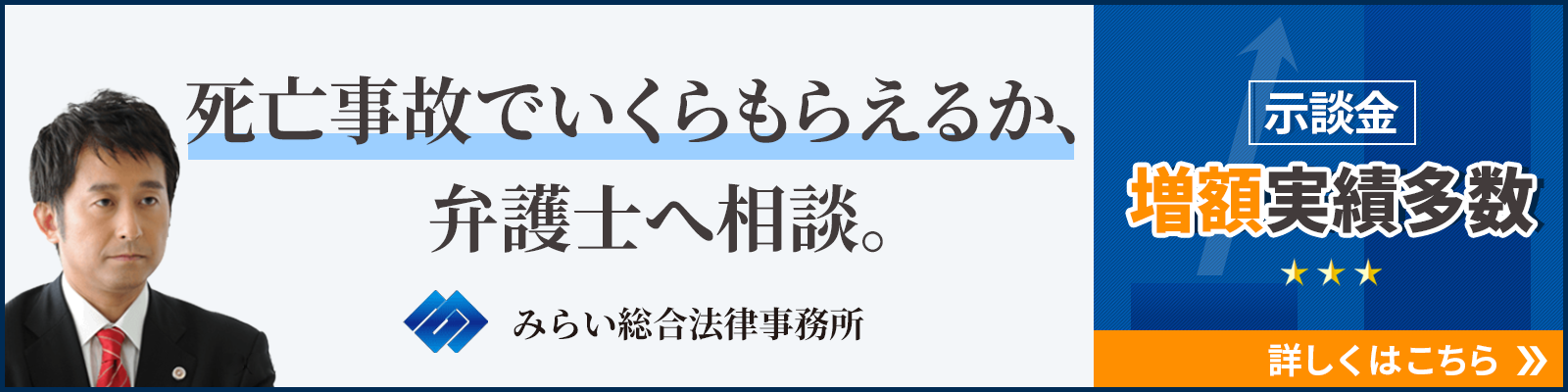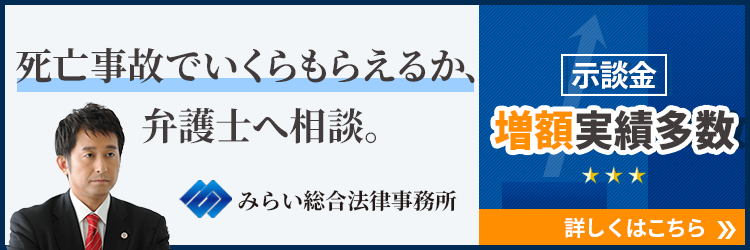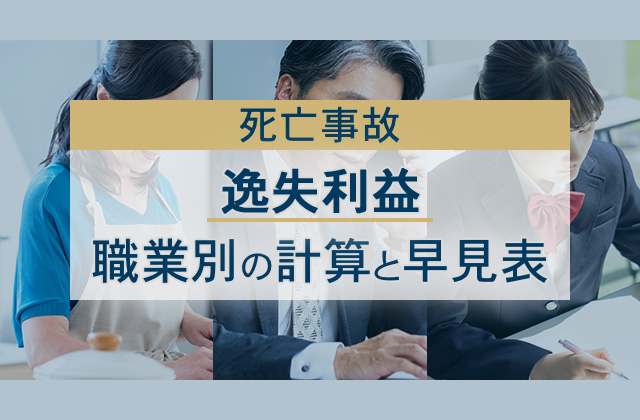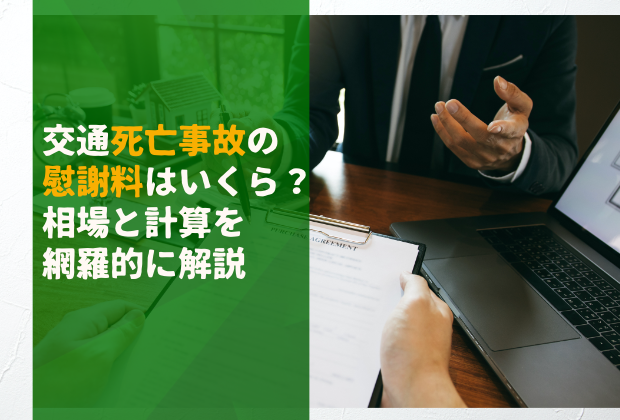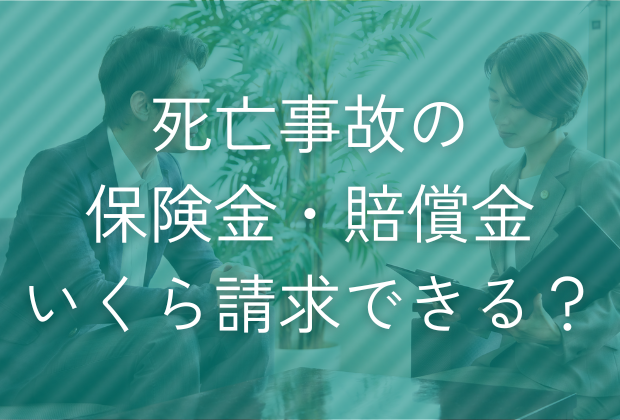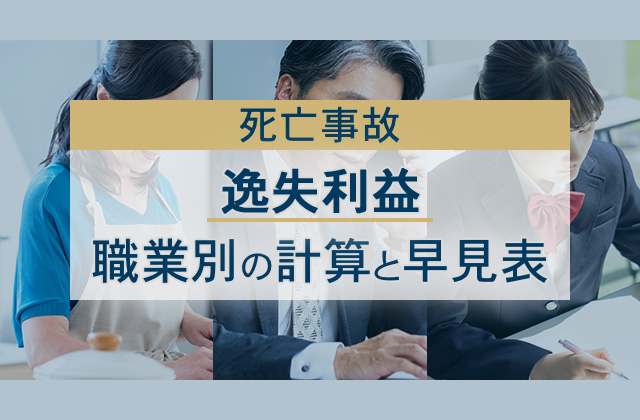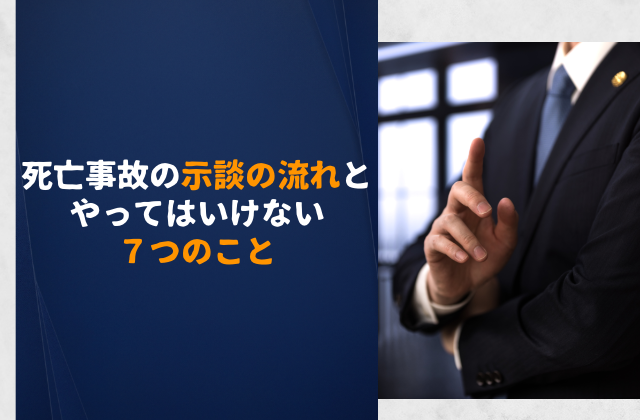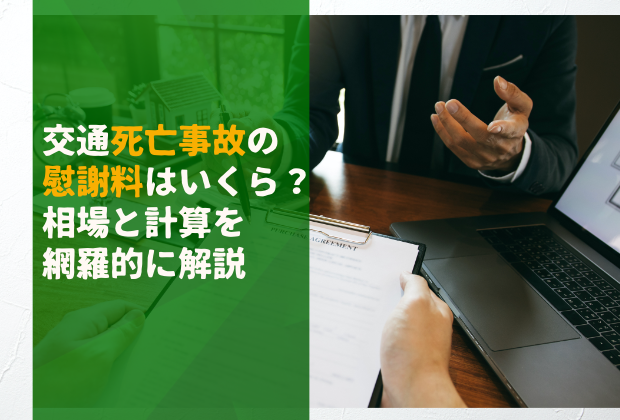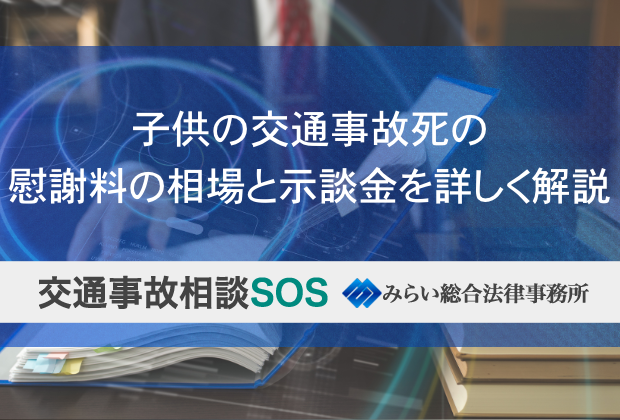死亡事故の相続の分配で誰が慰謝料・損害賠償金をもらえるのか

*タップすると解説を見ることができます。
死亡事故における慰謝料や損害賠償金は、「誰が受け取るのか」「どのように相続されるのか」といった点が複雑で、誤解が生じやすいです。
死亡事故の被害者の場合、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を受け取るのはご遺族であり、
その中の相続人になります。
配偶者はつねに相続人になり、その他の相続人には法的な「相続順位」と「分配割合」が定められています。
配偶者:2分の1
子:2分の1
配偶者:3分の2
親:3分の1
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
この記事では、死亡事故で発生する慰謝料や損害賠償金を誰が取得できるのか、また、相続の分配方法がどのように決まるのかについて、法律に基づきわかりやすく解説します。
慰謝料などの示談金は誰が受け取ることができるのか?
交通死亡事故で、加害者側の任意保険会社に損害賠償請求をして、慰謝料などの損害賠償金(示談金)を受け取ることができるのは、被害者の方の相続人になります。
そこでまず大切なことは、相続人の確定です。
相続人の種類と順位を
確定する
被害者の方に配偶者がいる場合は、つねに相続人になります。
配偶者以外の相続人には法律によって相続順位が決められています。
【相続人の順位】
第1位:子
相続人の中で第1位の順位になるのは
「子」です。
すでに子が死亡しており、子の子供(被害者の方の孫)がいれば、「代襲相続」により「孫」が相続人順位の第1位になります。
配偶者は、子や孫と一緒に相続人になります。
第2位:親
相続人の中で第2位の順位になるのは
「親(父母)」です。
被害者の方に子がいない場合は、親が配偶者とともに相続人になります。
養子縁組をした養父母も相続人になります。
第3位:兄弟姉妹
相続人の中で第3位の順位になるのは
「兄弟姉妹」です。
被害者の方に子や親がいない場合は、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子が同順位で相続人になります。
<注意ポイント>
※遺産相続では、認知されている子が相続の対象となります。
※胎児でも相続人になります。
※配偶者がいない場合は、それぞれの場合の筆頭の親族のみが相続人になり、それ以外の親族は相続人にはなりません。
相続人の分配の割合
次に相続の際の分配の割合について見てみます。
【相続人の法定相続分】
相続人が子の場合
| 配偶者 | 2分の1 |
|---|---|
| 子 | 2分の1 |
※子が2人の場合、2分の1を分けるので、1人の相続分は4分の1となる。
相続人が親の場合
| 配偶者 | 3分の2 |
|---|---|
| 親 | 3分の1 |
※両親(父母)がいる場合、3分の1を2人で分けるので、1人の相続分は6分の1となる。
相続人が兄弟姉妹の場合
| 配偶者 | 4分の3 |
|---|---|
| 兄弟姉妹 | 4分の1 |
※兄弟姉妹の割合である4分の1をその人数で分配する
これは、あくまでも法律で定められた割合のため、たとえば被害者の方の遺言書がある場合は、その内容に従うことになります。
また、相続人の間で話し合うことで、たとえば法的な相続権のない人を相続人の1人にしたり、分配率を変更したりということもできます。
ただし、その場合は相続人全員の同意が必要になります。
これを、「遺産分割協議」といいますが、後から争いにならないように、その内容を書面化しておくことも大切です。
交通死亡事故で請求できる損害項目
交通事故で被害者の方やご家族が受け取ることができる損害賠償金(状況によって示談金とも保険金ともいいます)は慰謝料だけではありません。
入通院での治療費や交通費、休業損害、将来介護費、逸失利益など、さまざまな損害項目を請求することができます。
交通死亡事故の場合でも、ご遺族が請求できるのは死亡慰謝料だけではありません。
ご遺族は漏れなく加害者側に請求していくことが大切です。
ここから、交通死亡事故で請求できる損害項目である以下の4つについて、1つずつ詳しく解説します。
(1)葬儀関係費
(2)死亡逸失利益
(3)慰謝料
(4)弁護士費用(裁判をした場合)
(1)葬儀関係費
自賠責保険から支払われる金額は、
定額100万円です。
たとえば、葬儀費用に120万円がかかった場合の請求方法は次の2通りがあります。
残りの20万円を加害者側の任意保険会社と交渉する。
②あるいは、初めから任意保険会社と120万円について示談交渉をしていく。
加害者側の任意保険会社との示談交渉が決裂して提訴した場合、裁判で認められる上限額は原則として150万円になります。
※ただし通常の場合、保険会社は120万円以内の金額を提示してくる場合が多いことに注意が必要です。
その他の墓石建立費、仏壇購入費、永代供養料などについては、それぞれの事案によって個別に判断されます。
(2)死亡逸失利益
生きていれば得られたはずだった収入を逸失利益といいます。
<死亡逸失利益の計算式>
(年収)
×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)
×(1-生活費控除率)
=(死亡逸失利益)
被害者の方が死亡した場合、所得はなくなってしまうため、「労働能力喪失率」は100%になります。
年収についは、事故前年の年収を基本に算出
します。
就労可能年数は、原則として18歳から67歳とされます。
ライプニッツ係数とは、現在と将来ではお金の価値に変動があるため、その差額を現時点で調整するために用いるものです。
※専門的には、中間利息を控除する、といいます。
ライプニッツ係数の率は3%であり、3年ごとに見直されるようになっています。
生活費控除率の相場は下記の表のようになっています。
<生活費控除率の目安>
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
|---|---|
| 被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 | 30% |
| 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |
| 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |
- 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人
- 40%
- 被害者が一家の支柱で被扶養者が2人
- 30%
- 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)
- 30%
- 被害者が男性(独身、幼児等含む)
- 50%
※被害者の方が男性の場合、生活費控除率は
50%とされます。
※ただし、一家の大黒柱で被扶養者がいる場合は、その人数によって30~40%になる場合があります。
死亡逸失利益について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(3)慰謝料
死亡事故のご遺族の方が受け取ることができる慰謝料には、じつは3つの種類があり、さらにご親族が受け取ることができるものもあります。
①入通院慰謝料(傷害慰謝料)
死亡までに治療をした場合に、治療のために入通院した被害者の方の精神的苦痛に対して支払われるものです。
②死亡慰謝料
・被害者の方が死亡した場合に、その精神的苦痛や損害対して支払われるもので、受取人は被害者の方の相続人になります。
・被害者の方の家庭内での立場や状況によって、下記のように概ねの相場金額が決まっていますが、事故の状況、悪質性などによっては交渉によって増額する場合があります。
<死亡慰謝料の相場額>
| 被害者が一家の支柱の場合 | 2,800万円 |
|---|---|
| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2,500万円 |
| 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 2,000万~2,500万円 |
- 被害者が一家の支柱の場合
- 2,800万円
- 被害者が母親・配偶者の場合
- 2,500万円
- 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合
- 2,000万~2,500万円
③近親者慰謝料
・被害者の方の近親者(ご家族など)が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるものです。
受け取る人が両親(父母)、配偶者(夫・妻)、子供の場合の金額は概ね、被害者本人の慰謝料の1~3割ほどになることが多いといえます。
・その他、内縁の夫や妻、兄弟姉妹、祖父母にも認められる場合があります。
(4)弁護士費用
(裁判をした場合)
示談交渉をしたものの、金額で和解できずに決裂した場合、提訴して裁判に持ち込むことができます。
そこで弁護士が必要と認められる事案では、認容額の10%程度を相当因果関係のある損害として、弁護士費用相当額が損害賠償額に加算されます。
なお、弁護士費用相当額は示談交渉では認められません。
裁判で判決までいった場合に認められることを覚えておいてください。
これは見方を変えると、ご自身で負担しなければならない弁護士報酬の一部を加害者側に負担させることができる、ということになります。
つまり、弁護士に依頼して裁判した場合のメリットのひとつということができるでしょう。
賠償金の相続の分配の計算例
ここでは、死亡事故で相続人が複数いる場合には、損害賠償金がどのように分配されることになるのか、具体例で計算してみたいと思います。
配偶者と子2人のケース
夫兼父親が交通事故で死亡し、相続人として、配偶者と子A、子Bの2人がいるケースを考えてみます。
以下は、仮の計算例です。
(2)死亡慰謝料 2,800万円
(3)逸失利益 8,000万円
合計 1億950万円
相続分としては、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつになります。
相続人それぞれの分配は、次のようになります。
子A:1億950万円 × 1/4
= 2,737万5,000円
子B:1億950万円 × 1/4
= 2,737万5,000円
配偶者と両親がいるケース
夫兼子が交通事故で死亡し、相続人として、配偶者と親A、親Bの2人がいるケースを考えてみます。
以下は、仮の計算例です。
(2)死亡慰謝料 2,800万円
(3)逸失利益 8,000万円
合計 1億950万円
相続分としては、配偶者が3分の2、親がそれぞれ6分の1ずつになります。
相続人それぞれの分配は、次のようになります。
親A:1億950万円 × 1/6 = 1,825万円
親B:1億950万円 × 1/6 = 1,825万円
配偶者と兄弟姉妹がいるケース
夫兼子が交通事故で死亡し、相続人として、配偶者と兄A、妹Bの2人がいるケースを考えてみます。
以下は、仮の計算例です。
(2)死亡慰謝料 2,800万円
(3)逸失利益 8,000万円
合計 1億950万円
相続分としては、配偶者が4分の3、親がそれぞれ8分の1ずつになります。
相続人それぞれの分配は、次のようになります。
= 8,212万5,000円
兄A:1億950万円 × 1/8
= 1,368万7,500円
妹B:1億950万円 × 1/8
= 1,368万7,500円
死亡事故の相続の分配でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠