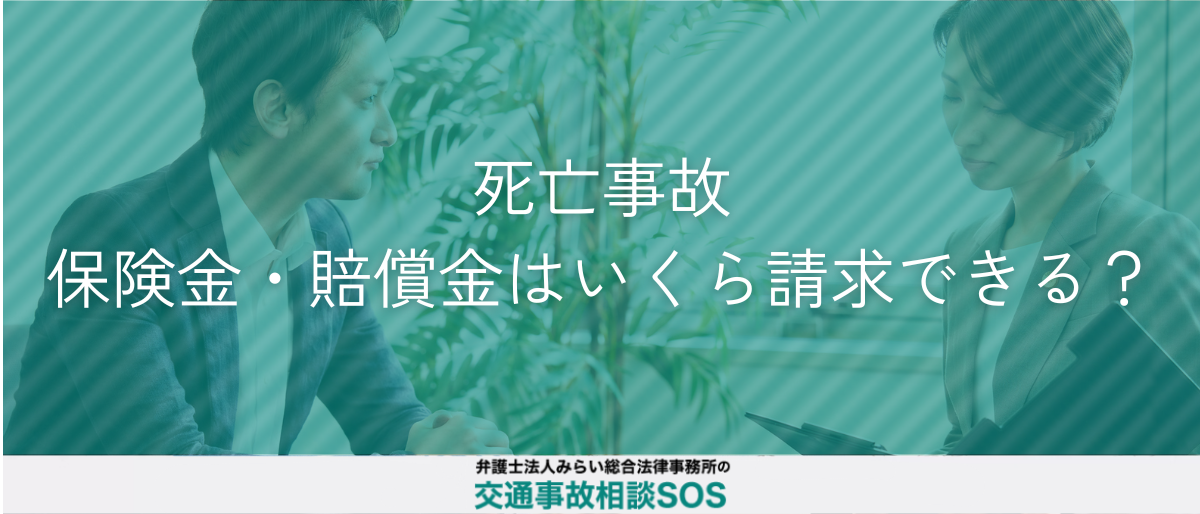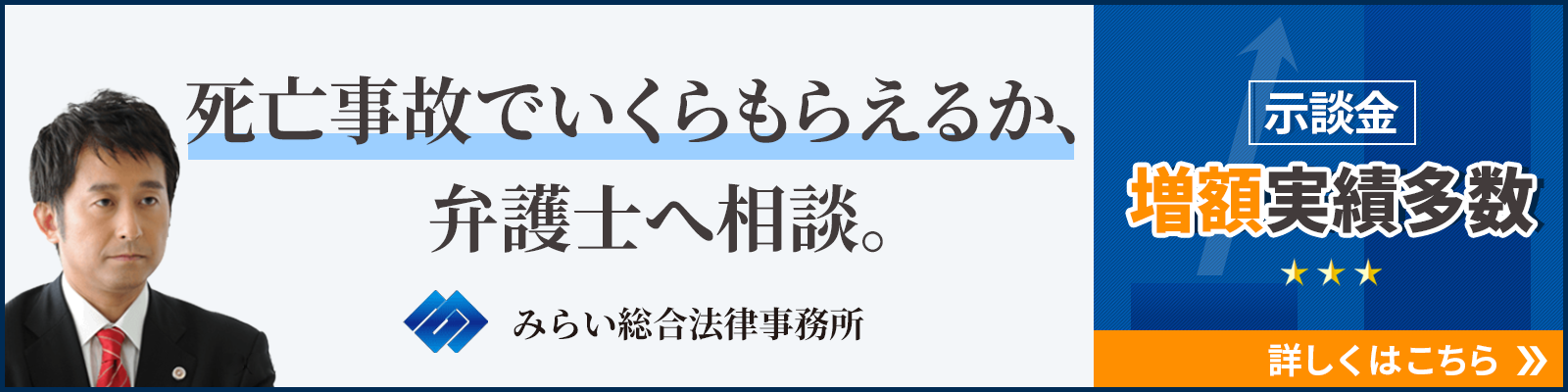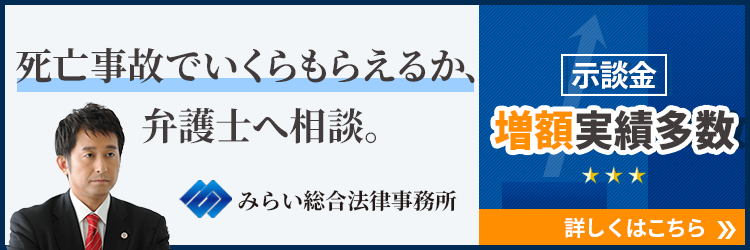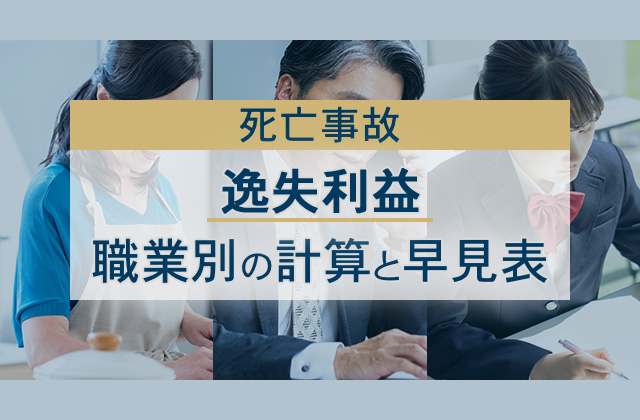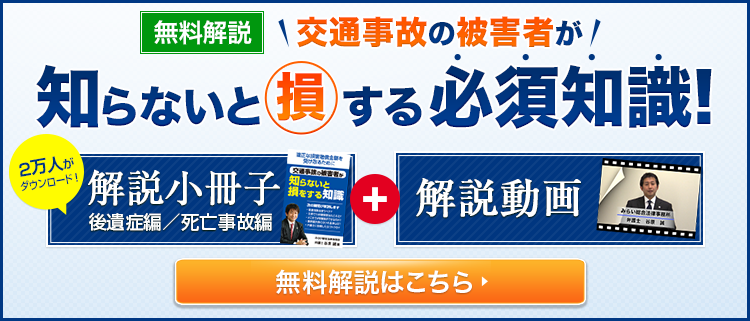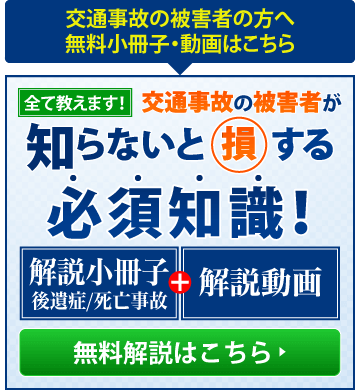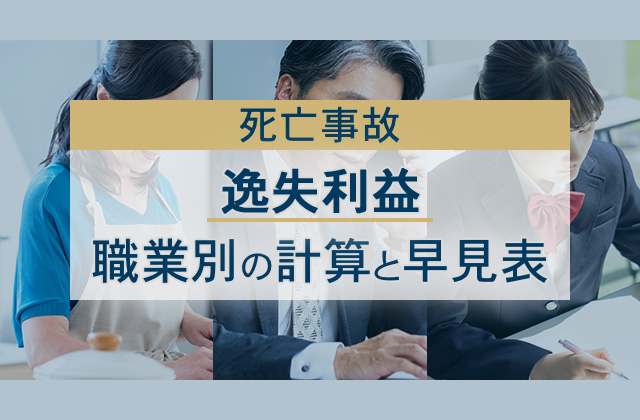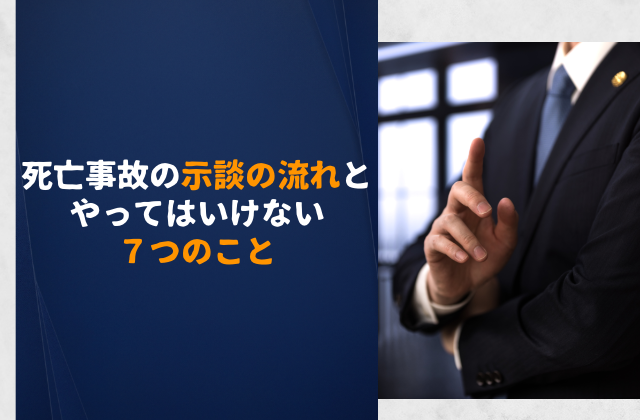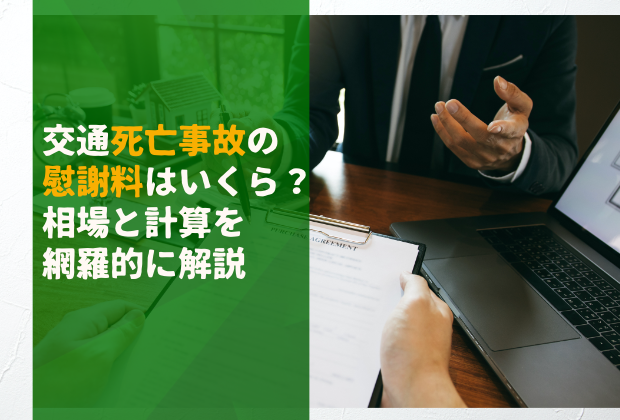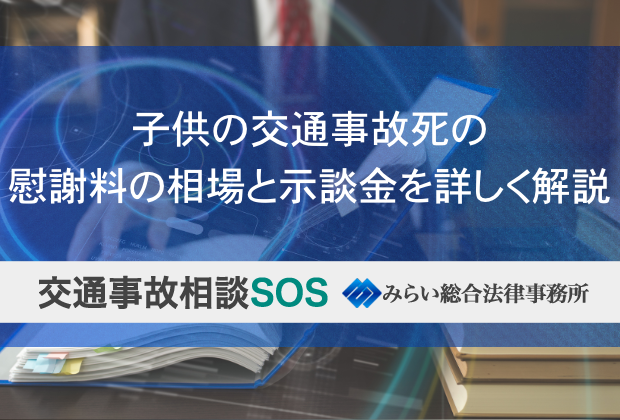死亡事故では保険金・賠償金はいくら請求できるか?【ポイントを詳しく解説】
*タップすると解説を見ることができます。
死亡事故でご遺族が請求できる賠償金には、
の3つがあり、また慰謝料以外にも
を受け取ることができます。
また、訴訟を提起して裁判になり、最終的な判決が出た場合は弁護士費用相当額も受け取ることができ、さらに遅延損害金が加算される場合があります。
これらの賠償金は任意保険にいくらぐらい請求できるものなのでしょうか?
本記事では、死亡事故の慰謝料の計算方法を解説したうえで、早見表を確認し、正しい相場金額や、加害者側との示談交渉の注意点などについて解説していきます。
目次
交通死亡事故の損害賠償
【4つのポイント】
ここでは、交通死亡事故の損害賠償についてポイントとなる以下の4つを1つずつ詳しく解説します。
(1)損害賠償金と保険金、示談金の違いに
ついて
(2)交通事故の慰謝料は1つではない?
(3)死亡慰謝料の受取人は誰になる?
(4)死亡事故の慰謝料に税金はかかるのか?
損害賠償金と保険金、示談金は何が違う?
交通事故の損害賠償実務では、慰謝料、保険金、示談金などの用語が出てきますが、これらは何が違うのでしょうか?
損害賠償金
被害者側から見ると、被った損害を加害者側から賠償してもらうお金なので、損害賠償金になります。
示談金
被害者側と加害者側の示談によって賠償金額が合意されるので、示談金といいます。
保険金
加害者側の任意保険会社の立場からすると、保険契約に基づいて被害者側に支払うものなので、保険金になります。
このように、見る立場や状況によって言い方が異なるだけで、これらはすべて同じものということを知っておいてください。
交通事故の慰謝料は1つでは
ない!?
交通事故の被害者の方が被った精神的苦痛を償うために支払われるのが慰謝料です。
つまり、保険金の中の1つの項目として慰謝料がある、ということになります。
ところで、交通事故の慰謝料は1つではなく、次の4つがあります。
なお、交通事故後に治療を受けて、その後に亡くなったような場合は入通院慰謝料も受け取ることができます。
よくわかる動画解説はこちら
死亡慰謝料の受取人は誰になる?
死亡慰謝料は、亡くなった被害者の方の精神的苦痛に対して支払われるものですが、被害者の方は亡くなっているため、受取人はご遺族になります。
ただし、ご遺族であればどなたでも受け取ることができるわけではない、ということに注意してください。
受取人は法的に定められた相続人となり、順位、分配割合が変わってきます。
相続人の順位と分配割合
配偶者がいる場合は、つねに相続人になります。
そのうえで、相続人の順位と法定相続分は次のようになります。
配偶者:2分の1
子:2分の1
※たとえば子が2人の場合、1人分は4分の1(2分の1を2人で分けるため)。
配偶者:3分の2
親:3分の1
※両親(父母)がいる場合、1人分は6分の1(3分の1を2人で分けるため)。
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
※兄弟姉妹が複数人いる場合は4分の1をその人数で分配する。
死亡事故の慰謝料に税金は
かかるのか?
交通死亡事故の場合、被害者本人が死亡しているので、ご遺族が損害賠償金を受け取ることになりますが、この場合、人的損害である慰謝料などと車両損害などの物的損害では税金の処理が異なることに注意が必要です。
慰謝料などの人的損害については、被害者本人が損害賠償金を受け取った時は所得税は非課税となります。
死亡事故の場合も同様、慰謝料については非課税です。
これに対し、物的損害については、被害者の方の所有物が損害賠償請求権という債権に代わったことになるので、相続財産として相続税の課税対象となります。
なお、これらの損害賠償金には加害者本人から支払がなされる損害賠償金だけではなく、損害保険契約に基づき加害者が加入している損害保険会社から支払を受ける場合も同様です。
慰謝料などの計算は基準の違いに注意!
慰謝料などの計算では、次の3つの基準が使われます。
どの基準を使うかで金額に大きな違いがで出るので注意が必要です。
1.自賠責基準
・自賠責保険で定められている基準。
・賠償金額がもっとも低くなる。
2.任意保険基準
・各損害保険会社が独自に設定している基準。
・各社非公表としているが、自賠責基準より少し高い金額になる。
3.弁護士(裁判)基準
・もっとも高額になる基準。
・被害者の方が受け取るべき正当な金額は、この基準で算定したもの。
・代理人として弁護士が加害者側と交渉する際には、この基準で算定した金額を主張する。
・これまでの多くの裁判例から導き出されている基準のため、裁判になった場合に認められる可能性が高い。
交通死亡事故で受け取ることが
できる慰謝料の相場と計算方法
ここからは交通死亡事故で、ご遺族が保険金として受け取ることができる損害賠償項目の内訳と計算方法について解説します。
大きく以下の3つに分け、それぞれわかりやすく解説します。
(1)死亡慰謝料の相場
(2)近親者慰謝料の相場
(3)慰謝料以外の損害賠償金項目
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料の算定方法や相場を解説するにあたって、「慰謝料などの計算は基準の違いに注意!」で記載の通り、慰謝料などの計算に使われる3つの基準のどの基準を使うかで大きく違いが出るため、それぞれの基準を使った場合に分けて解説します。
(1)自賠責基準での死亡慰謝料の算定方法と
相場
(2)任意保険基準での死亡慰謝料の相場
(3)弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場
自賠責基準での算定方法と相場
自賠責基準による死亡慰謝料は、「被害者本人の死亡慰謝料」と「近親者慰謝料(ご遺族分)」の合算として扱われます。
ご遺族:配偶者・父母・子の人数によって次のように変わる。
| ご遺族が1人の場合 | 550万円 |
|---|---|
| ご遺族が2人の場合 | 650万円 |
| ご遺族が3人以上の場合 | 750万円 |
| 扶養家族がいる場合 (ご遺族が被扶養者の場合) |
200万円が加算 |
※父母には、養父母も含まれる。
※子には、養子・認知した子・胎児も含まれる。
たとえば、死亡した被害者の方が家族の生計を支えていて、妻と2人の子供がいる場合の相場金額は次のようになります。
なお、自賠責保険には保険金全体の上限額があり、死亡事故の場合は3,000万円になります。
この金額を超えた分(不足分)については、ご遺族が任意保険会社と示談交渉していく必要があります。
| 損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名につき) | |
|---|---|---|
| 傷害(ケガ)による損害 | 慰謝料・治療関係費・文書料・ 休業損害など |
最高120万円 |
| 後遺障害による損害 | 慰謝料・逸失利益など | 障害の程度により神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護が必要な場合:最高4,000万円 随時介護が必要な場合:最高3,000万円 ・上記以外の場合 第1級 :最高3,000万円~ 第14級:最高75万円 |
| 死亡による損害 | 慰謝料(死亡慰謝料・近親者慰謝料)・ 葬儀費・逸失利益など |
最高3,000万円 |
| 死亡するまでの傷害による損害 | ※傷害(ケガ)による損害の場合と同じ | 最高120万円 |
- 傷害(ケガ)による損害
-
<損害の範囲>
慰謝料・治療関係費・文書料・休業損害など<支払限度額(被害者1名につき)>
最高120万円 - 後遺障害による損害
-
<損害の範囲>
慰謝料・逸失利益など<支払限度額(被害者1名につき)>
障害の程度により神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護が必要な場合:最高4,000万円
随時介護が必要な場合:最高3,000万円上記以外の場合
第1級 :最高3,000万円~
第14級:最高75万円 - 死亡による損害
-
<損害の範囲>
慰謝料(死亡慰謝料・近親者慰謝料)・葬儀費・逸失利益など<支払限度額(被害者1名につき)>
最高3,000万円 - 死亡するまでの傷害による損害
-
<損害の範囲>
※傷害(ケガ)による損害の場合と同じ<支払限度額(被害者1名につき)>
最高120万円
任意保険基準での死亡慰謝料の相場
任意保険基準は各社非公表のため正確ではありませんが、経験上、概ね次のように、被害者の方の家庭での立場や属性などによって金額が変わってきます。
<任意保険基準による
死亡慰謝料の相場金額早見表>
| 一家の支柱(一家の生計を立てている者) | 1,500~2,200万円 |
|---|---|
| 専業主婦(主夫)・配偶者 | 1,300~1,800万円 |
| 子供・高齢者など | 1,100~1,700万円 |
- 一家の支柱(一家の生計を立てている者)
- 1,500~2,200万円
- 専業主婦(主夫)・配偶者
- 1,300~1,800万円
- 子供・高齢者など
- 1,100~1,700万円
弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場
被害者の方の家庭での立場や状況によって概ねの相場金額が決められています。
<弁護士(裁判)基準による
死亡慰謝料の相場金額>
| 被害者の状況 | 死亡慰謝料の目安(近親者への支払い分を含む) |
|---|---|
| 被害者が一家の支柱の場合 | 2,800万円 |
| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2,500万円 |
| 被害者がその他の場合(子供・高齢者など) | 2,000万~2,500万円 |
- 被害者が一家の支柱の場合
- 2,800万円
- 被害者が母親・配偶者の場合
- 2,500万円
- 被害者がその他の場合(子供・高齢者など)
- 2,000万~2,500万円
このように、弁護士(裁判)基準による金額がもっとも高額になるということを覚えておいてください。
もっとも、この金額は絶対的なものではありません。
危険運転による事故、加害者の悪質性などの増額事由などがあれば増額する可能性があります。
(故意や重過失がある場合)
・飲酒運転
・著しいスピード違反
・薬物使用
・無免許運転
・センターラインオーバー
・ひき逃げ(救護義務違反)
・信号無視 など
②被害者の方に特別な事情がある場合
・腕や脚、指などの運動機能に麻痺等の
後遺症が残り、将来の夢が絶たれた。
・後遺障害を負ったことで、肢体障害のある
家族の介護などができなくなった。
・交通事故で負った傷害(ケガ)が胎児にも
影響し、人工中絶を余儀なくされた。
・交通事故で負った後遺障害が原因となり、
婚約破棄や離婚に至った。
・被害者がまだ幼い。
・ご遺族が大きな精神的ショックのため、
精神疾患を患ってしまった。 など
③加害者の態度などが悪質な場合
・警察に虚偽の供述をした。
・被害者やご遺族への謝罪がない。
・被害者やご遺族に対して悪態をつく。 など
これらの理由がある場合、ご遺族は主張・立証をしっかりして、加害者側の保険会社に認めさせることが大切になります。
事故の状況や被害者の方の置かれた立場などによって増額する場合があるので、一度、無料相談などを利用して弁護士の話を聞いてみるといいでしょう。
近親者慰謝料の相場
近親者慰謝料とは、近親者固有の慰謝料とも呼ばれるもので、被害者の近親者(家族など)が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるものです。
とはいっても、すべての交通事故で近親者慰謝料が認められるわけではないことに注意が必要です。
近親者慰謝料が認められる根拠となる判例には次のものがあります。
(最高裁 昭和33年8月5日判決)
また、「民法711条」では、近親者の慰謝料請求として、「他人の生命を侵害した者は」「被害者の父母、配偶者及び子」に対して損害賠償しなければならない旨を規定しています。
もっとも関係の近いご遺族は「被害者の父母、配偶者及び子」ですが、さらにこれら以外の近親者にも慰謝料が認められている判例があります。
また、内縁の配偶者や内縁の養子といった血縁関係がなく近親者に該当しない方でも慰謝料が認められている判例もあります。
近親者慰謝料の金額は、それぞれの事故によって個別具体的に判断されますが、多くとも数百万円というケースが一般的です。
ただし、注意していただきたいのは、たとえば前述の死亡慰謝料(被害者本人分)にさらに加算されるわけではなく、死亡慰謝料が減額され、それぞれの近親者の慰謝料に割り振られたり、調整が図られる場合があることに注意が必要です。
交通死亡事故における慰謝料以外の損害賠償金項目について
死亡事故で、ご遺族が受け取ることができる損害賠償金の項目(慰謝料以外)には主に次のものがあります。
1つ1つわかりやすく解説します。
死亡逸失利益
交通事故にあわずに生きていれば被害者の方が将来的に得られたであろうお金を死亡逸失利益といいます。
1.基礎収入(年収)
事故の前年に被害者の方が得ていた収入額で、年金なども基礎収入に含まれます。
2.就労可能年数
原則、18歳から67歳までとされますが、被害者の方の職種や地位、能力などによって、67歳を過ぎても就労することが可能だったと判断される場合は、その分の年数が認められる可能性があります。
3.ライプニッツ係数
死亡逸失利益は、将来に受け取るはずだった収入を前倒しで受け取ることになります。
そのため、将来的にお金の価値が変動した際には差額が生じてしまいます。
そこで、この差額を調整するためにライプニッツ係数を用います。
ライプニッツ係数は、あらかじめ定められている係数表から年齢によって求めることができます。
4.生活費控除率
生きていれば生活費がかかるので、これを控除するために使うのが生活費控除率です。
次のように、被害者の方の家庭での立場や状況によって相場の割合が決められています。
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
|---|---|
| 被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 | 30% |
| 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の 場合 |
30% |
| 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |
- 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合
- 40%
- 被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合
- 30%
- 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合
- 30%
- 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合
- 50%
詳しい内容や実際の計算例などは、こちらのページや動画を参考にしてください。
(後遺障害、死亡事故)
葬儀関係費
葬儀費用については次のような金額が認められます。
・自賠責保険:60万円(定額)
※この金額を超えた時は、「社会通念上、必要かつ妥当な実費」として、100万円まで認められる場合があります。
・加害者側の任意保険会社の提示額:
概ね120万円以内
・裁判で認められる金額:150万円(上限)
※弁護士に依頼して訴訟を起こした場合は弁護士(裁判)基準で算定した金額になります。
なお、墓石建立費、仏壇購入費、永代供養料などについては、これらが認められた裁判例があるので、各事案によって個別に判断されますが、香典返しの費用は認められていません。
弁護士費用
加害者側の任意保険会社との示談交渉が決裂した場合は、提訴して裁判に進みます。
その際、ご遺族だけでは対応できないため弁護士に依頼することになります。
最終的に判決までいった場合は、そこで認められた賠償金の10%程度が相当因果関係のある損害と判断され、弁護士費用相当額として保険金に加算されます。
判決までいった場合は、さらに遅延損害金も加算されます。
遅延損害金
遅延損害金というのは、利息のようなもので、事故の日の翌日から支払い済みまで、年3%の割合で計算されます。
たとえば、損害賠償金が1,000万円として、1年後に判決が出た場合、賠償金として1,030万円を受け取ることができる、ということです。
「裁判はしたくない」というご遺族もいらっしゃるのですが、賠償金が増額されることを知ったうえで、提訴するかどうか、弁護士に依頼するかどうかを検討するのがいいでしょう。
交通死亡事故の保険金の請求方法
交通死亡事故の保険金については、加害者側の自賠責保険に請求する方法と、任意保険会社に請求する方法があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、経済状況などを考えながら選択するのがいいでしょう。
「被害者請求」
被害者の方やご遺族が直接、自賠責保険に損害賠償額の請求をする方法です。
まずは自賠責保険からある程度まとまった保険金を受け取ることができるので、ご遺族に経済的な余裕がない場合などでは生活を安定させることができるというメリットがあります。
自賠責保険からの保険金では足りない部分は、加害者側の任意保険会社に請求することになりますが、先に自賠責保険金分を受け取ることで余裕をもって示談交渉ができるというのもメリットでしょう。
一方、被害者請求では、前述した遅延損害金が賦課されない、つまり遅れた期間について加算されないので、これはデメリットでしょう。
また、保険金請求のための書類などはご遺族が用意しなければいけないため、手間がかかってしまうというデメリットもあります。
「任意一括払い制度」
加害者側の任意保険会社が、被害者側に対して自賠責保険分も一括で支払うことを任意一括払い制度といいます。
任意保険会社は、被害者の方に保険金を支払い、その後に自賠責保険金分を自賠責保険に請求します。
被害者側のメリットとしては、遅延損害金が加算されることがあげられます。
また、手続きは任意保険がやってくれるので、ご遺族の負担が少なくなるのもメリットでしょう。
なぜ任意保険会社は正しい
保険金額を提示してこないのか?
保険会社は保険金を
少なくしたい
ところで、交通死亡事故のご遺族には知っておいていただきたい重要なことがあります。
それは、加害者側の任意保険会社は、本来であれば被害者の方とご遺族が受け取るべき正しい保険金額を提示してこない現実がある、ということです。
保険会社は営利法人ですから、利益を上げることがその経営目的です。
そのため、支出となる加害者側への保険金をできるだけ低く抑えようという力が働きます。
一方、ご遺族としては、亡くなった人は帰ってこないのですから、できるだけ高額な保険金を得ることが亡くなったご家族への、せめてもの供養にもなると思われるのではないでしょうか。
つまり、ご遺族と保険会社では求めるものが正反対なため、提示金額で合意が得られず、示談交渉がなかなか解決しないということが起きてしまうのです。
交通事故で頼りになる
弁護士という存在
ご遺族が、いくら適切な保険金額を求めても保険会社は増額に応じることは少ないのが現実です。
ところが、法的な根拠をしっかりと示し、立証してくる弁護士が加害者側の代理人となると、保険会社の対応は変わります。
というのも、弁護士は被害者とご遺族のために正しい保険金額を主張し、示談が決裂した場合は提訴して裁判での決着までを行なうからです。
裁判では、前述した弁護士(裁判)基準による金額が認められる可能性が高く、また弁護士(裁判)基準による賠償金の他に遅延損害金や弁護士費用相当額などが付加されてしまうので、そうであれば保険会社としては裁判にいく前に増額した保険金額を提示して和解したほうがいい、と判断するわけです。
保険金額を計算できる
慰謝料自動計算機をご利用ください
みらい総合法律事務所では、どなたでも簡単に慰謝料などの保険金額を知ることができる「慰謝料自動計算機」をWEB上にご用意しています。
この自動計算機で、被害者の方が受け取るべき適切な保険金の概ねの額がわかるので、ぜひご活用ください。
みらい総合法律事務所では、交通事故で苦しむ被害者、ご遺族から年間1,000件以上の相談を受け、その多くで保険金の増額を勝ち取っています。
無料相談を利用していただくと、費用はかかりません。
これまで交通事故問題を解決してきた専門の弁護士チームが解決に向けたアドバイスをお伝えしますので、納得がいただけたら正式にご依頼いただけばよろしいかと思います。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
なお、最新の増額解決事例もご覧いただけますので参考になさってください。
交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子もご用意しています。
ぜひダウンロードしてみてください。
代表社員 弁護士 谷原誠