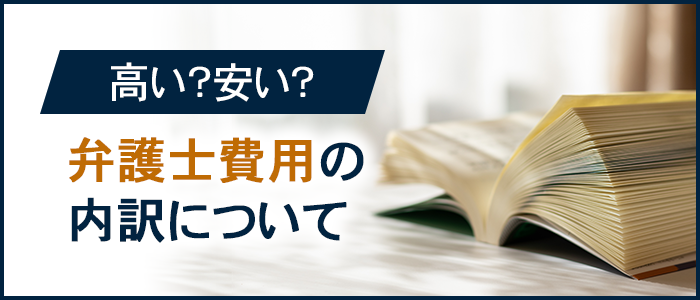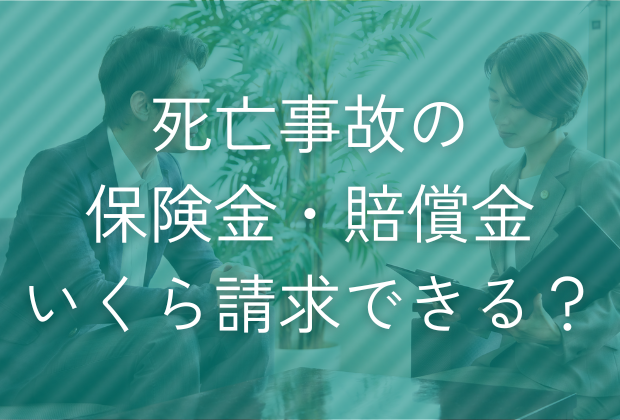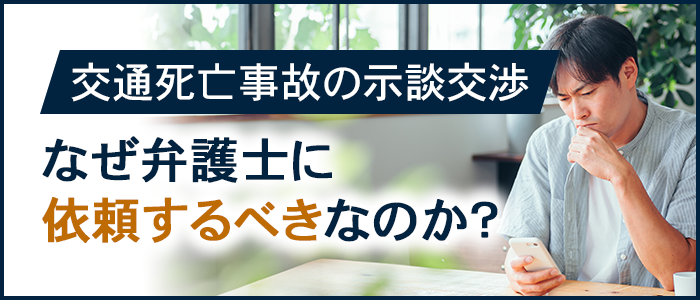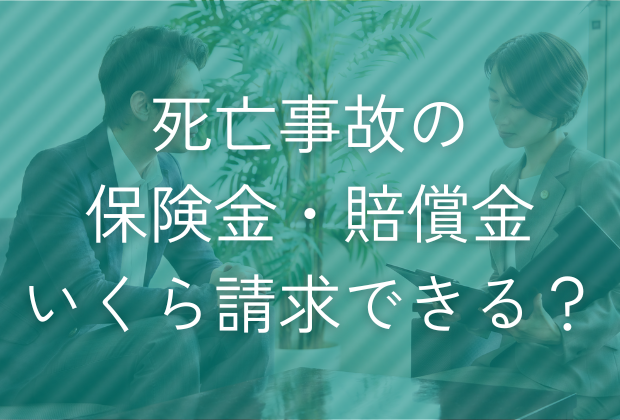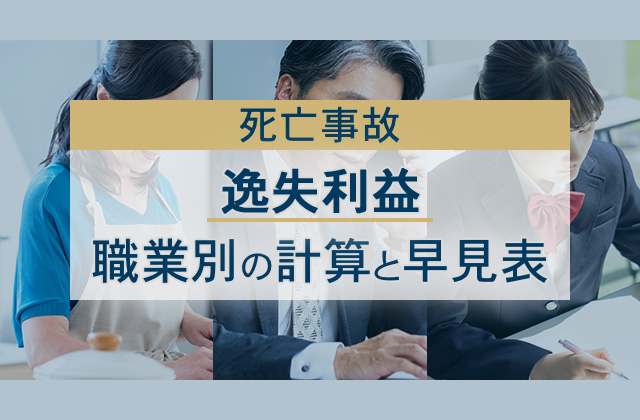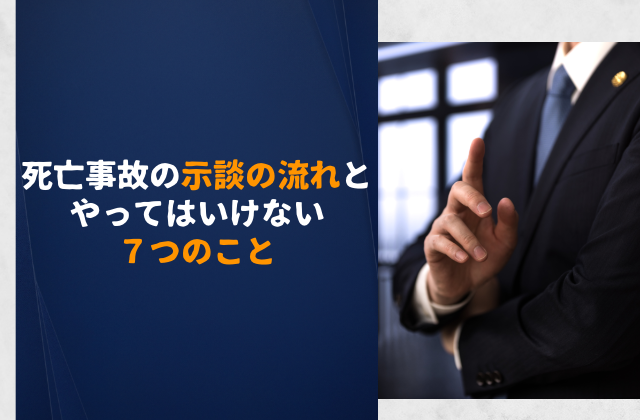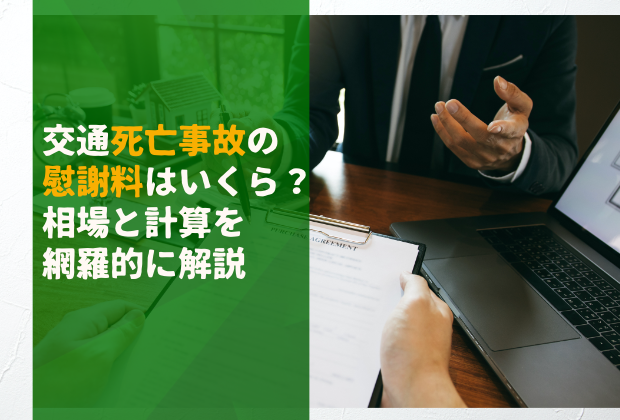死亡事故の弁護士費用の相場はいくら?
*タップすると解説を見ることができます。
交通死亡事故で弁護士に依頼した場合にかかる
弁護士費用の内訳は、一般的には次のようになります。
| ①相談料 | 弁護士に相談する際に まず支払うもの |
|---|---|
| ②着手金 | 実際に弁護士に依頼する際に 支払うもの |
| ③報酬金 | 案件が解決した際に弁護士に 支払うもの |
| ④その他 | 出張費、訴訟の際の印紙代・ 郵便切手代・刑事記録の謄写代など |
交通死亡事故の損害賠償問題を弁護士に依頼することで、ご遺族はさまざまなメリットが得られます。
-
☑慰謝料や逸失利益などの損害賠償金が
増額する可能性が高い
☑ご遺族が単独で交渉するより早く
示談解決できる
☑シビアな示談交渉から、ご遺族は解放される など
しかし、心配なのが、
いくら弁護士費用がかかるのか
です。
法律事務所によって違いはありますが、みらい総合法律事務所では、依頼者の負担軽減のため、増額しなければ報酬は1円もいただかない「完全成功報酬制」を採用しています。
死亡事故のご遺族が弁護士に委任した場合は弁護士費用はご遺族が負担するのが原則ですが、任意保険に弁護士費用特約がある場合は、最大300万円まで弁護士費用として保険金が支払われる場合があります。
また、裁判を起こし、判決を得ることで賠償金の10%程度を加害者側に負担させられることがあります。
死亡事故のご遺族として知っているのと知らないのとでは大きな差が出ますので、ぜひ、最後まで読んで、損をしないようにしていただきたいと思います。
※みらい総合法律事務所では、交通事故による死亡事故、または人身事故のご遺族・被害者のために、無料でLINE相談をはじめることができます。
LINE登録から相談の流れはこちらをご覧ください。

目次
死亡事故の弁護士費用の相場
一般的な交通死亡事故の弁護士費用については、①相談料、②着手金、③報酬金、④日当からなり、その他に実費がかかります。
相場としては、以下のとおりです。
順番に解説します。
「相談料」
相談料というのは、弁護士に相談する場合に支払うものです。
かつては、日弁連が弁護士報酬基準を定めており(旧報酬基準)、旧報酬基準では、法律相談料は、30分につき5,000円でした。
現在では、旧報酬基準は廃止されましたので、各法律事務所毎に決めていますが、まだ旧報酬基準を踏襲している弁護士が多数います。
また、現在では、相談料は無料としている法律事務所が増えていますので、探してみるといいと思います。
みらい総合法律事務所でも、人身事故の被害者からのご相談は、無料でお受けしております。
「着手金」
実際に依頼した場合に始めに弁護士に支払うもので、手付金のようなものだと考えるとわかりやすいと思います。
注意が必要なのは、最終的に案件が解決しなくても支払うものなので、仮に依頼者の望む結果が得られなくても返金されない点です。
旧報酬基準では、次のようになっています。
| 事件の経済的な利益の額 | 旧報酬基準 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5% + 9万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3% + 69万円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の2% + 369万円 |
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合- 経済的利益の8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 - 経済的利益の5% + 9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 - 経済的利益の3% + 69万円
3億円を超える場合 - 経済的利益の2% + 369万円
例えば、請求金額が1,000万円の場合には、
1,000万円 × 0.05 + 9万円
= 59万円となります。
現在では、交通事故に関しては、着手金を無料としている弁護士も複数いますので、確認してみるといいでしょう。
みらい総合法律事務所でも、弁護士費用特約保険がない場合には、原則として着手金は無料で対応しています。
「報酬金」
案件が解決した場合に、その成功報酬として弁護士に支払うものです。
依頼者としては、この金額がもっとも大きな支出となります。
成功報酬の考え方は各法律事務所によって違うため、利率(パーセンテージ)や金額に違いが出てくるので、依頼する前にしっかり確認しておくことが必要です。
旧報酬基準では、次のようになっています。
| 事件の経済的な利益の額 | 旧報酬基準 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10% + 18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6% + 138万円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の4% + 738万円 |
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合- 経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 - 経済的利益の10% + 18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 - 経済的利益の6% + 138万円
3億円を超える場合 - 経済的利益の4% + 738万円
例えば、獲得した金額が1,000万円の場合には、1,000万円 × 0.1 × 18万円 = 118万円
となります。
また、報酬金を確認したら、必ず契約書を締結するようにし、その契約書の中に報酬金の計算方法を記載してもらうようにしましょう。
「日当」
日当は、弁護士の外出業務が発生したり、地方出張するような場合に発生する弁護士費用のことです。
時間で金額が決められる場合や、1日出張単位でいくらにする、などと取り決めがされることが多いです。
相場は0円~10万円になります。
みらい総合法律事務所の弁護士費用
みらい総合法律事務所では依頼者の負担をできるだけ減らすために相談料と着手金は無料にしています。
また、対象案件(依頼をお引き受けできる案件)については、完全成功報酬制のため、慰謝料などの増額を勝ち取れなかった場合は、1円もいただかないというシステムを採用しています。
なお、報酬については、増額した金額ではなく、最終的に獲得した金額の10%(消費税別途)のみをいただいています。
実際の事例で弁護士費用を計算|
みらい総合法律事務所版
では、交通死亡事故の場合の弁護士費用は、一体どのくらいかかるものなのでしょうか?
みらい総合法律事務所が実際に解決した事例を例に説明いたします。
-
74歳女性が、交通事故で死亡しました。
加害者側から、本件では2,000万円以上の支払義務はない、という債務不存在確認訴訟を起こされました。
ご遺族がみらい総合法律事務所の弁護士に依頼しました。
裁判での解決ですが、最終的に、4,857万円で和解が成立しました。
保険会社提示額から約2,857万円増額したことになります。
みらい総合法律事務所の報酬基準は、原則としては、
・報酬金 獲得金額の10%(消費税別途)
ですから、
本件での弁護士費用は、534万2,700円です。
高いように思えるかもしれませんが、裁判に応じなければ2,000万円で終わりになるところ、ご遺族の手元に4,322万2730円が残ることになったわけですから、弁護士に依頼したメリットは十分にあった、ということになると思います。
死亡事故の保険金や賠償金について詳しく知りたい方はこちらもご確認ください。
交通死亡事故を弁護士に
依頼した方がいい理由
交通死亡事故で大切なご家族を亡くしたご遺族は、深い悲しみの中にいますが、死亡事故の賠償金は、故人の「命の値段」です。
しっかりと適正額を請求する必要があります。
そのためには、弁護士に依頼して処理をした方がいいのですが、その理由について解説していきます。
弁護士に依頼した方がいい理由は、以下のとおりです。
- ・刑事事件のサポートをしてくれる。
- ・賠償金が増額する
- ・保険会社とのやり取りから解放される
- ・裁判をすると、賠償額が増える
順番に解説します。
刑事事件のサポートをしてくれる
死亡事故が起きると、加害者は、過失運転致死罪や危険運転致死罪により刑事事件に付されます。
刑事事件は、加害者にどのような刑罰を科すか、ということなので、被害者は直接の当事者ではありません。
しかし、加害者の刑事裁判には、「被害者参加」という制度があり、被害者のご遺族が裁判所に出廷して、質問したり、意見を述べたりすることができるものがあります。
みらい総合法律事務所で受任している死亡事故でも、かなりのご遺族が被害者参加をしています。
そして、私達は、示談交渉のご依頼を受けた場合には、被害者参加のサポートも合わせて行っています。
被害者参加などしたことがない方がほとんどだと思いますので、この点は、弁護士に依頼した方がいい理由となります。
また、ご遺族は警察等で供述調書を取られますが、その際の供述内容の助言もいたします。
賠償金が増額する
保険会社は営利法人ですから利益の追求が目的です。
ボランティア活動をしているわけではないので、被害者の方やご遺族の味方ではありません。
ですから、自社が有利になるようにご遺族への示談金(保険金とも損害賠償金ともいいます)をできるだけ低く算出して提示してきます。
実は、死亡事故の賠償金の計算方法には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準、の3つがあります。
弁護士基準が最も高額なのですが、保険会社が提示してくる賠償金額は、それよりも低い自賠責基準か任意保険基準となっています。
そこで、金額に納得がいかない場合は双方で示談交渉をしていくのですが、ご遺族がいくら増額を求めても、多くの場合に保険会社は応じません。
弁護士は、最も高額の弁護士基準で交渉をしていきますので、多くの場合に、賠償金が増額します。
この点でも、死亡事故で被害者のご遺族が弁護士に依頼する方がいいといえるでしょう。
ただし、依頼する弁護士は誰でもいいというわけではありません。
適正な賠償金を受け取るためには、交通死亡事故に強い弁護士に依頼する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
実際に弁護士に依頼して慰謝料が
増額した事例
示談交渉を弁護士に依頼した方がいいのかどうか、ご検討いただくために、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等の増額事例をご紹介します。
加害者側の任意保険会社は、どのくらいの金額を提示してくるのか。
そして、弁護士が示談交渉に入ると、どのくらい増額するものなのか知っていただきたいと思います。
79歳女性の慰謝料が
約2,000万円増額
79歳の女性が自転車で走行中、後方から自動車に追突された交通事故。
加害者側の任意保険会社は被害者のご遺族に示談金として約2,017万円を提示しましたが、この金額が正しいものか判断ができなかったご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士から「この金額は低すぎる」との意見があったため、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が交渉したところ、保険会社は弁護士基準に準じる金額までの増額に同意したため、4,000万円での解決となりました。
加害者側の任意保険会社の提示額から約2倍、約2,000万円増額した事例です。
4歳男児の慰謝料が
約2,200万円増額
4歳男児が母親と駐車場内を歩行していたところ、自動車に衝突された交通事故です。
四十九日が過ぎ、加害者側の任意保険会社がご両親に対して約2,885万円の損害賠償金額を提示しました。
そこでご両親が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「まだ増額は可能」というものだったことから、示談交渉を依頼されました。
弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴。
裁判では過失割合について激しく争われましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、5,100万円で解決した事例です。
当初提示額から約2,200万円増額したことになります。
参考記事:実際の解決事例(死亡事故)
弁護士費用特約
死亡事故のご遺族が弁護士に依頼するのを躊躇するのは、やはり弁護士費用が心配なことが多いです。
弁護士に委任した場合には、弁護士費用は被害者のご遺族が負担するのが原則です。
しかし、自分がかけている保険から保険金として弁護士費用が支払われる場合があります。
それが、「弁護士費用特約」です。
被害者や同居の親族、未婚の場合は別居の両親などがかけている任意保険などに「弁護士費用特約」がついている場合は最大300万円まで弁護士費用が保険金として支払われる場合があります。
弁護士費用特約がついている場合には、それを使って弁護士に委任した方がいいでしょう。
弁護士費用を相手に負担させる方法
被害者が負担するべき弁護士費用を相手に負担させる方法があります。
それは、裁判を起こし、判決を得ることです。
判決が出される場合には、被害者が受け取るべき賠償金の約10%程度の弁護士費用相当額がプラスされるのが実務です。
例えば、賠償金が1,000万円だとすると、判決では、その10%である100万円がプラスされ、1,100万円の支払いが命じられることになります。
また、判決では、この他、遅延損害金もプラスされます。
遅延損害金とは、利息のようなもので、事故の日を基準として、賠償金が支払われるまで加算されることになります。
裁判のメリットといえるでしょう。
交通事故の死亡事故でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
【動画解説】 交通事故の弁護士費用を説明します
代表社員 弁護士 谷原誠