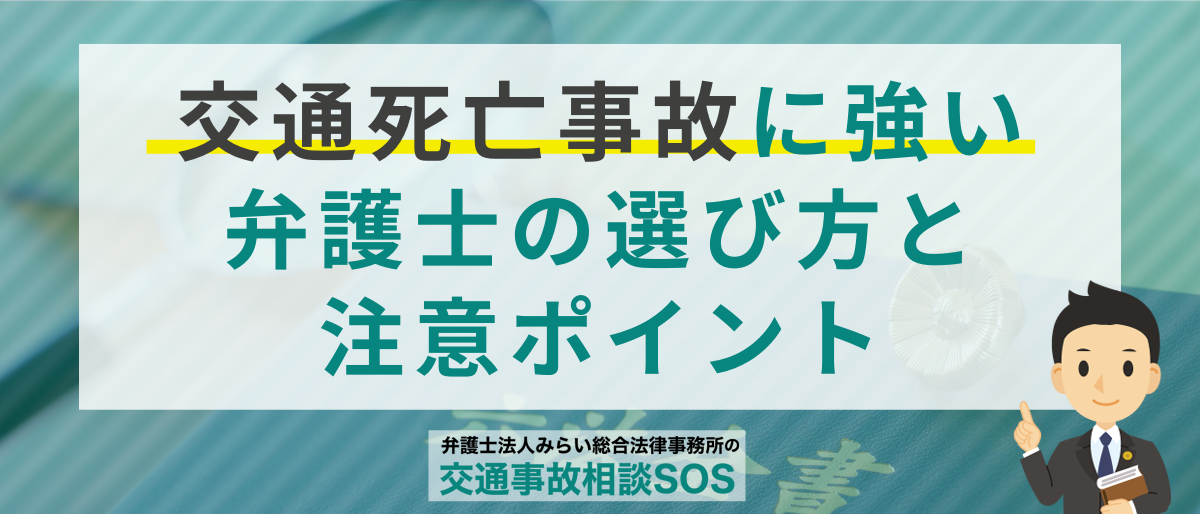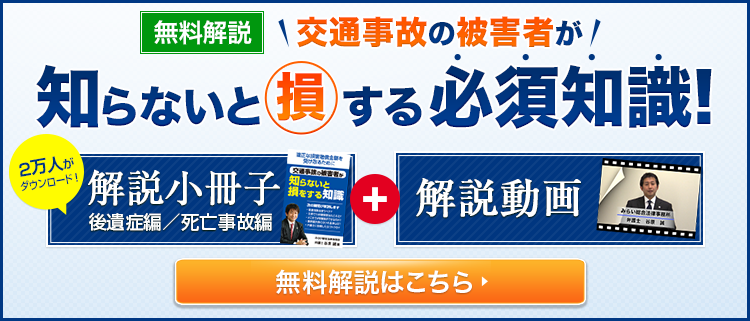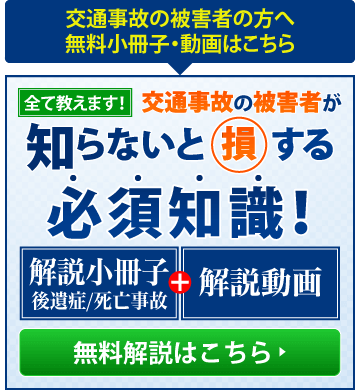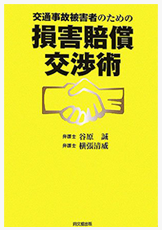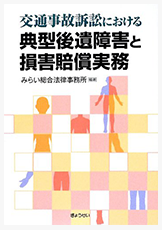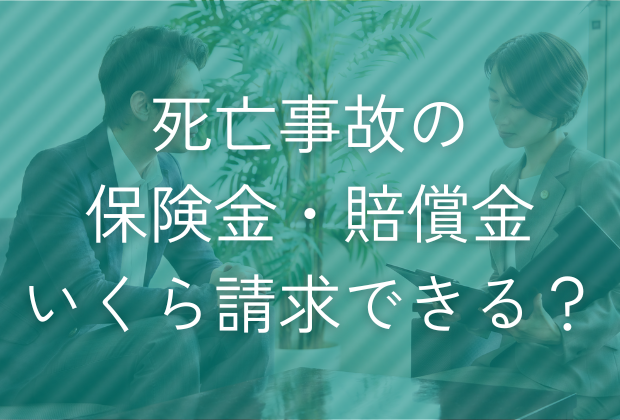交通死亡事故に強い弁護士の選び方と注意ポイント
*タップすると解説を見ることができます。
交通死亡事故に強い弁護士の選び方は、次の2点です。
そして、交通死亡事故に強い弁護士に相談・依頼する時の注意点は、次の6点です。
交通死亡事故で大切なご家族を失ったご遺族の方にお伝えしたいことがあります。
それは、慰謝料などの損害賠償金(保険金)に関することなど、今後やるべきことについてです。
「お金の話などしたくない」という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、加害者側からの償いとして損害賠償金をしっかり受け取ることは亡くなった方への供養でもあり、同時に亡くなった方から残されたご遺族の方々への思いを形にすることになるとも思います。
ところが、加害者側の保険会社との示談交渉では、さまざまな問題が浮上してきて話し合いがまとまらないということがよく起きてしまいます。
・正しい基準を知らずに示談してしまったために、ご遺族が慰謝料などでも大きな損害を被ってしまう。
こうした問題が起きるのは、なぜでしょうか?
どうすれば、こうした問題を解決することができるのでしょうか?
有効な手段として、交通死亡事故に強い弁護士に相談・依頼するという選択があるのをご存知でしょうか?
そこで、今回は、ご遺族が交通死亡事故に強い弁護士に相談・依頼するべき理由、そして死亡事故に強い弁護士を選ぶ方法などについてお話していきます。
みらい総合法律事務所での解決事例を紹介
まず、なぜ死亡事故で弁護士に依頼した方がいいかについて、みらい総合法律事務所による実際の解決事例をご紹介します。
弁護士に依頼することによって、慰謝料が大きく増額することがあることを知っていただきたいと思います。
現在、ご遺族の方がおかれている状況と照らし合わせながら参考にしてみてください。
解決事例①:男児(4歳)の
交通死亡事故で損害賠償金が
約2,200万円増額
駐車場内で母親と歩行していた4歳男児が自動車に追突された交通死亡事故です。
加害者の加入する任意保険会社は被害者男児の四十九日が終わってから、ご遺族である両親に約2,900万円の示談金(損害賠償金)を提示しましたが、この金額ははたして妥当なのか判断ができなかったご遺族が、みらい総合法律事務所に相談・依頼しました。
弁護士と保険会社の示談交渉が決裂したため裁判に移行し、過失割合が激しく争われましたが、その結果、弁護士の主張が認められ、約2,200万円増額の約5,100万円で解決したものです。
解決事例②:74歳女性の
交通死亡事故で損害賠償金が
約8.6倍に増額
信号機のある交差点を自転車で横断していた当時74歳の女性に、左折してきた自動車が衝突した交通死亡事故です。
加害者側の任意保険会社は治療費などで約1,300万円を支払い、その他に慰謝料など約370万円を示談金として提示してきました。
みらい総合法律事務所の弁護士が、ご遺族から依頼を受け交渉しましたが逸失利益や過失割合などで合意に至らず、結果として裁判で約3,200万円が認められ、既払い金と合わせると約4,500万円で解決しました。
解決事例③:55歳の女性の
交通死亡事故で7,200万円
獲得
会社員の女性(当時55歳)が、青信号の横断歩道を歩行中にあった交通死亡事故。
過失割合は、100対0という事故でした。
被害者女性のご両親は、加害者側の任意保険会社とは一切の対応、交渉はしたくないということで、みらい総合法律事務所の弁護士にすべてを依頼しました。
弁護士が保険会社と交渉した結果、弁護士(裁判)基準による慰謝料等で合意することができたため、当初の保険会社提示額よりも増額し、7,200万円を獲得することができました。
解決事例④:11歳女児の
交通死亡事故で
約2,300万円増額
青信号で自転車横断帯を走行していた11歳女児が左折トラックに衝突され死亡した事故です。
ご遺族に対し、加害者側の任意保険会社は約3,800万円を提示しましたが、ご遺族が加害者の刑事事件への「被害者参加制度」の利用を希望したこともあり、みらい総合法律事務所にすべての交渉を依頼しました。
弁護士は刑事裁判が終了後に加害者側の保険会社と示談交渉を開始。
最終的に約2,300万円増額して解決に至りました。
なお、弁護士に依頼した場合は必ず裁判にまで進んでしまうということはありません。
しかし、訴訟を提起して裁判をしたほうが、じつは損害賠償金が増額する場合があります。
被害者参加制度について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子もご用意しています。
ぜひダウンロードしてみてください。
弁護士に相談・依頼すべき理由
みらい総合法律事務所の解決事例を読んで、次のような疑問が湧いたのではないでしょうか。
なぜ加害者側の任意保険会社は、本来であればご遺族が受け取ることができる金額よりも低い損害賠償金額を提示してくるのか?
解決事例のように、ご遺族が示談交渉をしても慰謝料などの損害賠償金は増額しないのに、なぜ弁護士が交渉に入ると裁判も含めて増額に至る可能性が高くなるのか?
その理由については、こちらのページをご覧ください。
さまざまな疑問が解けていくと思います。
そして同時に、ただの弁護士ではなく、交通死亡事故に強い弁護士に依頼すべき理由もおわかりいただけると思います。
その上で、ここからは、交通死亡事故に強い弁護士の選び方と相談・依頼する際にやってはいけないことについてお話していきます。
交通死亡事故に強い弁護士の選び方
交通死亡事故に強い弁護士の選び方は、次の2点です。
1つずつわかりやすく解説します。
交通死亡事故の経験豊富な
弁護士を選ぶ
交通死亡事故に強い弁護士の条件の第一は、死亡事故の経験が豊富なことです。
弁護士にも得意・不得意があります。
交通死亡事故を扱うには、
- ・損害賠償法の知識
- ・裁判例の知識
- ・保険の知識
- ・死亡事故特有の論点の知識
などが必要です。
しかし、これらは、司法試験には出ませんし、弁護士といえども、事件を扱わなければ一生知らずに過ぎていきます。
これらの知識は、実際に交通死亡事故を扱い、事件を解決する過程で研究をして、身につけていくものだからです。
したがって、ホームページなどにより、その法律事務所が交通死亡事故について豊富な経験を有しているかどうかを確認するようにしましょう。
法律専門書を執筆している
弁護士を選ぶ
交通死亡事故に強い弁護士の第二の条件は、法律専門書を執筆している弁護士を選ぶことです。
書籍には色々な種類がありますが、法律専門書というのは、その道の専門家が読む書籍のことです。
交通事故で言えば、裁判や弁護士などです。
これに対し、一般書というのは、専門家以外の交通事故の被害者などが読む本で、これは弁護士であれば、色々な類書を参考にすることで執筆することができます。
しかし、専門書は、その分野で深い知識を有していなければ書くことができません。
また、法律専門書を出版する出版社は、専門的知識を有する者にしか、専門書を書かせてはくれません。
なぜなら、法律業界で、交通事故に精通していると認知されている者が著者でなければ、本が売れないためです。
したがって、交通事故の法律専門書の著者であれば、法律業界で、一応、交通事故に精通していると推定が働くことになります。
みらい総合法律事務所でも、
「典型後遺障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
など、以下のような複数の法律専門書を執筆しています。
弁護士に相談・依頼する時の
注意ポイント
交通死亡事故に強い弁護士に相談・依頼する時の注意点は、次の7点です。
わかりやすく解説します。
(1)交通死亡事故に弱い
弁護士に依頼してはいけない
ひとくちに弁護士といっても、その専門分野はさまざまです。
ですから、知り合いから紹介された交通死亡事故に強くない弁護士に相談・依頼してしまうと、ご遺族が希望する結果が得られない可能性があります。
たとえば、交通事故を扱ったことがなく、日常的に金融法務ばかりを扱っている弁護士が、すぐに交通死亡事故の問題点を察知し、適切な対応をしていくことを期待するのはかなり難しいのではないでしょうか。
交通死亡事故に強い弁護士であれば、交通事故に関する法律だけでなく、逸失利益や過失割合など示談交渉に関わる知識と経験を豊富に持っています。
また、医学的な知見や損害保険の知識も持っていますから、加害者側の保険会社との示談交渉でご遺族に有利な主張をして、適切な額の損害賠償金を獲得できる可能性が高くなるのです。
(2)弁護士ランキングや
口コミ、おすすめサイトを
信用してはいけない
インターネット上には弁護士の口コミ評判やランキング、おすすめの弁護士を掲載しているサイトがありますが、これらには落とし穴があります。
これらを参考に交通事故に強い弁護士を選ぶことは難しいため、注意が必要です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)法律事務所のWEBサイトを安易に信用してはいけない
「交通死亡事故」、「弁護士」、「慰謝料」などのキーワードで検索してみると、たくさんのサイトが見つかります。
現在では、さまざまなことがWEBサイトで検索可能ですから、弁護士を探す時にはまずインターネットで検索をしてみるという方も多いでしょう。
しかし、注意が必要です。
なぜなら、法律事務所のWEBサイトは誰でも作ることができるものですから、その法律事務所が交通事故に精通しているかどうかは無関係です。
交通事故の専門書を出しているかどうかなど、その弁護士のキャリアに着目するようにしましょう。
(4)WEBサイトに記載の
弁護士の実績を鵜呑みにしては
いけない
法律事務所のWEBサイトには、解決事例が掲載されている場合も多いと思いますが、その解決事例は、「その事務所が」解決した事例でしょうか?
単に判例集から掲載した事例の紹介であることもあります。
「当事務所の解決事例」と記載してあるかどうかを確認するようにしましょう。
(5)弁護士と実際に会話を
しないで依頼してはいけない
SNSが発達した現在ですから、実際に会わない、会話をしないでさまざまな物事を決定することが多くなっています。
しかし、交通死亡事故に強い弁護士かどうかを判断するには、やはりその弁護士に会ってみるか、少なくとも会話してみることなしに依頼してはいけないでしょう。
電話に出て、実際に話をしている人が弁護士か、事務員かを確認するようにしましょう。
(6)こんな弁護士には
依頼してはいけない
弁護士と面談したり、電話で話をする際、次のような質問をしたり、回答する時の様子をよく観察してみてください。
こんな弁護士には依頼してはいけない、ということがおわかりいただけると思います。
- ・交通死亡事故の慰謝料などの相場や弁護士(裁判)基準により計算した損害賠償金額を答えられない
- ・慰謝料が相場より増額する事由に該当するかどうかを知らない
- ・自賠責保険での過失減額について質問しても答えることができない
- ・質問をしても答えをはぐらかしたり、面倒臭そうな態度をとる
- ・相談者に対して横柄な態度をとったり、突然怒りだしたりする
- ・弁護士費用などのお金の話ばかりする
このような弁護士に依頼してしまったなら、今からでも遅くありませんので、すぐにセカンドオピニオンで交通死亡事故に強い弁護士に相談するべきです。
(7)弁護士費用を確認せずに依頼してはいけない
多くの法律事務所では、弁護士費用については次のような内訳になっていると思います。
- ①相談料
- ②着手金
- ③報酬金
- ④その他
現在では相談料を無料にしている法律事務所も増えていますが、各法律事務所で考え方やシステムは違うので確認することが大切です。
弁護士に依頼した際にまず支払うのが着手金です。
契約の際の手付金のようなものと考えていただいていいと思います。
着手金は最終的に成果が出るかどうかに関係なく支払う費用ですから、着手金をいただくシステムの法律事務所に依頼した場合、依頼者の望む結果に至らなくても返金されないことに注意が必要です。
報酬金というのは、依頼した案件が解決した場合に、その成功報酬として弁護士に支払う費用です。
我々みらい総合法律事務所では、交通事故に関するご相談について、相談料と着手金は原則としていただいていません。
対象案件については完全成功報酬制を採用しているため、報酬金は増額した金額ではなく、原則として実際に獲得した金額の10%のみをいただいています。
(ただし、対象案件ではない場合で受任する際には、別途の基準を提示させていただいています)
「交通事故の被害者の方々の負担を少しでも軽減したい」という考えから、当法律事務所ではこのようなシステムを採用しているのです。
死亡事故の弁護士費用の相場の詳細はこちらの記事でご確認ください。
交通死亡事故の場合、亡くなったご家族の四十九日が過ぎると、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。
まずは、この時点で交通死亡事故に強い弁護士に相談していただければと思います。
みらい総合法律事務所は、死亡事故と後遺症事案について、無料相談を受け付けています。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
死亡事故の保険金や賠償金について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
代表社員 弁護士 谷原誠