交通事故の被害者参加をサポート|みらい総合法律事務所
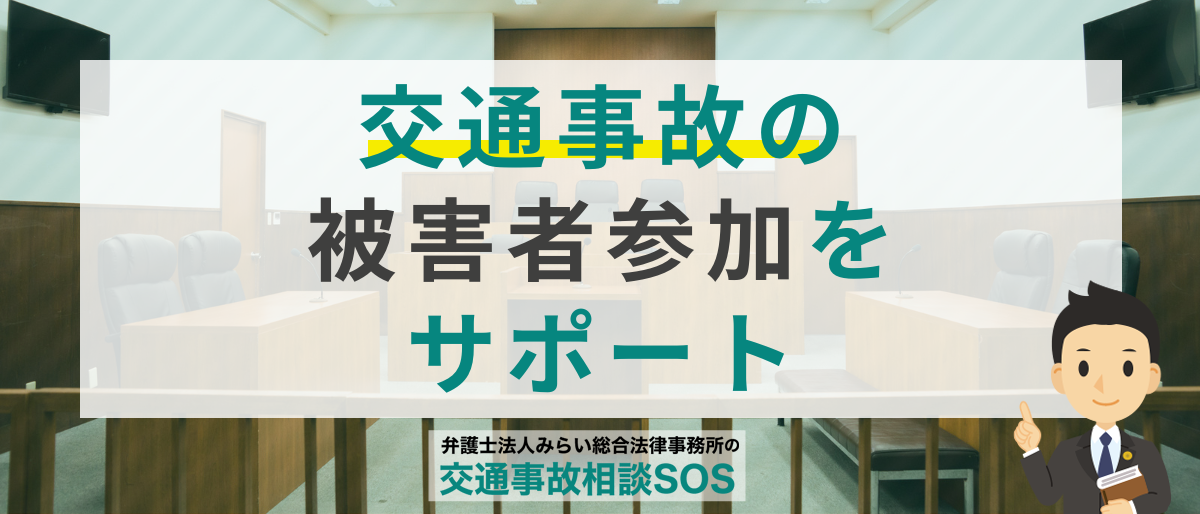
交通事故の被害者参加制度とは、事故の被害者やご遺族等が、加害者の刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるという制度です。
被害者参加制度は、故意の犯罪行為により人を死傷させた事件(殺人、傷害、危険運転致死など)や、強制わいせつ、強姦、逮捕・監禁、過失運転致死など、一定の刑事事件に適用があります。(刑事訴訟法290条の2)
したがって、交通事故で被害者が死傷した場合に、この制度を利用することができます。
刑事裁判への参加を許可された被害者やご遺族等の方々は「被害者参加人」と呼ばれます。
被害者参加人として刑事裁判に参加できるのは、被害者、または被害者が死亡もしくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族もしくは兄弟姉妹などの方々、もしくは被害者の法定代理人などです。
本記事では、被害者参加制度のメリットや流れ、被害者参加人ができることなどについて解説していきます。
被害者参加を検討されている方々の参考になれば幸いです。
なお、みらい総合法律事務所では、ご遺族のために被害者参加をサポートしており、交通事故の示談交渉のご依頼をいただいた場合には、被害者参加サポートの弁護士費用は遠方への出張費用などを除き、いただいておりません。
被害者参加のメリット
交通事故の被害者参加制度は、事故の被害者やご遺族等が、加害者の刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるという制度ということは前述しましたが、それでは被害者参加のメリットはどんなことがあるのでしょうか?
被害者参加のメリット①刑事
裁判前の刑事記録の閲覧謄写
刑事事件の捜査では、捜査段階で被害者側に事故の詳しい状況や加害者の供述内容等が明かされる事は少ないです。
したがって、刑事裁判になって初めて加害者側がどう供述しているかなどを知ることができるのが通常です。
しかし、被害者参加をすれば、第一回公判期日の前に、刑事記録の閲覧謄写が可能になります。
早期に刑事記録を閲覧することによって、加害者の供述の嘘や矛盾を公判期日で追求することが可能になる場合もあります。
被害者参加のメリット②裁判官に直接訴えることができる
刑事事件で、加害者が罪を認めているような場合には、検察官の立証は通常、書類のみを裁判所に提出することが多いです。
そうすると、裁判官は書面だけを見て、被害感情などを知ることになります。
しかし、被害者参加制度を利用して、実際に公判期日で、意見を陳述するなどすれば、迫真性のある供述をすることができ、被害者側の感情をリアルに裁判官に伝えることが可能となります。
刑事裁判の流れ
被害者参加は、刑事裁判へ参加することになりますが、刑事裁判の具体的な流れを解説します。
刑事裁判の流れ①冒頭手続き
刑事事件はまず冒頭手続きを行います。
冒頭手続きは、加害者を特定するための手続きです。
次に、検察官が起訴状を朗読します。
起訴状朗読の後、裁判官から、加害者に対して、黙秘権の告知があります。
黙秘権の告知をした上で、加害者が罪を認めるかどうかという罪状認否手続きが行われます。
その後裁判官は弁護人に意見を聞きます。
そうすると、加害者の主張が明らかになりますので、次に、必要なことについて証拠調べ手続きが行われます。
刑事裁判の流れ②証拠調べ手続き
証拠調べ手続きには順番があります。
まず検察官が立証活動を行います。
立証活動とは、被告人が有罪であることを裁判官に証明するための活動のことです。
検察官の立証活動が終わると、弁護人が立証活動を行います。
刑事裁判の流れ③弁論
双方の立証活動が終わると、検察官が論告求刑を行い、弁護人が最終弁論を行います。
そして、最後に、被告人が意見陳述を行って、結審します。
結審とは、裁判所がこれ以上証拠調べや双方の主張を聞く必要がないと判断し、審理を終了することです。
刑事裁判の流れ④判決言渡し
そして、後日、裁判所による判決が下されることになります。
刑事手続きについてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
被害者参加は、上記の刑事手続に参加していく手続となります。
被害者参加の手続き
被害者参加を希望する場合には、刑事裁判への参加について、事件を担当する検察官に申し出ることになります。
検察官は、被害者が刑事裁判に参加することについて意見をつけて裁判所に通知します。
裁判所は、検察官からの通知を受けて、被告人又は弁護人の意見を聞きます。
その上で、犯罪の性質などいろいろな事情を考慮して、相当と判断した場合には、許可します。
裁判所の許可を得ることにより、刑事裁判に被害者参加人として参加することができることになります。
ただし、参加が許可された場合にも、手続きによっては参加が許可されない場合もあります。
被害者参加人ができること
被害者参加人は、次の行為を行うことができます。
1つずつ詳しく解説します。
①公判期日に出席すること
被害者参加人には公判の期日が通知されます。
また、被害者参加に対して、国がその旅費等を支給する制度もあります。
公判期日には、被害者参加人は法廷に入り、検察官席の隣などに座って裁判に出席することができます 。
②検察官の権限行使に関して意見を述べ、説明を受けること
刑事裁判の証拠調べの請求や論告、求刑などの検察官の訴訟活動に関して被害者参加人が意見を述べたり、検察官に説明を求めることができます。
③証人に尋問すること
被害者参加人は、裁判所から許可を受けた場合には、情状に関する事項について、証人尋問を行うことができます。
ここで、情状とは、有罪判決を前提として、どの程度の量刑にするのかを判断するための事情のことをいいます。
ここで、検察官の反対尋問だけではなく、被害者参加人自身が考えた質問事項を尋問することができる、ということです。
この場合、被害者参加人本人、その代理人である弁護士のどちらからでも質問をすることができます。
ご本人の場合、裁判の尋問に慣れていないため、質問ではなく、意見のようになってしまうことも多いので、弁護士に任せてしまうことも検討しましょう。
④被告人に質問をすること
被害者参加人が意見を述べるために必要と認められる場合には、裁判所の許可を得て、被告人に質問することができます。
被告人質問については、情状に関する事項のみならず、犯罪事実についても質問することができます。
この場合も、被害者参加人本人、その代理人である弁護士のどちらからでも質問をすることができます。
⑤事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
証拠調べが終わった後、被害者参加人は、事実または法律の適用について法廷で意見を述べることができます。
またこれらの手続きについて、弁護士を選任することもできます。
被害者参加を何度も経験する事はないと思いますので、どのような質問が効果的か、また意見陳述はどのように行えば良いのか等についてわからないことが多いと思います。
専門的な手続きなので、可能であれば、弁護士の援助を受けながら手続きを進める方が良いと思います。
なお、みらい総合法律事務所では、ご遺族のために被害者参加をサポートしています。
無料相談を行なっていますので、被害者参加をご検討の方はぜひご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
こちらの記事もよく読まれています
代表社員 弁護士 谷原誠



















の後遺障害等級.png)


