交通事故による鎖骨変形|後遺障害認定や慰謝料のポイントを解説
交通事故で鎖骨が変形すると、治療が終わっても日常生活に支障が出ることがあります。
被った損害に対する慰謝料は、後遺障害の有無でも変わりますし、認定等級によっても異なるため、適切に認定手続きを進めることが重要です。
本記事では、鎖骨変形に関する後遺障害認定の基準と慰謝料の相場、後遺障害の認定を受ける際の注意点を解説します。
目次
交通事故で鎖骨が変形する原因と
症状
交通事故の衝撃によって鎖骨に強い負荷がかかると、骨折や亜脱臼(あだっきゅう・関節が完全には外れていないものの、正常な位置からずれてしまっている状態)を引き起こし、変形が残ることがあります。
変形の主な原因は衝突や
転倒による骨折
交通事故では、シートベルトによる圧迫や地面への強打などで鎖骨を骨折することがあります。
たとえば、自転車やバイクの事故、車両との衝突では、肩に直接的な力が加わりやすく、鎖骨が折れてしまうことも珍しくありません。
骨折した鎖骨が正しくくっつかなかったり、ずれたまま回復したりすると、見た目に明らかな変形が残ってしまいます。
また、初期治療が遅れると、その後の機能障害や慢性的な痛みにつながることもあるため、早期の診断と処置が重要です。
事故直後に現れやすい
鎖骨損傷の初期症状
骨折に伴って肩を動かせない、腕の可動域が制限される、深呼吸で痛みが走るといった症状が出る場合には、鎖骨骨折が疑われます。
骨折の部位によっては、皮膚の下に骨の突出が確認されたり、左右非対称の変形が視認されたりすることもあります。
これらの症状が見られるときは、速やかに整形外科を受診し、レントゲンやCT検査によって正確な診断を受けてください。
鎖骨変形がもたらす痛み・
可動域制限・外見上の違和感
鎖骨の変形は、日常生活に支障をきたすほどの痛みや不快感を伴います。
たとえば、腕を上げたり肩を回したりする際につっぱり感や違和感が生じたり、重いものを持つ動作で神経の圧迫による痛みが起きたりします。
また、衣服の上からでもわかる骨の突出や左右差が、外見上のストレスとなるケースも少なくありません。
治療を続けても鎖骨の変形が事故前の状態に戻らない場合は、後遺障害として認定される可能性があるため、適切な手続きを進めることが大切です。
鎖骨変形は後遺障害として
認められる?
交通事故による鎖骨の変形が後遺障害として認定されるケースはいくつか考えられます。
鎖骨変形が後遺障害として
認定されるケース
鎖骨の変形によって「変形障害」「機能障害」「神経障害」の症状が残った場合には、後遺障害として認定される可能性があります。
変形障害は、鎖骨に著しい変形が生じ、それが外見上も明らかである場合に認められる障害です。
たとえば、骨の突出や左右差が明確で、衣服を着た状態でも視認できるような変形があるときは、変形障害と判断される可能性が高くなります。
機能障害は、鎖骨の骨折によって身体の動きに制限が生じる障害をいいます。
腕や肩の可動域が狭くなっている、継続的な痛みがある、運動機能が低下しているといった症状が認められる場合には、後遺障害と認められることがあります。
神経障害は、治療後も疼痛が残る状態をいいます。
なお、これらの障害が後遺障害として認定されるためには、診断と客観的な所見がそろっていることが前提となるため、通院を継続するなどの対処が求められます。
後遺障害として認定された際の
等級
鎖骨が変形したことで生じる後遺は複数考えられるため、認定される等級も症状によって変わってきます。
たとえば、視覚的にも鎖骨の変形が明らかな場合は、「12級5号」に該当する可能性があります。
鎖骨骨折による肩関節の機能障害が残るケースでは、「10級10号」「12級6号」と認定される可能性があります。
また、見た目の変形が軽度であっても、痛みや違和感が長期にわたって継続する場合は、「14級9号」として認定される可能性があります。
これらの等級は、慰謝料や逸失利益の算定基準となるため、事故との因果関係を客観的に証明する資料の提出が求められます。
鎖骨変形による慰謝料・
損害賠償の相場
交通事故による鎖骨変形が後遺障害として認定された場合でも、認定された等級によって慰謝料や損害賠償金の額は異なります。
怪我・後遺障害の程度によって
金額は変動する
慰謝料や損害賠償額は、鎖骨の変形による実生活への支障の度合いに応じて変動します。
外見上の影響が強い場合や、腕や肩の可動域制限によって職業上の支障が生じている場合は、賠償額が増額される傾向があります。
たとえば、身体を使う仕事や人前に立つ業務では、見た目の違和感や痛みによる能力低下が逸失利益として算定されることもあります。
変形の程度が軽度であっても、職業との関連性が強ければ損害賠償額が大きくなることがあるため、状況に応じて適切に資料を提示することが大切です。
後遺障害の等級に応じた
慰謝料の目安
後遺障害は、認定された等級に応じて慰謝料の基準額が定められています。
たとえば、後遺障害等級が12級5号に該当する場合、自賠責基準では94万円の慰謝料が支払われる可能性があります。
痛みや違和感が残り、14級9号として認定された場合の慰謝料は32万円程度です。
なお、これらの金額はあくまで自賠責基準に基づくものであり、弁護士基準を用いることで、より実情に見合った金額を受け取れる可能性もあります。
慰謝料の金額は採用する
算定基準によっても変わる
鎖骨の変形が後遺障害として認定された場合、慰謝料の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」のいずれかが用いられます。
自賠責基準は、自動車損害賠償責任保険に基づき、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるための基準です。
最低限の補償を目的としているため、鎖骨変形が後遺障害として認定された場合でも、受け取れる慰謝料は低くなる傾向があります。
任意保険基準は、保険会社が独自に設定する基準です。
慰謝料は自賠責基準より高額になることが多いものの、詳細な算定方法は公表されていません。
弁護士基準(裁判基準)は、裁判で認められる慰謝料の基準であり、3つの算定基準の中では最も高額な慰謝料が認められる可能性があります。
たとえば、鎖骨に著しい変形が残り、12級5号の後遺障害等級の認定を受けた場合、自賠責基準では慰謝料として94万円が支払われます。
一方、弁護士基準で算定した場合には、290万円を超える慰謝料が認められるケースもあります。
なお、弁護士基準での請求には専門的な知識や交渉力が求められるため、状況に応じて弁護士に相談することが望ましいでしょう。
鎖骨変形による後遺障害と
逸失利益の請求
交通事故によって鎖骨が変形したことが仕事に影響した場合、「逸失利益」を請求できる可能性があります。
逸失利益は将来の収入減に
対する補償
逸失利益とは、交通事故による後遺障害によって労働能力が低下し、将来的に得られるはずだった収入が減少することに対する損害賠償です。
鎖骨変形が残存し、動作制限や外見上の異常によって職務遂行に支障が生じた場合には、労働能力喪失率を根拠として損害額が算定されます。
補償額は職業・年齢・
就労可能年数によって異なる
逸失利益は単なる治療費や慰謝料とは異なり、長期的な収入減に焦点を当てた補償です。
そのため、逸失利益の金額は、被害者の職業・収入水準・年齢・就労可能年数などによって大きく左右されます。
たとえば、若年層の正社員が鎖骨変形により業務に支障をきたす場合は、長期的な収入減が見込まれるため、補償額は高額になる傾向があります。
一方で、高齢者や非正規雇用者の場合は、労働能力喪失による収入減が限定的と見なされ、補償額が低く算定されることもあります。
適正な評価を得るためには、職務内容・収入証明・医師の所見などを含む精緻な資料と主張が不可欠です。
後遺障害認定を受けるための
ポイント
交通事故で鎖骨が変形したとしても、治療や通院を続けないと後遺障害として認定されないので注意してください。
交通事故との因果関係の証明は
不可欠
後遺障害の申請では、損傷が交通事故によって発生したという因果関係を示すことが最も重要です。
事故証明書や医師の診断書などの資料を通じて、受傷の経緯と部位を明確に示す必要があります。
鎖骨変形が他の疾病や過去の外傷によるものではないと証明するためには、事故当日から一貫した診療記録が求められます。
通院を続けることで、医師による事故直後の評価と治療経過の記録が蓄積され、因果関係の信頼性を高めることにつながります。
レントゲン・MRIなどの検査と
継続的な診察記録の重要性
後遺障害の認定にあたっては、継続的な診察および検査結果が客観的証拠として求められます。
鎖骨の変形を示す画像所見としては、レントゲン・CT・MRIなどが有効であり、骨の癒合状況や突出の程度を視覚的に示すことが重要です。
後遺障害として症状が残存していることを証明するには、定期的な診察と画像記録を通じて、構造的異常の持続や変形の固定性を明らかにする必要があります。
また、通院頻度や医師の所見内容も後遺障害等級の判断材料となるため、診療ごとに記録を残しておくことが望ましいでしょう。
医師に診断書の作成依頼をする
鎖骨の変形による後遺障害の認定を受けるには、医師の診断書の提出が必須です。
診断書には、骨の変形の部位や程度、見た目の異常、動作制限の有無、痛みの持続状況などを具体的に記載してもらう必要があります。
ただし、後遺障害に関する診断書は、症状固定の状態に至らなければ作成できません。
症状固定とは、治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない状態を指します。
適切に症状固定と判断されるためには、一定期間にわたる継続的な治療と通院が必要です。
鎖骨の変形が残っている場合でも、症状固定前に診断書を依頼すると、後遺障害として認定されない可能性があるので注意してください。
交通事故で鎖骨が変形したときは
弁護士に要相談
交通事故によって鎖骨が変形した場合、外見上の問題だけでなく、運動機能の制限や精神的な負担を伴う可能性があります。
こうした症状は、後遺障害として認定されることで、適切な補償を受ける道が開かれますが、後遺障害に該当するかどうかの判断には、専門的な知識が不可欠です。
また、交通事故の示談交渉では、過失割合の争点や保険会社との複雑なやり取りが発生し、被害者にとって大きな精神的負担となることがあります。
これらの対応を被害者自身で行うのは容易ではないため、早い段階で弁護士に相談し、必要な手続きを専門家に任せることを検討してください。
交通事故による鎖骨変形でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠





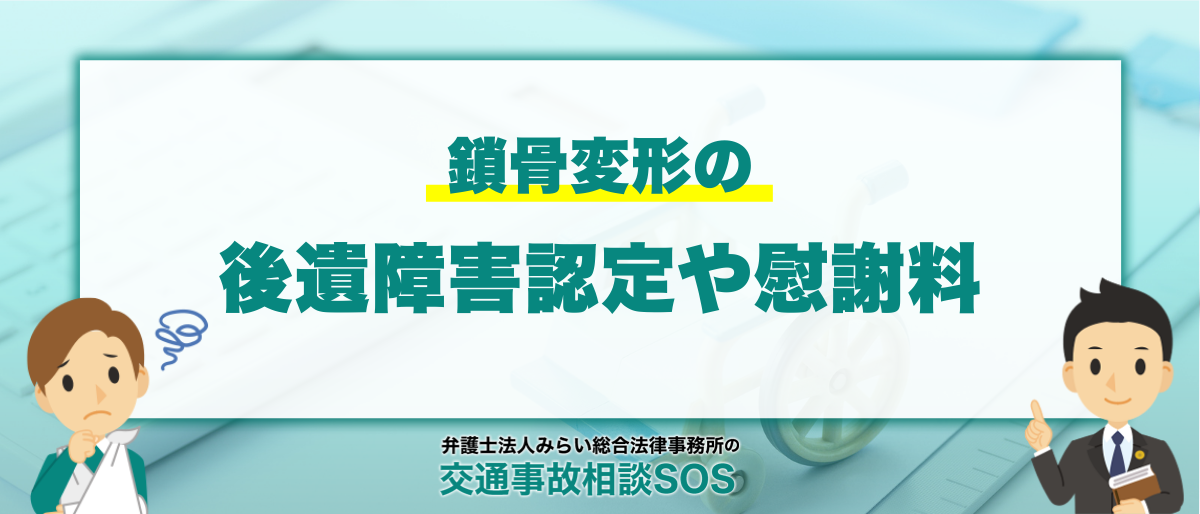
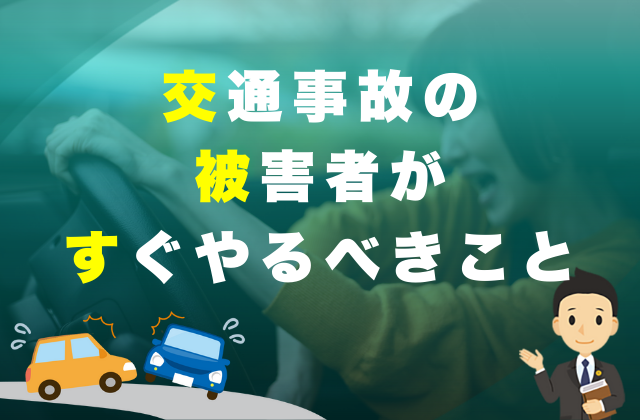











の後遺障害等級.png)


