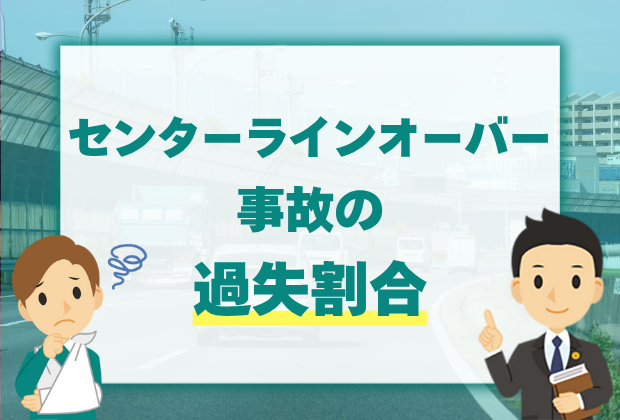交通事故の自賠責保険の金額・手続と計算
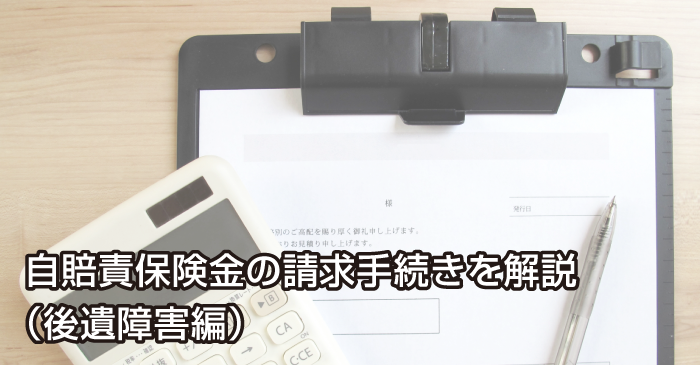
*タップすると解説を見ることができます。
交通事故に関わる手続きや用語には、難しいものが多いと感じる方もいらっしゃるでしょう。
また、知っているようで、じつはよく知らない、しっかり理解できていないというものもあると思います。
そこで今回は、「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)について解説します。
交通事故の被害者は、負ってしまったケガや後遺障害の等級に応じた慰謝料などの損害賠償金(保険金)を受け取ることができます。
その際、まず関わってくるのが自賠責保険です。
ここでは、自賠責保険の内容や、保険金の請求の際に必要となる手続きである「被害者請求」と「事前認定」の違いなどについて見ていきます。
目次
自動車損害賠償責任保険とは?
自動車損害賠償責任保険とは、自動車やバイクを使用する際に、法律によってすべての運転者が強制的に加入しなければならない損害保険です。(自動車損害賠償法第5条)
加入が義務付けられていることから「強制保険」と呼ばれることもありますが、略称である「自賠責保険」として認識している人も多いでしょう。
自賠責保険は、人身事故の被害者を救済するために作られた保険です。
そのため、自損事故によるケガや物損事故には適用されず、人身事故の被害の場合にのみ保険金などが支払われることになります。
一方、任意保険はドライバーや自動車の所有者などが任意で加入する保険です。
各損害保険会社が、さまざまな内容の保険を打ち出しています。
被害者としては、自賠責保険からの保険金では足りない部分の損害賠償金額や、自賠責保険金額を含んだ損害賠償金額を加害者側の任意保険会社に請求することになります。
なお、被害者自らがかけている任意保険から保険金を受け取る場合もあります。
自賠責保険の慰謝料などの
金額と計算
自賠責保険で補償される保険金額等は法律によって定められています。
傷害部分
交通事故により、後遺障害が残った場合には、症状固定を境に、「傷害部分」と「後遺障害部分」に分けられます。
傷害部分として自賠責保険に請求できる金額としては、以下のものがあります。
治療関係費
これは、ケガの治療に関係する費用で、以下のものがあります。
- ・応急手当費
- ・診察料
- ・入院料
- ・投薬料、手術料、処置料等
- ・通院費、転院費、入院費又は退院費
- ・看護料
- ・諸雑費
- ・柔道整復等の費用
- ・義肢等の費用
- ・診断書等の費用
示談交渉で請求できる治療費について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
休業損害
休業損害は、ケガにより仕事を休まざるを得ないことによる収入減少を補償するものです。
休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を試用した場合に、1日について原則として
6,100円です。
家事従事者ももらえます。
弁護士基準による休業補償について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
慰謝料
慰謝料は、1日につき4,300円です。
慰謝料がもらえる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、症状固定までの範囲内です。
弁護士基準による慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
後遺障害部分
後遺障害部分について、自賠責保険からもらえるものとしては、逸失利益と慰謝料等があります。
逸失利益
逸失利益は、以下の計算式を用います。
(後遺障害確定時の年齢における
就労可能年数のライプニッツ係数)
年収は、仕事をもっている人の場合は、事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とします。
労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級に応じて、以下のように定められています。
【労働能力喪失率】
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35 |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
ライプニッツ係数は、中間利息の控除のための係数です。
つまり、逸失利益は、将来の収入減少分の補償なので、今受け取ると、中間利息分得をすることになります。
そこで、計算結果から中間利息分を控除しよう、というものです。
【参考情報】:「就労可能年数とライプニッツ係数表」国土交通省
慰謝料等
慰謝料等の金額についても、認定された後遺障害等級によって定められています。
自賠責法別表第1
| 等級 | 保険金額 |
|---|---|
| 第1級 | 1,650万円 |
| 第2級 | 1,203万円 |
自賠責法別表第2
| 等級 | 保険金額 |
|---|---|
| 第1級 | 1,150万円 |
| 第2級 | 998万円 |
| 第3級 | 861万円 |
| 第4級 | 737万円 |
| 第5級 | 618万円 |
| 第6級 | 512万円 |
| 第7級 | 419万円 |
| 第8級 | 331万円 |
| 第9級 | 249万円 |
| 第10級 | 190万円 |
| 第11級 | 136万円 |
| 第12級 | 94万円 |
| 第13級 | 57万円 |
| 第14級 | 32万円 |
自賠責保険金の限度額
自賠責保険金については、上記で計算された金額の全額が払われるわけではなく、限度額が定められています。
傷害部分については、120万円です。
傷害を負ったことにより後遺障害が残り、介護が必要な場合は4,000万~3,000万円、その他の後遺障害の場合は1級から14級の後遺障害等級に応じて3,000万円~75万円となっています。
自賠責法別表第1
| 等級 | 保険金額 |
|---|---|
| 第1級 | 4,000万円 |
| 第2級 | 3,000万円 |
自賠責法別表第2
| 等級 | 保険金額 |
|---|---|
| 第1級 | 3,000万円 |
| 第2級 | 2,590万円 |
| 第3級 | 2,219万円 |
| 第4級 | 1,889万円 |
| 第5級 | 1,574万円 |
| 第6級 | 1,296万円 |
| 第7級 | 1,051万円 |
| 第8級 | 819万円 |
| 第9級 | 616万円 |
| 第10級 | 461万円 |
| 第11級 | 331万円 |
| 第12級 | 224万円 |
| 第13級 | 139万円 |
| 第14級 | 75万円 |
参考記事:国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」
自賠責保険で行なうべき手続き
症状固定
交通事故の被害者でケガを負ってしまった場合、まずは病院で入院や通院をしてケガの治療を行ないます。
ここで大切になってくるのが「症状固定」という概念です。
ケガの治療のかいなく、残念ながらこれ以上の治療を続けても完治することがない、よくなることがない、と担当医師が判断した場合、症状固定となります。
後遺障害等級の認定
症状固定となると、後遺症が残ることになります。
ここで大切なのは、自分の後遺症がどの程度なのかを知ることです。
これは、後遺障害等級で表されます。
自動車損害賠償保障法(自賠法)では、後遺障害等級は症状の重い1級から14級まで、さらに後遺障害を負った部位の違いによって各号数が細かく分類されています。
たとえば、片方の眼を失明し、もう片方の眼の視力が0.02以下になった場合は8級1号、胸腹部臓器の機能に著しい障害が残ってしまい、生涯にわたって仕事ができないような場合は3級4号と認定される可能性があります。
後遺障害等級認定の手続き
被害者は「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)に後遺障害等級認定の申請をします。
ご自身の後遺障害等級は、今後始まる損害賠償の示談交渉の際も大切になってくるので、間違いなどのないように申請しなければいけません。
なぜなら、後遺障害等級がひとつ違っただけで、最終的な示談金が何十万から何百万、重度なものになると何千万円も変わってくることがあるからです。
被害者としては、受け取る保険金で損をしないようにしなければいけません。
後遺障害等級認定について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
被害者請求と事前認定の違いとは?
後遺障害等級認定を申請するには2つの方法があります。
「被害者請求」と「事前認定」です。
それぞれにメリットとデメリットがあります。
被害者請求
被害者請求とは
被害者請求とは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に直接申請する方法です。
被害者請求によって後遺障害等級が認定されると、最初に自賠責保険金がまとまった金額で支払われます。
仮に、被害者とご家族に金銭的な余裕がない場合などは、まずは自賠責保険金を受け取ることで精神的にも余裕をもてるというメリットがあります。
というのも、この後に足りない損害賠償金額分を受け取るために加害者側の保険会社と示談交渉を進めていかなければいけないのですが、金額等で和解できなければ裁判などに進むこともあり、長い期間交渉がまとまらないということもあるからです。
また、被害者請求の名の通り、被害者が自分で資料を集めて申請することになります。
すると、手続の流れや、提出する書面を自分で把握できるので、これもメリットになります。
なぜなら、人任せにしていると間違った後遺障害が認定された時など、どこが間違っていたのか、何の資料・書類が足りなかったのかなどがわからないため対処が難しくなってしまう場合もあるからです。
しかし同時に、これがデメリットにもなります。
被害者請求では、さまざまな資料や書類を自分で用意しなければならないため、被害者としては手間がかかってしまうからです。
なお、加害者側の保険会社との示談交渉が決裂した場合は訴訟を提起して裁判に突入していく可能性があります。
判決で決着した場合、最終的に決定した損害賠償金には事故時からの遅延損害金がつきます。
しかし、被害者請求で最初にまとまったお金をもらっていると、最後に受け取る賠償金は当然少なくなるので、その分、遅延損害金も少なくなるというデメリットもあることに注意が必要です。
具体的には、「事故証明書」を見ると、加害者側の自賠責保険会社がわかりますので、そこに電話し、被害者請求に必要な書類一式を送るようお願いします。
そうすると、パンフレットや用紙等が送られてきますので、それに従って、申請をすることになります。
ただ、どのような医証を送るのがよいのか、など、特に重傷事案では難しいので、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
参考論文:「自動車損害賠償保障法における 被害者の直接請求」(岳衛著、立命館法学2004年1月)
後遺障害の被害者請求での必要書類
被害者請求をするには、自賠責保険会社に対して請求手続をすることになりますが、この手続は、書類を提出して行うことになります。
後遺障害で自賠責保険に被害者請求をする際に、主に必要な書類は、以下のとおりです。
- ・保険金(共済金)、損害賠償額、仮渡金支払請求書
- ・交通事故証明書
- ・事故発生状況報告書
- ・医師の診断書
- ・診療報酬明細書
- ・付添看護自認書または看護料領収書
- ・休業損害の証明書
- ・損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
- ・委任状および(委任者の)印鑑証明
- ・後遺障害診断書
- ・レントゲン等の画像
被害者請求について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
事前認定
事前認定とは、被害者が直接ではなく、加害者側の任意保険会社を通して自賠責保険に申請する方法です。
通常、加害者側の任意保険には、示談代行サービスがついており、保険会社の担当者と示談交渉を行うことになります。
そして、任意保険会社と示談をした場合には、自賠責保険の金額を含んだ総額で損害賠償金の支払がなされます。
その上で、任意保険会社は、自賠責保険に対し、支払われるべき自賠責保険の金額を回収する、という段取りになります。
そうすると、任意保険会社としては、示談をした後で、自賠責保険からいくら支払われるか、自賠責保険が、被害者の後遺障害等級を何級と認定するか、を把握しておかなければなりません。
そこで、「事前に」任意保険会社は、自賠責後遺障害等級を認定するよう請求することになります。
これが、「事前認定」です。
被害者のメリットとしては、加害者側の任意保険会社が手続をやってくれるので、被害者請求のように資料や書類を集めて申請するといった手間がかからないことがあげられます。
さらに、示談交渉が上手くいかず最終的に裁判までいった場合、事故時から賠償金に遅延損害金がつくというメリットもあります。
被害者としては、事前認定で申請しておいて、判決後に足りない分の損害賠償金をもらった方が最終的な獲得金額が増えるわけです。
逆にデメリットとしては、どのような書類・資料が任意保険会社から提出されているのかわからないため、被害者としては提出書類に不備・不足がないかどうか確認することができないということがあげられます。
被害者請求と事前認定のどちらがいいのかは一概には決められないところがあります。
被害者のおかれている状況などを考えながら選択することになるでしょう。
後遺障害等級については
異議申立ができる
仮に、提出した書類に不備や不足があった場合、本来認定されるはずの後遺障害等級ではなく低い等級が認定されてしまう可能性があります。
そうなると、支払われる慰謝料などの損害賠償金も低くなってしまうことに注意しなければいけません。
認定された後遺障害等級に納得がいかない場合や、より上位の後遺障害等級が認定される可能性がある場合には、新たな資料等を提出して異議申立」をすることができます。
このあたりになると、法的知識の他、医学的知識や自賠責後遺障害等級認定基準などの知識も必要となってくるので、交通事故に詳しい弁護士に相談した方がよいでしょう。
異議申立について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
加害者が自賠責保険に
入っていなかった場合どうする?
強制加入であるはずの自賠責保険に加害者が加入していないという場合も考えられます。
その場合は、「政府保障事業」という制度を利用するとよいでしょう。
交通事故の被害にあったうえに損害賠償もされないのでは、あまりに被害者に酷です。
そのため、被害者救済として、自動車損害賠償保障法において政府保障事業という制度が設けられており、政府からの保障を受けることができるようになっているのです。
政府保障事業は、無保険者が事故を起こした場合の他、ひき逃げのように加害者がどこの誰なのかわからない場合にも自賠責保険と同額の補償をしてくれます。
政府保障事業について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
自賠責保険について不安な時は
弁護士に相談を!
ここまで、自賠責保険の内容から後遺障害等級認定、被害者請求と事前認定、異議申立などについて解説しました。
しかし、法律や保険に関する知識や手続きは難しいと感じる方もいらっしゃるでしょう。
また、「被害者請求」がいいのか、「事前認定」がいいのか、など、迷うこともあるでしょう。
その場合は一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することを検討してみてください。
みらい総合法律事務所は、死亡事故と後遺症事案について、無料相談を受け付けています。
まず、無料で弁護士に相談し、弁護士に依頼した方が得になりそうな場合に、初めて弁護士に依頼すればよいと思います。
その際、必ず契約書を締結して、報酬金額を確認しておきましょう。
「報酬は後で話し合いましょう」というような法律事務所は避けてください。
また、交通事故の事案では、法律知識の他、医学的知識や自賠責後遺障害等級認定に関する実務知識、保険の知識などが要求されますが、すべての弁護士がこうした知識や実務に詳しいわけではありません。
できる限り、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
②交通事故の専門書に執筆している
③ニュース番組などから「交通事故の専門家」として取材を受けている
これらの条件に当てはまるのであれば、交通事故に精通した弁護士といえるでしょう。
なお、みらい総合法律事務所では、死亡事故と後遺症示談に注力して専門性を高めており、
「典型後遺障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)など専門書を複数執筆しています。
また、テレビ、新聞、出版等の各メディアから「交通事故の専門家」として取材を受けています。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
【動画解説】自賠責保険に対する被害者請求の方法
代表社員 弁護士 谷原誠












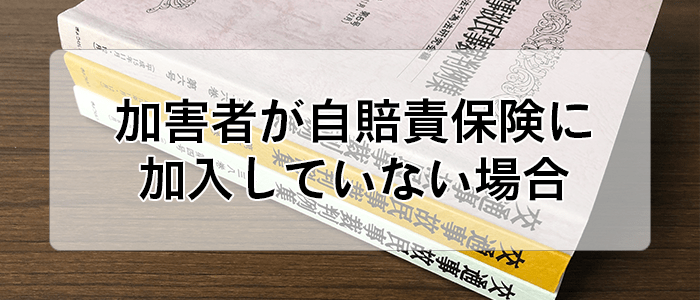
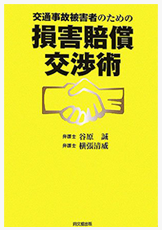



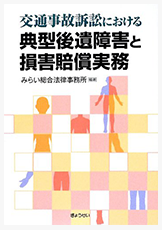



の後遺障害等級.png)