交通事故の示談金額に納得できない場合の対処法
*タップすると解説を見ることができます。
交通事故にあい、被害者の方が傷害(ケガ)を負った場合、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社から示談金(損害賠償金、保険金)の提示があります。
そのタイミングは、被害者の方に後遺症が残った場合は後遺障害等級が認定された後、ということになります。
ところで、ここで大きな問題があります。
それは、交通事故の損害賠償実務でも最大級のポイントの1つである、示談金の提示がかなり低い、という問題です。
加害者側の任意保険会社は、被害者の方が本来受け取るべき正しい金額を提示してきません。
- それはなぜなのか?
- では、適切な示談金の相場はいくらになるのか?
- 保険会社との示談交渉のポイントは?
- 正当な示談金を受け取るための対処法とは?
本記事では、これらのテーマを中心、お話ししていきます。
なぜ保険会社は低い示談金を提示してくるのか?
加害者が任意保険に加入している場合、一般的にはその保険会社から示談金の提示があります。
しかしここでは、本来であれば被害者の方が受け取るはずの金額よりも、かなり低い金額が提示されることが多いです。
保険会社は営利会社ですから、利益を出すために活動しています。
そうすると、できるだけ収入を増やして、支出を抑えようという動きが起きてきます。
そのため、被害者側と加害者側の主張が食い違い、求めることも正反対なことから、示談交渉がなかなか進まず、長引いてしまうことがよくあります。
被害者の方がいくら、「この示談金額は適切ではないから不服だ」「示談金額が低すぎるから上げてほしい」と主張しても、保険会社はまず応じることはありません。
それは、なぜなのか…動画と記事で解説しました。
ぜひ、ご覧になって、その理由を確かめてみてください。
よくわかる動画解説はこちら
増額しない理由は?
示談金の正しい相場金額とは?(慰謝料自動計算機)
では、正しい示談金の相場金額は、一体いくらくらいになるのでしょうか?
じつは、
・交通事故の態様
・被害者の方のケガの程度や入通院期間
・後遺症の有無
・後遺障害等級で何級が認定されたか
・被害者の方の職業
・被害者の方の会社や家庭での立場
・加害者の悪質性
・慰謝料などの計算基準
などなど、示談金額を算出するには、さまざまな要素があり、その交通事故の全体の状況によって示談金額は変わってきます。
ですから、明確に、わかりやすく、「相場はこの金額です」とは言えないのです。
でも、がっかりしないでください!
みらい総合法律事務所では、WEB上にどなたでも使える「慰謝料自動計算機」を設置しています。
指示に従って数字などを入力すると、慰謝料などの損害賠償金額の概算金額がすぐにわかるようになっているので、ぜひご活用ください。
交通事故の示談金額に納得いかない場合の対処法
加害者側の任意保険会社から提示された示談金額に納得できない場合、どうすればいいのでしょうか?
じつは、示談金額を可能な限り増額させる方法があります。
損害賠償項目の内訳と金額の確認する
被害者の方に後遺障害等級が認定されると、加害者側の任意保険会社から、損害賠償項目と金額が書かれた書類が届きます。
まず、内容をよく見てください。
❏損害項目に漏れはないか?
❏適切な金額の基準は正確にはわからないが、あきらかに低すぎると違和感を覚えないか?
記載されている損害項目と金額を必ず確認してください。
よくわかる動画解説はこちら
後遺障害等級が正しく認定されているか確認する
実際、正しい後遺障害等級が認定されていない場合もあります。
というのは、最終的な等級認定は損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関が行なうのですが、出された申請書や書類などからのみ等級認定を行なうからです。
ということは、提出書類に不足や不備があると、その通りに審査されてしまうということです。
弁護士が被害者の方やご家族から依頼を受けた場合は、まず後遺障害等級が正しいかどうかの調査から始めます。
等級が違うと慰謝料などの金額が大きく違ってくるからです。
なお、等級に納得がいかない場合は、「異議申立」をすることができます。
よくわかる動画解説はこちら
ポイント
弁護士基準で慰謝料などを計算して主張していく
前述したように、慰謝料などの計算では3つの基準が使われます。
その中では、弁護士(裁判)基準がもっとも高額になるので、この基準で算定した金額を主張していくことが大切です。
示談交渉は交通事故に強い弁護士に依頼する
なんとか、ご自身で加害者側の任意保険会社と示談交渉を行なおうとする被害者の方がいらっしゃいます。
しかし、ここまでお話ししたように、交通事故の示談交渉では、交通事故と後遺障害の法的知識だけでなく、医学的な知識も必要です。
また、加害者側の保険会社は被害者の方がいくら主張しても、示談金の増額にはなかなか応じることはありません。
ですから、やはり、まずは、
・交通事故に強い弁護士に無料相談してみる。
・そして、説明に納得がいけば正式に示談交渉を依頼する
という流れで、示談交渉は交通事故に強い弁護士に任せてしまうことが、結果的にすべてが上手くいく選択だともいえます。
詳しい内容はは「交通事故示談の流れと弁護士に相談・依頼するメリット・デメリット」でも解説しています。
よくわかる動画解説はこちら
7つの理由
最終的には提訴して裁判での決着も検討する
「裁判までするのは嫌だ」という方がいらっしゃいます。
しかし、知っておいていただきたいのは、裁判をすると得な場合もある、ということです。
つまり、最終的な示談金が増額するのです。
裁判を起こして判決までいった場合、被害者の方には「弁護士費用相当額」と「遅延損害金」が追加で支払われます。
ですから、示談金を増額させたい場合は、裁判も検討することをおすすめします。
こちらの記事もよく読まれています
わかりやすい動画解説はこちら
最新の増額事例はこちらからご覧ください
代表社員 弁護士 谷原誠









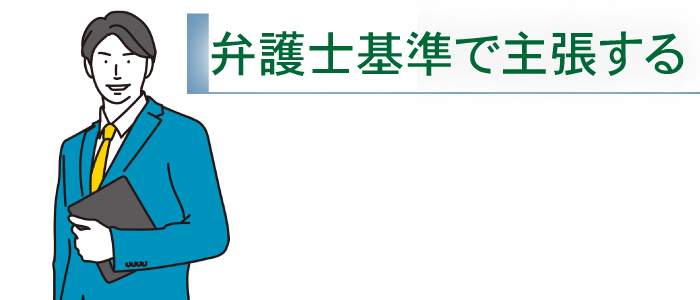





の後遺障害等級.png)


