交通事故で神経障害の後遺症認定のポイント
交通事故で傷害(ケガ)を負った場合、入通院をして完治すればいいのですが、後遺症が残ってしまうと、これからの人生に大きな影響が出てしまいます。
- 日常生活への支障が心配だ
- 仕事に復帰できるのか?
- 収入が減ってしまうのは不安だ
- これからの人生をどう生きていけばいいのか…
被害者の方やご家族の心配や不安は絶えないでしょう。
ところで、後遺症が残った場合、ご自身の後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた慰謝料や逸失利益、治療費などを合計した損害賠償金を受け取ることができます。
被害者の方は、あきらめないでください!
本記事では、神経障害の後遺症の認定ポイントや慰謝料などの損害賠償請求で注意するべきことなどについて詳しくお話ししていきます。
神経系統の障害と後遺症とは?
交通事故で負った傷害(ケガ)による神経系統の障害は、 「中枢神経系統」(脳や脊髄)と身体のさまざまな部位を走っている「末梢神経系統」に大別されます。
主な中枢神経系統の障害
①脳の障害
交通事故で頭部外傷により脳損傷を受けると、次のような後遺症(後遺障害)が現れる場合があります。
「高次脳機能障害」
脳の損傷により、高度なレベルの脳機能を失い、日常生活や仕事などで行なってきたさまざまな思考や行動ができなくなってしまう障害です。
程度の違いによって、次の後遺障害等級が認定されます。
- 1級1号:常時介護が必要となるもの
- 2級1号:随時介護が必要となるもの
- 3級3号:介護は必要ないが終身労務ができないもの
- 5級2号:特に軽易な労務以外はできないもの
- 7級4号:軽易な労務以外はできないもの
- 9級10号:できる労務が相当な程度、制限されるもの
症状の程度などについては次の記事と動画を参考にしてください。
よくわかる動画解説はこちら
慰謝料獲得法
「身体機能の障害」
脳の損傷により身体の各部位に麻痺が起きる障害です。
麻痺には、四肢麻痺、片麻痺、対麻痺、単麻痺があり、その程度によって、次の後遺障害等級が認定されます。
・2級1号:随時介護が必要となるもの
・3級3号:介護は必要ないが終身労務ができないもの
・5級2号:特に軽易な労務以外はできないもの
・7級4号:軽易な労務以外はできないもの
・9級10号:できる労務が相当な程度、制限されるもの
・12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
麻痺の範囲や程度などについては次の記事を参考にしてください。
②脊髄の障害
脊髄を損傷したことで、さまざまな部位に麻痺が起きる障害です。
認定される後遺障害等級や麻痺の範囲や程度などについては、脳の損傷の場合に準じます。
わかりやすい動画解説はこちら
慰謝料獲得法
主な末梢神経系統の障害
末梢神経は中枢神経から身体の各部位に分かれて走っているもので、骨折や脱臼、打撲など交通事故によるケガが原因で、手足の痛みやしびれ、感覚麻痺などの神経症状や、関節可動域制限、筋力低下などの運動機能障害などの後遺症が残る場合があります。
後遺症の程度によって、次の後遺障害等級が認定されます。
- 7級4号:軽易な労務以外はできないもの
- 9級10号:できる労務が相当な程度、制限されるもの
- 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号:局部に神経症状を残すもの
神経障害の原因となる傷害(ケガ)には次のようなものがあります。
・靭帯損傷
・椎間板ヘルニア
・むち打ち など
むち打ち症の後遺障害等級と認定基準
交通事故で多い“むち打ち症”とは?
交通事故でもっとも多いものに、後ろから追突される、いわゆる“もらい事故”があります。
こうした“もらい事故”による後遺症で多いのが、頸椎捻挫(むち打ち症)と腰椎捻挫です。
そして、むち打ち症は損害賠償実務での扱いが非常に難しいものの1つなのです。
むち打ち症では、12級13号か14級9号の後遺障害等級が認定されるのですが、その症状と認定基準を見ると次のようになっています。
<むち打ち症の認定基準>
「12級13号」
後遺障害の内容:局部に頑固な神経症状を残すもの
認定基準:他覚所見により神経系統の障害が証明されるもの
「14級9号」
後遺障害の内容::局部に神経症状を残すもの
認定基準:神経系統の障害が医学的に説明可能なもの
むち打ちの後遺障害等級認定での注意ポイント
①12級で重要な他覚所見とは?
12級と14級の後遺症の違いは、”頑固な”神経症状なのかどうかの違いだけです。
これで、等級が2つも変わり、慰謝料などの損害賠償金額も大きく変わってきます。
後ほど詳しくお話ししますが、12級と14級では慰謝料だけでも180万円もの差が生まれてきます。
また、12級の認定基準にある「他覚所見」というのは、①医師による診察(触診や視診など)、②医学的検査(血液検査や神経伝導検査など)、③画像検査(レントゲンやMRIなど)等により、客観的に捉えることができる症状のことです。
画像所見(MRI画像上の異常状態など)、および神経学的所見(スパーリングテストなどにおける異常所見)が認められ、これらを医学的に証明できると判断されれば、後遺障害等級12級13号が認定されます。
②14級の認定基準は曖昧!?
一方、14級の認定基準は「医学的に説明可能なもの」です。
たとえば、手や足のしびれがある場合、
・その原因が、交通事故のケガによる外傷性のものなのか、年齢の加齢性のものなのか判断できないが、
・神経学的異常所見が認められ、
・神経系統の障害が医学的に説明可能
となれば、14級9号が認定されます。
つまり、「他覚所見により医学的に証明できる」か「医学的に説明可能」かの違いが、
12級と14級の認定基準の違いということになります。
これは、交通事故の実務に詳しい医師でないと、適切な対応が難しいかもしれません。
また、被害者の方にも交通事故の損害賠償実務と医学的な知識がないと大変でしょう。
正しい後遺障害等級認定を受けるためには一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
代表社員 弁護士 谷原誠





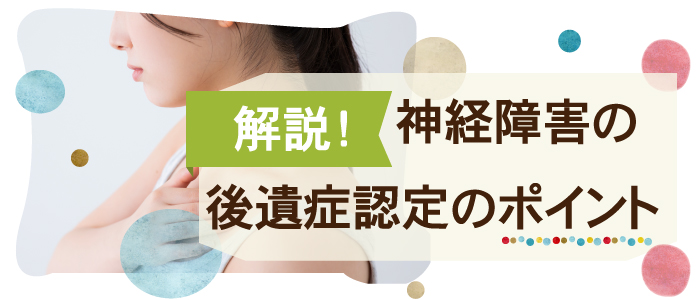
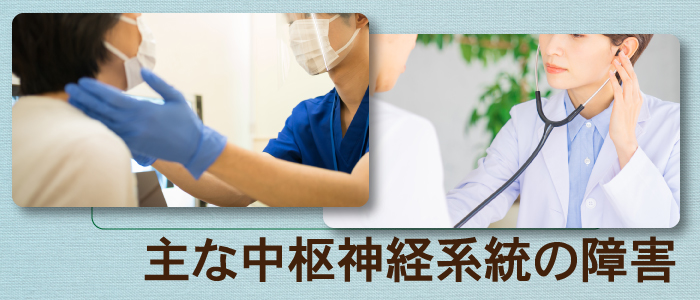






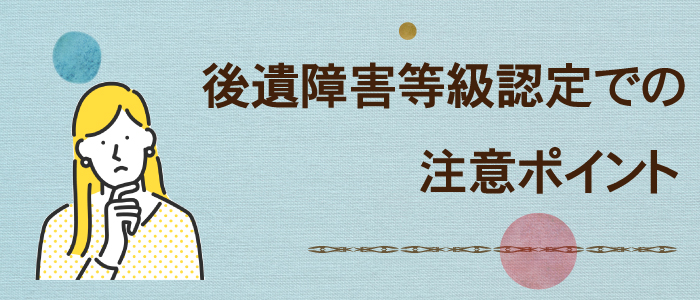
の慰謝料額と増額事例.png)







