交通事故の示談交渉が「もめる原因」と「対処法」
交通事故の被害者の方は慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができます。
加害者が任意保険に加入していれば、まずその保険会社から示談金の提示があります。
その金額で納得がいくなら、示談成立です。
しかし、保険会社の提示額は、じつはかなり低く、被害者の方が本来受け取るべき金額の2分の1や3分の1、さらには10分の1以下という場合があります。
ご自身の正確な慰謝料額まで知らなくても、「この金額は低すぎるのではないか?」、「この金額では納得できない」と感じる被害者の方は、保険会社との示談交渉に進みます。
しかし、この示談交渉が問題で、「もめる」「なかなか進展しない」「和解できずにいつまでも解決できない」といったことが起きがちです。
・なぜ、保険会社は低い示談金を提示してくるのか?
・どうして、示談交渉はもめてしまって、なかなか解決できないのか?
本記事では、保険会社の論理・言い分を分析しながら、示談交渉がもめる原因と対処法について、お話ししていきます。
示談交渉がもめる理由とは?
なぜ示談交渉はもめるのか?
☑被害者の方としては、いつまでも交通事故を引きずらず、早く示談を成立させたいと思うでしょう。
しかし、示談はなかなか成立しないのが現実です。
☑なぜなら、保険会社から提示される示談金は被害者の方が受け取るべき本当の金額より、かなり低く設定されているからです。
☑保険会社は利益を上げることを目的とした営利法人ですから、売上を増やして、支出をできるだけ抑えようとします。
☑一方、被害者の方は突然の交通事故で精神的、肉体的な苦痛、損害を被っていますし、将来的な収入の不安もあるでしょう。
そのため、金銭的な補償はできるだけ多く受取りたいと考えるでしょうし、低い金額を提示されたら納得がいかないのは当然です。
☑つまり、双方の利害はまったく真逆なため、示談交渉がなかなか進まない、示談がまとまらないということが起きてしまうわけです。
保険会社の論理・言い分を分析してみる
では、保険会社はどういった論理で、どのような言い分を主張してくるのか、保険会社の交渉の進め方を分析してみましょう。
①上位権限者のテクニック
加害者側の任意保険会社の担当者が、こんなことを言ってくる場合があります。
「上司から、これ以上の金額の提示は難しいと言われまして・・・」
「社内規定上、この金額が、当社がご提示できる限度額です」
これは交渉術では「上位権限者のテクニック」と呼ばれるものです。
「(担当者である)私は、もっと金額を増やしたいのですが、上司(会社)が増額は難しいと言っているのです。だから、どうしようもないのです」
と言って、相手を納得させようとしているわけです。
②グッドガイ・バッドガイのテクニック
保険会社の担当者が、こんなことを言ってくるケースもあります。
「もう少し増額できるように上司に掛け合ってみます」
そして、少し経ってから、このように言います。
「やはりダメでした……」
初めは被害者の方の味方(グッドガイ)であるかのように振る舞い、あとで「私は、頑張がんばりました。しかし上司(バッドガイ)からダメだと言われました」と言ってくるわけです。
被害者の方としては、「ここまでやってくれたのだから」と示談書にサインをしてしまうこともあると思いますが、ここで示談してしまっては、本来よりかなり低い金額しか受け取ることができない、ということになってしまいます。
③最後の譲歩
「なんとか〇〇円の増額を会社から認めてもらいました」
このように相手が言ってくるのは、最後の譲歩と呼ばれるテクニックです。
交渉について、人は「勝ち・負け」で判断しがちです。
そうすると、「最後に自分が勝った」「自分のほうが有利になった」という状況になると、交渉妥結となりやすい心理が働きやすくなるのです。
保険会社は、最後に少しだけ増額することで、じつは自分たちが有利な結果を得るという交渉テクニックを使ってくる場合もあるのです。
④内心の表れ
「弁護士に依頼しても増額しませんよ」
「弁護士に頼んでも無駄ですよ」
保険会社の担当者が、こうしたこと言ってくる場合もあります。
この場合の心理は、「弁護士に依頼されると困る」という内心の表れだと読み替えることができます。
ですから、弁護士に示談交渉を依頼することが有効な手段になるわけです。
示談交渉がもめる5つの理由とその対処法
次に、保険会社が慰謝料などの損害賠償金の増額を認めない理由と、その対処法についてお話しします。
保険会社が支払い基準の限界を主張してきた場合
慰謝料などの計算では次の3つの基準が使われます。
1.自賠責基準
自賠責保険の基準で、金額がもっとも低くなる。
2.任意保険基準
各任意保険会社が、それぞれ独自に設けている基準(各社非公表)。
自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されている。
3.弁護士(裁判)基準
・金額がもっとも高額になる基準。
・過去の裁判例から導き出されているため、弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合に主張する。
・裁判で認められる可能性が高くなる基準で、被害者の方が本来受け取るべき金額になる。
つまり、慰謝料の増額を実現するには、弁護士に依頼して、弁護士(裁判)基準で計算した慰謝料額で示談解決するべきなのです。
被害者の過失割合を主張してくる場合
交通事故の示談交渉では、過失割合が争点になることも多くあります。
過失割合とは、交通事故の原因となった過失(責任)が、被害者と加害者それぞれにどのくらいの割合であるのかを表すものです。
たとえば、被害者30%対加害者70%というように表されるのですが、被害者の方としては過失割合が高くなれば、その分を損害賠償金から減額されてしまうことに注意が必要です。(これを過失相殺といいます)
過失割合については、交通事故の損害賠償実務に詳しい弁護士でないと、保険のプロである保険会社には太刀打ちできません。
ですから、ここでも弁護士に依頼するのが示談解決への近道になるのです。
被害者の逸失利益を認めない場合
交通事故の被害にあい、後遺障害が残った場合は、以前のように働くことができない可能性があります。
その場合は、今後の収入に直結してくるので、被害者の方にとっては大きな問題です。
このように、交通事故にあっていなければ将来的に得られるはずだった収入(利益)を逸失利益といいます。
加害者側の任意保険会社は、示談交渉で被害者の方の逸失利益を低く見積もったり、否定してくる場合があります。
こうした場合でも、交通事故に強い弁護士に依頼することで逸失利益が増額し、示談が解決する可能性が高くなります。
加害者が無保険の場合
自賠責保険は、すべての運転者が加入しなければならない強制保険です。
それにもかかわらず、加害者が加入していない、期限が切れていた、というケースがあります。
また、加害者が任意保険に加入していないケースもあります。
こうしたケースでは、交渉相手が保険会社ではなく加害者本人になるため、示談交渉がなかなか進まない、もめる場合が多くあります。
加害者が自賠責保険に加入していない場合は、「政府補償事業」という制度があります。
また、加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者ご自身やご家族が任意保険の「人身傷害補償特約」や「搭乗者傷害保険」に加入しているなら、そこから保険金を受け取ることができます。
いずれの場合でも、まずは弁護士に相談していただきたいと思います。
被害者が単独で示談交渉をしている場合
保険会社は、被害者の方が単独で示談交渉に臨んでいるうちは増額しなくてもいいと考えています。
わざわざ正確に求められていないのに弁護士(裁判)基準での金額を提示する必要はない、と考えているのでしょう。
しかし、示談交渉に弁護士が入っ
てくると、最終的には提訴されて、裁判での決着となれば、裁判所から弁護士(裁判)基準での金額を求められてしまうので、その前に和解しようという判断をしてくるわけです。
ですから、被害者の方が単独での示談交渉は避けるべきだといえます。
以上、交通事故の示談交渉がもめる理由と対処法について解説しました。
代表社員 弁護士 谷原誠





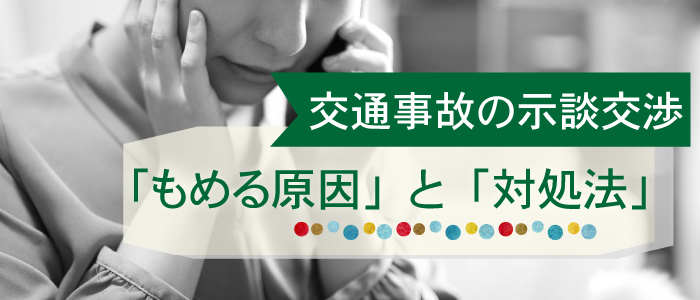










の後遺障害等級.png)


