交通事故被害者の裁判のメリットとデメリット
*タップすると解説を見ることができます。
交通事故の被害者が裁判をすることのメリットは、以下です。
| メリット1 | 賠償額が増額する |
|---|---|
| メリット2 | 相手に弁護士費用を請求できる |
| メリット3 | 遅延損害金を請求できる |
| メリット4 | 慰謝料が相場金額より増額する |
| メリット5 | 支払い拒否でも強制的に回収できる |
交通事故の被害者が裁判をするデメリットは、以下です。
| デメリット1 | 判決までに時間がかかる |
|---|---|
| デメリット2 | 裁判所に出廷する必要がある |
| デメリット3 | 訴訟費用がかかる |
| デメリット4 | 被害者が自分で行うのは難しい |
被害者の中には、「裁判は気が引ける」「裁判のような大ごとにしたくない」という方もいらっしゃいます。
しかし、示談交渉がまとまらない以上、裁判をしなければ賠償金を受け取ることができません。
また、譲歩して示談してしまっては、金銭的な損害を被ってしまいます。
そこで、本記事では、交通事故の被害者が裁判をするメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
交通事故の裁判のメリットとデメリット
ここでは、裁判を起した場合のメリットとデメリットについて解説していきます。
裁判のメリット
メリット1.賠償金が増額する
1つ目のメリットは、裁判になった場合は賠償金が増額する可能性が高くなることです。
なぜかというと、弁護士(裁判)基準による適正な金額に増額するからです。
交通事故の損害賠償金の計算には次の3つの基準が使われます。
「自賠責基準」
自賠責保険による基準で、もっとも金額が低くなります。
「任意保険基準」
各任意保険会社が独自に設けている基準で、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されています。
「弁護士(裁判)基準」
・過去の膨大な裁判例から導き出されている基準で、金額がもっとも高額になります。
・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合にも主張する計算基準です。
・この基準で算定した金額が、被害者の方が受け取るべき正しいものになります。
交通事故の示談交渉では、保険会社は、任意保険基準で示談金を提示してくることが多いです。
そこで、適正な計算基準である弁護士基準になるように交渉しますが、示談は、双方が合意しなければ成立しません。
つまり、保険会社が弁護士基準による計算により賠償金を計算することに合意しなければ示談は成立しない、ということになります。
しかし、裁判では、裁判所は、弁護士(裁判)基準により計算するので、示談で保険会社が譲歩しない場合には、裁判を起こすことにより損害賠償金が増額するのです。
メリット2.相手に弁護士費用を請求できる
2つ目のメリットは、相手に被害者が負担すべき弁護士費用の一部を請求できることです。
交通事故で弁護士に依頼すると示談金が増額することが多いのですが、心配なのは弁護士費用です。
この弁護士費用は、原則として、被害者が負担する必要があります。
また、加害者の保険会社が示談交渉で、被害者の弁護士費用を負担してくれることはありません。(被害者が自分がかけている弁護士費用特約は使えます)
しかし、裁判を起こし、判決までいくと、そこで認められた損害賠償金に約10%の「弁護士費用相当額」が上乗せされます。
例えば、裁判所が被害者の損害を1,000万円と見積もった場合、判決では、「1,100万円を支払え」と命じてくれる、ということです。
考え方によっては、裁判をすることで、弁護士費用を加害者側に支払ってもらうことができるわけです。
メリット3.遅延損害金を請求できる
3つ目のメリットは、相手に遅延損害金を請求できることです。
裁判で判決までいくと、損害賠償金に遅延損害金が追加されます。
これは、裁判を行なって時間がかかったため、損害賠償支払債務が遅滞に陥ったとして、利息のようなものをつけてくれる、と考えるといいでしょう。
遅延損害金は年3%の割合で計算し、3年毎に率が見直されることとなっています。
例えば、損害額が1,000万円だとすると、1年後には、30万円の遅延損害金がついて、1,030万円になっている、ということです。
メリット4.慰謝料が相場金額より増額する
4つ目のメリットは、裁判を起こすことによって、事情によっては、慰謝料が相場の金額よりも増額する、とういうことです。
慰謝料には、一応の相場金額があります。
たとえば、死亡事故に関しては、被害者が家庭内でどのような立場かによって、以下のような慰謝料の相場があります。
| 被害者の状況 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2,800万円 |
| 母親、配偶者 | 2,500万円 |
| 独身の男女、子供、幼児等 | 2,000万円~2,500万円 |
保険会社は、示談交渉では、慰謝料をこの相場より低く主張してくることが多く、また、この相場より増額してくれることは、まずありません。
しかし、裁判所は、裁判になった場合には、一定の特殊事情がある場合には、相場金額よりも増額した慰謝料を認定してくれることがあります。
たとえば、次のような理由・事情がある場合、慰謝料が増額する可能性があります。
・著しいスピード違反
・飲酒運転
・薬物使用
・無免許運転
・信号無視
・センターラインオーバー
・ひき逃げ(救護義務違反)
・ながら運転 など
2.被害者に特別な事情がある場合
・交通事故の被害により胎児にも影響があり、人工中絶を余儀なくされた。
・腕・指の運動機能に麻痺の後遺症が残り、音楽家になる夢が絶たれた。
・肢体障害を持つ家族がいるが自分が後遺障害を負ったことで、介護などができなくなった。
・交通事故で負った後遺障害が原因で婚約破棄や離婚に至った。
・被害者がまだ幼すぎる。
・遺族が精神疾患を患った。 など
3.加害者の態度が悪質
・被害者や遺族への謝罪がない。
・被害者や遺族に対して悪態をつく。
・警察に虚偽の供述をした。 など
慰謝料が相場より増額するならば、裁判にするメリットは十分になると思います。
但し、慰謝料が増額するかどうかは難しい判断ですので、交通事故に精通した弁護士に相談するようにしましょう。
メリット5.支払い拒否でも強制的に回収できる
5つ目のメリットは、加害者や保険会社が支払いを拒否しても、強制的に回収できることです。
保険会社と示談交渉をする場合、保険会社が譲歩しなければいつまでも示談が成立しません。
示談が成立しないと、賠償金を支払ってもらうこともできません。
しかし、裁判を起こし、和解が成立し、または判決が確定した場合、賠償金を強制的に回収することができます。
裁判で被告とした加害者や保険会社が賠償金を支払わない場合、法的手続である強制執行をすることができます。
強制執行というのは、例えば、保険会社の預金や不動産などを差し押さえ、お金に換えて回収することです。
この強力な力が裁判のメリットの一つです。
裁判のデメリット
デメリット1.判決までに時間がかかる
裁判をする1つ目のデメリットは、判決までに時間がかかることです。
示談交渉がスムーズに進むと、数ヶ月で示談が成立し、2週間~1ヶ月程度で示談金が振り込まれます。
しかし、裁判は、個別の事案ごとに行なわれるため、判決が出るまでに決まった期間というものはありません。
ケースバイケースですが、提訴してから判決が出るまで、およそ半年から1年かかるケースが多いといえます。
ケガや後遺障害の程度、争点の内容などによって1年以上かかってしまうケースもあることはデメリットだといえるでしょう。
裁判の前に、数カ月間は示談交渉をするのが通常なので、そこに裁判の期間が余分にかかる、ということです。
但し、先ほどメリットで挙げたように、判決には遅延損害金がつきますので、事故から長引けば長引くほど遅延損害金の額は高額となります。
そこで、長くかかる期間については、資産形成をしていると頭を切り替えて裁判に臨む、ということも考えてもいいかもしれません。
デメリット2.裁判所に出廷する必要がある
2つ目のデメリットは、被害者が裁判所に出廷しなければならない可能性があることです。
通常の手続は弁護士が代わりに裁判所に出廷するので、被害者の方は一度も裁判所に行かずに裁判が終わることも多くあります。
しかし、過失割合が争点となっており、裁判所に提出した実況見分調書などの証拠だけでは過失割合の判断ができない場合には、被害者が直接事故状況を裁判所で証言する必要が出てくる場合があります。
ただ、裁判所で証言するのは、被害者の賠償金を増額させるためですので、そこは頑張っていただきたいと思います。
デメリット3.訴訟費用がかかる
3つ目のデメリットは、訴訟費用がかかることです。
訴訟費用というのは、裁判を起こす時に、裁判所に収めなければならない印紙や郵便切手などの実費のことです。
印紙代の目安としては、以下の程度の金額です。
| 訴訟提起の印紙代の目安 | |
|---|---|
| 訴訟提起の金額 | 印紙代 |
| 1,000万円 | 6万円程度 |
| 3,000万円 | 12万円程度 |
| 5,000万円 | 18万円程度 |
| 1億円 | 33万円程度 |
裁判を起こす時には、この訴訟費用の負担も含めて弁護士が見通しを判断してくれますし、どうしてもお金がなければ自賠責保険に先に被害者請求をして、お金を確保してから裁判を起こせばよいと思います。
また、弁護士費用特約がある場合は、そこからも支払われる可能性があります。
デメリット4.被害者が自分で行うのは難しい
4つ目のデメリットは、被害者が自分で裁判を起こすのは難しい、ということです。
法律では、裁判は弁護士に依頼する必要はなく、自分で起こすことができます。
しかし、現実問題としては、訴状の書き方、証拠の出し方などの手続面や戦略面で困難があります。
また、交通事故の裁判で必要となる知識は、損害賠償法、民事訴訟法、裁判例、自賠責後遺障害等級認定システム、医学、保険など様々な知識が必要となります。
実際には被害者が自分で裁判を起こすことはおすすめしませんし、結果としても、良い結果とはならないでしょう。
但し、弁護士に依頼すると費用倒れになるような少額の場合には、自分で裁判を起こしても、それほど損になることはないので、チャレンジしてみてもよいでしょう。
裁判をしたほうがいいケース
次に、交通事故の被害者が裁判をした方がいいケースを解説します。
ケース1.賠償金額が大きい場合
損害賠償金が大きいケースでは、示談よりも裁判によって加害者側に支払い命令を出してもらうほうが金額が高額になることが多いので、裁判をするメリットがあります。
特に1億円を超えるような事例では、被害者側と保険会社側の主張金額が大きくかけ離れることが多いです。
たとえば、みらい総合法律事務所が経験した実際のケースは、以下のようなものです。
自賠責後遺障害等級は、1級1号が認定されました。
保険会社は、示談金として、被害者に対し、8,985万7,547円を提示しました。
被害者は、みらい総合法律事務所に依頼し、裁判を起こしました。
最終的には、2億3,900円で解決しました。
裁判をしたことで、約1億4,000万円も増額したことになります。
ケース2.被害者側の主張に法的な根拠・証拠がある場合
示談交渉では、加害者側が法的な根拠のない主張をしてくるケースがあります。
たとえば、法的な根拠もなしに逸失利益を認めない場合や、不当に被害者の方が高い過失割合を主張してくるようなケースです。
このようなケースでは、被害者側の主張に法的な根拠や証拠があれば裁判で認められやすいので、裁判をする方がいいでしょう。
ケース3.保険会社の算定基準が低い場合
前述したように、加害者側の任意保険会社からの提示額が自賠責基準や任意保険基準で計算されていて低い場合は、弁護士(裁判)基準で算定した金額を裁判で主張することで、認定される可能性が高くなります。
しかし、保険会社がいつまでも譲歩せず、示談交渉がまとまらない場合があります。
このようなケースでは、裁判をする方がいいでしょう。
裁判をしない方がいいケース
反対に、裁判をしない方がいいケースを解説します。
ケース1.被害者側の根拠・証拠が乏しい場合
被害者の方に裁判で争うだけの根拠・証拠が乏しいケースでは、裁判を行なっても主張が認められない場合が考えられるため、注意が必要です。
むしろ、示談交渉時の示談金額より裁判をした金額の方が低額になってしまうケースもあります。
したがって、そのような場合には、交通事故に精通した弁護士に相談しながら、裁判をするかどうか、考えるのがいいでしょう。
ケース2.加害者に支払い能力がない場合
加害者が任意保険に加入していないケースでは損害賠償能力がない場合も考えられます。
このような場合では、裁判を行なっても損害賠償金を回収できない可能性が高くなります。
ただし、被害者の方が弁護士費用特約に加入しているなら、弁護士費用は保険からまかなえるので、裁判を行なってもいいでしょう。
一定以上の多額の損害が発生している場合は、裁判をしたほうがメリットがある場合もあるので、弁護士に相談してみることをおすすめします。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠





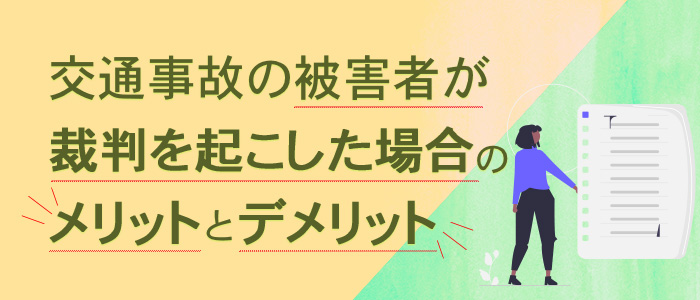
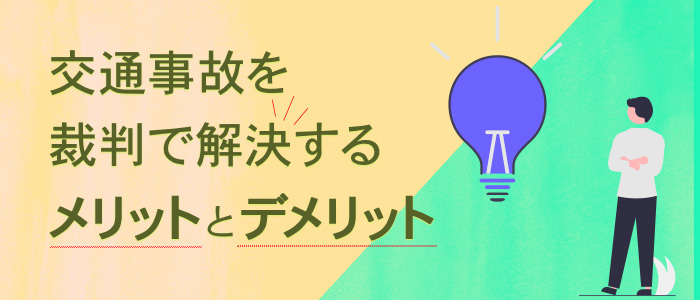





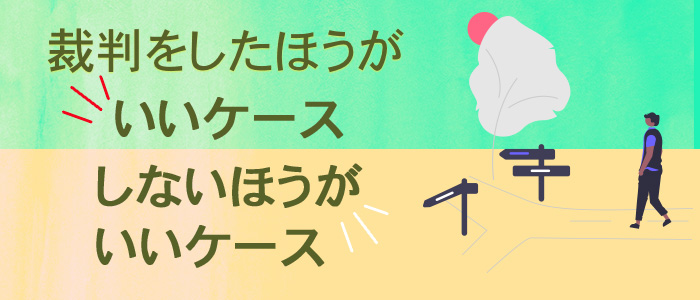







の後遺障害等級.png)

