交通死亡事故でご家族が亡くなった場合の支援制度
交通事故では刑事事件と民事事件が並行して進んでいきます。
ご遺族としては、いずれも初めてという方がほとんどでしょうから、どのように対応すればいいのかわからないと思います。
また、一家の支柱の方が亡くなった場合は、今後のご遺族の経済的な不安も大きいと思います。
そこで本記事では、ご家族が亡くなった場合の精神的、経済的なさまざまな支援制度について解説します。
目次
刑事事件と民事事件について
加害者が交通事故を起こした場合、3つの責任が発生します。
①刑事上の責任
加害者が交通事故を起こしたことにより、罪を犯したとして刑事罰に処されることです。
刑事罰には次のようなものがあります。
- ・道路交通法違反(信号無視、スピード違反、無免許運転などの違反をした場合)
- ・過失運転致死傷罪(交通事故で他人にケガを負わせた場合、あるいは死亡させた場合)
- ・危険運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪の中でも特に悪質な交通事故の場合) など
参考情報:刑事事件(最高裁判所)
②民事上の責任
被害者に対する加害者からの損害賠償の責任のことです。
自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)、民法に基づく不法行為責任(民法709条)、使用者責任(民法715条)などにより責任が発生します。
通常、加害者が任意保険に加入している場合は、この任意保険会社と被害者の間で示談交渉が行なわれ、慰謝料などの損害賠償金額を決定します。
合意に至らない場合は、民事裁判に進みます。
③行政上の責任
加害者が免許の停止や取消しの処分を受けることです。
詳しくはこちらの記事もご参照ください。
刑事手続きの流れと注意ポイント
刑事手続きの流れと概要
☑交通事故が発生し、警察に通報すると、警察官が現場に急行して捜査を開始します。
☑証拠を収集して事実を明らかにするために、現場検証(実況見分)を行ない「実況見分調書」を作成し、被害者と加害者双方に聞き取り調査を行ない「供述調書」を作成します。
☑警察は必要な場合には被疑者(加害者)を逮捕して、事件として検察に送致します。
☑事件の送致を受けた検察官は、さらに捜査を行ない、事件を起訴するか、不起訴にするかを決定します。
※起訴=裁判にかけること/不起訴=裁判にかけないこと
☑起訴には次の2種類があります。
・略式命令請求/裁判が開かれず書類審査で刑罰(罰金など)が言い渡されるもの
ご遺族が刑事事件に関わる際の注意ポイント
ご遺族には、警察官や検察官による事情聴取が行われる場合もあります。
被害者の方の生前の状況やご遺族の気持ちなどは素直に話して、事情聴取に協力をしてください。
なお、刑事裁判に被害者の方やご遺族が参加できる「被害者参加制度」というものがあります。
裁判では、被害にあったときの状況や被告人に対する気持ちなどを証言することができるので、希望される場合は一度、交通事故に強い弁護士に相談してください。
こちらの関連記事もご覧ください。
刑事手続きに関する被害者の
支援制度について
警察、検察、民間団体などが行なっている被害者支援には次のようなものがあります。
※「交通事故にあったときには」(国土交通省)より抜粋。
警察が行なっている被害者支援
警察では次のような交通事故の被害者の方への支援を行なっています。
「被害者への情報提供」
・刑事手続の概要
・被害者等が利用できる制度
・捜査の状況
・自動車損害賠償責任保険等の自動車保険制度
・各種相談機関、窓口 など
「相談・カウンセリング体制の整備」
・警察本部や最寄りの警察署交通課における相談窓口の設置
・精神的被害を軽減するためのカウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置
・精神科医や民間のカウンセラーとの連携 など
「捜査過程における被害者等の負担軽減」
・被害者用事情聴取室、被害者支援用車両の整備
・実況見分や病院への付添い、各種相談の受理 など
「被害者等の安全の確保」
・同じ加害者から再び危害を加えられること等の防止 など
※支援内容の詳しい情報については、警察庁のホームページを参照してください(「警察庁 犯罪被害者支援」で検索)。
※なお、詳しいことは交通事故を取り扱った警察署へ相談してください。
検察庁などが行なっている被害者支援
「被害者支援員制度」
・被害者やご家族等からの相談対応
・法廷への案内等、付添い
・事件記録の閲覧
・証拠品の返還等の各種手続の手助け
・関係機関等の紹介 など
「被害者等通知制度」
・被害者やご家族等に対する事件の処分結果、刑事裁判の結果、犯人の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所時期等に関する情報提供 など
「公判段階における制度」
・被害者参加
・心情等の意見陳述
・被害者等の優先的な傍聴
・公判記録の閲覧、謄写
・刑事和解
・損害賠償命令 など
「事件記録の閲覧制度」
起訴され、確定した刑事訴訟記録、不起訴記録の閲覧 など
「その他の制度」
・加害者の仮釈放等審理における意見等聴取制度
・加害者の保護観察中における被害者の心情等伝達制度
※支援内容の詳しい情報については、法務省のホームページを参照してください(「法務省 犯罪被害者の方々へ」で検索)。
「犯罪被害者の方々へ」(法務省)
※詳しいことは、事件担当検察官、または事件を扱った検察庁や最寄りの検察庁の「被害者ホットライン」に相談してください(「法務省 被害者ホットライン」で検索)。
民間支援団体が行なっている
被害者支援
警察などの関係機関との連携を図りながら、認定特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワークに加盟している各都道府県の民間被害者支援団体(センター)が次のような活動を行なっています。
- ・電話相談、面接相談
- ・病院や警察、裁判所等への付添い
- ・日常生活の支援
- ・自助グループ(被害者遺族の会等)への支援 など
※加盟センターに関する詳しい情報については、認定特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワークのホームページ(メニュー:全国の支援センター)を参照してください(「全国被害者支援ネットワーク」で検索)。
※全国被害者支援ネットワークのホームページから、お住まいの都道府県の加盟民間被害者支援団体(センター)を知ることができます。
ご家族が亡くなった場合の支援制度について
交通事故でご家族が亡くなった場合の、ご遺族への支援制度には次のようなものがあります。
※「交通事故にあったときには」(国土交通省)より抜粋。
経済的な支援
交通事故によって一家の大黒柱を亡くされ、経済的な困難に直面している場合は、次のような遺族・遺児を支援する制度があります。
①「遺族年金((独)日本年金機構)」
- ・公的年金納付者が対象になります。
- ・亡くなった方が加入していた年金(国民年金・厚生年金)によって制度が異なります。
遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18 歳到達年度の末日までにある子(障害者は20 歳未満)のいる配偶者」または「子」に支給されます。
「厚生年金(遺族厚生年金)」
遺族厚生年金は、厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1. 配偶者または子、2. 父母、3. 孫、4. 祖父母の中で優先順位の高い方)に支給されます。
なお、子のある妻または子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。
※受給要件、支給額等の詳しい情報については、(独)日本年金機構のホームページ(年金の制度・手続き)を参照してください(「年金機構 遺族年金」で検索)。
年金の制度・手続き(日本年金機構)
※詳しいことは、「年金ダイヤル」または、お近くの「年金事務所」、「街角の年金相談センター」 に相談してください。
なお、国民年金については、お住まいの市区町村でも相談できます。
●年金ダイヤル/0570-05-1165
祝日、年末年始を除く 8:30~17:15
(月曜日は19:00 まで、第2土曜日は9:30~16:00)
●年金事務所・街角の年金相談センター
年金事務所などの所在地や連絡先は、日本年金機構のホームページ を参照してください(「年金事務所 所在地一覧」で検索)。
全国の相談・手続き窓口(日本年金機構)
②「労災年金(労働基準監督署)」
- ・業務中または通勤途中の事故が対象になります。
- ・業務中または通勤途中の交通事故によって亡くなった場合は、遺族補償給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)がご遺族に支給されます。
- ・また、葬祭を行なったご遺族などに対して、葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。
- ・遺族(補償)年金の受給資格者は、被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹になります。
ただし、妻以外の遺族については条件があることに注意が必要です。 - ・なお、労災年金は国民年金(遺族基礎年金)や厚生年金(遺族厚生年金)と併給できますが、その場合は労災年金が減額されて支給されます。
※詳しいことは、「労災保険相談ダイヤル」または、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署に相談してください。
●労災保険相談ダイヤル/0570-006031
土日祝日・年末年始を除く 9:00~17:00
●労働基準監督署
勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地・連絡先は、厚生労働省のホームページを参照してください(「労働基準監督署 所在地一覧」で検索)。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧(厚生労働省)
③「生活福祉資金貸付制度
(各市区町村の社会福祉協議会)」
- ・交通事故の被害者ご遺族だけでなく、低所得者や障害者手帳をお持ちの世帯が対象になります。
- ・生活に必要な資金を他から借り受けることが困難な低所得世帯や障害者手帳の交付を受けた方が属する世帯に対して、「必要な資金の貸付け」と「社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援」をセットで行なう制度です。
- ・ご遺族などの生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的としています。
※詳しいことは、お住まいの地域の社会福祉協議会に相談してください。
●お住まいの地域の社会福祉協議会の所在地や連絡先
「〇○○社会福祉協議会」で検索してください。(〇○○には、お住まいの市区町村名を入力)。
●お住まいの市区町村の社会福祉協議会のホームページがない場合
全国社会福祉協議会のホームページ(「都道府県社協 一覧」で検索)から、各都道府県社会福祉協議会の連絡先を確認し、各市区町村社会福祉協議会の所在地や連絡先を問い合わせてください。
④母子・父子福祉資金貸付制度
(各地方公共団体)
- ・ひとり親家庭や父母のいない児童が対象になります。
- ・ひとり親家庭の親などが、就労や児童の就学などで資金が必要になった場合に、都道府県、指定都市、または中核市から資金の貸付けを受けられる制度です。
- ・ひとり親家庭の親の経済的自立の支援、生活意欲の促進、扶養している児童の福祉の増進を目的としています。
- ・無利子貸付制度ですが、連帯保証人がいない場合は有利子貸付になります。
※詳しいことは、お住まいの地域の市区町村の子育て担当部署に相談してください。
被害者の子を対象とした
貸付制度
①交通遺児等貸付制度
((独)自動車事故対策機構(NASVA))
- ・被害者の子を対象とした貸付制度です。
- ・自動車事故で保護者が死亡、または重度の後遺障害が残ってしまったご家族(生活困窮家庭)の中学校卒業までの子供が対象になります。
- ・NASVAから生活資金の貸付を無利子で受けることができます。
- ・貸付金額(子供一人につき)は次のとおりです。
最初に一時金として 155,000 円/決定月以後の月額 10,000 円、または 20,000 円(選択制) - ・なお希望があれば、小学校と中学校入学時に入学支度金として、それぞれ44,000円の貸付けを受けることができます。
※貸付の対象者、申込方法などの情報については、NASVA(「ナスバ 交通遺児等貸付」で検索)のホームページを参照してください。
交通遺児等貸付のご案内(NASVA)
②奨学金貸与制度
((公財)交通遺児育英会)
- ・被害者の子を対象とした奨学金の貸付制度です。
- ・保護者などが道路における交通事故で死亡、または重度の後遺障害のために働けなくなった家庭の高校生以上の学生が対象になります。
- ・奨学金を貸与(大学等は一部給付制度あり)して修学支援を行ない、将来、社会的に有用な人材を育成することを目的とした事業を行なっています。
※奨学金の種類、貸与・給付額等の詳しい情報は、(公財)交通遺児育英会のホームページを参照してください。
(公財)交通遺児育英会
※詳しいことは、交通遺児育英会に相談してください。
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-1 平河町ビル3階
0120-521-286
③奨学金貸与制度((独)日本学生支援機構)
- ・交通事故被害に限らず、経済的理由により修学が困難である優れた短期大学・大学・大学院等の学生を対象に奨学金の貸与を行なっています。
※奨学金の採用方法・種類などの詳しい情報については、(独)日本学生支援機構のホームページを参照してください。
※詳しいことは、在学中の大学等に相談してください。
被害者の子を対象とした
年金制度
交通遺児育成基金制度((公財)交通遺児等育成基金)
- ・自動車事故で亡くなった方の残された子供(満16歳未満)が対象になります。
- ・損害保険会社(組合)などから支払われる損害賠償金等の中から、拠出金を(公財)交通遺児等育成基金に払い込んで基金に加入します。
- ・拠出金に国や民間からの援助金を加えたものを安全・確実に運用し、子供が満19歳に達するまで育成給付金の支給を受けることができます。
※加入条件、申込方法などの詳しい情報については、(公財)交通遺児等育成基金ホームページを参照してください。
(公財)交通遺児等育成基金ホームページ
※詳しいことは、(公財)交通遺児等育成基金に相談してください。
〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-5 海事センタービル 7 階
0120-16-3611
被害者の子を対象とした
給付制度
①生活資金等の支給((公財)交通遺児等育成基金)
- ・自動車事故で死亡、または重度の後遺障害が残ってしまった被害者の子供(中学校卒業まで)が対象になります。
- ・特に生計困窮度の高い家庭は、越年資金、入学支度金、就職支度金などの支給を受けることができます。
※支給要件、申込方法などの詳しい情報については、(公財)交通遺児等育成基金のホームページを参照してください。
(公財)交通遺児等育成基金ホームページ
※詳しいことは、(公財)交通遺児等育成基金に相談してください。
〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-5 海事センタービル 7階
0120-16-3611
②交通遺児修学資金支援事業
((一財)道路厚生会)
- ・東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社が管理する道路での交通事故で亡くなった方の子供で、経済的な理由から修学困難な高校生などが対象です。
- ・返済の必要のない修学資金の給付を行なっており、この給付を受けて高等学校などを卒業した子供には、卒業祝金も給付しています。
- ・修学資金は、他の団体などから奨学金や一時金の貸付・給付を受けている場合でも、給付されます。
※給付対象者や給付額などの詳しい情報は、(一財)道路厚生会のホームページを参照してください。
(一財)道路厚生会のホームページ
※詳しいことは、(一財)道路厚生会に相談してください。
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-12 紀尾井町ビル
03-3288-8393
精神的な支援
①交通遺児等友の会
((独)自動車事故対策機構(NASVA))
- ・自動車事故で死亡、または重度の後遺障害が残ってしまった被害者の子供(中学生まで)が対象になります。
- ・交通遺児とその家族が会員(会費無料/会員約2,000名)である「交通遺児等友の会」が設置されており、会員相互の連帯感を高め、交通遺児の健全な育成のための活動を行なっています。
【主な活動内容】
・会報「友の会だより」(四季報)の発行
全国から届けられる会員の近況報告や友の会の集いの様子などを掲載。
子供たちや家族の交流の場が提供されている。
・絵画・書道等のコンテストの開催
作品の創造をとおして、子供たちの感性を豊かにし、作品が完成した時の達成感を味わうことで子供たちのやる気を促進する機会が設けられている。
・自然とのふれあいや体験学習など友の会の集いの実施
全国50か所で、自然とのふれあいやもの作り体験(陶芸・そば打ちなど)など地域ごとに工夫を凝らした集いを開催。
家族と子供たち、家族同士の楽しい思い出づくりの機会が設けられている。
※入会資格、入会方法などの情報については、NASVAホームページを参照してください(「ナスバ 友の会」で検索)。
独立行政法人自動車事故対策機構交通遺児友の会のご案内(NASVA)
※詳しいことは、お住まいの地域のNASVA支所に相談してください。
②交通事故被害者サポート事業
(警察庁)
- ・警察庁が、被害者支援の現場の声や実情を踏まえて、支援担当者や自助グループへの支援のマニュアル、交通事故被害者に向けたパンフレットなどを作成しています。
- ・これらの資料は、交通事故被害者の方々などが抱える問題の理解や解決のために活用できるものです。
※詳しいことは、警察庁のホームページ(「警察庁 交通事故被害者サポート事業」で検索)を参照してください。
交通事故被害者サポート事業
交通事故の慰謝料などの示談交渉は弁護士にご相談ください
死亡事故で受け取ることができる損害賠償項目とは?
交通事故の被害者の方は慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができます。
そして、損害賠償金には治療費や介護費、休業損害や逸失利益、慰謝料などさまざまな項目が含まれます。
ただし、死亡事故の場合は請求できる項目に違いがあることに注意が必要です。
死亡事故で受け取ることができる主な損害賠償項目は次のものになります。
- ①葬儀関係費
- ②死亡慰謝料
- ③死亡逸失利益
- ④弁護士費用
※入院して治療を受けた後に亡くなった場合は、治療費や入通院慰謝料なども受け取ることができます。
死亡慰謝料などは誰が受け取ることが
できるのか?
死亡事故の場合、被害者の方は亡くなっているため、受取人はご遺族になります。
ただし、ご遺族のどなたでも受け取ることができるわけではありません。
法的な相続人には順位と分配割合が決められています。
なぜ保険会社の提示額は
低すぎるのか?
加害者が任意保険に加入しているなら、その保険会社から慰謝料などの損害賠償金額の提示があります。
ただし、ここで注意が必要なのは、保険会社の提示額は、本来被害者の方(ご遺族)が受け取ることができる金額よりかなり低いことが多いという現実です。
保険会社が株式会社の場合、その運営の目的は利益の追求です。
そのため、会社の支出となる被害者の方への損害賠償金をできるだけ低く算定して、提示してくるのです。
そしてさらに問題なのは、被害者の方やご遺族が示談交渉をしても、増額要求を保険会社が受け入れることは少ないという事実です。
では、ご遺族はどうすればいいのでしょうか?
交通死亡事故に強い弁護士に
相談してください!
- ・死亡事故の示談交渉がなかなか進まない
- ・慰謝料などの増額が実現しない
このような場合、まずは交通事故に強い弁護士に相談してください。
依頼を受けた弁護士は、ご遺族の代理人として保険会社との交渉を行なうので、
シビアな金額交渉からご遺族は解放されます。
また、弁護士が示談交渉に入ることで、慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性がかなり高くなります。
また、交通事故に精通した弁護士であれば、増額理由を丁寧に主張・立証していくことができますし、交渉が決裂したなら訴訟を提起して裁判での決着を図ることができます。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
・あなたの慰謝料が少ない5つの理由。弁護士解説
・残念ながら、被害者が交渉しても慰謝料が増額しない理由
・裁判で得する人、損する人の違いとは?
代表社員 弁護士 谷原誠










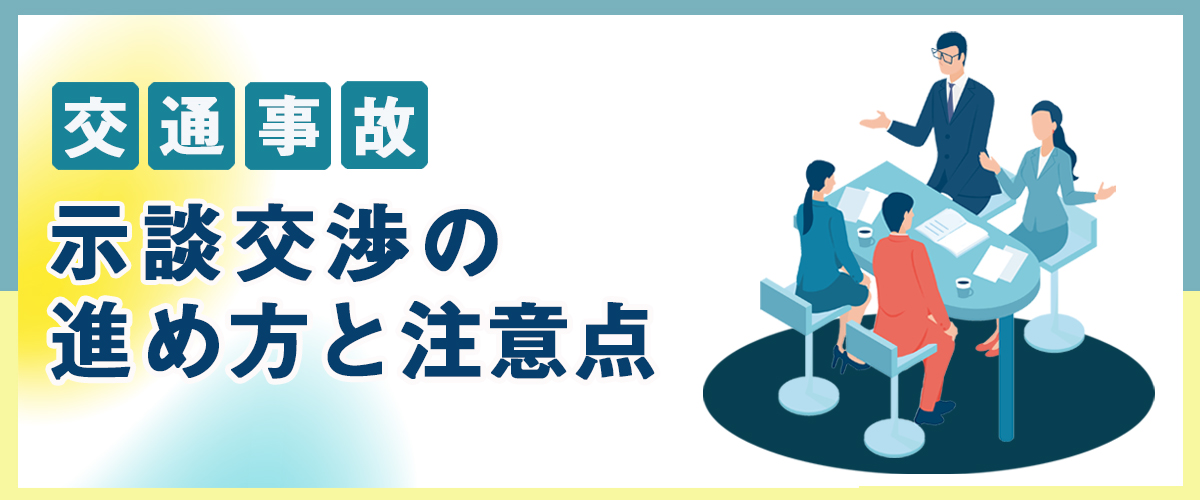







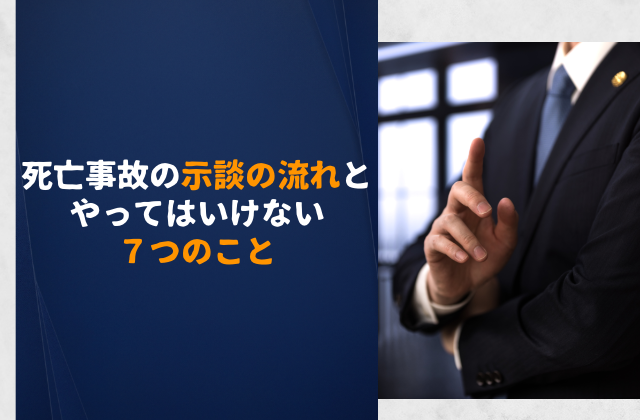
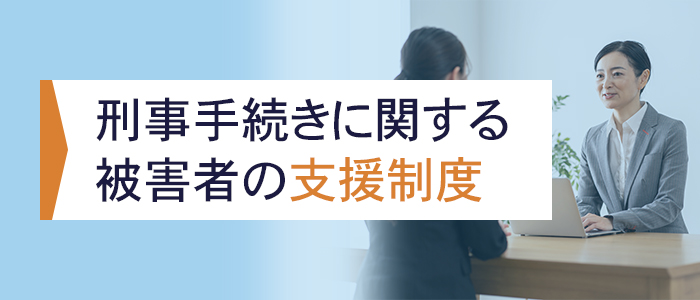


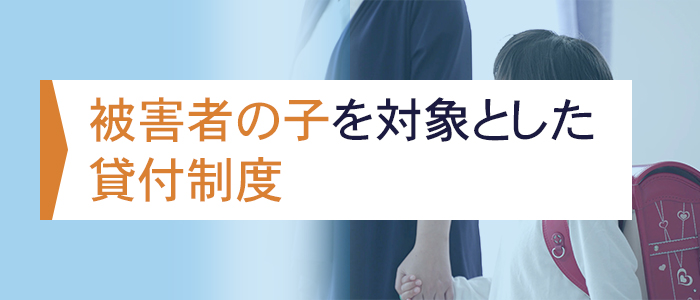


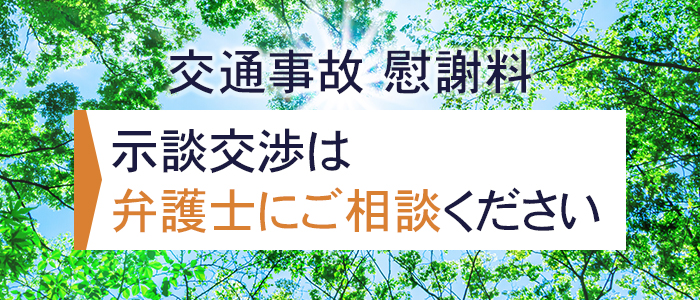





の後遺障害等級.png)

