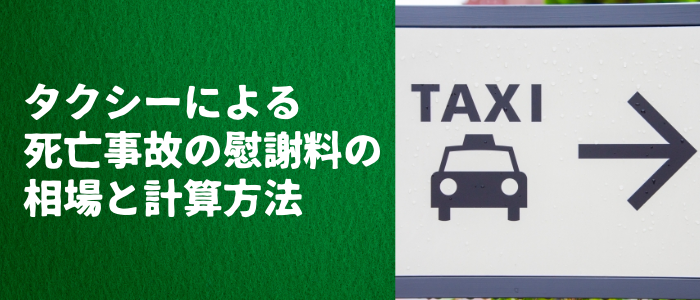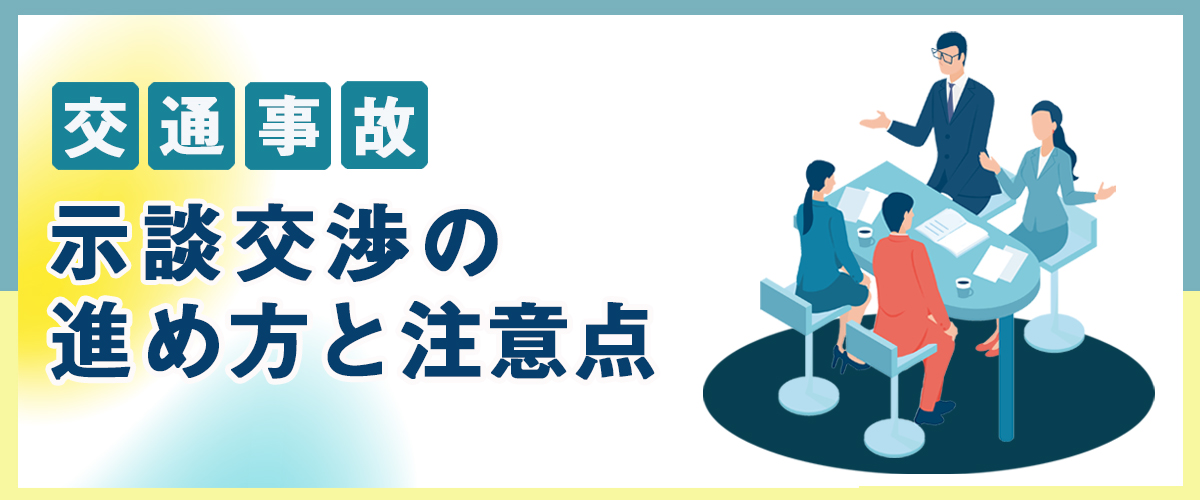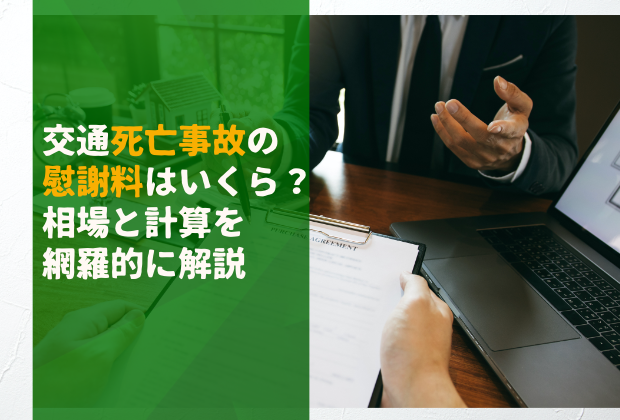タクシーによる死亡事故の慰謝料の相場と計算方法
この記事では、タクシーによる交通死亡事故で被害者の方が受け取るべき正しい慰謝料額の算出方法、増額を勝ち取るため方法や注意するべきポイントなどについて解説していきます。
具体的には、この記事を読むことで次のことがわかります。
- ・タクシーによる交通死亡事故の注意点
- ・慰謝料の他に 請求できる項目
- ・タクシーによる交通死亡事故の慰謝料額の算出方法
- ・交通事故の示談交渉における素人と弁護士の違い
- ・タクシーによる交通死亡事故の慰謝料等が増額する理由
- ・弁護士に相談・依頼するメリット
- ・頼れる弁護士の正しい探し方
みらい総合法律事務所の実際の解決事例
まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決したタクシーによる交通死亡事故の事例をご紹介します。
36歳男性のタクシーによる交通死亡事故で遺族が約4,470万円を獲得
道路上で横臥していた36歳の男性が、走行してきたタクシーにひかれた交通事故。
加害者側の保険会社は、死亡事故の原因は被害者が道路に横臥していたものであるとして慰謝料等の支払いを拒否。
困ってしまったご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談の解決を依頼されました。
弁護士と保険会社の交渉は難航し、解決の糸口が見つからなかったため弁護士が提訴。
裁判では弁護士の主張が認められ、最終的には約4,470万円で解決しました。
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら
加害者がタクシーの交通死亡事故の場合の慰謝料
タクシーによる交通事故により親しい方を亡くされたご遺族の方には、心からお悔やみ申し上げます。
車社会である現代において、交通事故は誰の身にも起こり得ることで、決して他人事ではありません。
ある日突然、自分や家族が交通事故に巻き込まれ、ケガをしたり、亡くなってしまうことがあるのです。
タクシーの交通事故に関していえば、特に都会ではタクシーの利用頻度が高く、街中を走っているタクシーの台数も多いため、タクシーに乗車中に事故に巻き込まれてしまったり、タクシーに追突されてしまったりといった事故が起きてしまうことも少なくありません。
死亡事故の場合には、亡くなってしまった被害者に代わって、ご遺族が加害者であるタクシー運転手やタクシー会社を相手に損害賠償についての交渉をしていくことになります。
ご遺族としては、亡くなった被害者の方のためにも適正な損害賠償金額を支払ってもらうことを望まれると思います。
しかし、後で詳しく説明しますが、相手がタクシーの場合、示談交渉は難航する場合が多く、本来もらえるはずの損害賠償金額よりも低い金額で示談をしてしまっているご遺族の方が多いのではないか、と推測しています。
そのようなことを防ぎ、適正な金額を受け取るためには、やはり交通事故の損害賠償に関する知識が必要になってきます。
また、死亡事故の場合には、損害賠償金額も高額になることが予想され、一般の方が交渉してもなかなか納得のいく金額を支払ってもらうことは難しいという現実があります。
そのため、交通事故に詳しい弁護士等の専門家に依頼することをおすすめしますが、その場合でも基礎的な知識があった方がより納得して依頼することができると思います。
そこで今回は、タクシーによる死亡事故の場合の損害賠償の問題について、基礎的な事項をご説明したいと思います。
示談交渉について
示談とは
交通事故の損害賠償の問題について交渉することを、一般的に「示談交渉をする」という言い方をするかと思います。
示談とは、交通事故によって被害者が被った損害がいくらになるのか、支払いはどのようにするのか等の事項を、当事者の話し合いによって、お互いに譲歩しながら決定し、解決することをいいます。
法律的にいうと、民法上の「和解」(民法695条)に該当します。
交通事故の死亡事故の場合、まずは被害者の通夜や葬儀が行なわれると思いますが、その後、四十九日の法要が終わったあたりで、加害者側から遺族に連絡があり、示談の話を始めるということが多いです。
タクシー運転手が加害者の場合、通常は加害者本人と直接示談交渉することはなく、雇い主であるタクシー会社の交通事故の担当者や、タクシー会社が加入している共済組合や保険会社の担当者が窓口となって示談を進めていくことが多いです。
具体的には、
(2)そこで提示された損害賠償金額を検討し、納得ができた場合には示談書(「免責証書」という名前の書面の場合もあります)に署名捺印
(3)示談書に記載された損害賠償金が支払われて終了
という流れにになります。
提示された金額に納得できない場合には、その後も話し合いを続け、話し合いでもお互いが合意できなかった場合には裁判を行なうことになります。
裁判の場合は、判決を出してもらって解決する場合と、裁判の途中で当事者が裁判上の和解をして解決する場合があります。
示談の注意点
示談交渉の時に一番やってはいけないことは、加害者側からの損害賠償金の提示金額の内容をあまり検討せずに、提示された金額のまま安易に示談してしまうことです。
示談書に署名押印すると示談が成立したことになり、交通事故の損害賠償の問題が最終的に解決した、ということになります。
示談した後に、じつはその示談金額が、裁判をした場合に認められうる金額である裁判基準よりもかなり低い金額であったということがわかったとしても、追加で請求したりすることは原則としてできません。
ここで重要なポイントは、加害者側が最初から適正な損害賠償金額を提示してくることはほとんどない、ということです。
なぜなら、保険金を支払う側としては、支払う保険金額が少ない方が会社の利益になるからです。
ですので、加害者側からの提示金額を適正な金額だろうと勘違いして示談をしてしまうと、被害者とご遺族は損をしている可能性が高いということになります。
また、示談が成立しているかどうかというのは、加害者の刑事罰にも関係してくる可能性もあります。
交通死亡事故の場合、加害者は刑法上の過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの罪で逮捕、起訴され、刑事罰を受ける可能性がありますが、裁判所がその量刑を判断する際に、先に示談が成立している場合には、被害者に対する賠償が済んでいるとの考えから、加害者の量刑が軽くなるということもあるからです。
ご遺族としては、加害者には刑事罰を受けてきちんと罪を償ってほしいと思うことは当然だと思いますので、示談交渉は加害者の刑事裁判が終わってから始めるということにしてもいいと思います。
死亡事故の損害賠償金の項目について
交通事故の損害賠償金というと、世間的には「慰謝料をもらう」というような言い方をすることも多いかと思いますが、交通事故の損害賠償金というのは慰謝料のことだけを指すのではなく、さまざまな損害賠償の項目の合計金額になります。
交通死亡事故の場合に請求できる損害賠償金の主な項目には、以下のものがあります。
1つずつ詳しく解説します。
葬儀費用
葬儀費用は、自賠責保険の場合は定額で金額は60万円です。
任意保険会社等は、定額で定められている自賠責保険では足りない部分を補うものですが、葬儀費用については、だいたい120万円以内くらいで提示してくることが多いです。
裁判を起こした場合に認められる金額である裁判基準では、葬儀費用は原則として150万円です。
ただし、実際にかかった金額が150万円を下回る場合は、実際に支出した額になります。
被害者の社会的地位が高い場合などで、実際にかかった葬儀費用が相場よりも高額であるような場合は、その支出の必要性が認められれば150万円より高額な金額が認められる可能性もあります。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が生きていれば労働などにより将来にわたって得られたはずのお金のことです。
死亡逸失利益は、以下の計算式で算定します。
基礎収入は、被害者が働いていた場合、原則として事故前年の実際の年収額とします。
被害者が幼児や学生であった場合は、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金を基礎収入とします。
被害者が主婦であった場合は、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入とします。
生活費控除とは、生きていればかかったはずである生活費を収入額から差し引くことをいいます。
生活費控除率は、被害者の立場によって以下のように目安があります。
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
|---|---|
| 被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 | 30% |
| 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |
| 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |
- 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合
- 40%
- 被害者が一家の支柱で被扶養者が2人の場合
- 30%
- 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合
- 30%
- 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合
- 50%
ライプニッツ係数とは、損害賠償の場合は将来にかけて得られたはずのお金をまとめて受け取ることになるため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。
2020年4月1日に発生した交通事故については、この利息は3%となり、その後3年毎に見直されることになります。
就労可能年数とは、働くことが可能であると考えられる年数のことです。
就労の終了時期は、原則として67歳までとされています。
被害者が67歳よりも高齢であった場合は、簡易生命表の平均余命の2分の1とされています。
被害者が幼児や学生の場合、就労の始まりの時期は、原則として18歳とされています。
被害者が大学生で大学卒業が具体的に決まっている場合や卒業の可能性が高い場合などは、大学卒業予定時を就労の始まる時期とします。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者の立場によってある程度の相場が定められています。
裁判基準により相場は以下のようになっています。
| 被害者が一家の支柱の場合 | 2,800万円 |
|---|---|
| 被害者が母親、配偶者の場合 | 2,500万円 |
| その他(独身の男女、子供、幼児等)の場合 | 2,000万円~2,500万円 |
- 被害者が一家の支柱の場合
- 2,800万円
- 被害者が母親、配偶者の場合
- 2,500万円
- その他(独身の男女、子供、幼児等)の場合
- 2,000万円~2,500万円
加害者側が提示してきた死亡慰謝料額が上記の相場より低い場合は、交渉することになります。
また、事故態様が、加害者の無免許、ひき逃げ、飲酒、信号無視、薬物等のため正常な運転ができない状態での運転による場合や、事故後の対応が著しく不誠実な態度である場合など、悪質であると考えられる場合には、上記の相場の金額よりも高い慰謝料額を請求できる場合もあります。
なお、近親者にも固有の慰謝料が認められます。
弁護士費用
加害者側との示談交渉がうまくいかず裁判になる場合には、弁護士に依頼することになると思いますが、その裁判で判決が出される際には、裁判で認められた損害賠償金額の10%程度が弁護士費用として加算されます。
たとえば、裁判で認められた損害賠償金額を5,000万円とした場合、弁護士費用分として10%の500万円が追加され、加害者が支払いを命じられる金額は5,500万円となります。
タクシーを相手とした交通事故の場合の問題点
過失相殺は争いになりやすい
過失相殺とは、交通事故が起きたことについて、被害者側にも何らかの過失があった場合に、被害者の過失を考慮して、その過失の割合を損害賠償額から減額することです。
たとえば、過失割合が「90対10」とされた場合、加害者の過失が90%、被害者の過失が10%ということになります。
この場合の損害賠償金額の合計額が1,000万円だとした場合、1,000万円の10%である100万円を差し引いた900万円が、被害者側に支払われる金額となります。
タクシーに客として乗車中に交通事故にあった場合、被害者にはなんの落ち度もありませんので、原則として被害者の過失割合は0です。
被害者が自分の車を運転していて、タクシーと接触する等の事故により死亡した場合は、停車中にタクシーに衝突された場合など被害者がどうしようもなかった場合には被害者の過失は0ですが、お互い走行中に起きた事故の場合は、それぞれの事故態様によって過失割合が認定されることになります。
死亡事故の場合には、被害者が死亡しているため事故の状況について被害者の言い分を聞くことができないことから、過失割合について争いとなりやすいです。
特に、タクシー運転手を相手とした事故の場合には、タクシー会社としての評判や業績が落ちたり、保険を使うことによって翌年の保険料が上がってしまったり、タクシー運転手としての仕事を続けることができなくなったりする等のリスクがあるためか、タクシー側が過失を認めなかったり、過失割合を実際よりも低く主張してきたりすることがあり、交渉が難航することが多いです。
死亡事故のように、損害賠償金額が多額になることが予想される事故ほど、過失割合が10%違っただけでも被害者側が受け取れる金額が何百万や何千万も変わってしまう場合もありますので、加害者側が過失を低く言ってきたような場合でも、簡単に応じてはいけません。
タクシー会社との交渉について
上述したように、タクシーを相手とした交通事故の場合には、タクシー会社側としては支払う保険金額を少しでも抑えたいとの考えから過失相殺で争いになったり、裁判をした場合に支払われる可能性のある金額よりも低い金額で示談をしようとしてきたりすることがあります。
また、タクシー会社の担当者は、交通事故に関する交渉にも慣れていることから、被害者側の言い分にまったく耳を貸さなかったり、時には高圧的な対応をする場合もあるようです。
実際、当事務所に相談にいらっしゃる方からもそのようなことを聞いています。
そのような場合に、家族を亡くされて精神的にもつらい思いをしている遺族の方に、担当者との交渉を強いるのは酷なことであると思いますし、対等に交渉をして適正な損害賠償金額を支払ってもらうというのは現実的には大変難しいことであると思います。
タクシー会社や保険会社から慰謝料の増額が持ちかけられることはありません。
また、裁判になった場合、裁判所が被害者の感情を考慮してくれて、黙っていても勝手に慰謝料等を増額してくれる、ということもありません。
慰謝料の増額を得るためには、被害者の方のご遺族が強く主張していくことが必要なのです。
できれば、ご遺族も交通事故や損害賠償、保険に関する知識学んで、どのような場合に慰謝料が増額されるのか、損害賠償請求できる項目が抜けていないかなどをチェックできればいいのですが、それは法律や保険の素人には難しいでしょう。
そのような意味でも、タクシーによる死亡事故の示談交渉は、やはり弁護士に相談・依頼することを検討したほうがよいと思います。
交通死亡事故の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠