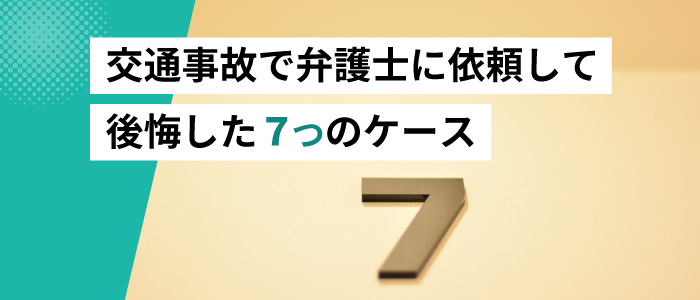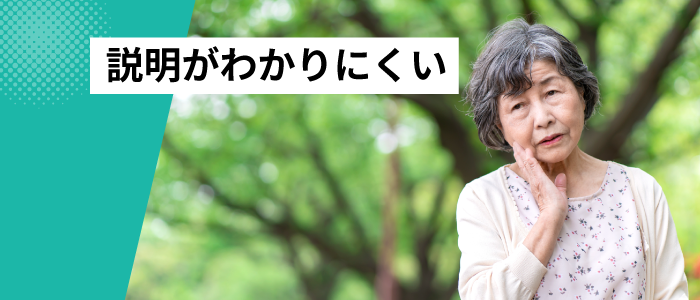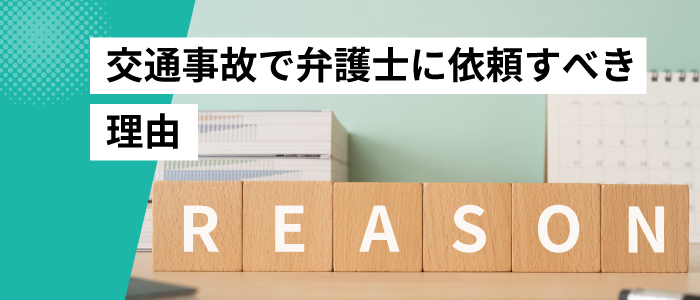交通事故で弁護士に依頼して後悔した7つのケース|その対策
交通事故の被害者が、交通事故の損害賠償問題を弁護士に依頼して良い解決をしようとしたにもかかわらず、かえって弁護士に依頼したことを後悔したケースがあります。
まず、どのような場合に弁護士に依頼すると後悔するのかを知ることです。
そして、弁護士に依頼して後悔しないための対策もありますので、それを知っていただき、きちんと対策をして、後悔のない弁護士選びをしていただければと思います。
交通事故では、弁護士に依頼した方がメリットのあるケースが多いので、本記事を最後まで読んで、交通事故問題で後悔をしないように気をつけていただければと思います。
弁護士に依頼して後悔した7つのケース
みらい総合法律事務所では、年間に1,000件以上の被害者からご相談を受けており、その中には、すでに弁護士に依頼をしているものの、後悔している内容のものが多数含まれています。
交通事故の被害者が弁護士に示談交渉を依頼して後悔したケースには、次のようなものがあります。
順番に解説していきます。
交通事故を扱った経験がない
医者に専門があるように、弁護士にも専門があり、得意不得意があります。
交通事故の事件を処理するためには、交通事故に関する判例の知識、損害賠償額の計算の知識、医学的な知識、自賠責後遺障害等級認定システムの知識、保険の知識など、膨大な知識が必要となります。
交通事故の事件処理の知識は、司法試験などには出ませんので、弁護士になって、実際に事件を処理しながら身につけていくことになります。
したがって、交通事故を扱ったことがなければ、交通事故の事件処理に関する知識がないことになり、ゼロから学びながら事件を処理しなければなりません。
そうすると、当然のことながら、ミスを犯しやすくなりますし、請求すべき金額に漏れが出てくることになりかねません。
一つ一つ調べながらですから、時間もかかると思います。
そのようなことから、交通事故の被害者の方から、「今、依頼している弁護士は交通事故に詳しくないようだ」という相談が、みらい総合法律事務所に寄せられています。
このように、依頼した弁護士が交通事故を扱ったことがない、又は得意ではない、という場合には、弁護士に依頼して後悔することがあります。
費用倒れになった
弁護士に依頼した方が確かに示談金は増額するケースが多いです。しかし、ただ示談金が増額すればいい、というわけではありません。
実際に被害者が手にするお金が増額するかどうかが問題です。なぜなら、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合には、弁護士費用がかかるためです。
示談金から、その弁護士費用を差し引いても、被害者が手にするお金が増額するかどうかを確認する必要があります。
そして、事案によっては「費用倒れ」になるケースがあります。
弁護士に支払う報酬などの費用が損害賠償金の増額分を上回ってしまうことがあるのです。
例えば、被害者が保険会社と交渉して示談金額が100万円になったとします。
そこで弁護士に依頼したところ、弁護士が保険会社と交渉して示談金が110万円になりました。
弁護士報酬が獲得金額の10%+20万円(消費税込)だとすると、弁護士報酬は、31万円です。
そうすると、被害者の手元に残るお金は、110万円 ー 31万円 = 79万円となり、自分で交渉した金額である100万円よりも少なくなってしまうことになります。
これでは、示談交渉などが解決しても、喜べません。
このような費用倒れのケースでは、交通事故の被害者は、弁護士に依頼したことで後悔することになるでしょう。
連絡が取れない
交通事故の被害者からみらい総合法律事務所に寄せられる相談の中には、「弁護士と連絡が取れない」というものがあります。
「そんなことがあるのか?」
と疑問に思うかもしれませんが、実際にあるのです。
そして、依頼している弁護士に質問したいけれども連絡が取れないので、みらい総合法律事務所に相談した、というケースもあります。
弁護士と連絡が取れないのは、主に依頼した弁護士が忙しすぎることが理由になっていることが多いようです。
特に1人で弁護士事務所をやっていると、事務所の経営、職員の管理、営業活動、マーケティングをやりながら事件処理をしなければならないので、多忙な弁護士は、本当に多忙になります。
そのため、連絡が取りづらい、という現象が起きてしまうのです。
せっかく弁護士に依頼しても、連絡が取れないということでは、進捗状況もわかりませんし、聞きたいことも聞けません。
このようなケースは、交通事故の被害者が弁護士に依頼して後悔するケースといえるでしょう。
放置されている
交通事故の被害者からみらい総合法律事務所に寄せられる相談の中には、「依頼している弁護士が案件を全く進めてくれない」「案件を放置されている」というようなものがあります。
これも、先程の連絡が取れないケースと同様に、依頼した弁護士が忙しすぎて後回しになってしまっているケースがあります。
また、交通事故が得意ではない弁護士の場合、どのように処理していったらよいのかわからず、なんとなく後回しになってしまっている、というケースもあるでしょう。
交通事故の被害者としては、一刻も早く解決をして賠償金を得て、交通事故の悪い思い出を忘れてしまいたいのに、いつまでも解決しないことになってしまいます。
最悪の事態は、弁護士が放置しすぎて、消滅時効が完成し、賠償金が0円になってしまうことです。
このような案件を放置するような弁護士に依頼した場合、被害者は、後悔することになるでしょう。
態度が悪い
弁護士に対する苦情でよく聞くのが「弁護士の態度が悪い」というものです。
これには色々な種類があり、「態度が横柄だ」「すぐに怒り出す」「態度がはっきりしないので、どうしたらいいかわからない」などがあります。
これは、依頼する前の相談の際に、じっくりと弁護士の人となりを観察しておかなかったという原因もあると思います。
すぐに怒り出すような弁護士に依頼してしまうと、交通事故の被害者としては、言いたいことも言えない、ということも出てきて、満足な解決ができないことになってしまい、後悔することになるでしょう。
説明がわかりにくい
交通事故の被害者が弁護士に依頼して後悔するケースとして、「説明がわかりにくい」「専門用語で説明され、理解できない」というようなものがあります。
これは、専門家の世界ではよくある状況です。
専門家は、自分たちの世界では専門用語は常識ですので、そのまま専門用語を使って説明をしがちです。
しかし、被害者は、法律の素人ですから、専門用語の意味がわかりません。
たとえば、「逸失利益の計算にはライプニッツ係数をかける必要があります」と言われても、被害者にとっては意味がわかりません。
また、専門用語を使っていなくても、弁護士の場合、説明を正確にしようとして、回りくどい説明になったり、二重に否定が使われたりして、聞いている方がとてもわかりにくい、というケースもあります。
このような場合には、被害者としては、弁護士に依頼して後悔することもあるでしょう。
弁護士費用が高い
弁護士費用が高いことで被害者が弁護士に依頼したことを後悔するケースもあります。
たとえ費用倒れにならなかったとしても、弁護士費用が高すぎて、被害者の手元に残るお金が少なくなってしまうことは避けたいところです。
なぜ、このようなことが起こるのかというと、弁護士費用には統一的な基準がなく、弁護士毎に取り決めているからです。
そのため、着手金、報酬金と2度弁護士費用がかかる事務所もあれば、着手金0円で成功報酬は、獲得金額の10%という弁護士もいますし、成功報酬が獲得金額の20%という弁護士もいます。
このようなケースで後悔するのは、弁護士に依頼する前に弁護士費用を取り決めて契約書に記載していないようなケースや、弁護士費用を取り決める時に、具体的な解決結果に当てはめて予想していない、などの原因が考えられます。
弁護士費用が高すぎて被害者の手元に残るお金が少なくなってしまっては、被害者は弁護士に依頼したことを後悔することになるでしょう。
後悔しないための7つの対策
では、これまで説明してきたような、被害者が弁護士に依頼して後悔する事態に陥らないようにするには、どうしたらよいでしょうか。
その対策を7つ解説していきます。
相談の前に実績を確認する
交通事故の被害者が、示談交渉を依頼した弁護士が交通事故を扱ったことがない、苦手だ、などの理由により依頼したことを後悔しないためには、弁護士に相談する前に、ある程度その弁護士のことを調べておくことが望ましいです。
ホームページがあれば、ホームページの内容を見て、交通事故を扱っているかどうか、確認します。
知人の紹介であれば、その知人を通して弁護士に対して交通事故が得意かどうか確認してもらいます。
死亡事故や後遺障害事案などの理由により、特に交通事故に精通した弁護士に依頼したい場合には、法律専門書の出版、ホームページの実績の確認などにより交通事故の専門性を確認することが必要となります。
法律相談の前に交通事故の実績を確認しておけば、少なくとも、依頼した弁護士が交通事故が苦手だ、という事態は避けることができるでしょう。
弁護士費用を確認し、契約書に明記する
弁護士費用が高すぎることや、費用倒れにより後悔するのを回避する方法の一つは、弁護士と契約をする前に、弁護士費用を確認し、それを契約書に明記してもらうことです。
ホームページに弁護士費用の計算方法を記載している場合もあるので、できれば法律相談の前に確認しておくようにしましょう。
弁護士が事件の依頼を受けた時には契約書を作成しなければならないのですが、未だに契約書を作成しない弁護士もいるようです。
しかし、それでは、交通事故の被害者は、弁護士に依頼することでいくら弁護士費用を払うことになるのかがわかりません。
その結果、弁護士費用が想定以上に高額であったり、費用倒れになってしまったり、という事態が想定されます。
そこで、交通事故の被害者は、弁護士と契約する前に、必ず弁護士費用を確認し、契約書に明記してもらうことをおすすめします。
それによって、いくら弁護士費用を払うことになるかが明確になり、安心して弁護士に依頼することができるでしょう。
参考記事:みらい総合法律事務所の弁護士費用
弁護士費用特約を利用する
弁護士費用が高すぎたり、費用倒れになることによって、弁護士に依頼することを後悔する事態を回避するもう一つの方法は、「弁護士費用特約」を利用することです。
弁護士費用特約は、被害者がかけている自動車の任意保険、同居の親族や未婚の場合の別居の両親などがかけている任意保険に付帯している保険です。
多くの場合に、最大300万円まで保険会社が被害者の弁護士費用を負担してくれます。
※保険約款をご確認ください。
この弁護士費用特約を利用すれば、保険である程度までの弁護士費用を払ってくれるので、安心して弁護士に依頼することができます。
もちろん、高額の賠償請求の場合には、弁護士費用特約では足りずに被害者が自分で弁護士費用を負担しなければならなくなりますが、その場合には、高額の賠償金を得られることになりますので、弁護士費用の負担もそれほど大きな負担にはならないことが多いでしょう。
なぜなら、弁護士に依頼することで賠償金が増額し、弁護士基準による賠償額での解決となっていることが多いためです。
解決の見通しを確認する
交通事故を弁護士に依頼した場合の費用倒れは、解決金額の中から弁護士費用を支払うことによって被害者の手元に残るお金が少なくなってしまうことによって生じます。
したがって、解決金額も重要な要素となります。
そこで、弁護士に依頼する前の相談段階で、最終的にいくらくらいで解決するのか、その見通しを弁護士に確認しておく必要があります。
解決の見通しを確認することにより、その解決金額と弁護士費用の予想額を比較して、費用倒れにならないか、弁護士に依頼するメリットがあるかどうかを検討することになります。
また、交通事故が苦手な弁護士を見極めるためにも、解決の見通しを確認することは有効な手段となります。
交通事故を扱ったことがなかったり、苦手な場合は、解決の見通しを立てることができません。
しかし、日常的に交通事故を扱っていれば、相談の段階で、資料が揃っていることが条件ですが、解決の見通しをある程度予想することができます。
この意味からも、相談段階で弁護士に対して解決の見通しを確認することは大切といえるでしょう。
適宜状況を確認する
自分の案件を後回しにされ、放置されるのを防ぐためには、依頼した弁護士に対し、適宜連絡をして状況を確認するようにしましょう。
通常、弁護士は多数の事件を受任し、併行して処理をしています。
自分の事件だけを優先して処理をしてくれるわけではありません。
全ての事件について、処理状況を記録していない場合には、忘れてしまい、結果として放置した状態になっている可能性もなくはありません。
そのようなことがないよう、被害者の方から適宜弁護士に連絡をして状況を確認することにより、放置されることを防止することができます。
また、弁護士から何も連絡がないと、どの程度状況が進展しているのかがわからず、不安になります。
適宜状況を確認することにより、引き続き安心して弁護士に任せることができます。
依頼する前に弁護士に直接相談する
依頼した弁護士と性格が合わない、という後悔や、依頼した弁護士の説明がわかりにくい、という後悔をしないための対策は、依頼の前に担当弁護士に直接相談し、疑問点をぶつけることです。
中には、事務員とだけやり取りをして、依頼してしまう被害者もいます。
しかし、それでは、実際に担当する弁護士との相性やその弁護士が交通事故に精通しているかどうか、また、わかりやすく説明してくれるかどうかなどがわかりません。
依頼した後にはじめてわかることになります。
しかし、契約してしまった以上、後の祭りです。
もちろん解約はできますが、すでに費用が発生していまったり、解約違約金が発生したり、という可能性もあります。
したがって、弁護士に依頼する前には、必ず担当弁護士に直接相談し、全てを任せることができるかどうか、見極めることが大切です。
弁護士を代える
交通事故の被害者が弁護士に依頼することで後悔することを防ぐために、弁護士を代える、という方法があります。
これまで解説してきた交通事故の被害者が弁護士に依頼して後悔するような状況を一気に変える方法が、弁護士を代えてしまうことです。
被害者の中には、一度弁護士と契約をした以上、弁護士を代えることはできない、と思っている人がいるかもしれません。
しかし、契約書に解約を禁止する条項がなければ、途中で弁護士との契約を解約し、違う弁護士に依頼し直すことは可能です。
但し、前の弁護士との契約で解約の方法や解約によるお金の精算などが発生する可能性がありますので、解約の前に、その点の確認をしておく必要があります。
また、途中で弁護士がいなくなると、交通事故の損害賠償問題が中断してしまいますので、次の弁護士を決めてから、前の弁護士との契約を解約した方がいいでしょう。
弁護士の交代の仕方については、次の記事を参考にしてください。
交通事故で弁護士に依頼すべき理由
そんなに弁護士に依頼して後悔する場合があるならば、むしろ示談交渉を弁護士に依頼しない方がいいのでは、と思うかも知れません。
しかし、多くの場合において、交通事故で被害者が弁護士に依頼するメリットの方が大きいでしょう。
その点について、解説します。
交通事故の示談で後悔しないために
交通事故で被害者が弁護士に依頼するメリットが大きい、というのは、つまり、被害者が自分で交通事故の損害賠償問題を適切に解決することは難しく、弁護士に依頼した方がメリットが大きい、ということです。
弁護士に依頼して後悔することを恐れ、自分一人で解決しようとすると、かえって後悔する結果となる可能性があります。
保険会社が株式会社である場合には、保険会社は自社の利益を増大させるため、支出を抑えようとし、被害者に対する示談金を低くしようとします。
それによって保険会社の利益を確保しようとするのです。
そのため、保険会社は、被害者に対し、適正な金額よりも低い示談金を提示してきます。
そして、被害者が自分で増額交渉しても、なかなか保険会社は譲歩しないことが多いです。
「当社の基準では、これが限界です。これ以上は増額できません」
「これが適正金額です」
などと言って、増額しないのが現実です。
そのような場合に、諦めてその金額で示談してしまうと、かえって被害者は損をすることになってしまいます。
そのようなことを避けるため、後悔しない弁護士選びが必要になってくるわけです。
弁護士に依頼するメリット6選
交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットは、主に6つあります。
被害者と弁護士は利害が一致する
すでに説明したように、保険会社は自社の利益を確保するため、示談金を低く抑えようとします。
そのため、なるべく示談金を高額にしようとする交通事故の被害者と保険会社との利害は相反しているといえます。
しかし、弁護士の場合、多くの場合に成功報酬は示談金額と連動しているため、被害者と弁護士の利害は一致するといえます。
刑事事件に適切に助言してもらえる
裁判所、検察、警察を除けば、刑事事件の専門家は弁護士しかいません。
したがって、被害者が依頼して刑事事件に適切に助言をくれる専門家は、弁護士となります。
被害者は、加害者の刑事事件に関与することになりますので、弁護士に相談しながら進めていくことをおすすめします。
また、被害者が加害者の刑事事件に参加する「被害者参加」でも、弁護士が適切にサポートしてくれます。
適正な弁護士基準で慰謝料を獲得できる
交通事故の慰謝料の計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
このうち、保険会社が提示してくるのは、自賠責基準か任意保険基準です。
しかし、それらの金額は被害者が得るべき適切な金額より低い計算方法です。
弁護士基準が最も高額で適切な金額となり、弁護士に依頼すると、弁護士基準で賠償金を計算して交渉してくれます。
交通事故を弁護士に頼むと、示談金が増額される
交通事故の示談交渉において、被害者と保険会社は利害が相反しており、保険会社は多くの場合に適正金額より低い示談金を提示します。
そして、被害者が増額交渉をしても、なかなか増額してくれません。
しかし、弁護士が交渉すると、賠償金が増額することが多いです。
みらい総合法律事務所の解決事例をご覧ください。
参考記事:みらい総合法律事務所の解決事例
実際にかなり増額していることが多いです。
このことからも、弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。
保険会社とのやり取りから解放される
交通事故の示談交渉を被害者が一人で行うのはかなりの精神的負担です。
交通事故で怪我をして痛みをこらえて交渉したり、死亡事故で大切なご家族を亡くした悲しみをこらえて交渉するのは大変です。
弁護士に依頼すれば、保険会社との煩わしい交渉は全て弁護士が代行してくれるので、被害者は保険会社とのやり取りから解放されることになります。
裁判をすると、賠償額が増える
交通事故の損害賠償問題は、全て示談で解決するわけではありません。
被害者と保険会社との利害は相反しますので、金額に隔たりが大きく、裁判になることもあります。
被害者が自分で裁判を起こすのは大変ですから、弁護士に依頼することになります。
実は、裁判を起こすと、裁判所は、最も高額の弁護士基準で賠償金を計算してくれます。
また、判決になると、賠償額に「弁護士費用相当額」と「遅延損害金」というものを付加してくれます。
そのような理由から、裁判をすると、賠償額が増えることがありますので、弁護士に依頼して積極的に活用することも検討しましょう。
交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット・デメリット等の詳細は、以下の記事を参考にしてください。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠