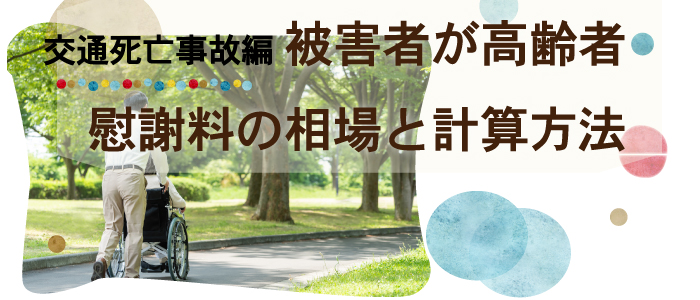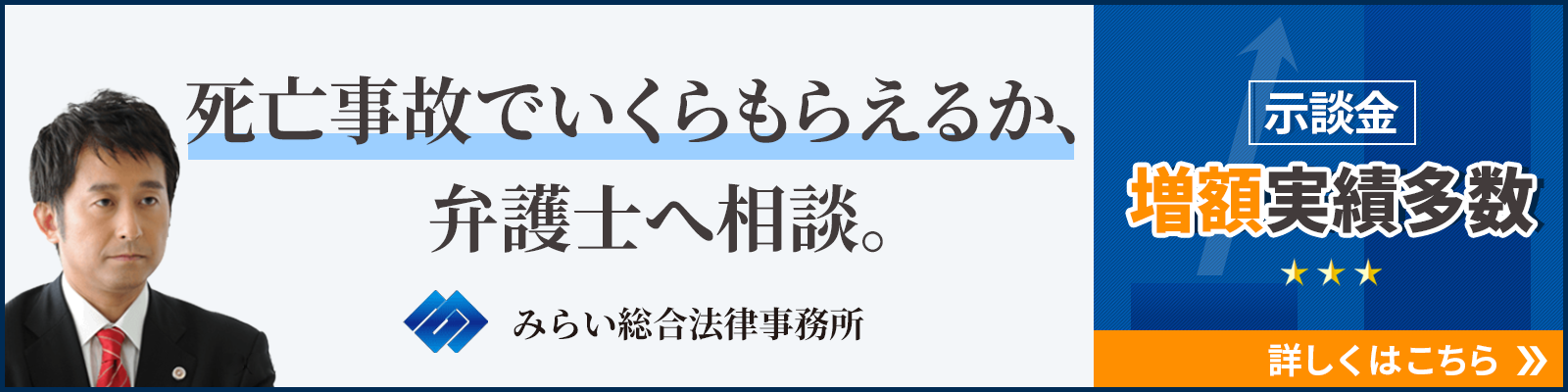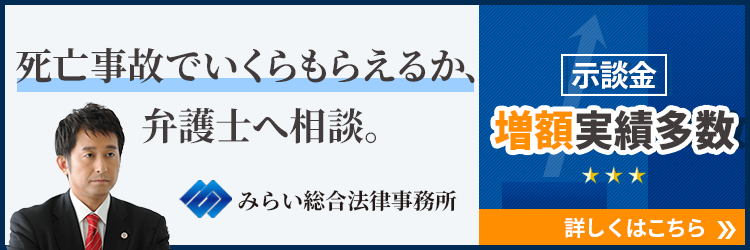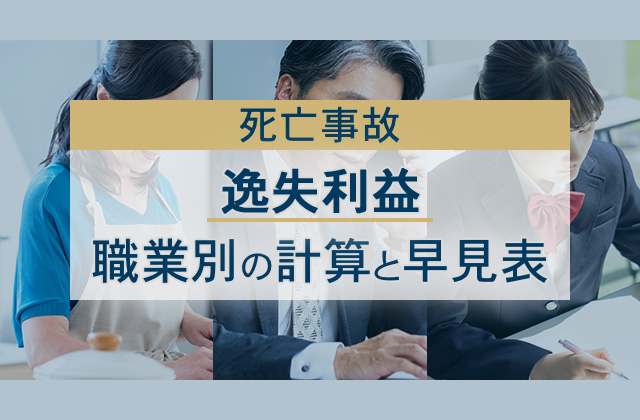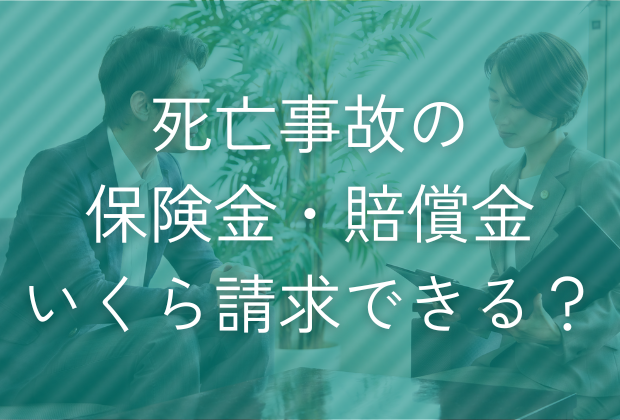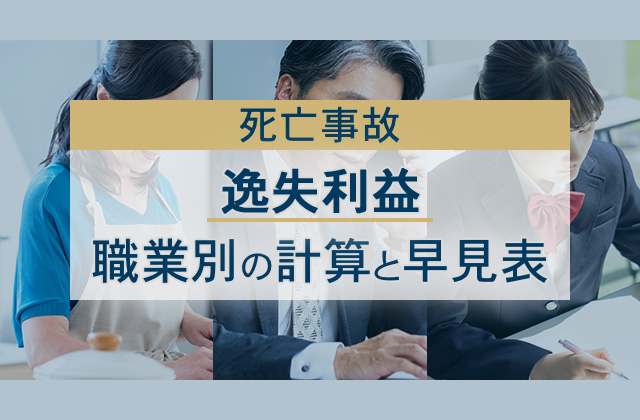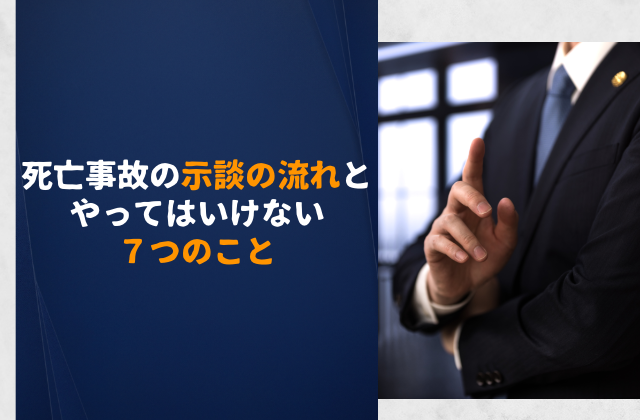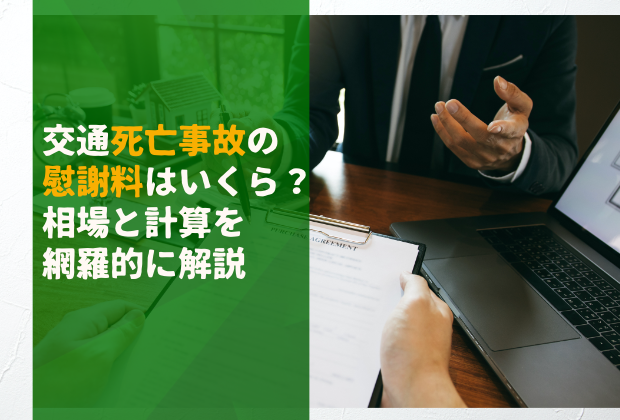80歳の高齢者の死亡事故で慰謝料の計算と相場
*タップすると解説を見ることができます。
80歳の高齢者の死亡事故で、加害者側の任意保険会社との示談交渉で大きな争点になるのは「慰謝料」「逸失利益」「過失割合」です。
80歳代の高齢者の方で、経済的に一家の支柱(家庭の経済的・精神的な支えとなっている人)でない場合は、2,000~2,500万円が適切な慰謝料の相場金額になります。
死亡逸失利益は、被害者の方が交通事故で亡くならなければ、将来的に得られるはずだった利益(収入)です。
高齢者の場合、将来的に働くことができる期間が限定され、収入は低い傾向にあるので、加害者側の任意保険会社は逸失利益を低く見積もってくることが多いです。
過失割合とは、事故についての加害者と被害者の過失(責任)の割合のことで、加害者9に対して被害者1、あるいは加害者80%対被害者20%というように表現されます。
死亡事故では、保険会社から被害者の方の過失を大きく主張され、それを受け入れてしまうと被害者の方が大きな損失を被ることになります。
本記事では、被害者が80歳の場合の死亡事故の慰謝料の計算と相場金額について網羅的に解説しますので、ご遺族は、本記事を最後まで読んで、決して損をしないようにしてください。
目次
高齢者の事故で争点になる過失割合・逸失利益・慰謝料
高齢者の過失割合
交通事故で大きな争点となるものに過失割合があります。
過失割合とは、その交通事故の原因となる過失が、被害者と加害者でそれぞれどのくらいの割合あったのかの比率であり、その割合に基づいて慰謝料などの損害賠償金が決まります。
たとえば、損害賠償金額が1,000万円で、過失割合が被害者と加害者で、20% : 80%の場合、被害者の過失分の200万円が引かれることになるのですが、これを過失相殺といいます。
そして、被害者の方が受け取る金額は800万円になるという仕組みです。
つまり、被害者の方の過失割合を高く見積もられるほど、受け取る金額が少なくなってしまうのです。
過失割合については、過去の膨大な裁判例から、だいたいの基準が決まっているのですが、高齢者の場合には、その基本となる過失割合が修正されることがあるので、注意が必要です。
できる限り、被害者に有利な過失割合を主張していくことが大切です。
高齢者の逸失利益
交通事故の被害にあわずに生きていれば、得られたはずだった収入(利益)を死亡逸失利益といいます。
高齢者の場合、収入を得られる期間が若者などよりも短いため、加害者側の任意保険会社に低く見積もられてしまい、相場金額よりも低い金額が提示される場合があります。
こうした場合は、適正な金額を算出して、示談交渉で加害者側(通常の場合は加害者が加入している任意保険会社)に主張していくことが大切です。
また、高齢者の死亡事故の場合、年金収入の中にも、逸失利益として含まれるものもありますので、漏れのないように請求していく必要があります。
高齢者の慰謝料
交通事故にあうのが初めての方は、ほとんどの方が慰謝料について以下のように考えていると思います。
しかし、覚えておいていただきたいのは、慰謝料には次の4つがあることです。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
- 死亡慰謝料
- 近親者慰謝料
死亡事故で請求できるのは、本人分の死亡慰謝料と近親者慰謝料です。
治療の後死亡した場合には、入通院慰謝料を請求することができます。
高齢者で一人暮らしの場合には、死亡慰謝料の相場が2,000万円~2,500万円と幅があるので、できる限り有利に主張していくことが大切になってきます。
死亡事故で請求できる損害賠償項目と相場金額
被害者の方が亡くなった場合に加害者側(通常の場合は加害者が加入している任意保険会社)に請求できる損害賠償項目には次のものがあります。
葬儀関係費
・自賠責保険から支払われる金額は、100万円(定額)
・裁判で認められる上限額は原則として150万円
・通常の場合、任意保険会社は120万円以内の金額を提示してくる場合が多い
・その他、墓石建立費、仏壇購入費、永代供養料などについては、それぞれの事案によって個別に判断される
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、交通事故にあわずに生きていれば得られたはずだった収入(利益)分のことで、次の計算式で算出します。
(基礎年収) ×
(就労可能年数に対するライプニッツ係数) ×
(1 - 生活費控除率)= (死亡逸失利益)
| 基礎年収 | 事故前年の年収を基本にする。 |
|---|---|
| 就労可能年数 | 原則として18歳から67歳とされる。 |
| ライプニッツ係数 |
|
| 生活費控除率 | 被害者の方の家庭での立場や状況によって、おおよその相場の割合が決まっている。 |
基礎年収 - 事故前年の年収を基本にする。
就労可能年数 - 原則として18歳から67歳とされる。
ライプニッツ係数 -
- ・現在と将来ではお金の価値に変動があるため、その差額を現時点で調整する必要が出てくる(これを専門的には、中間利息を控除する、という)が、そのために用いる。
- ・ライプニッツ係数の算出は複雑なため、あらかじめ定められている。
- ・民法改正により、2020年4月1日以降に起きた交通事故の場合は、ライプニッツ係数の率は3%となり、以降は3年ごとに見直されるようになっている。
80歳女性(専業主婦)の方が交通事故で亡くなった場合を例に数字を当てはめた計算例は、80歳の方の死亡逸失利益をご覧ください。
慰謝料
被害者の方が死亡した場合の慰謝料には、
「死亡慰謝料」と「近親者慰謝料」の2つが
あります。
「死亡慰謝料」
死亡慰謝料は、亡くなった被害者の方の精神的苦痛や損害対して支払われるものです。
慰謝料の計算では、次の3つの基準が用いられます。
どの基準で計算するかによって金額に大きな違いが出るので注意が必要です。
1つずつ解説します。
(1)自賠責基準
法律によって定められた自賠責保険の基準です。
自賠責保険は被害者救済のために設立されたものであるため、金額には上限があり、3つの基準の中ではもっとも低い金額になります。
<死亡慰謝料の自賠責基準による相場金額>
自賠責保険では、死亡慰謝料は被害者本人の死亡慰謝料と、ご家族などの近親者慰謝料の合算として扱われます。
| 被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円(一律) |
|---|---|
| 近親者慰謝料 | 配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって金額が変わります。
・1人の場合/550万円
・2人の場合/650万円 ・3人の場合/750万円 |
- 被害者本人の死亡慰謝料
- 400万円(一律)
- 近親者慰謝料
- 配偶者・父母(養父母も含む)・
子(養子・認知した子・胎児も含む)の
人数によって金額が変わります。・1人の場合・・・550万円
・2人の場合・・・650万円
・3人の場合・・・750万円
※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされます。
(2)任意保険基準
各任意保険会社が独自に設けている基準です。
各社非公表なのですが、概ね自賠責基準より少し高い金額で設定されていると考えられます。
被害者の方の家庭での立場などによって金額が変わってきます。
| 一家の支柱(一家の生計を立てている者) | 1,500~2,000万円 |
|---|---|
| 専業主婦(主夫)・配偶者 | 1,300~1,600万円 |
| 子供・高齢者など | 1,100~1,500万円 |
- 一家の支柱(一家の生計を立てている者)
- 1,500~2,000万円
- 専業主婦(主夫)・配偶者
- 1,300~1,600万円
- 子供・高齢者など
- 1,100~1,500万円
(3)弁護士(裁判)基準
過去の裁判例から算出されている基準で、もっとも金額が高額になります。
弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉する時は、この基準で算出した金額を主張していきます。
また、法的根拠がしっかりしているので、裁判で認められる可能性が高くなります。
<死亡慰謝料の弁護士(裁判)基準の相場金額>
| 被害者が一家の支柱の場合 | 2,800万円 |
|---|---|
| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2,500万円 |
| 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 2,000万~2,500万円 |
- 被害者が一家の支柱の場合
- 2,800万円
- 被害者が母親・配偶者の場合
- 2,500万円
- 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合
- 2,000万~2,500万円
被害者のご遺族としては、この弁護士(裁判)基準での慰謝料を主張していくことが大切です。
近親者慰謝料
被害者の方のご家族など、近親者が被った精神的苦痛・損害に対して支払われる慰謝料です。
通常、受け取る人が両親(父母)、配偶者(夫・妻)、子供の場合の金額は、概ね被害者本人の慰謝料の1~3割ほどになります。
内縁の夫や妻、兄弟姉妹、祖父母にも認められる場合があります。
弁護士費用
加害者側の任意保険会社との示談交渉が決裂した場合、提訴して裁判で決着をつけることになりますが、そこで弁護士が必要と認められる事案では、弁護士費用相当額が損害賠償額に加算されます。
金額は、相当因果関係のある損害として、認容額の10%程度です。
弁護士費用相当額は示談交渉では認められず、裁判で判決までいった場合に認められます。
つまり、交通事故の示談交渉では、弁護士に依頼して裁判になった場合は、その費用を加害者側に負担させることができる可能性があるということです。
慰謝料は誰が受け取ることができるのか?
交通死亡事故の場合、被害者の方は亡くなっているため、慰謝料などの損害賠償金(示談金)を受け取ることができるのは相続人になります。
相続人の順位と分配の割合は、法律によって次のように決まっています。
なお、被害者の方に配偶者がいる場合は、つねに相続人になります。
相続人の順位と法定相続分
<第1位:子>
相続順位の第1位は「子」です。
すでに子が亡くなっており、子の子供(被害者の方の孫)がいれば、「代襲相続」により「孫」が相続順位の第1位になります。
配偶者は、子や孫と一緒に相続人になります。
<相続人が子の場合の法定相続分>
| 配偶者 | 2分の1 |
|---|---|
| 子 | 2分の1(※子が2人の場合、2分の1を分けるので、1人の相続分は4分の1となります) |
<第2位:親>
相続順位の第2位の順位は「親(父母)」です。
被害者の方に子がいない場合は、親が配偶者とともに相続人になります。
養父母も相続人となります。
<相続人が親の場合の法定相続分>
| 配偶者 | 3分の2 |
|---|---|
| 親 | 3分の1(※両親(父母)がいる場合、3分の1を2人で分けるので、1人の相続分は6分の1となります) |
<第3位:兄弟姉妹>
相続順位の第3位は「兄弟姉妹」です。
被害者の方に子や親がいない場合は、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子が同順位で相続人になります。
<相続人が兄弟姉妹の場合の法定相続分>
| 配偶者 | 4分の3 |
|---|---|
| 兄弟姉妹 | 4分の1(※複数いる場合は、この4分の1を兄弟姉妹の人数で分配する) |
注意するべきポイント
- 遺産相続では、認知されている子が相続の対象となり、胎児も相続人になります。
- 配偶者がいない場合は、それぞれのケースの筆頭の親族のみが相続人になり、それ以外の親族は相続人にはなりません。
- 法定相続分は、あくまでも法律で定められた割合です。そのため、たとえば被害者の方の遺言書がある場合は、その内容に従うことになります。
- 相続人の間で話し合うこと(遺産分割協議)で、たとえば法的な相続権のない人を相続人の1人にしたり、分配率を変更したりということもできます。
- ただし、遺産分割協議では相続人全員の同意が必要になります。
- その際、のちに争いが起きないように、その内容を書面化しておくことも大切になります。
80歳の慰謝料金額の計算例
では、慰謝料などの損害賠償金額について、ここでは80歳女性(専業主婦)の方が交通事故で亡くなった場合を例に、具体的に計算をしてみましょう。
計算上、80歳女性(専業主婦)の方の損害賠償金は、次のようになります。
1つ1つの項目の意味をわかりやすく説明します。
葬儀関係費
示談交渉を弁護士に依頼した場合、また裁判になった場合に弁護士が主張するのが「弁護士(裁判)基準」で算出した金額です。
この弁護士(裁判)基準は、加害者側の保険会社が主張してくる自賠責基準や任意保険基準より高い金額で、2倍、3倍、場合によってはそれ以上の違いがあります。
ここでは、もっとも高額になる弁護士(裁判)基準での算出を採用することとして、葬儀関係費を150万円とします。
死亡逸失利益
前述したように、死亡逸失利益の計算式は次の通りとなります。
(基礎年収)
×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)
×(1-生活費控除率)
=(死亡逸失利益)
①基礎収入
前年度の収入(年金も含む)を基礎とします。
高齢の家事従事者の基礎収入については、次のように分類されています。
ⅱ)女性労働者の全年齢平均賃金から何割か
減額した額としたもの
ⅲ)年齢別の女性労働者の平均賃金としたもの
ⅳ)年齢別の女性労働者の平均賃金から
何割か減額した額としたもの
実際の交通事故の損害賠償実務では、被害者の方が行なっていた家事の内容や程度を個別の事案ごとに具体的に評価して決定していきますが、ここでは「令和元年の賃金センサス女性学歴計全年齢平均賃金」である、388万100円を基礎収入とします。
高齢者の場合には、年金収入がある場合があり、その種類によって基礎収入に入るものと入らないものがあります。
②生活費控除率
生活費控除とは、生きていればかかったはずの生活費を基礎収入から差し引くことです。
<生活費控除率の目安>
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
|---|---|
| 被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 | 30% |
| 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |
| 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |
- 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合
- 40%
- 被害者が一家の支柱で被扶養者が2人の場合
- 30%
- 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合
- 30%
- 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合
- 50%
③就労可能年数
原則、18歳から67歳までとされますが、被害者の方の職種、地位、能力等によっては67歳を過ぎても就労することが可能だったと思われるケースがあります。
その場合は、67歳を過ぎた分についても認められる場合もあります。
ここでは、「就労可能年数とライプニッツ係数表」(国土交通省)による80歳の就労可能年数である「5年」を使って計算していきます。
④ライプニッツ係数
被害者の方が受け取る損害賠償金は、将来にわたる収入を前倒しで受け取るものです。
すると、現在と将来ではお金の価値に違いがあるため、その差を調整する必要がでてきます。
その際に用いるのが、ライプニッツ係数です。
ここでは、80歳のライプニッツ係数「4.580」を用います。
80歳の方の死亡逸失利益
以上から、80歳の方の死亡逸失利益は、次のようになります。
女性学歴計全年齢平均賃金)
×
(1-0.3)
× 4.580(ライプニッツ係数)
=1,243万9,600円
死亡慰謝料
80歳の高齢者のため、ここでは前述の数字の中から、2,200万円とします。
弁護士費用
弁護士費用として認められるのは認容額の10%程度になるので、次のように算出します。
+ 1,243万9600円
(年金を除いた死亡逸失利益)
+
2,200万円(慰謝料)) × 0.1
=359万3,960円
以上から、前述の通り、80歳女性(専業主婦)の方の損害賠償金は、計算上次のようになります。
+ 1,243万9,600円
(年金を除いた死亡逸失利益)
+
2200万円(慰謝料)
+359万3,960円(弁護士費用)
= 3,953万3,560円
80歳以上の死亡事故の実際の
慰謝料増額事例
ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した80歳以上の死亡事故の事例をご紹介していきます。
今後の示談交渉のためにも、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。
解決事例①:82歳女性の
死亡事故の慰謝料等が
約550万円増額した事例
| 被害者 | 82歳女性 | ||
|---|---|---|---|
| ご相談の経緯 |
ご遺族が保険会社と交渉した後の交渉を |
||
| 保険会社提示の示談金 |
1,666万6,130円 |
||
| 解決額 |
2,200万円 |
||
82歳女性が自転車で交差点を直進していたところ、直進自動車に衝突された死亡事故です。
ご遺族が保険会社と交渉し、示談金額が1,666万6,130円となりました。
そこで、ご遺族がその後の交渉をみらい総合法律事務所に依頼しました。
弁護士が保険会社と交渉し、死亡慰謝料の相場金額が2,000万円~2,500万円のところ、2,400万円で妥結し、逸失利益は弁護士基準で示談となりました。
過失相殺の結果、最終的には2,200万円で解決となりました。
解決事例②:80歳女性の
死亡事故の慰謝料等で
3,300万円獲得した事例
| 被害者 | 80歳女性 | ||
|---|---|---|---|
| ご相談の経緯 |
保険会社が金額を提示しないことから、ご遺族がみらい総合法律事務所に示談交渉を依頼。 |
||
| 解決額 |
3,300万円 |
||
80歳女性が自動車に同乗中、衝突により死亡した事故です。
保険会社が金額を提示しないことから、ご遺族がみらい総合法律事務所に示談交渉を依頼しました。
弁護士が裁判を起こしたところ、加害者側は、逸失利益がないと主張しました。
しかし、最終的には弁護士の主張が認められ、家事労働の逸失利益を含め、3,300万円で解決しました。
解決事例③:83歳女性の
死亡事故の慰謝料等で
4,200万円獲得した事例
| 被害者 | 83歳女性 | ||
|---|---|---|---|
| ご相談の経緯 |
ご遺族は、事故直後から、手続に間違いがないように、みらい総合法律事務所にすべての手続を依頼。 |
||
| 解決額 |
4,200万円 |
||
83歳女性が、横断歩道を歩行中、右折自動車に衝突された死亡事故です。
ご遺族は、事故直後から、手続に間違いがないように、みらい総合法律事務所にすべての手続を依頼しました。
刑事事件終了後、弁護士が裁判を起こし、最終的には、83歳にしては高額の慰謝料2,500万円の和解案が提示され、慰謝料を含めた合計4,200万円で和解解決しました。
WEB上の自動計算機で慰謝料等を計算してみる
みらい総合法律事務所では、どなたでも簡単に慰謝料などの損害賠償金額を知ることができる「慰謝料自動計算機」をWEB上にご用意しています。
実際の損害賠償実務では、各事案によって詳しく計算していくのですが、この自動計算機でおおまかな金額を知ることができますので、ぜひ活用してください。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠