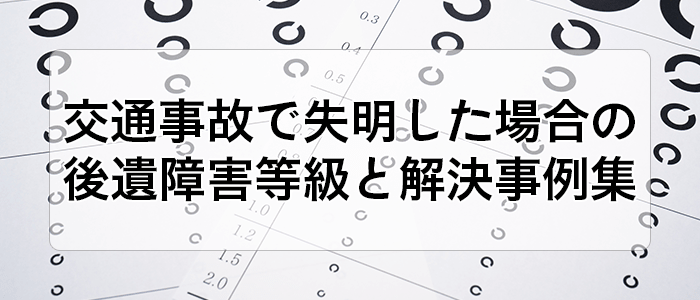交通事故で失明(視力低下)した場合の後遺障害等級と解決事例集
*タップすると解説を見ることができます。
交通事故の傷害(ケガ)により、被害者の方が
失明という障害を負うことがあります。
この場合、将来に渡って重大な影響がありますので、その損害を十分な慰謝料等で補償してもらわなければなりません。
しかし、交通事故で後遺症を負った被害者の方とご家族にとっては何をどうすればいいのか、わからないことばかりだと思います。
ここでは、交通事故で失明という重大な後遺障害を負ってしまった被害者の方とご家族のために、後遺障害等級認定の仕組みから示談交渉、慰謝料などの損害賠償金の増額事例までを解説していきます。
失明の場合に認定される
後遺障害等級一覧
後遺障害等級認定における失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、あるいは明暗を区別できないか、もしくはようやく明暗を区別できる状態をいいます。
視力障害の視力とは、矯正視力をいい、万国式試視力表によります。これには、眼鏡による矯正、医学的に装用可能なコンタクトレンズまたは眼内レンズによる矯正が含まれます。
失明で認定される後遺障害等級には次のものがあります。
後遺障害等級1級1号
(自賠法別表第2)
・両眼が失明したもの
・自賠責保険金額:3,000万円
・労働能力喪失率:100%
後遺障害等級2級1号
(自賠法別表第2)
・一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下に
なったもの
・自賠責保険金額:2,590万円
・労働能力喪失率:100%
※視力については裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズを使用した矯正視力であることに注意(以下同)
後遺障害等級3級1号
(自賠法別表第2)
・一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下に
なったもの
・自賠責保険金額:2,219万円
・労働能力喪失率:100%
後遺障害等級5級1号
(自賠法別表第2)
・一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下に
なったもの
・自賠責保険金額:1,574万円
・労働能力喪失率:79%
後遺障害等級7級1号
(自賠法別表第2)
・一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に
なったもの
・自賠責保険金額:1,051万円
・労働能力喪失率:56%
後遺障害等級8級1号
(自賠法別表第2)
・一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下に
なったもの
・自賠責保険金額:819万円
・労働能力喪失率:45%
※障害が残った眼が左眼か右眼かの区別はないことに注意
自賠責の後遺障害認定は、原則として、労災補償の災害補償の障害認定基準に準拠すべきとされています。
参考記事:眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省)
視力障害で因果関係が争われた
裁判例
視力障害については、裁判で因果関係が争われることも多いので、ここでは、視力障害について争われた裁判例をご紹介します。
(1)視力障害で因果関係を
否定した裁判例
交通事故直後に視力低下を訴えておらず、事故後3ヶ月ほど経過した時点で大型免許の更新ができており、事故後4ヶ月を経過したころからはじめて視力低下を訴えた、という事案です。
裁判所は、視力低下の訴えには合理的な疑いが残ること、仮に視力障害が生じていたとしても、前回の事故の影響がある疑いが濃い、として、交通事故と視力低下の因果関係を否定しました(東京地裁平成8年10月30日判決、出典:交民29巻5号1570頁)。
【本判決の分析】
本判決では、交通事故と視力障害との因果関係の立証責任が原告側にあることを前提に、原告が提出した証拠では視力低下が立証しきれていない、と判断されたものと考えられます。
(2)視力障害で因果関係を
肯定した裁判例
交通事故から約2年後に発症した視力低下に伴った黄斑円孔による網膜はく離について、因果関係を争われた事案です。
裁判所は、事故によって眼球を打撲したことで事故直後から視力が低下し、組織変性などが一層進行して突発性黄斑円孔、さらには網膜はく離に至ったと認められるとして、交通事故との因果関係を認めました(大阪地裁平成12年8月25日判決、出典:交民33巻4号1335頁)。
【本判決の分析】
本判決では、事故直後からの症状の経過を重視して、交通事故と後遺障害との因果関係を認めたものと考えられます。
視力障害で減収がないことから
争われた裁判例
視力障害の後遺障害が残った場合、物が見えにくくなることから、労働に支障が出て、収入の減少につながる場合、逸失利益の請求をすることができます。
しかし、逸失利益は、将来の収入の減少分の補填となりますので、将来の収入が減少する蓋然性を原告側で立証することが必要です。
この点、被害者の収入が減少していない場合には、逸失利益が争われることがあります。
そこで、この点が争われた裁判例をご紹介します。
左視束管骨折、左上腕骨開放骨折等のケガを負い、視力障害の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級9級2号が認定されました。
後遺障害等級9級の労働能力喪失率は35%であるところ、裁判所は、労働能力喪失率20%を認めました。
理由としては、
- ・被害者が会社役員・参事として当面は
後遺障害に基づく減収が存在しない - ・労働実態は、本件事故に遭わなかったとした場合に可能であると推測される
労働内容と比較すれば低下している - ・給与は寡婦である原告への生活保証の趣旨も含まれていると評価できる
- ・退職後の再就職を含めた就労に制約がある
などの理由から、収入の減少がみられないことを考慮しても20%の労働能力の喪失があるとしました(東京地裁平成12年11月6日、出典:自保ジャーナル1402号)
【本判決の分析】
本判決は、被害者に減収がないことから自賠責後遺障害等級どおりの労働能力喪失率は認められないことを前提として、事実認定により実態に即した労働能力喪失率を認めたものと考えられます。
みらい総合法律事務所の
慰謝料増額解決事例集
次に、みらい総合法律事務所で実際に解決した事例について解説します。
実際の交通事故の示談交渉の現場は、どのように進んでいくのか?
示談交渉に弁護士が入ると、どんなことが起きるのか?
ご自身の状況や状態と照らし合わせながら、事例を参考にしてみてください。
増額事例①:28歳男性が
慰謝料等で6,550万円超を
獲得
28歳の男性が、交通事故で失明などの後遺症を負った事例です。
被害者男性は右眼球破裂、右涙道閉塞などの傷害を負い、右眼失明、流涙、右眼まぶたの著しい運動障害、外貌醜状などの後遺症が残り、症状固定しました。
そこで、自賠責後遺障害等級認定の申請をしたところ併合7級が認定され、被害者の方は後遺障害が重いことから、みらい総合法律事務所に示談交渉のすべてを依頼されました。
加害者側の任意保険会社と示談交渉を進めたものの成立に至らなかったために弁護士が提訴。
裁判では弁護士の主張が認められ、最終的には6,551万円で解決に至りました。
増額事例②:32歳男性の
慰謝料等が5,500万円で
解決!
32歳の男性が頭部や眼に障害を負った交通事故。
治療をしましたが症状固定したため、被害者男性が自賠責後遺障害等級認定に申請したところ、脳挫傷痕で12級13号、失明と視力障害で8級1号、眼瞼運動障害で12級2号の併合7級が認定されました。
被害者の方は自力での示談交渉では解決は難しいと感じ、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉の解決を依頼しました。
弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を進めたところ、結果的に示談金が5,500万円で解決したものです。
【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら
交通事故による失明でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
【動画解説】失明・視力低下の後遺障害等級と慰謝料請求のポイント
代表社員 弁護士 谷原誠