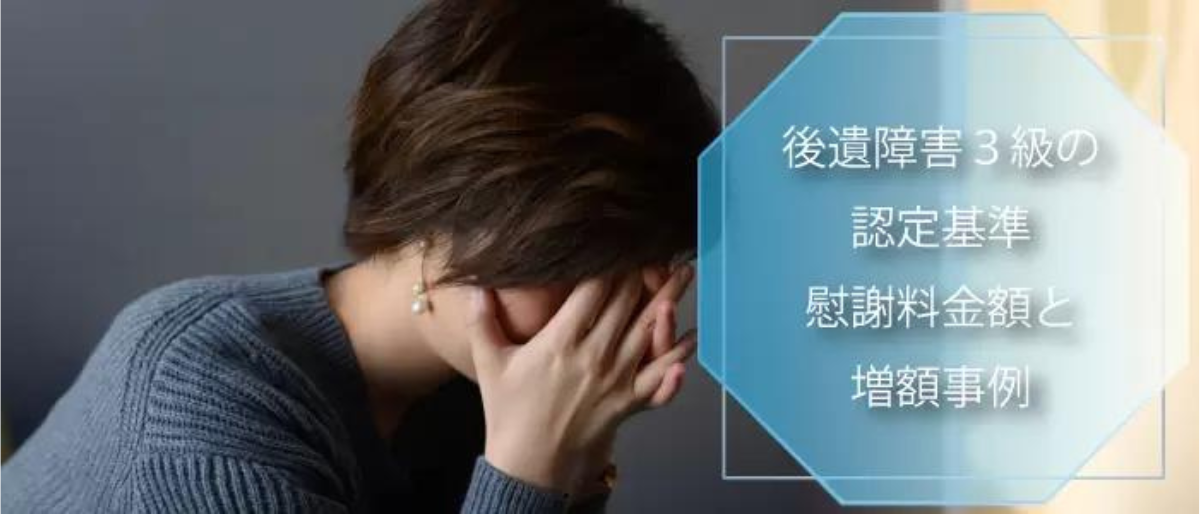後遺障害3級の認定基準・慰謝料金額と増額事例
後遺障害3級は、
- ・眼や口の機能障害
- ・手指の欠損
- ・胸腹部の機能障害
- ・高次脳機能障害
などが残ってしまった場合に認定されます。
重い後遺障害が残ってしまうため、労働能力喪失率は100%です。
また、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料は、1,190万円になります。
後遺障害3級が認定された被害者の方とご家族は、まず次の2つのことを確認してください。
- 正しい後遺障害等級が認定されているか
- 適正な相場金額の慰謝料等が提示されているか
本記事では、これらのことを確認していきながら、後遺障害3級が認定される場合の後遺症の症状や認定基準、慰謝料等の損害賠償金額などについて、みらい総合法律事務所で実際に増額解決した事例と合わせて解説していきます。
交通事故で後遺障害等級認定を受けた場合の慰謝料の相場
後遺障害等級が決まると、慰謝料などの損害賠償金額が提示され、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。
被害者の方が受け取ることができる慰謝料には以下の2つがあります。
傷害(ケガ)の治療のために入通院した時の精神的な苦痛を慰謝するためのもの。
・後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
今後の人生で後遺症(後遺障害)を抱えたまま生きていかなければならないことに対する、精神的な苦痛を慰謝するためのもの。
すでに保険会社から示談金(損害賠償金)の提示がある場合は、その内訳の中で後遺障害慰謝料の欄を見てください。
金額が以下の基準を満たしていない場合は、「低すぎるのではないか」と疑ってください。
(※等級をクリックすると、各等級の詳細ページを表示します。)
「裁判基準による後遺障害慰謝料の相場金額」
| 後遺障害等級 | 慰謝料 |
|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 |
| 第2級 | 2,370万円 |
| 第3級 | 1,990万円 |
| 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 |
| 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
後遺障害等級3級の後遺障害慰謝料は1,990万円です。
これより低いなら、それは適正な金額ではないということになります。
【出典】:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)
後遺障害3級の認定基準と保険金限度額
| 後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
|---|---|
| 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 5. 両手の手指の全部を失ったもの |
2,219万円 |
第3級1号
失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、あるいは明暗を区別できないか、もしくはようやく明暗を区別できる状態をいいます。
3級1号は、片方の眼の視力を完全に失い、かつ失明していない方の眼の視力が裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズで矯正しても0.06以下の場合に認定されます。
第3級2号
咀嚼(そしゃく)とは、食べ物をよく噛んで飲み込むことです。
事故によって顎(あご)の骨や筋肉、神経などに傷害を負ったことで、咀嚼機能を失い、スープなどの流動食しか食べられなくなった状態です。
言語機能については、1級2号と同様に4つの子音(口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音)のうち3つ以上発音できない場合に認められます。
この2つのどちらかの障害が残った場合、3級2号に認定されます。
両方の傷害がある場合は、1級2号となります。
第3級3号
3級3号では、麻痺の場合には、以下の症状が該当します。
②中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
つまり、脳や神経に障害があるものの、日常生活では随時介護がなくても食事や入浴、排泄などはできる状態です。
高次脳機能障害で3級3号が認定されるのは、自宅周辺を1人で外出できても、記憶力や注意力、学習能力、人間関係維持能力などの低下があるため、 一般就労は難しい状態です。
なお、高次脳機能障害による記憶力や注意力などの低下や性格の変貌などはわかりにくいため、認定に時間がかかることもあります。
また、外傷性てんかんとなり、発作による精神障害のために終身労務が難しい場合も3級3号に認定されます。
第3級4号
呼吸器、循環器、腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腹壁瘢痕ヘルニア等)、泌尿器、生殖器の障害などにより日常生活や自宅周辺の散歩などはできても、生涯にわたって仕事に就くことができない場合、3級4号に認定されます。
第3級5号
両手の指をすべて失ったものが該当します。
指は根元から失った場合はもちろん、親指の場合は第1関節から、その他の指は第2関節から失ったケースでも3級5号が認定されます。
みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集
交通事故における実際の示談交渉では、加害者側の保険会社からどのくらいの金額の示談金(損害賠償金)が提示されるものなのでしょうか?
そして、弁護士が示談交渉に入ることで、どのくらいの増額を獲得することができるのでしょうか?
示談交渉の経験のない被害者の方は、よくわからず不安に感じると思います。
ここでは、みらい総合法律事務所が依頼を受け、実際に慰謝料などの増額を勝ち取った自賠責後遺障害等級3級の解決事例についてご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせて、参考にしていただければと思います。
増額事例①:支払い拒絶から約1,000万円の増額
72歳の女性が、信号機のない交差点を原付バイクで走行中に起きた交通事故です。
女性は外傷性脳損傷などを負い、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまいました。
後遺障害3級3号が認定され、ケガの治療後に女性は治療費や自賠責保険金で合計約2,300万円を受け取りました。
その後、被害者女性は加害者側の任意保険会社に対して、残りの損害賠償金の請求をしましたが、保険会社の回答は、「被害者側の過失が大きいため、既に支払い済みの金額で十分と考え、これ以上の支払いは拒絶する」というものでした。
納得のいかない被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉を依頼しました。
弁護士が交渉したところ、保険会社は被害者側の過失が65%あるとして支払いを拒否してきたため、訴訟を提起して裁判に突入しました。
裁判では弁護士の過失割合の主張が採用されて、最終的には45%と認定されたことで、追加の損害賠償金として約1,000万円が認められました。
増額事例②:70歳女性が約1,300万円の増額を獲得
交通事故被害のため、70歳の女性が脳挫傷などを負い、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまいました。
後遺障害等級認定を申請したところ3級が認定され、加害者側の保険会社は既払いの治療費などの他に約2,400万円の示談金を提示してきました。
この金額が適切なものかどうか判断ができなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の回答は「まだ増額は可能」というものだったので、そのまま示談交渉を依頼しました。
弁護士と加害者側保険会社の示談交渉では、慰謝料や将来介護費用などについて争われましたが、最終的には満額での合意に達し、約1,300万円増額の約3,700万円で解決した事例です。
増額事例③:69歳女性が約2,500万円の増額を獲得
69歳の女性が交通事故の被害で頭部外傷、脊椎圧迫骨折などを負ってしまった事例です。
被害者女性は、高次脳機能障害の後遺症で後遺障害5級2号、脊柱運動障害の後遺症で8級2号、併合で3級が認定されました。
これに対し、加害者側の保険会社は約2,900万円の示談金を提示。
この金額に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所に相談し、そのまま示談解決を依頼しました。
示談交渉では、粘り強く交渉した弁護士の主張を保険会社が受け入れ、約2,500万円増額の約5,400万円で解決しました。
【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら
後遺障害3級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
詳しい動画解説はこちら
代表社員 弁護士 谷原誠