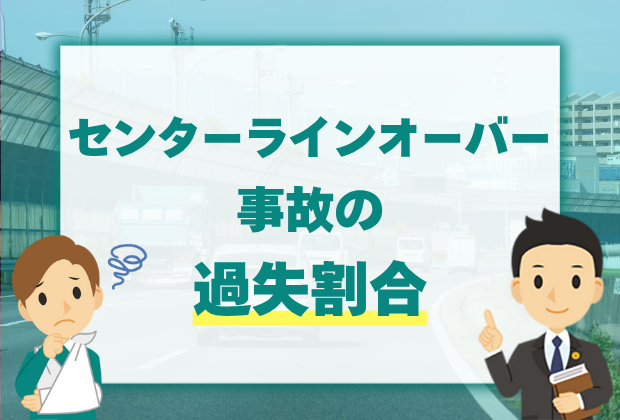後遺障害13級の認定基準・慰謝料金額と増額事例
後遺障害13級は、眼、歯、手足の指、胸腹部の機能障害などが残ってしまった場合に認定されます。
認定条件は多岐にわたり、1号から11号までが設定されています。
最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料は180万円になります。
後遺障害13級が認定された被害者の方は、次の2つのことを最初に確認してください。
- 後遺障害等級と認定理由を確認!本当に正しい等級か?
- 慰謝料は適切な相場金額が提示されているか?
本記事では、後遺障害等級13級に該当する場合の後遺症の症状や認定基準、慰謝料等の損害賠償金額などについて、みらい総合法律事務所で実際に増額解決した事例を交えながら解説していきます。
交通事故で後遺障害等級認定を受けた場合の慰謝料の相場
後遺障害等級が決まると、慰謝料などの損害賠償金額が提示され、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。
被害者の方が受け取ることができる慰謝料には以下の2つがあります。
傷害(ケガ)の治療のために入通院した時の精神的な苦痛を慰謝するためのもの。
・後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
今後の人生で後遺症(後遺障害)を抱えたまま生きていかなければならないことに対する、精神的な苦痛を慰謝するためのもの。
すでに保険会社から示談金(損害賠償金)の提示がある場合は、その内訳の中で後遺障害慰謝料の欄を見てください。
金額が以下の基準を満たしていない場合は、「低すぎるのではないか」と疑ってください。
(※等級をクリックすると、各等級の詳細ページを表示します。)
「裁判基準による後遺障害慰謝料の相場金額」
| 後遺障害等級 | 慰謝料 |
|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 |
| 第2級 | 2,370万円 |
| 第3級 | 1,990万円 |
| 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 |
| 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
後遺障害等級13級の後遺障害慰謝料は180万円です。
これより低いなら、それは適正な金額ではないということになります。
【出典】:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)
後遺障害等級13級の認定基準と保険金額
後遺障害等級13級は、眼や歯、指、内臓などの障害について細かく11に分類されています。
13級の労働能力喪失率は9%と、かなり低く設定されていることからもわかるように、後遺障害の程度としては軽いほうのレベルと判断されます。
また、この等級の後遺障害は医師の診断からも客観的に判断しやすいものも多いといえるでしょう。
「後遺障害等級13級の認定基準及び保険金限度額」
<自賠法別表第2>
| 後遺障害 | 保険金 (共済金) |
|---|---|
| 1.一眼の視力が0.6以下になったもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげ を残すもの 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.一手のこ指の用を廃したもの 7.一手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失った もの 10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足 指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指 以下の三の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
139万円 |
第13級1号
交通事故による傷害(ケガ)で、片方の眼の矯正視力が0.6以下になってしまった場合、13級1号が認定されます。
正常な状態でも、少し視力が落ちた人の中には、0・6の視力の人もいると思いますが、ここでは裸眼ではなく矯正視力であることに注意が必要です。
ちなみに、両眼の矯正視力が0.6以下になってしまった場合は9級1号に認定されます。
第13級2号
正面以外を見た時に、「複視」の症状が残る場合は13級2号に認定されます。
複視とは、ものが二重に見える状態をいい、頭痛やめまいが起きることなどから日常生活に困難が生じる場合があります。
両眼で見た時に、ものが二重に見え、片方の眼で見た時はひとつに見える状態を「両眼複視」、片方の眼で見た時に二重に見えるものを「単眼複視」といいます。
これらの症状は、頭部の外傷や眼の周囲の骨折などにより、眼球の動きをコントロールする神経や筋肉に障害が残ることで起きるものです。
なお、正面を見た時に複視の症状が残る場合は10級2号に認定されます。
第13級3号
視神経への障害のために、片方の眼に「半盲症」、「視野狭窄」、「視野変状」の症状が残ってしまった場合に13級3号が認定されます。
これら3つの症状は視力自体が失われることで起きるものではなく、ものの見え方や視野に障害が残る症状です。
半盲症とは視界の一部、たとえば片方の眼の視界全体のうち右半分、あるいは左半分が見えなくなるものです。
視野狭窄とは、視野の一部が見えなくなるのではなく、視野自体が周辺から狭くなってしまう症状です。
また、視野の中に部分的に見えない部分ができ、穴が開いた状態のように見えなくなるものを視野変状といいます。
第13級4号
まぶたの障害には欠損障害と運動障害がありますが、13級4号では欠損障害が該当します。
両眼のまぶたの一部に欠損を残した場合とは、普通にまぶたを閉じた時に黒目は隠れるものの、角膜が完全に覆われず白目の一部が露出してしまう状態をいいます。
また、まぶたの障害の有無に関わらず、まつ毛の半分以上を失った場合もこの等級に該当します。
第13級5号
交通事故による傷害で、5本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合に13級5号が認定されます。
人間の永久歯は、上下それぞれ14本ずつの計28本ありますが、そのうちの約5分の1以上に障害が残った状態ということになります。
歯科補綴とは、差し歯や入れ歯、クラウン、ブリッジ、インプラントなどで欠損した歯の機能や見た目を治療することで、こうした歯科補綴を施した歯に対して等級が認定されることになります。
なお、14本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために歯科補綴をした場合は10級4号、10本以上の場合は11級4号、7本以上の場合は12級3号がそれぞれ認定されます。
第13級6号/7号
片方の手の小指の用を廃した場合は13級6号に認定されます。
この場合は、以下のような症状が該当します。
- ・小指の第一関節より先の骨(末節骨)を失い、長さが2分の1以下になった場合
- ・小指の根元、または第二関節の可動域が2分の1以下になった場合
- ・小指の感覚を失ってしまった場合
また、片方の手の親指の骨の一部を失った場合、あるいは骨がつかずに「遊離骨折」した場合は13級7号に認定されます。
なお、右手か左手か、利き手かどうかによる区別はありません。
第13級8号
交通事故による傷害のために片方の足の長さが1cm以上(3cm未満まで)短縮してしまった場合は13級8号に認定されます。
なお、5cm以上短縮してしまった場合は8級5号、3cm以上(5cm未満まで)短縮してしまった場合は10級8号になります。
第13級9号/10号
片方の足の中指、薬指、小指の3本のうち、1本もしくは2本の指を第一関節から根元の間で失ってしまった場合、13級9号に認定されます。
また、①片方の足の指のうち人差し指の用を廃した場合、②人差し指を含む2本の指の用を廃した場合、③中指と薬指と小指の指の用を廃した場合、13級10号に認定されます。
詳しくまとめると、次のようになります。
- 片方の足の人差し指が、根元から第一関節の間で切断した場合や、可動域が2分の1以下になった場合
- 片方の足の人差し指に加えて、中指・薬指・小指のうちの1本が、根元から第一関節の間で切断した場合や、可動域が2分の1以下になった場合
- 片方の足の中指・薬指・小指の3本が、根元から第一関節の間で切断した場合や、可動域が2分の1以下になった場合
第13級11号
胸腹部臓器の機能に障害が残った場合は13級11号に認定されます。
具体的には以下のような症状が該当します。
- ・胃の全部、あるいは一部を切除した場合
- ・胆のうを失った場合
- ・脾臓を失った場合
- ・腎臓を失うか、腎臓の機能を著しく失った場合
- ・生殖器のうち、片方の睾丸、卵巣を失った場合
被害者の方が気をつけなければいけないことの1つは、認定された等級が間違っている場合です。
後遺障害等級が1級分でも違っただけで、慰謝料や逸失利益などを合計した損害賠償金額が数百万円も低くなってしまうことがあります。
ですから、万が一ご自身が認定された後遺障害等級に不満があるのであれば、決してあきらめてはいけません。
被害者の方には「異議申立」をする権利が認められているからです。
異議申立について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集
ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した「自賠責後遺障害等級13級」の増額事例をご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら参考にしてください。
みらい総合法律事務所の増額事例①:40歳男性が慰謝料等で約1,730万円獲得
40歳の男性会社員が自転車で走行中、後方から進行してきた自動車に追突された交通事故。
肩関節の脱臼などの傷害を負い、被害者男性には左滑車神経麻痺にともなう眼球運動障害で13級2号、左肩痛で14級9号、併合で13級の後遺障害等級が認定されました。
被害者の方は、加害者側の保険会社との示談交渉をどのように進めていけばいいのかわからなかったため、みらい総合法律事務所にすべてを委任。
保険会社との交渉で弁護士は、弁護士(裁判)基準による逸失利益を主張し、これらが認められたことで最終的には約1,730万円で和解することになった事例です。
みらい総合法律事務所の増額事例②:35歳男性の慰謝料等が約3.2倍に増額!
原付バイクで直進していた35歳の男性に、右折してきた自動車が衝突した交通事故。
被害者男性には、右小指基節骨骨折の傷害の他に、左足背皮膚潰瘍後の左足関節前方肥厚性瘢痕などの後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級は13級6号と14級5号の併合13級が認定されました。
加害者側の保険会社からは、既払い金の他に、慰謝料などの損害賠償金として約190万円が提示されましたが、この金額の妥当性に疑問を感じた被害者男性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼することにしました。
弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴し、裁判では最終的に600万円が認められました。
当初提示額から約3.2倍に増額したことになります。
【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら
後遺障害13級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
【参考動画】 後遺障害等級13級の認定基準と慰謝料の動画解説
【動画解説】交通事故の被害者が、後遺障害等級を確実に獲得していく方法
代表社員 弁護士 谷原誠






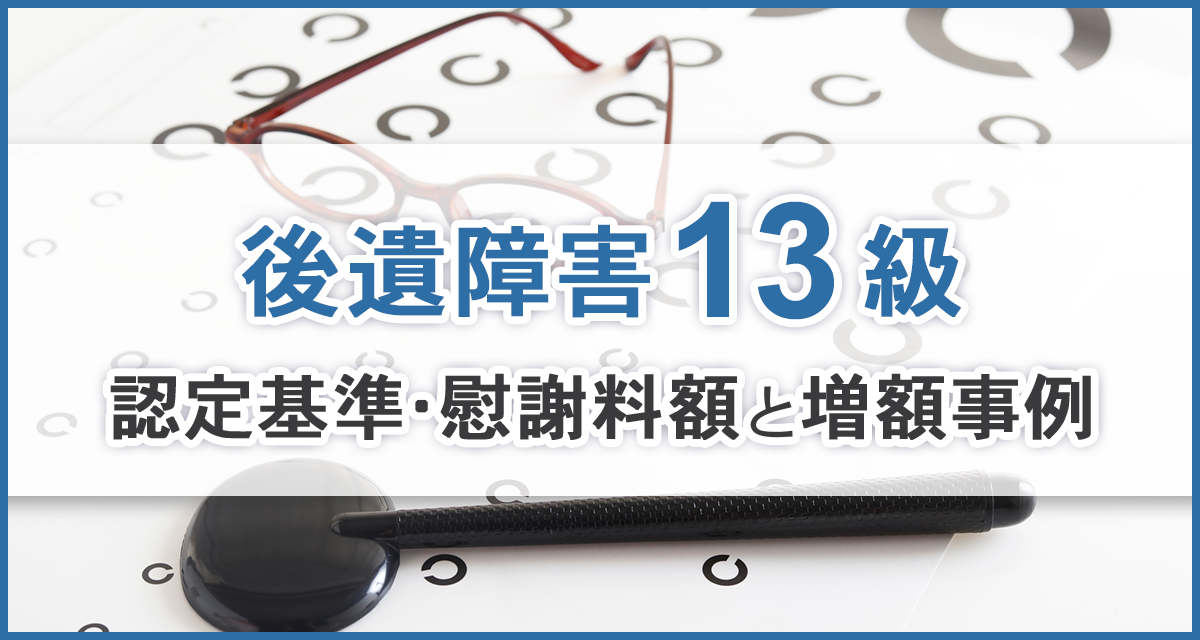












の後遺障害等級.png)