下肢(股関節から足指まで)の欠損・変形・短縮の後遺障害
交通事故で下肢に傷害(ケガ)を負って、欠損や変形、短縮などの後遺障害が残ってしまう、つまり下肢機能障害になってしまった場合、後遺障害等級で何級が認定されるのかを中心に解説していきます。
足に障害を負うと、その後の生活で不自由を強いられてしまいます。
すると、仕事も制限されてしまうため、収入の問題も起きてきます。
これからの自分の人生、家族の将来など心配や不安は尽きないでしょう。
そこで重要なのが、認定される後遺障害等級です。
というのは、後遺障害等級によって慰謝料などの損害賠償金(保険金)が大きく変わってくるからです。
本記事では、下肢に残った後遺障害の種類別、認定された後遺障害等級別に保険金額などについてもお話ししていきます。
下肢とはどこからどこまでなのか?
下肢というと足のことだとわかると思います。
では、医学的にはどこからどこまでが下肢になるのかというと、股関節から大腿部 (だいたいぶ)、膝(ひざ)、脛(すね)、足首、足指まで、ということになります。
足、脚に関する骨の名称と読み方、簡単な説明は以下になります。
| 漢字名 | 読み方 | 説明 |
|---|---|---|
| 大腿骨 | だいたいこつ | 太ももの骨で、人体で 最も長くて太い骨 |
| 膝関節 | ひざかんせつ (しつかんせつ) |
太ももとすねの間にある 関節(「ひざ」) |
| 膝蓋骨 | ひざがいこつ (しつがいこつ) |
膝の前にある丸い骨 (「ひざのお皿」) |
| 脛骨 | けいこつ | すねの前側にある太い骨 |
| 腓骨 | ひこつ | 脛骨の外側にある細い骨 |
| 踵骨 | しょうこつ | かかとの骨 (足のかかとの部分) |
| 足根骨 | そっこんこつ | 足首やかかと周辺の小さな骨(距骨・踵骨など) |
| 中足骨 | ちゅうそくこつ | 足の甲にある骨(足指の 付け根部分に位置する) |
| 趾骨 | しこつ | 足指を構成する骨(1本の 足指に2~3個ずつある) |
骨格で見ると、股関節から大腿骨、膝関節、膝蓋骨、脛骨、腓骨、足関節とつながり、踵骨、足指の足根骨、中足骨、趾骨などで構成されています。
ちなみに、股関節の運動範囲は、上肢の肩関節より狭くなっています。
大腿骨は、いわゆる太ももの骨、脛(すね)の親指側にあるのが太いほうの脛骨で、小指側にあるのが細いほうの腓骨です。
参考資料:下肢の骨格(imidas)
下肢機能障害
(かしきのうしょうがい)とは?
下肢機能障害とは、足(つまり下肢)に関する関節や筋肉、神経などの機能が部分的、または全体的に失われている状態を指します。
具体的には、歩く、立つ、しゃがむ、階段の上り下りなど、日常生活での基本的な動作が困難になる障害のことを言います。
下肢の後遺症と後遺障害等級一覧
下肢の後遺障害は、次の4つに区分されます。
- 欠損障害
- 機能障害
- 変形障害
- 短縮障害
参考資料:肢体の障害(厚生労働省)
下肢(股関節から足首)の欠損による障害
下肢を切断して欠損した場合、その部位によって認定される後遺障害等級は次のようになります。
| 後遺障害の内容 | 両下肢を膝関節以上で失ったもの(両脚の股関節から膝関節の間) |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 3000万円 |
| 労働能力喪失率 | 100% |
後遺障害の内容 - 両下肢を膝関節以上で失ったもの
(両脚の股関節から膝関節の間) 自賠責保険金額 - 3000万円
労働能力喪失率 - 100%
| 後遺障害の内容 | 両下肢を足関節以上で失ったもの(両脚の膝関節から足首の間) |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 2590万円 |
| 労働能力喪失率 | 100% |
後遺障害の内容 - 両下肢を足関節以上で失ったもの
(両脚の膝関節から足首の間) 自賠責保険金額 - 2590万円
労働能力喪失率 - 100%
| 後遺障害の内容 | 一下肢を膝関節以上で失ったもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 1889万円 |
| 労働能力喪失率 | 92% |
後遺障害の内容 - 一下肢を膝関節以上で失ったもの
自賠責保険金額 - 1889万円
労働能力喪失率 - 92%
| 後遺障害の内容 | 一下肢を足関節以上で失つたもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 1574万円 |
| 労働能力喪失率 | 79% |
後遺障害の内容 - 一下肢を足関節以上で失つたもの
自賠責保険金額 - 1574万円
労働能力喪失率 - 79%
膝関節以上というのは、股関節から膝関節の間のことで、股関節と膝関節で切断した場合も含まれます。
足関節以上というのは、膝関節から足関節(足首)の間のことで、足首では脛骨・腓骨と距骨の間で切断した場合も含まれます。
足関節(足首)より下の欠損による障害
足関節(足首)より下の部分を切断して欠損した場合、その部位によって認定される後遺障害等級は次のようになります。
| 後遺障害の内容 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 1889万円 |
| 労働能力喪失率 | 92% |
後遺障害の内容 - 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
自賠責保険金額 - 1889万円
労働能力喪失率 - 92%
| 後遺障害の内容 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 1051万円 |
| 労働能力喪失率 | 56% |
後遺障害の内容 - 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
自賠責保険金額 - 1051万円
労働能力喪失率 - 56%
リスフラン関節とは、足の甲の中間あたりにある関節です。
下肢(股関節から足関節)の
変形による障害
下肢の骨折などの傷害のため、骨が変形してしまった場合は、その部位によって認定される後遺障害等級は次のようになります。
| 後遺障害の内容 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 1051万円 |
| 労働能力喪失率 | 56% |
後遺障害の内容 - 一下肢に偽関節を残し、
著しい運動障害を残すもの 自賠責保険金額 - 1051万円
労働能力喪失率 - 56%
| 後遺障害の内容 | 一下肢に偽関節を残すもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 819万円 |
| 労働能力喪失率 | 45% |
後遺障害の内容 - 一下肢に偽関節を残すもの
自賠責保険金額 - 819万円
労働能力喪失率 - 45%
| 後遺障害の内容 | 長管骨に変形を残すもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 224万円 |
| 労働能力喪失率 | 14% |
後遺障害の内容 - 長管骨に変形を残すもの
自賠責保険金額 - 224万円
労働能力喪失率 - 14%
<偽関節とは?>
偽関節とは、骨折部分が治癒していく過程で正常に骨がつかなかったために、その部分が関節のようにグラグラと動く状態になってしまったものです。
そのため、手足を動かすことが困難になります。
偽関節により著しい運動障害を残すものというのは、原則として、つねに硬性補装具を必要とする状態になります。
<長管骨とは?>
長管骨とは、手足を構成する骨のうち、比較的大きく、細長い骨のことです。
中が空洞の管状であることから、長管骨と呼ばれます。
下肢では、「大腿骨」、「脛骨」「腓骨」が該当します。
下肢(股関節から足関節)の
短縮による障害
交通事故の傷害(ケガ)によって下肢の短縮があった場合は、その長さによって次のような後遺障害等級が認定されます。
| 後遺障害の内容 | 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 819万円 |
| 労働能力喪失率 | 45% |
後遺障害の内容 - 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
自賠責保険金額 - 819万円
労働能力喪失率 - 45%
| 後遺障害の内容 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 461万円 |
| 労働能力喪失率 | 27% |
後遺障害の内容 - 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
自賠責保険金額 - 461万円
労働能力喪失率 - 27%
| 後遺障害の内容 | 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 139万円 |
| 労働能力喪失率 | 9% |
後遺障害の内容 - 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
自賠責保険金額 - 139万円
労働能力喪失率 - 9%
足指の後遺症と後遺障害等級一覧
足指の欠損による障害
足指を切断して欠損した場合、その部位によって認定される後遺障害等級は次のようになります。
| 後遺障害の内容 | 両足の足指の全部を失ったもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 1574万円 |
| 労働能力喪失率 | 79% |
後遺障害の内容 - 両足の足指の全部を失ったもの
自賠責保険金額 - 1574万円
労働能力喪失率 - 79%
| 後遺障害の内容 | 一足の足指の全部を失ったもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 819万円 |
| 労働能力喪失率 | 45% |
後遺障害の内容 - 一足の足指の全部を失ったもの
自賠責保険金額 - 819万円
労働能力喪失率 - 45%
| 後遺障害の内容 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 616万円 |
| 労働能力喪失率 | 35% |
後遺障害の内容 - 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
自賠責保険金額 - 616万円
労働能力喪失率 - 35%
| 後遺障害の内容 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 461万円 |
| 労働能力喪失率 | 27% |
後遺障害の内容 - 一足の第一の足指又は
他の四の足指を失ったもの 自賠責保険金額 - 461万円
労働能力喪失率 - 27%
| 後遺障害の内容 | 一足の第二の足指を失ったもの 第二の足指を含み二の足指を失ったもの 又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 224万円 |
| 労働能力喪失率 | 14% |
後遺障害の内容 - 一足の第二の足指を失ったもの
第二の足指を含み二の足指を失ったもの
又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 自賠責保険金額 - 224万円
労働能力喪失率 - 14%
| 後遺障害の内容 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 139万円 |
| 労働能力喪失率 | 9% |
後遺障害の内容 - 一足の第三の足指以下の一
又は二の足指を失ったもの 自賠責保険金額 - 139万円円
労働能力喪失率 - 9%
☑足指の切断は、指の付け根である中足指関節から失ったものになります。
☑後遺障害等級の世界では、足指は親指が第一の足指になり、順に第二、第三となります。
足指の用を廃した障害
(機能障害)
足指の用を廃した、というのは次のような場合が該当します。
- ・第一の足指(親指)の末節骨を2分の1以上失った
- ・第一の足指以外の足指を中節骨で切断した
- ・第一の足指以外の足指を基節骨で切断した
- ・第一の足指以外の足指を遠位指節間関節
(第1関節)で離断した - ・第一の足指以外の足指を近位指節間関節
(第2関節)で離断した - ・第一の足指の指節間関節の可動域が通常の
関節と比べて2分の1以下に制限された - ・第一の足指以外の足指の中足指節間関節
(指の根元の関節)、または
近位指節間関節の可動域が通常の関節と比べて2分の1以下に制限された
| 後遺障害の内容 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 1051万円 |
| 労働能力喪失率 | 56% |
後遺障害の内容 - 両足の足指の全部の用を廃したもの
自賠責保険金額 - 1051万円
労働能力喪失率 - 56%
| 後遺障害の内容 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 616万円 |
| 労働能力喪失率 | 35% |
後遺障害の内容 - 一足の足指の全部の用を廃したもの
自賠責保険金額 - 616万円
労働能力喪失率 - 35%
| 後遺障害の内容 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 224万円 |
| 労働能力喪失率 | 14% |
後遺障害の内容 - 一足の第一の足指又は
他の四の足指の用を廃したもの 自賠責保険金額 - 224万円
労働能力喪失率 - 14%
| 後遺障害の内容 | 一足の第二の足指の用を廃したもの 第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足 指の用を廃したもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 139万円 |
| 労働能力喪失率 | 9% |
後遺障害の内容 - 一足の第二の足指の用を廃したもの
第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足
指の用を廃したもの 自賠責保険金額 - 139万円
労働能力喪失率 - 9%
| 後遺障害の内容 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
|---|---|
| 自賠責保険金額 | 75万円 |
| 労働能力喪失率 | 5% |
後遺障害の内容 - 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
自賠責保険金額 - 75万円
労働能力喪失率 - 5%
下肢の後遺障害でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠





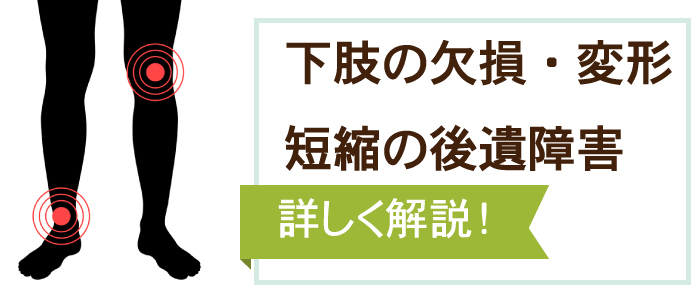





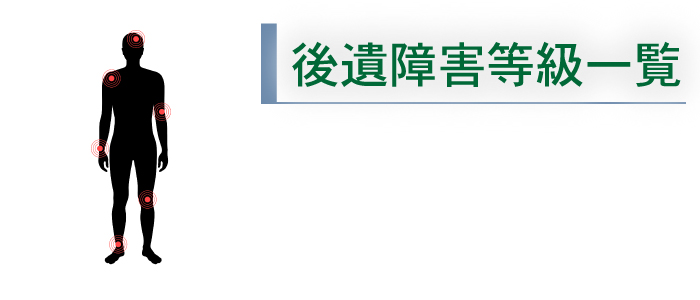







の後遺障害等級.png)

