事例でわかる!交通事故で弁護士に依頼するメリットとデメリット
交通事故の被害で重大な後遺障害が残ってしまった場合、被害者の方やそのご家族は苦しみや悲しみが癒えぬまま、さまざまな手続きなどに追われてしまいます。
その時、心強いパートナーになるのが弁護士です。
しかし、弁護士というと、どこか遠い存在のようで相談しにくいと感じる方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、交通事故を弁護士に相談した場合のメリットと同時にデメリットもあります。
そこで今回は、みらい総合法律事務所に寄せられた実話をもとに、交通事故の示談交渉を弁護士に相談するメリットとデメリットについて解説していきます。
目次
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットとデメリットとは?
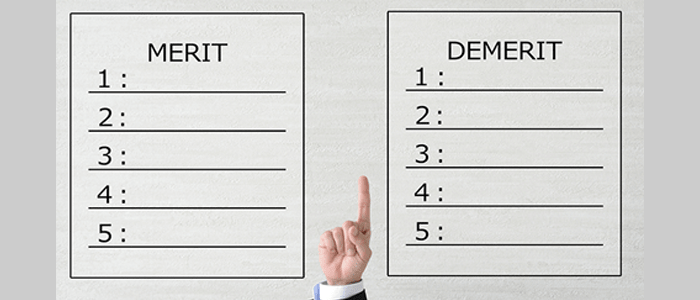
交通事故の損害賠償金の示談交渉を弁護士に依頼した場合にはメリットとデメリットがあります。
まず、メリットとしては主に次のことがあげられます。
- ①慰謝料などの損害賠償金が増額して正しい金額を手にすることができる
- ②加害者側の保険会社との煩わしい示談交渉から解放される
- ③自分で行なうよりも示談交渉を有利に進めることができる
- ④相談料や着手金が無料であれば負担が少なく相談・依頼しやすい
デメリットとしては、やはり費用がかかってしまうことでしょう。
しかし、最近では相談料や着手金を無料にしている法律事務所も増えています。
もちろん、みらい総合法律事務所でも相談料は無料、そして原則として、弁護活動に必要な費用としての着手金というのもいただいていません。
完全成功報酬として、示談金が増額した場合のみ報酬金をいただき、それ以外はすべて0円というシステムになっています。
ただし、物損事故やケガの程度が軽い事故の場合は弁護士費用が増額分を上回ってしまう「費用倒れ」になってしまう場合があるので注意が必要です。
この場合は弁護士に依頼することがメリットからデメリットに変わってしまいます。
なお、被害者ご本人が加入している自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」がついていれば、300万円までの弁護士費用が支払わる場合がありますので、こちらも確認するとよいと思います。
弁護士に相談するメリットとデメリットを考えた場合、まずは無料相談を利用して弁護士の意見を参考にしながら、最終的に依頼するかどうかを決めるというのがいいと思います。
ここからは、実際にみらい総合法律事務所に相談に来られた人の相談の流れを見ながら、弁護士に依頼するメリットがいかに大きいかを解説します。
突然の交通事故で人生が激変…後遺障害を背負う生活に

埼玉県某市在住のNさん(当時45歳)が交通事故の被害にあったのは2年前のことでした。
県道の交差点を歩行中、左折してきた乗用車に衝突されたのです。
土曜日の夕方、信号は青でした。
まさか自動車が突っ込んでくるとは夢にも思わなかったNさんは、ただ普通に横断歩道を歩いていたところ、突然ものすごい衝撃が体を襲ったのだそうです。
ほんの一瞬のことで、その時のことはよく覚えていないといいます。
意識が戻った時、Nさんは病院のベッドの上にいました。
妻と2人の子供は丸1日、付き添ってくれていたようで、意識が戻って初めて見たのは3人の心配そうな顔だったといいます。
診断では、幸い頭部の異常は見つかりませんでしたが、胸椎圧迫骨折の重傷でした。
Nさんには入院が必要で、しばらく寝たきりとなってしまいました。
数ヵ月後、担当医師から症状固定の診断を受けました。
症状固定とは、もうこれ以上の治療を続けてもケガが回復することも、完治することもないということです。
Nさんには後遺症が残ってしまい、まだ痛みが続いていましたが、交通事故についてやらなければいけない手続きがたくさんありました。
自分のことだけでなく、家族の将来への不安や心配もありました。
この頃は、Nさんにとって肉体的、精神的にかなりつらい時期だったようです。
ところで、交通事故の被害者の方が行なうべき手続きには、「後遺障害等級認定」の申請があります。
後遺障害等級は第1級から第14級まであり、後遺症の症状によって認定される等級が変わってきます。
第1級のほうが重く、慰謝料などの損害賠償金も高額になります。
Nさんが認定された後遺障害等級は8級2号の「脊柱に運動障害を残すもの」でした。
保険会社との示談交渉が始まるも難航…精神的に疲弊する
後遺障害等級が認定されると、保険会社との間で慰謝料などの損害賠償金の示談交渉が開始されます。
Nさんにとって交通事故は初めてのことでしたから、わからないことばかりでした。
もちろん、奥さんも両親も交通事故と保険についての知識は持っていませんでしたから、誰に相談することもできなかったといいます。
加害者からは謝罪の連絡は何もなく、一度もお見舞に来ませんでした。
その代わりに、加害者が加入している任意保険会社の担当者から連絡があり、示談金の金額の提示があったのです。
提示額は、約1,200万円。
正直なところ、その金額が正しいものなのかどうか、Nさんには判断がつきませんでした。
これまでの人生で、交通事故や損害賠償金とは無縁に生きていたNさんが正しい知識を身につけているわけはないのですから、それは無理もないことでした。
肉体的にも精神的にも苦痛を感じ、おまけに加害者への怒りも感じていたNさんは憤り、「その金額は正しい金額なのですか?」と保険会社の担当者に強い口調で問いました。
すると、その担当者は「この金額は当社が算出して、ご提示できる最高額です」と言うのです。
しかし、どうにも納得のいかないNさんは答えを保留。
その後、ネットなどで交通事故の損害賠償について調べ始めました。
ネットには、さまざまな情報がありました。
その中から、保険会社、法律事務所、まとめサイトなどをチェックしていくと、どうやら保険会社が提示してくる損害賠償金額は、被害者が実際に受け取ることができる金額よりも低いことが多い、ということがわかりました。
Nさんにとって、それからはまたつらい日々が続きました。
何度交渉を重ねても、保険会社の担当者が言ってくることは同じで、金額が上がることはありませんでした。
「弁護士に頼んでも同じですよ。これ以上は増額しません」などと言われたこともあったそうです。
次第にNさんは疲弊していきました。
交通事故でひどい目にあって、後遺障害が残り、肉体的、精神的につらいうえに、なぜ保険会社との示談交渉で苦労をしなければいけないのか……なぜ自分ばかりがこんなに苦しまなければいけないのか……。
Nさんは、らちの開かない示談交渉を続けていく気力を失っていきました。
そして、「もう限界だ……やはり専門家に相談してみよう」と思いました。
それでも、やはり気になるのは、弁護士に相談・依頼することのメリットとデメリットについてでした。
Nさんが、みらい総合法律事務の無料相談にいらしたのは、ちょうどその頃でした。
交通事故に強い弁護士事務所だからできる専門的できめ細かい対応
まず私は、ここまでの経緯をお聞きして、交通事故証明書や自賠責後遺障害診断書の写しなど、さまざまな必要書類に目を通させていただきました。
交通事故の被害者の方からのご相談で最初に弁護士が行なうことは、後遺障害等級に間違いがないかのチェックです。
後遺障害等級認定の手続きは、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)というところが行なっています。
そのため、被害者の方は損保料率機構に必要書類を提出して、認定申請をするのですが、その際に提出書類の内容に不備があったりすると正しい等級が認定されないということが起きるのです。
すると何が、どうなるのでしょうか?
間違った後遺障害等級の通りに審査が行なわれ、慰謝料などの損害賠償金も違った金額が提示されてしまいます。
等級が1級違っただけでも数百万円から、場合によっては数千万円も金額が違ってくるので、この等級は非常に大切なものです。
そのために、弁護士は正しい後遺障害等級が認定されているかどうかを、まず確認するのです。
Nさんの場合は、正しい後遺障害等級が認定されていました。
そこで、次に弁護士が行なうのが保険会社から提示されている損害賠償項目と金額の確認です。
じつは、損害賠償金にはさまざまな項目があります。
- ・治療費
- ・付添費
- ・将来介護費
- ・入院雑費
- ・通院交通費
- ・装具、器具等購入費
- ・家屋、自動車等改造費
- ・葬儀関係費
- ・死亡慰謝料
- ・休業損害
- ・傷害慰謝料
- ・後遺症慰謝料
- ・逸失利益
- ・修理費
- ・買替差額
- ・代車使用料 など
よく、慰謝料ということがいわれますが、項目例のように慰謝料は損害賠償金の一部ということになります。
これらの各項目について、正しい金額が算出され、提示されているかを弁護士は確認していきます。
とても一度で覚えきれるものではないですし、それぞれの項目について正しい金額を算出するのは、保険のプロや法律のプロなどの専門家でなければ難しいものです。
そして、もうひとつ難しい問題があります。
それは、加害者側の保険会社が提示してくる金額というのは、本来、被害者の方が受け取ることができる金額よりも低いことが多いということです。
じつは、損害賠償金の算定方法には、
- 「自賠責基準」
- 「任意保険基準」
- 「弁護士(裁判)基準」
という3つの基準があります。
自賠責基準がもっとも金額が低く、弁護士(裁判)基準がもっとも損害賠償金額が高くなります。
加害者側の保険会社は、任意保険基準で計算した金額を提示してくることがほとんどなので、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の中間くらいの金額になります。
これは被害者の方には、ほとんど知らされていないことだと思います。
任意保険会社は営利法人ですから、利益を上げるためにできるだけ支出となる被害者の方への支払金額を低くしようとします。
そのため、本来であれば被害者の方が受け取るべき金額よりも低い金額を提示してくるのです。
被害者の方が、いくら保険会社の担当者と示談交渉を行なっても、らちが開かずに平行線をたどってしまうことになるのは、こうした理由があるためです。
示談交渉というのは被害者の方が単独、独力で進めていくには難しい理由がおわかりいただけたかと思います。
煩わしい示談交渉から解放され、正しい損害賠償金を勝ち取るには?
私は、保険会社から提示された損害賠償金額は低いので、まだ十分に増額できると判断しました。
その事実を伝えると、Nさんは言いました。
「自分で示談交渉を行なって、満足のいく示談金を勝ち取るのは難しいことがわかりました。
それに私は……肉体的にも精神的にも、もうこれ以上……苦しみたくはありません。
弁護士さんにすべてをお願いします」
これまで多くの被害者弁護にあたってきた経験からもNさんの気持ちは痛いほどわかりました。
私たち弁護士は依頼を受けたなら、被害者の方のために精一杯、最善を尽くすのみです。
Nさんから依頼を受けた我々は、加害者側の保険会社との交渉を開始しました。
交渉では過失割合や逸失利益などが争点になりました。
過失割合とは、被害者と加害者の過失の割合を示すものです。
加害者の過失が大きいにも関わらず、被害者の過失を主張してくるのは保険会社の常とう手段です。
逸失利益とは、後遺障害を負わなければ被害者の方が将来的に得られていたであろう収入などの利益のことです。
まだまだ働き盛りのNさんが脊柱運動障害という重大な後遺症を負ったのですから、私たちは逸失利益が大きいことを主張していきました。
最終的には我々の主張が認められ、約3,600万円で示談が成立。
当初の保険会社提示額から、およそ3倍に増額して解決したことになります。
Nさんは言います。
「初めは弁護士に相談するなんて大げさだと思っていたのです。
それに、やはり高額な費用がかかるだろうと思ったことも弁護士さんに相談することを躊躇した理由です。
しかし、相手側の保険会社との示談交渉に疲れてしまい、しかも自分の知識と能力では担当者に対抗できないと感じ、それで依頼したのですが、正直なところ、みらい総合法律事務にお願いをしてよかったと思っています。
いつ終わるとも知れないような示談交渉の苦痛から解放されたこと、それに正しい損害賠償金を勝ち取ることができたことは本当にうれしいことでした。」
交通事故に強い弁護士に依頼してください
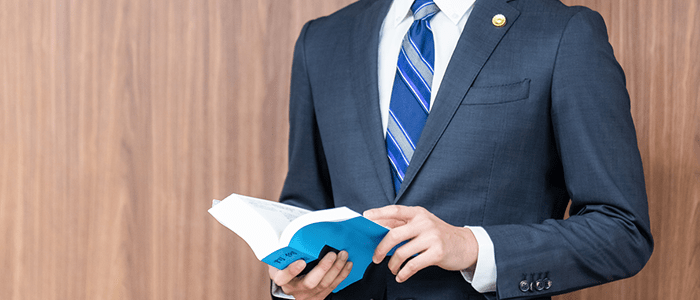
最後にひとつ、どうしてもお伝えしたいことがあります。
それは、弁護士なら誰でもいいわけではなく、できれば交通事故に強い弁護士に相談・依頼していただきたい、ということです。
弁護士には、当然のことですが、それぞれ得意不得意があり、専門分野があります。
たとえば、企業法務が専門の弁護士であれば、その分野には精通しているでしょうが、交通事故の被害者弁護は手掛けたことがない、ということが多くあります。
ケガや病気で病院に行く時のことを考えてみてください。
お腹が痛い時に歯科や整形外科にはいかないでしょう。
それと同じことが弁護士への相談・依頼の場合でも当てはまります。
とりあえず、知り合いから紹介された弁護士に相談・依頼してみたものの、交通事故がまったくの専門外の場合だと、請求項目を落としてしまったり、計算を間違えてしまったりと、被害者の方は逆に損をしてしまうこともあるのです。
それは大きなデメリットになってしまいかねません。
ですから、交通事故でお困りの場合は、交通事故で実績のある、専門家集団に相談・依頼されることをおすすめします。
※この記事で取り上げた事例は、実際の事例に修正を施しています。
その他の増額解決事例をご覧になりたい方はこちらから
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑





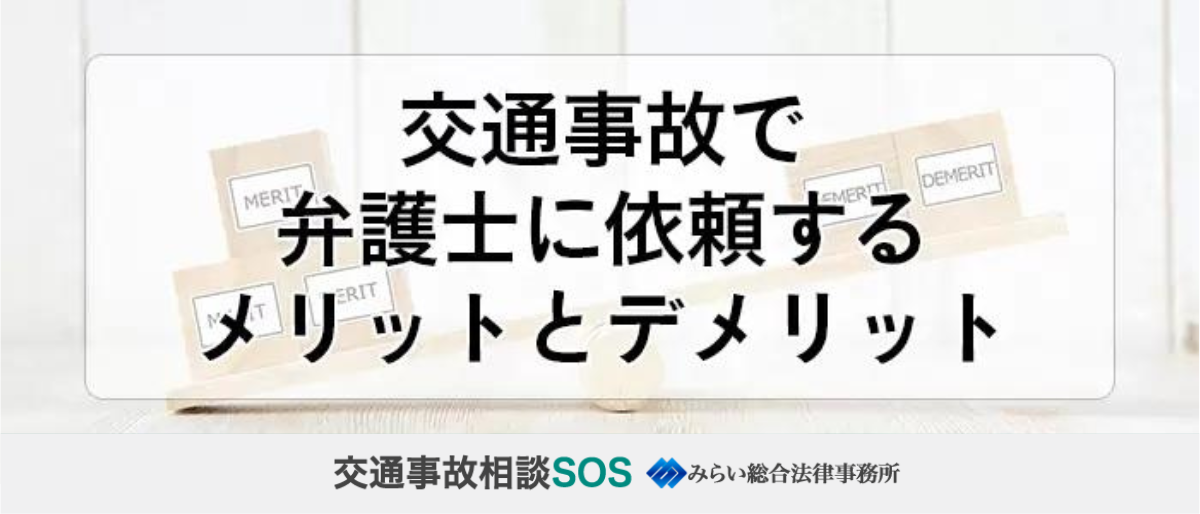


















の後遺障害等級.png)

