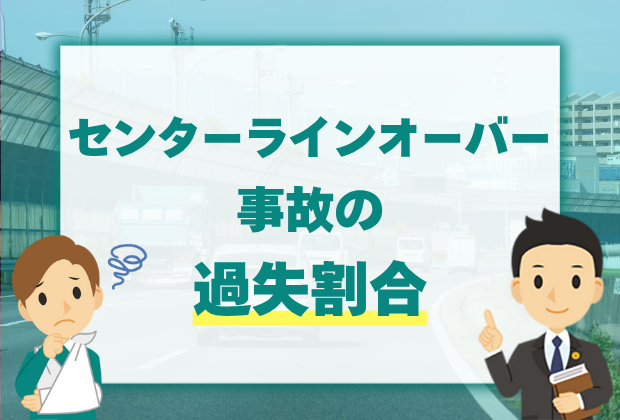高次脳機能障害の後遺障害等級と解決事例


目次
高次脳機能障害とはどのような後遺障害なのか?
交通事故で被害者の方が頭部に重大なケガをした場合、高次脳機能障害という後遺障害を負ってしまうことがあります。
高次脳機能とは、人間らしい思考や言動などを可能にしている複雑で高レベルの脳の働きのことです。
人間は、過去の物事を記憶し、その記憶をもとに判断を下し、物事に注意を向けます。
また、人によってさまざまな人格がありますが、こうした行動や人格などを高いレベルで作り出しているのが本来、人間が持っている脳の機能です。
こうした機能が失われた状態を高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害を負ってしまうと、記憶力や集中力が著しく低下したり、感情のコントロールができなくなってしまうために、以前とは別人のように人格そのものが大きく変わってしまうことがあります。
また、後遺障害が重篤な場合は、介護なしでは食事や入浴などの日常の生活ができなくなってしまいます。
高次脳機能障害を負ってしまった場合、その前後では生活も人生も大きく変わってしまうのです。
被害者の方とご家族にとっては、精神的な苦痛や肉体的な損害だけでなく、健康な頃のように働くことができなくなるために収入の問題が起きてきます。
さらに今後、将来にわたって介護が必要になった場合は、その介護費用をどうするのかという問題も起きてきます。
被害者の方とご家族は後遺障害等級の認定や慰謝料等の損害賠償金の示談交渉など、さまざまな手続きを行なっていかなければいけません。
これらの結果によっては、受け取ることができる示談金(損害賠償金)の金額に大きな違いが出てくるため、とても重要な手続きになってきます。
高次脳機能障害の症状について
高次脳機能障害の症状には、主に次のような「認知障害」と「人格変化」があります。
「認知障害」
・記憶力の低下(すぐに物を忘れてしまうようになった)
・集中力の低下(同じ作業を継続することができなくなった)
・判断力の低下(自分で判断できず人の指図が必要になった)
・頼まれたことができなくなった
・簡単な計算ができなくなった
・文章などを理解することができなくなった
・会話で適切な言葉が出てこなくなった
・繰り返し同じことばかり言うようになった
・相手の言葉が理解できずコミュニケーションがとれなくなった
「人格変化」
・攻撃的になり、怒りっぽく、すぐにキレるようになった
・暴言を吐いたり、暴力をふるうようになった
・感情がころころ変わるようになった
・よくしゃべるようになった
・嫉妬や被害妄想が激しくなった
・言動が子供っぽくなった
・無気力で、やる気がなくなった
症状は被害者の方によってさまざまですが、以前の仕事を辞めなければいけない、対人関係が悪化する、介護や付き添えが必要になる、ということが起きてくる場合もあります。
参考記事:「高次脳機能障害を理解する」国立障害者リハビリテーションセンター
高次脳機能障害の判断ポイント
後遺障害等級認定において、被害者の方に高次脳機能障害の疑いがある場合、調査事務所は「頭部外傷後の意識障害についての所見」や「脳外傷による精神症状等についての具体的な所見」という書類を医療機関に送付し、被害者の関係者には「日常生活状況報告表」を送付します。
これらの書類が返送され、審査の結果、被害者の方に高次脳機能障害の疑いが生じた場合、損保料率機構本部審査会、または地区本部審査会の「高次脳機能障害専門部会」が審査を担当することになります。
高次脳機能障害が後遺障害として認められ、後遺障害等級が認定されるための判断ポイントは次の4つです。
(1)頭部外傷による意識障害の有無とその程度
意識障害とは、意識を失っていたり、意識が朦朧としている状態のことをいいます。
交通事故後に意識障害があったかどうか、意識障害の程度はどのくらいかによって、高次脳機能障害である可能性を判断します。
意識障害について検査するのは、臨床上、脳外傷による高次脳機能障害は頭部外傷による意識障害の後に出現しやすい、ということに基づいているからです。
交通事故で頭部に打撲などがなくても、回転性の力が加わることで脳が激しく揺れて、神経細胞の繊維が広範囲に断裂して機能を失ってしまう場合があります。
これを、びまん性脳損傷(びまん性軸索損傷)といいます。
一次性びまん性脳損傷の場合は、交通事故直後に意識障害が発生しますが、二次性びまん性脳損傷の場合は、交通事故後しばらくしてから意識障害が発生します。
なお、意識障害については次の2つの判定があります。
・「昏睡~半昏睡で、刺激による開眼をしない程度の意識障害」か、「健忘症~軽症意識障害」かの判定
・意識障害が何時間、あるいは何日間続いたのかという期間の判定
(2)急性期の脳内出血が画像で確認できるか
高次脳機能障害ではMRIなどの画像で脳の損傷を確認しにくいのですが、たとえば、びまん性軸索損傷の場合は、軸索が損傷した部分に点状の出血が起きる、脳室内出血やくも膜下出血が起きる、ということがあるため、そうした出血の有無はMRI画像で確認できる場合があります。
急性期において脳内出血が確認される場合は、次の2点が判定基準となります。
・相当程度の軸索損傷が発生していると推定されること
・くも膜下血腫が認められる場合は、びまん性軸索損傷が推定されること
(3)脳室拡大、脳萎縮が画像で確認できるか
高次脳機能障害では、傷害を負ってから3ヵ月ほどで脳室拡大・脳萎縮が固定し、その後はあまり変化しないと考えられています。
そのため、この3ヵ月のうちで脳室拡大や脳萎縮がCTやMRI画像で確認できるかどうかもポイントになります。
また、時間の経過にともなう画像の比較が必要になるので、一定期間ごとに画像を撮影しておくことも大切です。
なお、治療の過程で被害者の方にこれらの事情があった場合には高次脳機能障害を疑い、高次脳機能検査を受けておく必要があります。
(4)その後の症状の経過はどうか
高次脳機能障害では、急性期の症状は急速に回復し、その後は時間の経過とともにゆるやかに回復する傾向にあります。
そのため、事故後1年程度は経過観察をしますが、1年以上が経過した時点で認知障害や人格変化などの症状が出ているのであれば、症状固定として後遺障害等級認定の申請をするのが望ましいでしょう。
高次脳機能障害は外からはわかりにくく、MRI画像などでも判断しにくいため、「隠れた障害」ともいわれます。
非常に専門的な知識や判断が必要になるので、早い段階で専門医の診断、検査を受けたほうがいいでしょう。
また、ご家族は、被害者の方を日常的に観察し、記録をつけておくなどの対応も必要になってきます。
参考記事:東京都医師会「高次脳機能障害について」
高次脳機能障害には6段階の後遺障害等級がある
「自動車損害賠償保障法施行令」により、高次脳機能障害はその程度に応じて、次のように6段階の後遺障害等級が認められています。
後遺障害等級1級1号(別表第1)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
もっとも重い後遺障害等級である1級1号に認定されるのは、次の2つの場合があります。
① 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
② 高次脳機能障害による高度の痴呆や情意の荒廃があるために、常時監視を要するもの
後遺障害等級2級1号(別表第1)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。
2級1号に認定されるのは、次の3つの場合があります。
① 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
② 高次脳機能障害による痴呆、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため、随時監視を必要とするもの
③ 重篤な高次脳機能障害のため、自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの
後遺障害等級3級3号(別表第2)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。
日常生活での動作を行なうことができ、自宅周辺を1人で外出できるものの、次のうちひとつ以上に該当し、一般就労できない場合です。
① 職場で他の人と意思疎通を図ることがまったくできない
② 課題を与えられても手順通りに仕事を進めることができず、働くことができない
③ 作業に取り組んでも、その作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない
④ たいした理由もなく突然、感情を爆発させ、職場で働くことができない
後遺障害等級5級2号(別表第2)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
次のうち、ひとつ以上の能力の大部分が失われているか、ひとつ以上の能力の半分程度が失われていることにより、単純繰り返し作業などの軽易な労働しかできず、頻繁な助言等が必要となる場合です。
① 職場で他の人と意思疎通を図る能力
② 課題を与えられて、手順通りに仕事を進める能力
③ 作業に集中する能力
④ 感情をコントロールする能力
後遺障害等級7級4号(別表第2)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
一般就労は維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどの理由から、一般人とは同等の作業ができず、時々、助言などが必要となる状態です。
後遺障害等級9級10号(別表第2)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。
一般就労は維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業維持力などに問題があるため、たまに助言などが必要となる状態です。
参考記事:損害保険料率算出機構「脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定」
高次脳機能障害と逸失利益
逸失利益とは、交通事故にあわなければ本来得られたはずの収入のことです。
交通事故で後遺症が残ると、事故前に比べて、仕事に支障が出てきます。その支障分に対する損害が逸失利益です。
逸失利益は、「一年あたりの基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」により計算します。
「一年あたりの基礎収入」は、被害者の年収で考えます。事故前の収入額がを基準とするのが原則となります。
たとえば、会社員など給与所得者は、交通事故の前の年の源泉徴収票が基準とし、本給だけではなく、手当てや賞与も含めて計算します。
個人事業主などは、交通事故の前の年の確定申告書写しなどを基準として計算します。
「労働能力喪失率」は、後遺症の重さにあわせて決められています。
後遺障害の影響が仕事の遂行にどれくらいの影響を与えているか、ということです。
自賠責後遺障害等級認定をうけて、その等級によって定まっています。
自賠責後遺障害等級は、重い方から1級から14級まで定められています。
参考情報:国土交通省「自賠責後遺障害等級表」
ライプニッツ係数は、将来的に稼げたはずのお金を、今受け取ることになるので、中間利息を差し引く必要がある、ということで定められています。
高次脳機能障害で争われる逸失利益
逸失利益における労働能力喪失率は、原則として、自賠責後遺障害等級に従って認定されますが、場合によっては、労働能力喪失率が争われることもあります。
その場合、相場となる労働能力喪失率より高い労働能力喪失率が認められることもあれば、低い労働能力喪失率が認められることもあります。
等級より高い労働能力喪失率が認められた裁判例
東京地判平成18年3月2日(出典:自保ジャーナル第1650号)
25歳ガラス工房勤務の女性の交通事故です。
ケガは、左前頭骨骨折、両側前頭葉脳挫傷、脳内出血、後頭部挫創、左肩甲骨骨折等です。
自賠責後遺障害等級高次脳機能障害5級2号、嗅覚障害12級、醜状障害7級12号(併合3級)です。
嗅覚障害、醜状障害については労働能力への影響を否定されましたので、相場となる労働能力喪失率は、5級に相当する79%となります。
原告は労働能力喪失率100%を主張しましたが、被告は、9級に相当する喪失率35%を主張し、仮に自賠責認定どおり高次脳機能障害が5級2号に相当するとしても、喪失率は79%とすべきであると主張しました。
裁判所は、労働能力喪失率92%と認定しました。
理由は、以下のとおりです。
裁判所は、
①「人格障害があり、易度性(ママ)、易興奮性等が認められ、意欲も減退していること」、
②「現在は仕事をしておらず、就業しようとしてアルバイトもてんかん発作のため、あるいは対人関係などに疲れ、自ら無理であるとして辞めている」ことから、「労働能力は相当程度喪失している」
他方で、
③各種検査の結果、原告の知能は正常で、精神心理検査の結果も良好であり、症状固定の診断をした医師も原告が従事していたガラス細工の仕事については、抗てんかん剤投与中で発作の生じる可能性はあるが、状況が許せば可能と考えていたこと
事故後も、④症状固定前から、結局継続していなかったとはいえアルバイトを試みており、当時は、自ら就職したいという意欲が窺えること
⑤1人暮らしをし、金銭のやりくりをして家事をこなしていたこと
に鑑み、100%労働能力を喪失したとは認め難いと判示し、労働能力喪失率を92%と認定しました。
したがって、喪失率は5級相当の79%の認定がされるのが通常であるところ、これより高い喪失率である92%を認定している点が特徴的です。
本裁判例が高い喪失率を認定した理由は、人格障害や易怒性・易興奮性等が認められ、てんかん発作等のため現在も就業できていないことを重視した点にあると思われます。
等級より低い労働能力喪失率が認められた裁判例
広島高裁松江支部判平成16年11月5日(出典:自保ジャーナル第1577号)
20歳の男性会社員の交通事故です。
ケガは、脳挫傷、左大腿骨折で、自賠責後遺障害等級は高次脳機能障害3級3号が認定されています。
相場となる労働能力喪失率は、100%です。
裁判所は、後遺障害を高次脳機能障害5級2号と認定し、労働能力喪失率を79%と認定しました。
理由は、以下のとおりです。
裁判所は、原告が
①自動車教習所に通うほか、定時制の工業高校に通学し卒業していること
②一人で徒歩あるいは自転車に乗って外出し、買い物をしていること
から、就労可能性を否定することはできず、後遺障害等級は、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものとして5級2号に相当すると認めるのが相当であるとしました。
しかし、本裁判例は、原告の高次脳機能障害を5級2号と判断して79%の喪失率を認めた点に特徴があります。
もっとも、本裁判例において、就労可能性を否定できない事情として挙げられているのは「定時制の工業高校に通学し卒業していること、一人で徒歩あるいは自転車に乗って外出し、買い物をすることができること」等の事情からただちに労働能力があるといえるかどうかは注意を要するところです。
介護に関わる5つの損害賠償項目について
交通事故の被害者の方が加害者側の保険会社に損害賠償請求できる項目には、治療費や入通院費、慰謝料や逸失利益など、さまざまなものがありますが、高次脳機能障害のように重度の後遺症が残った場合は将来の介護が必要になる可能性があります。
ここでは、介護が必要になった場合、被害者の方とご家族が損害賠償請求することができる項目について解説します。
(1)将来介護費
重度の後遺障害が残り、他人の介護を受けなければ生活できない場合に認められる費用です。
将来介護費は、次の計算式で算出します。
将来介護費 = 基準となる額 × 生存可能期間に対するライプニッツ係数
基準となる額は、職業付添人の場合は実費全額、近親者付添人の場合は1日につき8000円が目安とされています。
なお、この額は目安であるため、具体的な事情によっては増減することがあります。
生存可能期間は、原則として平均余命年数に従います。
ライプニッツ係数とは、現時点のお金の価値と将来のお金の価値が違うことから、その差を調整するための数値です。
一般的に、植物状態などの重い後遺障害を負った被害者の方は感染症にかかりやすいなどの理由から、通常よりも生存可能期間が短いとされます。
そのため、平均余命年数未満の生存可能期間を用いた判例もありますが、実務では平均余命までの生存期間を用いることのほうが多数です。
示談交渉で、加害者側の任意保険会社が短い期間を主張してきた場合、被害者側は平均余命いっぱいの生存可能期間をしっかりと主張するべきです。
将来介護費について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
(2)将来雑費
紙おむつ、タオル、手袋、カテーテル、防水シートなど重度後遺障害者の介護のために消費される物品の費用です。
将来雑費は、次の計算式で算出します。
将来雑費 = 雑費の年額 × 生存可能期間に対するライプニッツ係数
なお、訴訟になった場合、立証のために領収書が必要になるので、しっかり保存しておくことが大切です。
(3)装具・器具等購入費
義手、義足、歩行補助器具、車椅子、メガネ、盲導犬費用、介護支援ベッド、介護用浴槽など後遺障害者が日常生活を送るために必要となる物品の費用です。
(4)家屋・自動車等改造費
浴室やトイレ、出入口など自宅の改造費や自動車改造費など、後遺障害者が日常生活を送るために必要となる費用です。
(5)補助・保佐・成年後見開始の審判手続き費用
被害者本人が正常な判断ができなくなってしまった場合は、本人に代わって訴訟追行等の手続きを行なうため、法定代理人を選任する必要があります。
その際に成年後見人や保佐人、または補助人を選任するためにかかる費用も損害賠償請求することができます。
これらの審判手続きにかかる費用は、必要かつ相当な範囲で損害として認められています。
示談や裁判で必要な成年後見制度とは?
後遺障害等級が認定されると、被害者の方は加害者側の保険会社と示談交渉をしていくことになります。
しかし、高次脳機能障害で後遺障害等級1~3級が認定された時は、被害者の方に示談を締結する判断能力が欠けている場合があります。
そうなると、被害者ご自身が示談や裁判の当事者になることができなくなってしまいます。
こうした場合、原則として家庭裁判所に成年後見開始の審判手続きを行なう必要があります。
その結果、選任された成年後見人が本人に代わって示談や訴訟を行なうことになります。
成年後見制度は、被害者本人の判断能力の程度によって次のように区分されます。
・後見(本人の判断能力がまったくない場合)
・保佐(本人の判断能力が特に不十分な場合)
・補助(本人の判断能力が不十分な場合)
「成年後見」
成年後見とは、1人で日常生活を送ることができないなど、本人の判断能力がまったくない場合になされるものです。
後見開始の審判とともに、本人(成年被後見人)を援助する人として成年後見人が選任されます。
成年後見人は、本人を代理して示談や訴訟を行ないます。
「保佐」
保佐とは、本人の判断能力は失われていないものの、特に不十分な場合になされるものです。
保佐開始の審判とともに、本人(被保佐人)を援助する人として保佐人が選任されます。
保佐開始の審判を受けた本人は、一定の重要な行為、たとえば金銭の賃借、不動産および自動車などの売買、自宅の増改築などを保佐人の同意なしに単独で行なうことができなくなります。
交通事故の損害賠償については、保佐人に代理権が与えられる場合もありますが、本人の同意が必要です。
「補助」
補助とは、本人の判断能力が不十分な場合になされるものです。
補助開始の審判とともに、本人(被補助人)を援助する人として補助人が選任されます。
補助人は、本人が望む一定の事項について同意、取消、代理をすることで本人を援助していきます。
交通事故の損害賠償では、補助人に代理権が付与されることがありますが、本人の同意が必要です。
成年後見の申立における注意点
高次脳機能障害では、「後見」、「保佐」、「補助」のうちどの申立をすればいいのかわからない場合があります。
その際は、主治医の意見を参考にして、とりあえず近い類型の申立をすることになります。
裁判所から、「類型が異なる」という指摘を受ける場合がありますが、その際は申立をやり直す必要はなく、「申立の趣旨」の変更手続きを取ることになります。
これらの手続きには主治医の鑑定書が必要になるので、事前に主治医に協力を依頼しておくとスムーズに進みます。
その際の費用は別途、「交通事故による損害金」として請求することが認められています。
なお自賠責保険では、「問題が生じた場合には一切の責任を負う」という内容の念書を提出したうえで、成年後見人ではない者、通常は親族が保険金を受け取ることができる場合があります。
それは、つねに成年後見手続きが必要とすると、手続きに長い期間がかかるため、それでは被害者保護に欠ける場合があるからです。
成年後見制度については、次の裁判所ホームページの解説も参考にしてください。
参考記事:裁判所「成年後見制度」
裁判では介護の実態を立証する必要がある
高次脳機能障害を負った被害者の方には、損傷した脳の部位によってさまざまな症状が現れます。
体を自由に動かすことはできても、話す、聞く、読む、書くといったことができなくなる人がいます。
一方、話はできても、ボタンをかけたり手袋をはめたりすることができなくなる、人の顔を認識できなくなる、同じ話を何度もする、自宅でトイレに行くのに迷ってしまう、つねにボーっとしている、突然怒りだす、お金をあるだけ使ってしまう、といった症状が出る人もいるため幅広い介護が必要になります。
常時介護は必要なくても、つねに監視をしていなければいけない場合もあります。
高次脳機能障害のそれぞれの症状に応じて介護の内容も変わってくるため、損害賠償で裁判になった場合は具体的な介護の実態を立証しなければいけません。
立証する場合、医師や介護に携わっている人の意見書や報告書なども裁判で提出しますが、さらに具体的な介護状況を立証する必要がある場合には、現在ではビデオ機器の性能が向上して誰でも動画を撮影することができるので、被害者の様子をビデオ撮影して、その動画を提出したり、写真にするなどして提出する場合もあります。
みらい総合法律事務所の示談金増額解決事例
ここでは、高次脳機能障害で、私たちが依頼を受けて実際に増額解決したオリジナルの事例についてご紹介します。
交通事故の被害者の方から依頼を受け、示談交渉や裁判を経て、実際に慰謝料などの損害賠償金(示談金)で増額を勝ち取ったものばかりです。
交通事故の示談交渉や裁判がどのように行なわれるのか、経験したことがなければわからない世界だと思います。
ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせながら参考にしてください。
①:21歳女性が約2,200万円増額!
21歳の女子学生が青信号の丁字路交差点を自転車で走行中、信号無視のトラックに衝突された交通事故。
被害者女性は脳挫傷などの傷害(ケガ)を負い、後遺症が残ってしまったため自賠責後遺障害等級認定を申請したところ、高次脳機能障害で7級4号、味覚障害で14級相当、併合で7級が認められました。
加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約3,870万円を提示。
この金額が適切なものか判断できなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「この金額では低すぎる」との意見があったことから、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士と保険会社の交渉では逸失利益などが争点となりましたが、最終的には約2,200万円増額の約6,070万円で解決できた事例です。
②:19歳男性が1億3,500万円で解決
19歳の男性が、友人が運転するバイクの後部座席に乗車中、向かい側から右折してきた自動車と衝突した交通事故。
被害者男性は脳挫傷などの傷害(ケガ)を負い、高次脳機能障害の後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級3級3号が認定されました。
重傷でもあり、加害者の刑事事件に被害者参加することを希望していたことから、被害者男性は自分一人での示談解決は困難だと感じ、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまますべてを依頼しました。
刑事事件への被害者参加の後、弁護士と加害者側の保険会社との示談交渉が開始。
将来介護費などが争点となりましたが、最終的には裁判に進まず合意に達し、1億3,500万円で示談解決 したものです。
被害者参加について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
③:後遺障害7級の28歳男性が4,400万円獲得
トラック運転手の28歳男性の交通事故です。
自動車を運転して交差点に進入したところ右折車に衝突され、被害者男性は脳挫傷などのために高次脳機能障害を負い、自賠責後遺障害等級7級4号が認定されました。
加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約2,130万円を提示。
この金額が適切なものか判断がつかなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の回答は「増額可能」というものだったので、被害者男性は示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士と保険会社の交渉の結果、示談金は当初提示額から約2,300万円増額し、4,400万円で解決した事例です。
④:5歳男児が後遺障害7級で約1,540万円の増額
5歳男児が道路を横断していたところに直進車が衝突してきた交通事故です。
被害者男児は外傷性くも膜下出血、重傷頭部外傷、頭蓋骨骨折などの傷害を負い、治療のかいなく高次脳機能障害の後遺症が残ったことで、後遺障害7級4号が認定されました。
加害者側の保険会社は、慰謝料などの損害賠償金として約2,120万円を提示しましたが、被害者男児のご両親がみらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、「増額可能」とのアドバイスを弁護士から受けたことで示談交渉のすべてを依頼することを決意されました。
弁護士が示談交渉したところ、最終的に保険会社が約3,660万円を提示したことで合意。
当初提示額から約1,540万円増額することができたものです。
こちらの記事も参考にしてください。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
交通事故の慰謝料の相場や計算方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
代表社員 弁護士 谷原誠

















の後遺障害等級.png)