交通事故における示談交渉術とテクニック

交通事故の被害にあい、加害者側と示談交渉する際、加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社と担当者が交渉相手になります。
保険会社が株式会社であれば、その経営目的は「営利」ですから、慰謝料などの損害賠償金(示談金)をかなり低く提示してくることがよくあります。
提示額に納得がいかなければ示談交渉を行なうのですが、相手は保険と金額交渉のプロですから、簡単に増額を勝ち取ることはできません。
そこで大切なのが交渉でのテクニック=交渉術です。
有効なテクニックは以下となります。
- 示談金(損害賠償金)の内訳を書面に
書いて送ってもらう - 示談金の項目の内訳と内容を必ず確認する
- 正しい金額が提示されているか必ず
確認する - 相手の主張を鵜呑みにせず、簡単には
示談しない - 交渉で感情的にならないように第三者を
立てる
交通事故の示談交渉を被害者の方が有利に進めるためのテクニックなどあるのか?と驚く人もいると思いますが、じつはあるのです。
そうしたテクニックを上手に使うには、示談交渉についての正しい知識や、被害者の方には知らされていない本当のことを知る必要があります。
そこで本記事では、示談交渉の基礎知識から、被害者の方が知っておくべき大切なことまでをお話ししていきます。
示談交渉で知っておきたい9つの
ステップと手続き
ここでは、交通事故の被害で負ったケガで後遺症が残った場合の示談交渉の大まかな流れについて解説します。
1つずつ詳しく解説します。
(1)ケガの治療と症状固定の診断
入通院をしてケガの治療を続けていくと、ある時点で「症状固定」の診断を受ける場合があります。
症状固定とは、これ以上の治療を継続しても改善や完治の見込みがない状態のことで、医師が診断をするものです。
(2)ご自身の後遺障害等級の認定
症状固定後は、残念ながら被害者の方には後遺症が残ることになるため、加害者側と示談交渉を進めていくには、ご自身の後遺障害等級の認定を受けることが必要です。
というのは、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金額を算出するには、ご自身の後遺障害等級を確定させる必要があるからです。
(3)該当する損害項目から
賠償額(示談金額)が確定
通常、示談交渉の相手は加害者側の任意保険会社になります。
そこで、保険会社は被害者の方が被った損害について各損害項目の算定を行ない、自賠責基準や任意保険基準によって示談金額を算定します。
(4)加害者側の任意保険会社が示談金額を提示
加害者側の保険会社から示談金額の提示があるので、その内容と金額を必ずチェックしてください。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、治療費など、さまざまな項目があると思います。
しかし、保険会社から提示される金額は、本来であれば被害者の方が受け取るべき金額より、かなり低いものが記載されていることがほとんどです。
2分の1や3分の1、それよりもさらに低い金額であることがあるのですが、じつはこれが示談における現実なのです。
(5)ご自身の損害賠償金額(示談金額)を確認
提示された示談金額についての確認事項や注意ポイントについては、示談金の内訳の内容を必ずチェックするで詳しくお話ししていますので、確認してください。
(6)示談金額について示談交渉を開始
提示された示談金額に納得がいく場合は、交渉に入らず示談は成立となります。
また、金額には納得がいかないが、「このくらいのものなのだろう」とか「しょうがない」などとあきらめてしまって示談を成立させてしまうケースもあるでしょう。
一方、前述したように保険会社が提示してくる金額は、被害者の方が本当は受け取るべき金額よりかなり低いことが多いので、示談交渉に入っていく被害者の方もいます。
しかし、保険会社は被害者の方の主張を認めることは少ないので、交渉が長期化してしまうことがよくあるのです。
その理由については、のちほど詳しくお話ししますが、まずは次の記事をご覧になっていただきたいと思います。
(7)示談が成立したら保険会社から示談書が届く
(8)示談書に署名・捺印をして返送
示談書の書式には法的な規定はありませんが、どのような内容や項目が、どういった形式で書かれているのか、次の記事をお読みになって参考にしてください。
(9)慰謝料などの損害賠償金(示談金)が支払われて示談が
完了
通常は2週間~1か月程度で被害者の方が指定した銀行等の口座に示談金が支払われるので、それをもって示談が完了となります。
示談交渉を有利に進める!5つの
テクニック
被害者の方が示談交渉で注意するべきポイントがあるように、有利に示談交渉を進めるために大切なことがあります。
それが以下の5つになります。
1つずつ詳しく解説します。
(1)示談金の提示は書面に書いて送ってもらう
加害者側の保険会社から示談金の提示を受ける際、電話で話して口頭で伝えられる場合もあるのですが、そうした時は必ず、示談金(損害賠償金)の内訳を書面に書いて送ってもらうようにしてください。
というのは、口頭でのやり取りでは証拠として残らないので、今後、交渉を進めていくためには書面として残しておくことが大切だからです。
(2)示談金の内訳の内容を必ずチェックする
示談金の提示額が書かれた書面は「傷害部分」と「後遺障害部分」に分けられていると思います。
まずは、後遺障害部分を見てください。
①後遺障害の欄がひとつしかない
ここで、「後遺障害」の欄がひとつになっていて、「◯◯◯万円」と記載されているとしたら、それは「自賠責保険」の金額が記載されている可能性が高いと判断してください。
どういうことかというと、その金額は被害者の方が本来受け取る金額よりも低い金額ですから、交渉次第で増額する可能性が高いということなのです。
②後遺障害の欄がふたつに分かれて
いる
また、「後遺障害」の欄が「慰謝料」と「逸失利益」に分けられているかどうかを確認してください。
逸失利益とは、将来得られるはずだったのに、交通事故によるケガ、後遺症のために得られなくなってしまった、失ってしまった収入(利益)分です。
示談交渉や裁判では、この逸失利益は金額が大きくなるため争点になることが多くあります。
ということは、正当な逸失利益を受け取ることができれば、被害者の方は損をしないということになります。
(3)提示金額が正しいか
どうかの確認をする
前述したように、慰謝料などの損害賠償金の算定には3つの基準があり、弁護士(裁判)基準で計算した金額がもっとも高額になります。
ですから、相場の金額を知らずに示談を成立させてはいけません。
そこで、おすすめしたいのが、ご自身で損害賠償金を計算してみることです。
みらい総合法律事務所で独自開発した「慰謝料自動計算機」は、どなたでも、かんたんに慰謝料などの損害賠償金額を計算することができます。
実際の損害賠償実務では、交通事故の状況や、被害者の方のケガの状態によってさらに詳しく計算していきますが、この自動計算機で大まかな金額を計算することができます。
この自動計算機で出た金額と示談書に記載されている金額を比較してみてください。
もし金額に差があるなら、保険会社の提示額は正しい金額ではないということになります。
(4)示談内容に疑問や不服があるなら簡単に承諾せず答えを
保留してもいい
一度、示談交渉を成立させてしまうと、あとから金額などの条件内容を変更したくてもできなくなってしまいます。
ですから、示談金額に納得がいかない、疑問があるなら簡単に示談に応じてはいけません。
回答を保留してもいいのです。
その間に被害者の方は適切な回答を導き出さなければいけないのですが、その時に頼りになるのが、交通事故に強い弁護士です。
(5)示談交渉では感情的に
ならないように第三者を
代理人に立ててもいい
示談交渉では、被害者の方の主張が認められない、加害者側の保険会社が慰謝料などの増額を受け入れないため、なかなか進まないということが起きてしまいがちです。
そうした時、被害者の方としてはどうしても感情的になってしまうこともあると思います。
しかし、感情的になっても示談交渉が上手く進むわけではありませんし、慰謝料などが増額するわけでもありません。
相手は保険と示談交渉のプロですから、保険や法律の知識がなく、シビアな交渉経験のない被害者の方が互角以上に渡り合うのは、とても難しいことです。
プロ相手の交渉は、やはり法律のプロである交通事故の実務に精通した弁護士に任せてしまったほうが上手くいきますし、被害者の方はさまざまなメリットを手にすることができます。
ですから、まずは一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
実際に増額解決した数多くの
示談交渉事例
みらい総合法律事務所では、これまで数多くの示談交渉で示談金の増額を勝ち取ってきました。
次のページから、後遺症を負った部位別、後遺障害等級別、被害者の方の年代別などの増額解決事例をご覧いただけるので、参考にしていただければと思います。
交通事故の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠










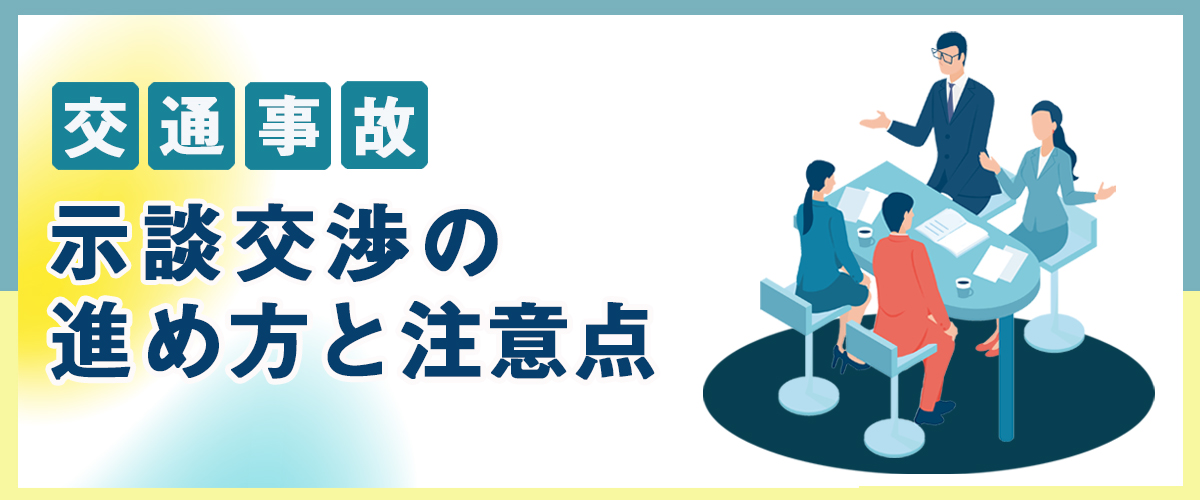



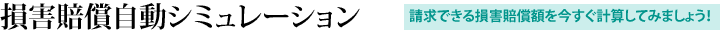
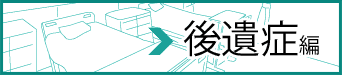
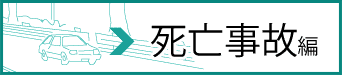
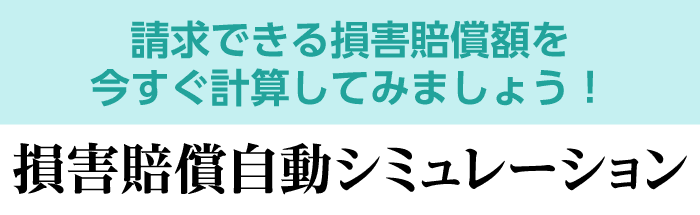








の後遺障害等級.png)


