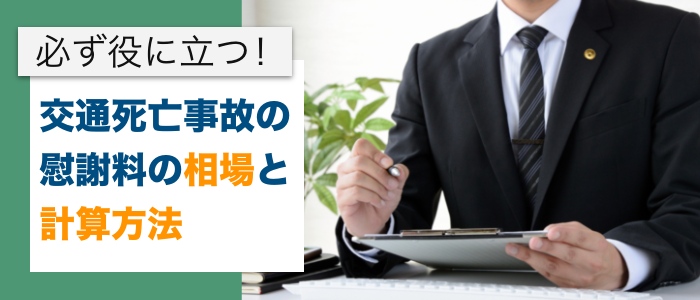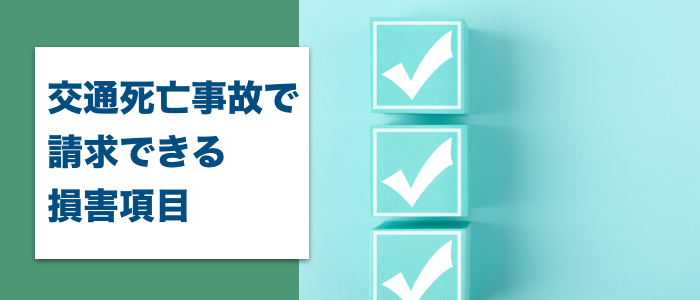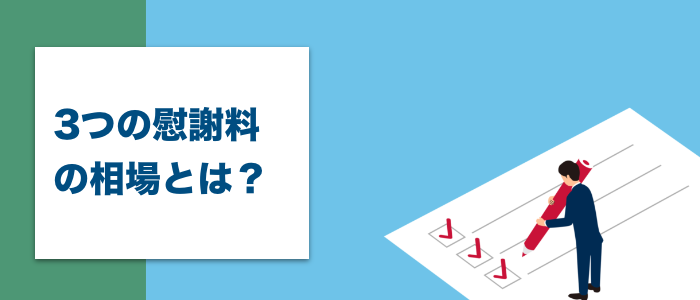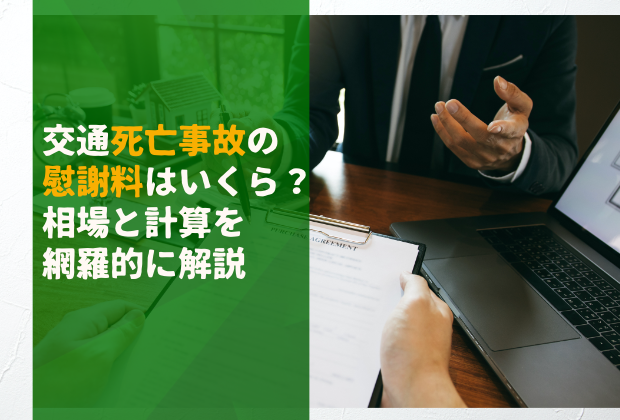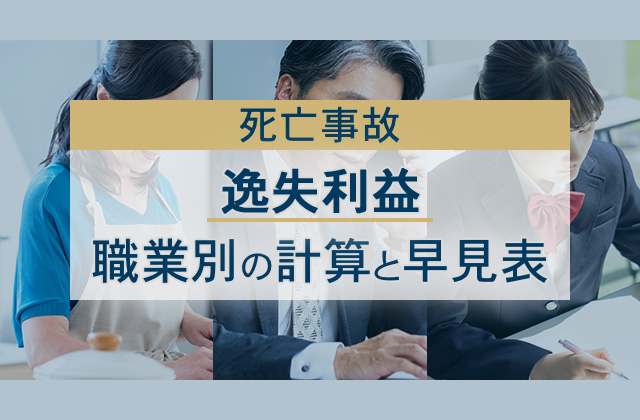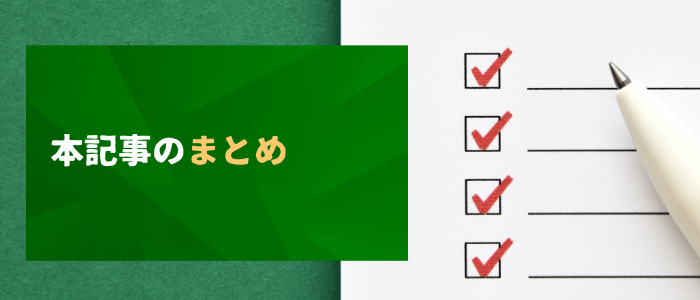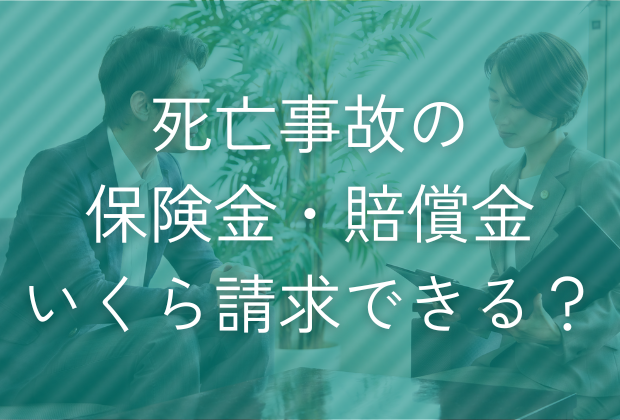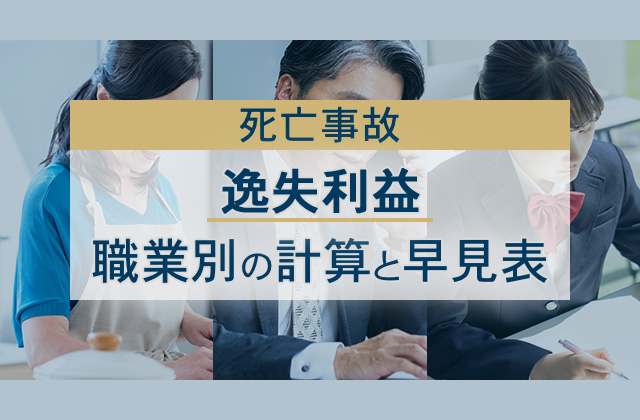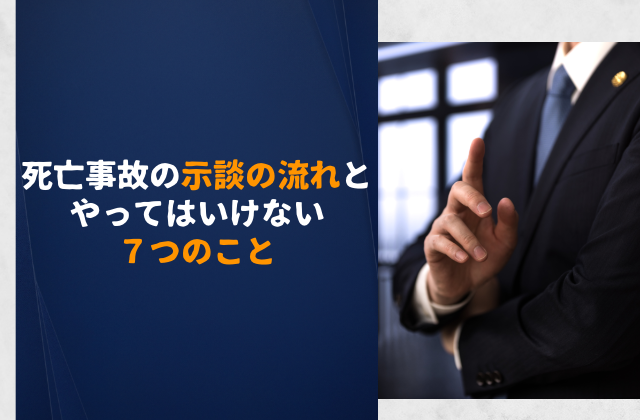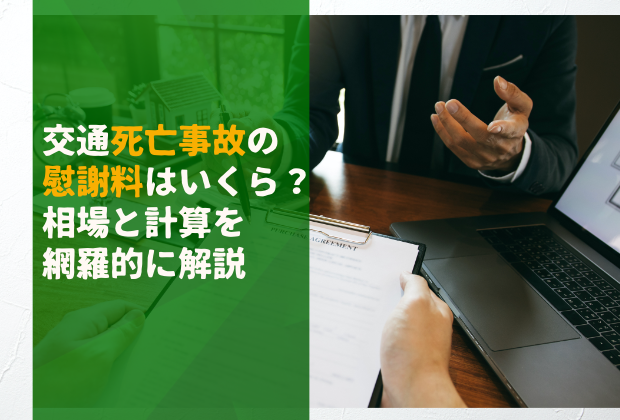交通死亡事故の慰謝料相場と請求方法を徹底解説!【遺族向け】
*タップすると解説を見ることができます。
死亡事故の慰謝料とは、死亡事故の被害者及び近親者の精神的な損害の賠償金のことです。
交通死亡事故の慰謝料には、
①入通院慰謝料、
②死亡慰謝料、
③近親者慰謝料の3つがあります。
「①入通院慰謝料」とは、死亡する前に医療機関に入通院しなければならなくなった精神的損害の賠償であり、例えば2ヶ月間の入院では
101万円が相場です。
「②死亡慰謝料」とは、交通事故による死亡によって被害者が受けた精神的損害の賠償であり、被害者の家庭内での立場により2,000万円~
2,800万円が相場です。
「③近親者慰謝料」とは、被害者が死亡した場合に認められる精神的損害の賠償であり、
被害者の慰謝料額10~30%程度が相場です。
慰謝料は、賠償金の一部であり、その他にも、葬儀関係費用、逸失利益などを請求することができます。
死亡事故で被害者の相続人が加害者側から受け取った慰謝料に対する税金はかかりません。
この記事では、死亡事故の慰謝料とは何か、他の損害賠償の項目など、死亡事故の被害者のご遺族が知るべき知識について、丁寧に、かつ網羅的に説明していきます。
目次
交通死亡事故で請求できる損害項目
交通死亡事故の被害者のご遺族が受け取ることができる損害賠償金には、さまざまな項目があります。
主なものは次の通りです。
②死亡逸失利益
(生きていれば得られたはずの収入)
③慰謝料
④弁護士費用(裁判をした場合)
これらの他にも、治療の後に死亡したような場合は、「治療費」、「付添看護費」、「通院交通費」等の実費を請求することができます。
また、損害賠償金を請求する際に必要となる「診断書」、「診療報酬明細書」、「交通事故証明書」等の文書を取得するためにかかった文書費用も、「損害賠償関係費」として請求できます。
つまり、損害賠償金には上記のようにさまざまな項目が含まれており、慰謝料はその一部だということです。
交通事故で発生する3つの慰謝料の相場とは?
そもそも、慰謝料とは何かといえば、「精神的な苦痛を被ったことに対する損害賠償金」ということになります。
交通事故に関する慰謝料には、次の3つがあります。
傷害慰謝料
傷害慰謝料は、交通事故で外傷を受けたことに対する肉体的苦痛や入通院加療を余儀なくされることなどに対する煩わしさや苦痛を緩和するために支払われる金銭のことで、通院期間によって算出されます。
死亡事故の場合には、交通事故と死亡との間に治療が入った場合に認められます。
後遺症慰謝料
後遺症慰謝料は、治療が完了しても後遺症が残ってしまい、これ以上よくならない場合(これを症状固定といいます)、その後遺症を負ったまま今後の人生を生きていくことに対する精神的損害を償うための賠償金のことです。
原則として、第1~第14級の後遺障害等級認定にしたがって算定されます。
後遺症慰謝料の相場は、以下のようになっています。
(等級をクリックすると、その等級の詳しい解説ページを表示します。)
弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場金額
| 後遺障害等級 | 慰謝料 |
|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 |
| 第2級 | 2,370万円 |
| 第3級 | 1,990万円 |
| 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 |
| 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
死亡慰謝料
死亡慰謝料の相場は、被害者が死亡したことにより被った精神的損害です。
弁護士基準による死亡慰謝料
弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者が置かれている状況によって、慰謝料の金額が異なってきます。
弁護士基準により死亡慰謝料の相場は、
以下のようになっています。
・母親、配偶者の場合 2,500万円
・その他の場合 2,000万~2,500万円
一家の支柱の方が亡くなったときの慰謝料が高額なのは、ご遺族の扶養を支える人がいなくなることに対する補償のためです。
自賠責基準による死亡慰謝料
自賠責基準による慰謝料は、次のようになっています。
自賠責保険に請求できる慰謝料は、被害者本人分とご遺族の慰謝料があります。
被害者本人分は400万円です。
ご遺族の分としては、父母、配偶者、子供が請求することができます。
ご遺族の人数によって以下のように異なってきます。
| 1人 | 550万円 |
|---|---|
| 2人 | 650万円 |
| 3人以上 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいる場合は、
200万円がプラスされます。
死亡慰謝料は相場より
増額することがある
死亡慰謝料には相場があるのですが、必ずその金額が認定されるわけではありません。
じつは、死亡慰謝料が増額するケースもあります。
それは、以下のような事情がある場合です。
被害者の精神的苦痛がより
大きいと思えるような場合
被害者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合としては、たとえば、次のようなものがあげられます。
- ・加害者の無免許、飲酒運転、赤信号無視
などの悪質な行為を原因としたもの - ・事故後に救急車を呼ばず、
ひき逃げをしたもの - ・事故後に遺族に暴言を吐いたり、
反省の態度がまったく見えないもの
このような場合には、慰謝料増額事由を
指摘して、慰謝料の増額を目指していくことになります。
慰謝料を相場より増額した過去の裁判例としては、次のようなものがあります。
死亡慰謝料の増額判例①
被害者男性が一家の支柱である事案。
加害者が無免許、飲酒、居眠り運転により、対向車線に進出して被害車両と衝突。
また事故後救助活動をせず、しかも自分は運転していない等虚偽の供述。
被害者及びその長男も死亡させ、被害者の妻や娘にも重傷を負わせるなど、一家全体に重大な結果を生じさせた。
これらの事情から、慰謝料の相場2,800万円のところ、本人2,500万円、妻300万円、子供3人に各200万円、父母各100万円の、合計3,600万円の慰謝料を認めた事例。(さいたま地裁平成19年11月30日判決)
死亡慰謝料の増額判例②
被害者が主婦兼アルバイトの女性である事案。
加害者が飲酒、居眠りにより交通事故を起こした。
事故の悪質さや運転動機の身勝手さ、3人の子供の成長を見届けることなく死亡した被害者の無念さ等を考慮し、当時の慰謝料の相場2,400万円のところ、本人2,700万円、子供3人に各100万円の、合計3,200万円の慰謝料を認めた事例。(東京地裁平成18年10月26日判決)
死亡慰謝料の増額判例③
被害者が3歳と1歳の姉妹である事案。
加害者が飲酒運転で縁石にぶつかりながら蛇行運転をするなどして、料金所の職員に注意されたにもかかわらず運転を続け、サービスエリアでもさらにウイスキーを飲酒したような状態で被害車両に追突して炎上させ、被害車両に閉じ込められた姉妹を焼死させた。
これらの事情から、当時の慰謝料の相場2,000万円~2,200万円のところ、被害者一人につき2,600万円、父母各400万円の、合計3,400万円の慰謝料を認めた事例。(東京地裁平成15年7月24日判決)
被害者側に特別な事情が
ある場合
被害者側に特別な事情がある場合としては、
たとえば、被害者の親族が精神疾患に罹患するような事例が考えられます。
慰謝料を相場より増額した過去の裁判例としては、次のようなものがあります。
「死亡慰謝料の増額判例」
被害者は、スナックに勤務する24歳の女性。
被害者が交通事故により死亡したことにより、母親は精神的ショックを受け、PTSDに罹患した。
そのような事情を考慮し、慰謝料の相場として、2,000万円~2,200万円であったところ、本人分2,000万円、父100万円、母300万円の合計2,400万円を認めた。(大阪高裁平成14年4月17日判決、出典:交民35巻2号323頁)
交通死亡事故の損害賠償金は
いくらになるのか?
では、交通事故死の場合の損害賠償金は、一体どのくらいの金額になるのでしょうか? 相場というものはあるのでしょうか?
実際に経験したことがない方がほとんどでしょうから、なかなか見当がつかないかもしれません。
そこで、ここでは70歳の主婦(夫と2人暮らし)の方が交通事故で死亡した場合をひとつの例として、賠償金とその相場について具体的に見ていきます。
葬儀関係費用
原則として150万円です。
実際にかかった金額が150万円より低い場合は、実際に支出した額となります。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者の方が交通事故で死亡したことにより、将来に労働により得られたはずの収入を得られなくなったために失われる利益のことです。
少し難しいのですが、死亡逸失利益は下記の計算式で算定できます。
× (1 - 生活費控除率)
× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
主婦の場合は実際の収入はありませんが、家事労働を行なっているので、逸失利益は認められることを覚えておいてください。
基礎収入
基礎収入とは、交通事故で死亡しなければ、将来に労働により得られたであろう収入のことで、基準となるのは前年の年収です。
高齢の家事従事者の基礎収入については、裁判例をみると、次のように分かれています。
ⅰ)女性労働者の全年齢平均賃金としたもの
ⅱ)女性労働者の全年齢平均賃金から何割か
減額した額としたもの
ⅲ)年齢別の女性労働者の平均賃金としたもの
ⅳ)年齢別の女性労働者の平均賃金から
何割か減額した額としたもの
実際には、個別の事案ごとに被害者の方がどの程度、家事を行なっていたかなど、具体的な事情を評価して決めることになりますが、今回のケースは上記ⅰの女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入とします。
なお、基礎収入は場合によっては減額されることもあるので注意が必要です。
生活費控除
生活費控除とは、生きていればかかったはずの生活費分を、基礎収入から差し引くことをいいます。
生活費控除率の目安は次のようになります。
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
|---|---|
| 一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |
| 女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |
| 男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |
- 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合
- 40%
- 一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合
- 30%
- 女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合
- 30%
- 男性(独身、幼児等含む)の場合
- 50%
「就労可能年数」
就労可能年数は、原則として18歳から67歳までとされています。
ただし、職種、地位、能力等によって67歳を過ぎても就労することが可能であったと思われる事情がある場合には、67歳を過ぎた分についても認められる場合もあります。
今回のケースでは、平成23年の簡易生命表によると、70歳の場合の平均余命は14.93年となっているので、その2分の1である7年間について今後も家事労働を行なうことができたと仮定します。
「ライプニッツ係数(中間利息控除)」
ライプニッツ係数とは、損害賠償の場合、本来は将来に仕事をして受け取るはずであった収入を前倒しで受け取るので、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことです。
この利率は、年3%となり、3年毎に見直されることになっています。
以上のことから、夫と2人暮らしの70歳の主婦の死亡逸失利益の計算式と金額は次のようになります。
× 8.5302 (ライプニッツ係数)
= 2,354万7,190円
なお、年金収入がある場合には、将来受給できたはずの年金額について、逸失利益として請求することができます。
ただし、遺族年金については、裁判例で逸失利益性が否定されています。
また、年金収入が逸失利益として認められる場合でも、年金は生活費として使われる場合が多いことを想定し、生活費控除率を高くする傾向にあるようです。
死亡逸失利益について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
死亡慰謝料
慰謝料の額は、これまでの交通事故の民事裁判で認定された慰謝料額の総計などから相場が定められています。
弁護士が被害者のご遺族から依頼を受けて、加害者側と交渉や裁判を行なう場合、損害賠償額を算定する際には通常、日弁連交通事故相談センターが出している書籍『民事交通事故訴訟損害賠償算定基準』(通称「赤い本」)を使用することになります。
この「赤い本」に書かれている基準を「裁判基準」といいます。
被害者が、一家の支柱の場合は2,800万円、母親・配偶者の場合は2,500万円、その他(子供、成人独身者、高齢者等)の場合は2,000万~2,500万円が相場となっています。
今回のケースでは、被害者の方は70歳の高齢者なので、仮に慰謝料を2,200万円とします。
なお、被害者本人の慰謝料とは別に、配偶者などの近親者の固有の慰謝料が認められる場合があります。
弁護士費用
損害賠償請求をするために弁護士に依頼して裁判を起こした場合は、請求認容額の10%程度が弁護士費用として認められます。
ここで認められる弁護士費用は、実際に支払う弁護士費用とは無関係です。
今回のケースでは、請求額は次のようになります。
+ 22,000,000円(慰謝料)
= 4,704万7,190円
ここから弁護士費用は、 470万4,719円と算出できます。
以上のことから、70歳で夫と2人暮らしの主婦の方が交通事故で死亡した場合の損害賠償額の合計は次のようになります。
+ 2,354万7,190円(死亡逸失利益)
+ 22,000,000円(慰謝料)
+ 470万4,719円(弁護士費用)
= 5,175万1,909円
死亡事故の場合、誰が慰謝料・
賠償金を受け取れるか
死亡事故の場合、慰謝料の請求主体である被害者は死亡しているため、その相続人が損害賠償金を受け取ることになります。
では、具体的に誰が受け取ることになるかは、民法が定めています。
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり、他の親族とともに賠償金を受け取ることになります。
具体的には、以下のようになります。
配偶者:2分の1
子:2分の1
※子が複数いる場合には、それぞれの子の相続分は等分となる。
※配偶者が1人、子が2人の場合、それぞれの子の相続分は4分の1となる。
配偶者:3分の2
親:3分の1
※親が複数いる場合には、それぞれの親の相続分は等分となる。
※配偶者が1人、親が2人の場合、それぞれの親の相続分は6分の1となる。
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
※兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの兄弟姉妹の相続分は等分となる。
※配偶者が1人、兄弟姉妹が2人の場合、それぞれの兄弟姉妹の相続分は8分の1となる。
交通死亡事故の慰謝料は弁護士に
依頼したほうがいい理由
ここまで、交通死亡事故の被害者のご遺族が手にすることのできる慰謝料などの賠償金の相場についてお話してきました。
ところで、最後にどうしてもお伝えしたいことがあります。
それは、被害者のご遺族が正しい金額の慰謝料などを受け取るためには、弁護士に相談・依頼したほうがいいということ。
そして、その理由について知っていただきたい、ということです。
前述したように、損害賠償について遺族の方は、加害者側の保険会社の担当者と示談交渉をしていくことになります。
しかし、保険会社が示談の段階で提示してくる損害賠償額は、そもそも被害者のご遺族が受け取ることができる金額よりも低い場合が多いのです。
なぜかというと……
じつは、交通事故の損害賠償には、
- ①自賠責基準
- ②任意保険基準
- ③弁護士(裁判)基準
の3つの基準があるのですが、保険会社はもっとも金額が低い自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してくるからです。
自賠責基準は、被害者に対する最低限の補償の金額です。
任意保険基準は、各保険会社が独自に定めていますが、適正な基準である弁護士基準よりは低い金額です。
任意保険会社は利益を出すことが目的ですから、支出をできるだけ少なくしようとします。
自賠責基準で計算した金額で被害者のご遺族が示談をしてくれれば、保険会社は自己資金を支出することなく、示談解決をすることができてしまいます。
任意保険基準で計算した金額で被害者のご遺族が示談をしてくれれば、保険会社は自分たちの都合で考える適正な支出額で示談を成立させることができるわけです。
しかし、本来の賠償金の適正金額は弁護士(裁判)基準で計算した金額です。
つまり、被害者のご遺族は、自賠責基準や任意保険基準で計算した慰謝料で示談してはいけない、ということです。
ところが、現実を見ると、ご遺族は示談交渉ではなかなか思うような金額を引き出すことができません。
なぜなら、相手は保険のプロである保険会社の担当者なのですから、当然でしょう。
また、示談交渉は、当事者双方が合意しなければ成立しないので、保険会社側としては、「この金額が限界です」と言い続ければ、いつまでも示談が成立しないことになります。
しかし、弁護士が出てきたときは状況が変わります。
低い金額では弁護士は示談しませんし、いつまでも増額しないと、すぐに裁判を起こされて、弁護士(裁判)基準で払わざるをえなくなります。
また、裁判を起こされてしまうと、保険会社も弁護士に依頼しなければならなくなり、弁護士費用までかかってしまいます。
そうした理由で、弁護士が示談交渉をすると、慰謝料が増額され、示談金額のアップにつながる、というわけです。
「大手の保険会社が提示する金額なのだから、間違いはないのだろう」と思ってはいけません。
「弁護士に依頼するのは何だか気が引ける」などと躊躇してはいけません。
実際は、弁護士に依頼したほうが交渉はスムーズに進みます。
裁判になれば、ほとんどの場合で適正な相場の金額を勝ち取ることができます。
ご遺族は、悲しみを抱えたまま難しい賠償金の示談交渉をする必要はないのです。
まとめ
交通死亡事故は、被害者の家族や遺族にとって非常につらい経験です。
このような状況で、慰謝料や賠償金の請求を考えることは、感情的にも複雑です。
しかし、正当な賠償を受け取るためには、計算方法や請求の過程を理解することが必要です。
(2)死亡逸失利益: これは、被害者が生きていれば得られたはずの収入を示します。計算は複雑ですが、非常に重要な部分です。
(3)示談交渉の難しさ: 保険会社との交渉は簡単ではありません。特に、適正な賠償金額を得るためには、弁護士の介入が有効です。
(4)弁護士の役割: 弁護士が交渉の場に入ると、賠償金の増額や、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
(5)遺族の感情: 被害者の家族や遺族は、事故のショックとともに、賠償金の交渉のストレスも抱えています。そのため、弁護士のサポートは、感情的なサポートとしても非常に有効です。
最後に、交通死亡事故に遭遇した場合、自分たちだけで交渉を進めることは難しく、適切な賠償金額を受け取るためには専門家の助けが必要です。適切な助言やサポートを受けるために、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠