自賠責の慰謝料金額と本来もらえる慰謝料との違い
自動車に関係する保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。
万が一、交通事故が起きたときのことを考えると、保険は被害者にとっても加害者にとっても、非常に重要なものです。
ですから、自動車を運転する際、ドライバーとしてはまず保険に加入しなければいけません。
(もし、保険に加入していない人がいたら、今すぐ手続きの段取りをとってください!)
しかし、みなさんは保険のことをどのくらいご存知でしょうか?
自賠責保険と任意保険の違いは?
自賠責保険から支払われる保険金と慰謝料は同じもの?
保険金や慰謝料は、どのくらいもらえるものなのか?
いざ考えてみると、次々に疑問が湧いてくるのではないでしょうか?
そこで今回は、交通事故の被害者の方が知っておくべき、自賠責保険と慰謝料の関係や慰謝料額の相場、増額方法などについて解説します。
目次
自賠責保険の仕組みと内容を理解する
自賠責保険は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といい、1955(昭和30)年の「自動車損害賠償保障法」施行にともない設立された対人保険制度です。
自動車やバイクなどを使用する際、ドライバーには自動車損害賠償保障法により自賠責保険への加入が義務付けられています。
つまり、自賠責保険は、すべてのドライバーが強制的に加入しなければならない損害保険だということです。
そのため、強制保険と呼ばれることもあります。
自動車損害賠償保障法
第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
これに違反すると、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます。(第86条の3)
自賠責保険は人身事故の被害者を救済するために作られた保険ですから、自損事故によるケガや物損事故には適用されません。
また、被害者救済という設立主旨から、その補償は必要最低限になっています。
つまり、人身事故の場合にのみ、被害者が被った損害に対して必要最低限の保険金が支払われるわけです。
一方、任意保険はその名称の通り強制ではなく、ドライバーが任意で加入するものです。
1997(平成9)年に保険が自由化されたことで、各損害保険会社がさまざまなプランを提供しているので、多様な補償内容や特約などから選ぶことができるようになっています。
現実の交通事故では、被害者が負った損害を自賠責の保険金だけでカバーできない状況が多く発生します。
そうした事態に備えて、ドライバーが加入するのが任意保険ということになります。
参考情報:自動車損害賠償保障法
自賠責保険の慰謝料はいくらになるのか?
自賠責保険で補償される保険金額は、自動車損害賠償保障法により次のように定められています。
自賠責法別表第1
| 等級 | 保険金額 |
|---|---|
| 第1級 | 4,000万円 |
| 第2級 | 3,000万円 |
自賠責法別表第2
| 等級 | 保険金額 |
|---|---|
| 第1級 | 3,000万円 |
| 第2級 | 2,590万円 |
| 第3級 | 2,219万円 |
| 第4級 | 1,889万円 |
| 第5級 | 1,574万円 |
| 第6級 | 1,296万円 |
| 第7級 | 1,051万円 |
| 第8級 | 819万円 |
| 第9級 | 616万円 |
| 第10級 | 461万円 |
| 第11級 | 331万円 |
| 第12級 | 224万円 |
| 第13級 | 139万円 |
| 第14級 | 75万円 |
自賠責法別表第1は、高次脳機能障害や遷延性意識障害、脊髄損傷など重度の後遺障害により、将来的に介護が必要になってしまった場合に適用されます。
その他の傷害による後遺障害については、自賠責法別表第2が適用されます。
なお、被害者が死亡した場合の最高金額は3,000万円になっています。
参考記事:国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」
後遺障害等級とは?
ケガの治療を続けていた被害者の方の健康が元に戻ればいいのですが、残念ながら治療を続けても、これ以上は回復しないという局面を迎えるときがあります。
これを「症状固定」といい、主治医が判断することになります。
症状固定と診断されると、後遺症が残ってしまうことになります。
被害者の方は後遺症を負い、大きな損害を被ったわけですから、その損害分を賠償してもらわなければいけません。
そこで必要になるのが、「後遺障害等級認定」です。
前述の自賠責法別表にあるように、後遺障害等級はもっとも重い1級から順に14級まであり、後遺症が残った身体の部位の違いによって各号数が設定されています。
後遺障害等級によって保険金額が大きく違ってくるので、認定されるのが何級の何号なのかは被害者の方にとって、とても大切になってくるのです。
参考情報:国土交通省「自賠責後遺障害等級表」
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」という2種類の申請方法があります。
どちらにもメリットとデメリットがあるので、それらを考え合わせながらご自身に合った方法を選ぶのがいいでしょう。
また、申請しても認定されない場合や間違った等級が認定されるケースもあります。
そうしたときは、「異議申立」をすることができます。
詳しくは、次のサイトをご覧になって参考にしてください。
示談交渉における注意ポイント
前述したように、自賠責保険はその元々の主旨が人身事故の被害者救済であることから、支払われるのは最低限の補償額になります。
すると、被害者の方にとっては困った問題が起きてくることがあります。
それは、自賠責保険から支払われる保険金だけでは被害者の方が負った損害のすべてを補償しきれないケースです。
後遺症が重度で、認定された後遺障害等級が高くなると、被害者の方が受け取るべき損害賠償金額は高額になります。
そこで、被害者の方は自賠責保険金では足りない分について、加害者が加入している任意保険会社に損害賠償請求することができるのです。
たとえば、事前認定の場合、後遺障害等級が認定されると加害者側の保険会社から保険金(示談金)の提示があります。
保険会社が自賠責保険の保障の範囲内と判断した場合は、その上限額以内に納まる金額が提示されますし、その金額では足りない分については加算されて提示されます。
(事前認定では、任意保険会社が自賠責保険金の分を立て替えて被害者に支払い、後から自賠責に保険金額を請求する仕組みのため)
この金額に納得したなら、示談書にサインをして、その後に保険会社から保険金があなたの銀行口座などに振り込まれれば、損害賠償請求の手続きや工程は終了です。
一方、提示金額に納得がいかないなら示談交渉がここから開始されることになります。
ところで、ここでも被害者の方にとっては、さらに困った問題が起きてくる場合があります。
それについては、後ほど詳しくお話します。
交通事故の示談交渉の注意点について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
自賠責保険金の補償内容について
では、自賠責保険の補償内容というのは、どのようになっているのでしょうか。
前述したように、自賠責保険は自損事故によるケガや物損事故には適用されないので、加害者のケガの治療費や自動車等の修理費、被害者側の自動車等の修理費などは支払われません。
あくまでも、人身事故によって生じた被害者の身体に対する損害賠償のみです。
損害の金額は、たとえば傷害による損害の場合であれば、支払限度額は最高で120万円(被害者1名につき)です。
治療関係費、文書料、休業損害、傷害慰謝料(被害者および遺族)などが損害の範囲と認められます。
後遺障害による損害の場合は、さらに逸失利益や後遺症慰謝料などが損害の範囲と認められます。(金額に関しては前述の表を参照)
自賠責保険金と慰謝料の違いとは?
ところで、交通事故の相談を受けていると、被害者の方の中には自賠責保険金が慰謝料そのものだと思っていたり、損害賠償金と保険金、示談金は別のものだと勘違いしていたり、逆にこれらが慰謝料と同じものだと思っている方がいます。
人生で交通事故に何度もあうことは確率的にもまれなことですから、被害者の方が交通事故に関する知識を持っていないことは、無理もないことです。
しかし、ご自身の今後の人生のために適切な金額を受け取ることや、加害者に罪を償ってもらうためには正しい交通事故の知識を身につけておくべきだと思います。
じつは、損害賠償金と保険金、示談金は、名前は違いますが、趣旨はすべて同じものです。
3つとも被害者の損失を填補しようとするものですが、状況によって法的な意味合いが異なってくるために名称が違ってくるわけです。
被害者の方が被った損害を賠償するから損害賠償金、保険契約に基づいて保険会社から支払われるから保険金、加害者(保険会社)との示談が成立した場合に支払われるから示談金というように、その状況によって呼び方が変わるということです。
また、慰謝料は保険金の中の一部、一項目です。
じつは、慰謝料だけでも、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料というように、さまざまなものがあるのです。
保険金(損害賠償金)の主な項目には次のものなどがあります。
- ・治療費
- ・付添費
- ・将来介護費
- ・入院雑費
- ・通院交通費
- ・装具・器具等購入費
- ・家屋・自動車等改造費
- ・葬儀関係費
- ・休業損害
- ・傷害慰謝料
- ・後遺症慰謝料
- ・死亡慰謝料
- ・逸失利益
これらをひとつにまとめたものを保険金、あるいは損害賠償金、示談金というわけです。
ですから、被害者の方が受け取ることができる損害賠償金には、さまざまな項目があるということを知っておいていただきたいと思います。
交通事故で請求できる損害項目について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
本来もらえる適正な慰謝料金額
加害者側の保険会社から示談金の提示があったら、必ずその内訳と金額を確認してください。
たとえば、記載されている慰謝料が本当に正しい金額なのかどうか、被害者の方にはよくわからないと思いますが、もしこの金額が本来受け取るべき金額より低いものであったとしたら……あなたはどうしますか?
じつは、慰謝料の算定には基準があるのですが、それはひとつではないのです。
「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士(裁判)基準」という3つの基準があることが、事を複雑にしているのです。
| 自賠責基準 | 自賠責保険に基づく基準のことで、もっとも低い金額が算出される |
|---|---|
| 任意保険基準 | 慰謝料などの算出の際にそれぞれの任意保険会社が独自に設定している基準 |
| 弁護士(裁判)基準 | これまでの実際の交通事故の裁判例から導き出された損害賠償金の基準で、裁判をした場合に認められ得るもの |
弁護士が被害者の方から委任され、加害者側の保険会社と交渉するとき、あるいは訴訟を提起して裁判を起こした場合に弁護士が主張するのは、弁護士(裁判)基準から算出した金額です。
これら3つの中では、弁護士(裁判)基準で算出した金額がもっとも高額になります。
たとえば、自賠責基準による慰謝料では、傷害による損害の場合は1日に4,200円が支払われるのですが、被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して、治療期間内で対象日数が決められます。
また、後遺障害による損害の場合、将来的な介護が必要となる後遺障害等級1級では1,600万円、第2級は1,163万円が支払われ、初期費用として、第1級は500万円、第2級は205万円が加算されます。
その他の傷害の場合は、第1級では1,100万円、第14級では32万円が支払われます。
一方、弁護士(裁判)基準による後遺症慰謝料の相場金額は次のようになっています。
※等級をクリックすると、各等級の詳細ページを表示します。
| 後遺障害等級 | 慰謝料 |
|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 |
| 第2級 | 2,370万円 |
| 第3級 | 1,990万円 |
| 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 |
| 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
比較してみると、金額の違いがおわかりいただけると思います。
ところで、ここでも疑問が浮かんできます。
保険会社から提示される金額は、被害者が本来受け取ることができる金額よりも低いのではないか?
なぜ、もっとも高い弁護士(裁判)基準で算出した金額が提示されないのか?
これらの疑問は何も間違っていません。
つまり、多くの場合、被害者の方は本当に適切な金額ではない安い金額しか受け取っていないというのが実態なのです。
適正な慰謝料額を受け取るためには弁護士に相談・依頼してください!
被害者の方が自力で、示談交渉で慰謝料などの増額を勝ち取ることは難しく、そのまま示談交渉を続けても、進展せずに長引いてしまう可能性が高いです。
そうした場合は、交通事故の損害賠償実務に精通した弁護士に相談・依頼されることを強くおすすめします。
被害者の方から依頼を受けた弁護士は、まず後遺障害等級が正しいかどうかの確認から始まり、慰謝料や逸失利益、過失割合、将来介護費用などを精査し、適正な金額を算出します。
そして、加害者側の任意保険会社に対して主張・立証していきます。
仮に示談交渉が決裂した場合は、提訴して裁判での解決を図ります。
裁判では、慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が、かなり高くなります。
また、被害者の方は保険会社とのシビアな金額交渉から解放されるというメリットもあります。
交通事故の損害賠償の示談交渉でお困りの場合は、みらい総合法律事務所にご相談下さい。
みらい総合法律事務所では、毎年1,000件以上のご相談をお受けし付けています。
これまで25年以上にわたって数多くの事案で慰謝料などを増額解決してきた実績があります。
当法律事務所では随時、無料相談を行なっています。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑





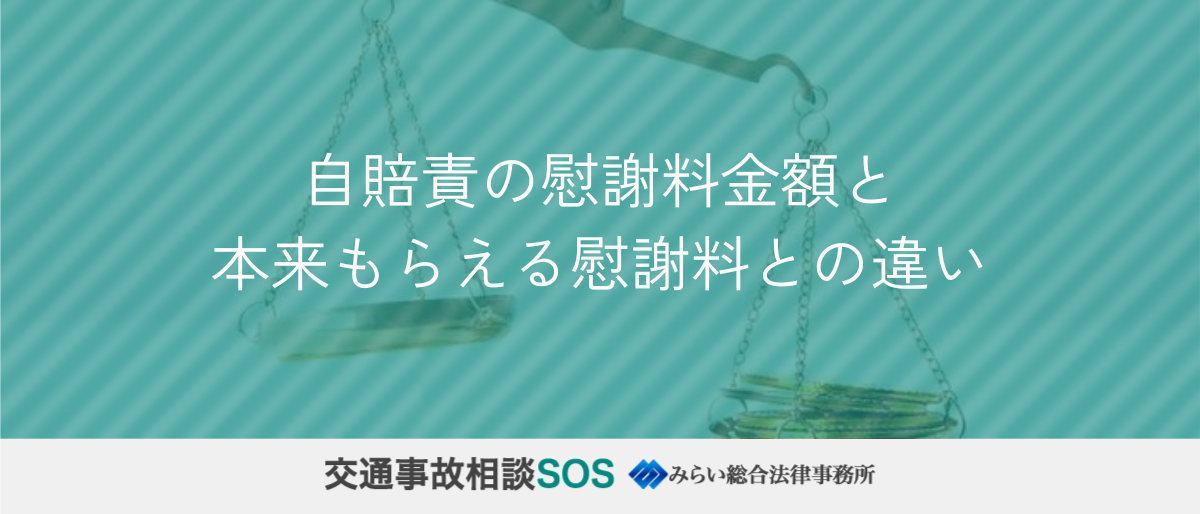






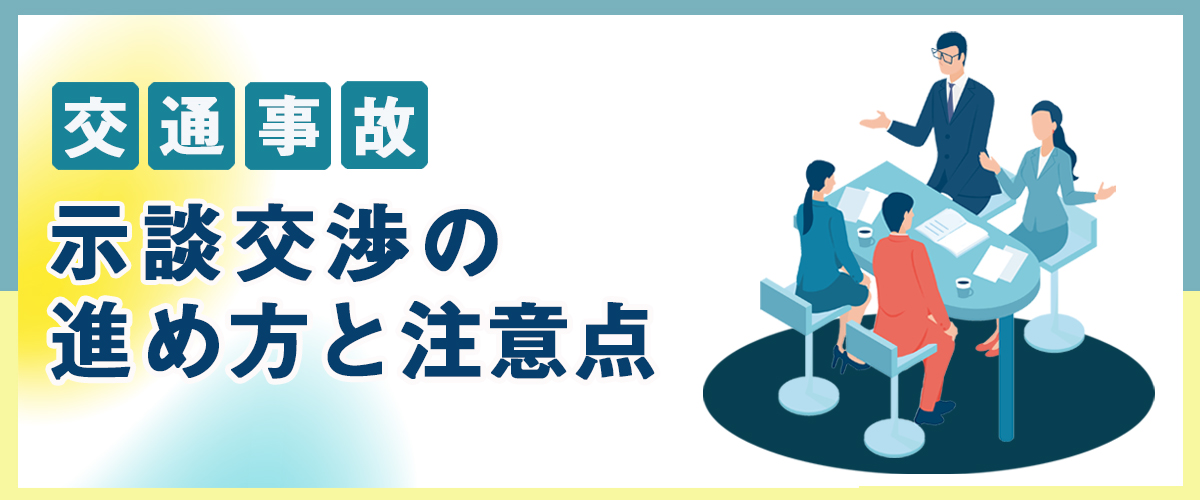







の後遺障害等級.png)

