追突事故(おかまほられた時)の慰謝料の相場はいくら?計算と請求方法
*タップすると解説を見ることができます。
自動車が後ろから別の自動車によってぶつけられる事故のことを「おかまほられた」と表現することがありますが、追突事故、つまりおかまほられた時の被害者の方が傷害(ケガ)を負って、後遺症が残った場合は、「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」と「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。
慰謝料額は入通院期間や算定基準、認定された後遺障害等級によって変わってきます。
追突事故で最も多い「むち打ち症」の後遺症が残ってしまい、後遺障害12級が認定された場合の後遺障害慰謝料を弁護士(裁判)基準で算定すると、290万円になります。
14級の場合は、110万円です。
じつは、これが正しい相場金額になるのですが、加害者側の任意保険会社(加害者が加入している場合)は、かなり低い金額を提示してくるので注意が必要です。
ここでは、おかまほられた、つまり追突事故にあった際にやるべきことや、慰謝料金額の相場と計算方法、請求時の注意点などをわかりやすく解説します。
追突事故(おかまほられた時)の
被害…その時やるべきこととは?
自動車同士の事故でもっとも多いもののひとつが追突事故です。
被害者の方としては、突然、後ろから追突されるのですから、まさに「寝耳に水」のようなトラブルでしょう。
「おかまほられた」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これがまさに「追突事故」のことで、信号待ちや停車中に、後ろの車からぶつけられた状態のことを指します。「もらい事故」と表現する場合もあります。
もし、おかまほられた際、つまり追突事故の被害者になってしまった時、まずは何をするべきなのか?
パニックになってしまうこともあるかもしれませんが、まずは落ち着いて、以下の順序で対応していきましょう。
- (1)事故の状況を確認
- (2)加害者の情報を確認
- (3)警察に連絡する
- (4)警察に事故の状況を説明する
- (5)目撃者にも協力してもらい証拠を集める
- (6)加害者の自賠責保険と任意保険を確認
- (7)自分が契約している保険会社へ連絡する
- (8)必ず病院に行く
1つずつ詳しく解説します。
(1)事故の状況を確認
まずは、道路上での安全を確保し、ご自身のケガの状況を確認します。
状況によっては、救急車を呼ぶなどの対応も必要ですし、ご自身のケガへの対処を最優先してください。
(2)加害者の情報を確認
加害者に運転免許証を提示して
もらう
今後の損害賠償問題のためにも加害者に運転免許証を提示してもらい、次の確認をします。
- 住所
- 氏名
- 連絡先(携帯電話、自宅の電話番号)
加害者に名刺をもらう
加害者が名刺を持っていれば、もらっておきます。
名刺はない、というのであれば、勤務先名や電話番号などをメモしておきましょう。
勤務中の従業員が起こした交通事故については、「民法715条(使用者責任)」および「自動車損害賠償保障法」という法律により、運転者だけでなく雇用主(会社)も損害賠償責任を負う場合があるため、加害者が勤務する会社に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができるからです。
加害車両のナンバーと保有者を
確認する
加害車両のナンバーと保有者も確認しておいてください。
「自動車損害賠償保障法」により、運転者だけでなく車両の保有者も損害賠償責任を負うためです。
保有者名は車検証に記載してあるので提示してもらい、写真を撮っておくとよいでしょう。
(3)警察に連絡する
交通事故の被害にあった場合は必ず警察に連絡してください。
加害者側の保険会社に慰謝料などの損害賠償金を請求するには、交通事故証明書や事故状況を検証した実況見分調書が必要になります。
しかし、交通事故を警察に連絡しなければこれらの書類は作成してもらえません。
そうなると被害者の方は慰謝料などを受け取ることができなくなってしまうので注意が必要です。
(4)警察に事故の状況を
説明する
事故現場に警察が到着したら、事故の状況についてできるだけ詳しく話してください。
加害者と言い分が異なり、後日争いになることも考えられます。
そうしたときの予防策のため、スマートフォンがあれば事故現場や車両の写真を撮影しておいたり、加害者の言い分を録音しておくことも有用です。
なお、被害者の方が救急搬送されたために事故現場で状況説明ができない場合でも、加害者の言い分と被害者の方の説明内容が異なることがあると思います。
そのため、できるだけ早急に被害者立会の実況見分調書を警察に作成してもらうよう申し出たほうがいいでしょう。
(5)目撃者にも協力してもらい証拠を集める
目撃者がいれば、その証言は追突事故の有力な証拠になるので、氏名・住所・連絡先などを教えてもらい、協力をお願いしましょう。
加害者は、事故の直後は責任を認めていても、後日になって異なる主張をしてくることがあるので注意が必要です。
また近年では、2017(平成29)年に起きた「東名高速道路あおり運転事故」の影響もあり、ドライブレコーダーを搭載している方も増えていると思います。
ドライブレコーダーの映像は有力な証拠になるので、必ず確保しておきましょう。
(6)加害者の自賠責保険と
任意保険を確認
被害者の方の入通院の治療費、慰謝料や逸失利益、休業損害などの損害賠償金について、通常の場合は加害者側の保険会社に請求することになります。
そのため、保険会社名や保険の証明書番号なども記録しておきましょう。
自賠責保険と任意保険について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
(7)自分が契約している
保険会社へ連絡する
被害者ご自身が契約している任意保険に「人身傷害補償特約」「弁護士費用特約」「搭乗者傷害特約」などがついているなら、保険金の支払いを受けることができる場合があるので、連絡をしてください。
加害者が無保険というケースもあります。
そうした場合は、ご自身の保険に「無保険者補償特約」がついていれば使うことができます。
また、両親などの家族が契約している保険にも使用できる特約がついている場合もあるので、保険会社には必ず連絡をして確認することも大切です。
(8)必ず病院に行く
交通事故の被害にあった後、とくに目立ったケガもないから、あるいは痛みもそれほどないから、といって病院に行かない方がいます。
しかし、これは絶対に避けてください。
たとえば、むち打ち症の場合、事故直後は痛みなどはなくても時間の経過とともに痛みが強くなったり、首を動かすことができないなどの運動障害が起きてくるケースがあります。
今後、入通院慰謝料や後遺傷害慰謝料などの損害賠償金にもかかわってくることのなので、追突事故の被害の後は必ず病院に行くようにしましょう。
3つの基準から
具体的な慰謝料金額を計算する
ここでは、おかまほられた場合にいくらもらえるかなど、追突事故の被害者の具体的な慰謝料の計算方法を分かりやすく解説します。
入通院慰謝料
交通事故の損害賠償額を決定する時には、「自賠責基準」「任意基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの算定基準が存在します。
ここでは、入通院慰謝料を3つの基準別に詳しく解説します。
自賠責基準の入通院慰謝料
自賠責基準による入通院慰謝料については、1日あたりの金額が定められており、次の計算式で算出します。
4,300円(1日あたりの金額) × 対象日数 = 入通院慰謝料
※民法の改正により、2020年3月31日以前に発生した交通事故では、1日あたりの金額は4,200円。
・対象日数は、①「実際の治療期間」、もしくは②「実際に治療した日数 × 2」のいずれか短いほうが採用されることになります。
・入通院慰謝料は、入院・通院した日数によって決まってくるので、仕事の事情や家庭環境、痛みを我慢するなどの理由から、途中で通院をやめてしまうと金額が低くなってしまいます。
任意保険基準での入通院慰謝料
各任意保険会社は具体的な基準を公開していないのですが、これまでの被害者弁護での経験上、概ね自賠責基準と弁護士(裁判)基準の中間くらいの金額で設定されています。
弁護士(裁判)基準での
入通院慰謝料
弁護士(裁判)基準で入通院慰謝料を算出する際は、日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している通称「赤い本」と呼ばれているものに記載されている「損害賠償額算定基準表」から算定します。
これは前述したように法的根拠のしっかりした基準なので、裁判所や弁護士が使用するものです。
通院をした月数別に算出した入通院慰謝料の日額を表にしてみました。
参考にしてください。
「通院を1か月した場合の慰謝料の日額」
| 自賠責基準 | 4,300円 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 経験上7,400円程度が多い |
| 弁護士基準 | 9,333円 |
※自賠責基準は、1か月のうち半分以上の日数の通院だったと仮定して計算。任意保険基準と弁護士基準については、ひと月を30日として割って日額を計算。
※自賠責基準12.9万円、任意保険基準12.6万円、弁護士(裁判)基準28万円を日額に換算。
※重傷の場合で計算
後遺障害慰謝料
被害者の方に後遺症が残ってしまった場合は、加害者側の保険会社に対して「後遺障害慰謝料」を請求することができます。
つまり、被害者の方は入通院慰謝料の他に後遺障害慰謝料も受け取ることができるということです。
後遺障害等級は、もっとも重度の1級から順に14級までが定められています。
金額は等級によって決められており、等級が重いほど慰謝料や逸失利益などの損害賠償金額が高くなります。
やはり被害者の方としては、後遺障害慰謝料についても、もっとも金額の高い弁護士(裁判)基準による金額を受け取ることを目指すべきでしょう。
では、後遺障害慰謝料は、いくらもらえるのか。以下で確認しておきましょう。
※等級をクリックすると、各等級の詳細ページを表示します。
「弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の
相場金額表」
| 後遺障害等級 | 慰謝料 |
|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 |
| 第2級 | 2,370万円 |
| 第3級 | 1,990万円 |
| 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 |
| 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
追突事故(おかまほられた時)の
慰謝料請求ではここに注意!
追突事故だからといって他の事故とは慰謝料の請求金額や方法が変わるわけではありません。
ただし、追突事故では注意するべきポイントがいくつかあります。
一つずつ詳しく解説します。
自賠責基準で慰謝料を
計算されがち
追突事故の場合、被害者の方のケガは比較的軽度な場合が多く、そうしたケースでは治療費や休業損害、慰謝料などは自賠責基準で計算されてしまうことが多いのが現実です。
すると、被害者の方が受け取る金額が少なくなってしまうことになります。
治療を一定期間で
打ち切られてしまいがち
そこで治療費の支払いは打ち切ります」
これは誰の言葉かというと、加害者側の保険会社の担当者のものです。
前述したように、保険会社はできるだけ被害者への保険金という支出を減らしたいために、治療費の打ち切りを告げてきますが、大体の場合、事故から3か月~6か月後が多いようです。
「保険会社がそう言うのであれば仕方がないのか…」とあきらめてしまう被害者の方も多いのですが、ここで保険会社の言うことをそのまま信じてはいけません。
なぜなら、症状固定というのは、主治医が診断するものであって、保険会社が決められるものではないからです。
ですから、たとえ治療費の支払いを打ち切られたとしても、主治医から症状固定の診断がないのであれば、それはまだ治療の効果が上がっているということですから、ご自身の健康保険に切り替えるなどして治療を続けてください。
そして、あとで行なう示談交渉でその治療費も請求していくようにしましょう。
その際、治療費の領収書等はすべて保管しておくことが大切です。
後遺障害等級が
認定されないこともある!?
治療を終えてケガが完治すればいいのですが、後遺症が残ってしまった場合、被害者の方は後遺障害等級の申請を行なう必要があります。
しかし、ここで問題となるのは、後遺症が自覚できるのに後遺障害等級が認められない場合があることです。
たとえば、追突事故でもっとも多い傷害(ケガ)のひとつに、むち打ち症があります。
むち打ち症では、後遺障害等級12級か14級が認定される可能性があるのですが、その場合は痛みなどの神経症状や運動障害などについての診断書の他、レントゲンやCT、MRIなどの画像が必要となります。
しかし、医学的に異常が認められないと判断されてしまうと後遺障害等級が認定されず、被害者の方としては後遺障害慰謝料をもらえなくなってしまう可能性があるので、注意が必要です。
算定基準で違いが
出てしまう場合がある
じつは、入通院慰謝料の弁護士(裁判)基準には「軽傷用」と「重傷用」の2つの算定表があります。
比較をしてみると、たとえば入院なし、通院1か月の場合、軽傷用の算定表では19万円、重傷用の算定表では28万円となります。
通院2か月の場合は、それぞれ36万円と52万円、通院3か月では53万円と73万円となり、通勤期間が長くなるほど金額に差が出てしまうことになります。
追突事故によるむち打ち症で、後遺障害等級が認定されない場合は軽傷用の算定表を使用することになっているので注意が必要です。
おかまほられた被害者の方や、追突事故の慰謝料でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑





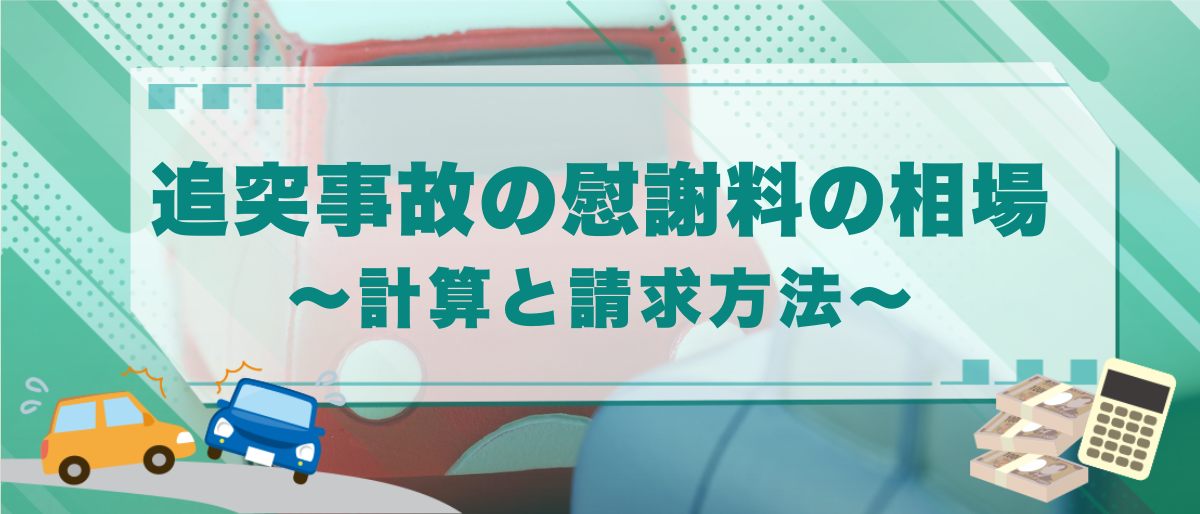


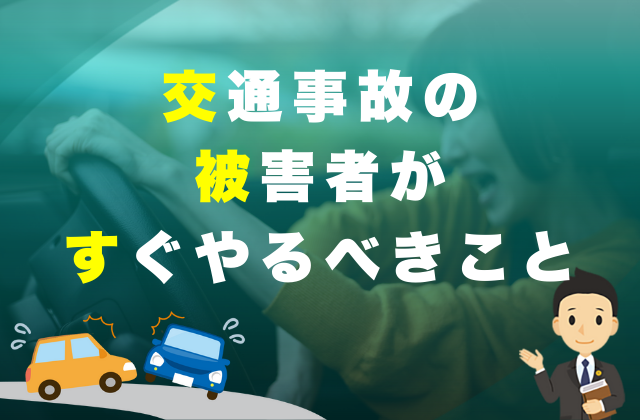





の慰謝料額と増額事例.png)








